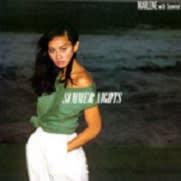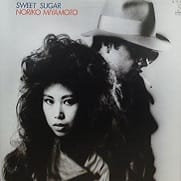このブログ開始以来初めてとなる8cmの短冊シングルCD紹介。1997年と98年に一枚ずつシングルをリリースした後、表舞台からは姿を消し裏方に回ったミュージシャンによるデビュー作。あいにくリアルタイムでは聴いていないのですが、この度どういうわけかディスク・ユニオンのThink!から7inchカットされるということで興味が涌き、なんとなく購入してみることにしました。実際聴いてみた感想としては、まぁ可もなく不可もなくと言ったところ。たしかに全体的に山下達郎っぽい(と言うか、ほぼそのままな)音作りになっていているため、初めて聴いたときのインパクトはそれなりのものがありますが、残念ながらそれ以上のサムシングを感じることは出来ないので、DJプレイのアクセントで飛び道具的にかけるくらいが関の山というのが正直なところです。歌声まで本人に似せているというわけではないですが、10年早かったジャンク・フジヤマというのが個人的な印象。ちなみに僕としてはどちらかと言うと、Loveland, Island風で人気のあるM-2「レッツ・キッス・ベイビー」よりも、ミディアムアップで瑞々しく弾ける表題曲であるM-1の方が好み。どうやら当時カネボウのCMソングとしてタイアップされていたようで、言われてみれば確かにそんな感じですね。オリジナルのシングルはやや高騰しているので、わざわざ買うほどの一枚かどうかと言われると微妙ですが、冒頭にも書いたように今度リイシューされるようなので、興味のある人は聴いてみても良いかもしれません。正直なぜCDや配信ではなくアナログで復刻するのかは疑問ですが、おそらく一部でニーズがあるのでしょう。ちなみに僕の場合アナログで購入欲が涌くのは、元々アナログでリリースされた作品とジャケの雰囲気から音に至るまでアナログ時代の質感を完璧にトレースしている作品だけなので、ジャケットも音も思いっきりCDっぽいこの作品は多分買いません…。
80年代~90年代序盤にかけて活動していた男性シンガー・ソングライター川村康一氏による1990年の2ndアルバム。もちろんリアルタイムで聴いていたわけではなく、今の時代で知名度が高い人ということでもないので、正直このアルバムを聴くまで名前を聴いたことがなかったのですが、ご本人のホームページを見る限り「AOR(Adult Oriented Rock)をこよなく愛し、リゾートミュージックの代表の1人」だそうです。作風的にはAFTER 5 CLASH以降の80's角松サウンドに近いテイスト。時代背景的なところも多分にあるのでしょうが、全編打ち込みの固いドラム・ビートに載せた産業ロック~フュージョン・サウンドとなっており、正直今聴くには少しツラい曲が多いです。この時代の楽曲でも生ドラム主体のアコースティックサウンドかアシッド・ジャズのエッセンスを取り入れた「揺れる」打ち込みビートならば問題なく聴けるのですが、ここまで直球に打ち込まれてしまうと正直しんどいかなと言ったところ。M-2のHot "Jammin" StepやM-7のLet's Get, Babyのように上モノの鳴りとメロディー自体は良いものもあるだけに残念です。ただ、そうした惜しい楽曲の中で見逃してはいけないのがM-5のWHITE MEMORIES (マーヴィン・ゲイに捧ぐ)。タイトルからも分かるように思い切りマービン・ゲイをモチーフしたミディアム~スロウのAORナンバーなのですが、なんとヴォーカルに当時カラパナへ復帰していたマッキー・フェアリーがゲスト参加しています。あの甘くとろけるマッキーの歌声でのマーヴィン・ゲイ風ナンバーは見事の一言。カラパナ好きなら確実にやられることでしょう。アマゾンでも格安で販売されているので、聴いたことないという人は騙されたと思って是非一度聴いてみてください。この一曲のためだけに買う価値のある一枚と思います。
このブログで取り上げるのは実に9年ぶりとなるピチカート・ファイブ。今回記事を書くにあたり、そう言えば以前取り上げたことがあったかなと過去の履歴を確認していたら、前に記事を書いたのがまさかの2005年で自分でもちょっと驚いています。本作は彼らが1989年にCBS/Sonyから発表した3作目のアルバム「女王陛下のピチカート・ファイブ」リリース時に少数だけ製作された45回転の4曲入りプロモ12インチ。その存在自体は前回ブログ掲載時以前から知っていたものの、彼らが野宮真貴を擁し渋谷系の旗手として大ブレイクする前の、おまけにプロモ盤ということで想像以上に入手に手間取り、気づけばいつの間にか10年間が経ってしまいました。本作に収録されているのはA-1「夜をぶっとばせ」、B-1「恋のテレヴィジョン・エイジ」、B-2「バナナの皮」、B-3「新ベリッシマ」というアルバムでもハイライトとなる4曲。いずれもCDのテイクと同じものなので内容的には最早言うことなしですが、この大傑作を直径30cmのアナログ盤、しかも凝った装丁の特殊ジャケで所持することが出来る喜びとは、ピチカートマニアとしてはやはり格別というものです。製作時期がアナログLP最末期、さらに1980年代最後の89年というのも個人的にはポイント高め。実際のところは分かりませんが、個人的にはこの4ヶ月後にリリースされた山下達郎のJoyと本作が(クラブDJや一部マニア向けに後年あえて製作されたのではない)最後のアナログ・レコードというイメージなので、そういう意味でも非常に価値のある一枚かと思います。角松やオメガ・トライブあたりを中心にした80年代のJ-AOR系譜を追っていくとき、最後の一枚を飾ると同時に、このジャンルの次の10年の展開を示唆した記念すべき作品。はっきり言って完全にマニア向けな一枚ですが、興味のある方は是非探してみてください。ちなみに9年前に紹介したベリッシマのLP盤は、当時の書き込みで存在情報を得たにも関わらず未だ出会ったことなし。プロモオンリーの本作とは異なり一応正規販売されたはずなので、一度くらい見かけても不思議はないはずなのですが…。
また少しマニアックな作品の紹介が続いたので、たまには趣向を変えてこんなどこにでもある一枚を。1984年にカネボウ化粧品夏のキャンペーンソングとなった「君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね。」で知られる女性シンガーソングライターの中原めいこが、大ブレイク前夜の83年にリリースしたアルバムです。このところの和モノ再評価の流れの中では、その「君たちキウイ・・・」が収録された翌年のアルバム「ロートスの果実」がAOR歌謡として人気ですが、本作もそれに負けず劣らずの高クォリティな一枚となっており、個人的には存在を知った数年前から愛聴盤の一つ。なんと言っても彼女最大の魅力はその歌声。それほど抜群にうまいと言うわけではなものの、現行の女性ヴォーカルにはいないタイプの「ロマンティックくれそう」なお姉さんボイスは、幼いころドラゴンボールで育った世代には破壊力抜群です。僕自身がわりと声フェチだということもありますが、少女らしい可愛さと大人っぽいセクシーさが同居するこの手の歌声はわりと男性受け良いのではないでしょうか。肝心の楽曲はというと、全編通じてややファンカラティーナの雰囲気漂うAOR歌謡。いわゆる本格派のサウンドとは少し趣を異にしますが、これはこれで一つのJ-AORの形として楽しむのが今風の聴き方というものでしょう。特に当時アルバムからの先行シングルとしてもリリースされていたB-1の「月夜に気をつけて!」は、いかにも80'sサウンドと言った雰囲気の煌びやかなナンバーで、個人的に非常に大好きな一曲。言ってしまえばただの歌謡曲なんですが、なんというか単純に好きなタイプの楽曲なんですよね。逆に最近のライトメロウ・ブーム的においしいのはB-5の「ペパーミントの朝」。ボサノバを下敷きにしたクロスオーヴァー・サウンドで、曲中に入る鳥の声のSE含め非常にその手のファン好みの音になっています。いずれにしろLPであれば3桁で買える一枚だと思うので、気になる人は是非。確かitunesでも配信されていたはずなので、まずはそちらから試してみても良いかもしれません。
たまにはこんなどこにでも売っている作品も紹介。フィリピンはマニラ出身のフュージョン系シンガー、マリーンによる1982年の2ndアルバムです。歌い手がフィリピーナで歌詞は全英語詞、それでいて演奏を務めるのはハワイ出身のCCM系バンドであるシーウィンドと、普段のこのブログのカテゴライズではどこに入れるか悩みますが、国内オンリーのリリースであることから、一応ここでは通例に従いJapanese AORとしておきましょう。本作が今でも衰えず人気な理由はやはり瑞々しいアップテンポで始まるA-1のタイトル曲。実はBamaというブルーアイドソウル系バンドによる曲のカバーだったりするのですが、オールド・ファンにしてみればやはりこの曲はマリーンのものという印象が強いことと思います。豪快なシーウィンドのホーン・セクションをバックに疾走するフュージョン系AORの傑作ナンバー。マリーン自体の歌声もまた素晴らしく、たとえばマリリン・スコットあたりのフィメールAORが好きならばまず間違いなくハマることでしょう。正直この曲のインパクトが強すぎてその他の収録曲が霞んでしまいますが、実はミディアム~スロウなナンバーの中にも隠れ名曲が潜んでおり、中でもA-4のTryとB-2のJust Say I Love Youは埋もれさせるには惜しい絶品アイランド・メロウ・チューン。シーウィンドがバックを務めていることもあり、コンテンポラリー・ハワイアンの中に混ぜてかけても違和感なく機能する素敵なナンバーとなっています。LemuriaやAuraあたりが好きな人はチェックしてみると面白いかもしれません。CDだと店によっては微妙にプレミア価格が付いているものの、LPならばどこで見ても二束三文。僕自身も牛丼並盛以下の値段で買っていますが、内容については折り紙つき。巷で売られているミドル級廃盤くらいなら軽く蹴散らすクォリティを誇る一枚です。財布に優しい名盤なので、まだ聴いたことないという人は悩む前にまず買うべき作品。あらゆる意味でお勧めのアルバムです。
先日参加させて頂いたadd-o-ramaで教えてもらった作品。あのX JAPANのYOSHIKIも通っていたことで知られる専門学校「青山レコーディングスクール」のオリジナル・レーベルNescoから、80年代中ごろにリリースされた4曲入り12インチ盤です。ご本人たちのホームページに書かれたプロフィール等から紐解く限り、この時点では東京女子大のサークルバンドを母体とした女性4人組バンドとのこと。1980年に開催されたヤマハ「East Westコンテスト」でレディース部門グランプリを受賞したことがきっかけとなり、本作製作のチャンスを得ることが出来たようです。「ときめきはムーンライト・サスペンス!今、予感はラヴ・シューティング!!」という意味不明な帯の煽り文句と、クリスタル感に満ちたこのジャケット、そしてこのタイトルにして半自主盤と四拍子揃っているためJ-AOR好きとしては否応なく食指が動くのですが、内容のほうはまぁそれなりと言ったところ。あまり期待しすぎると肩透かしを食らいますが、全体的に曲の完成度は一定の水準を保っており、たまにターンテーブルに乗せるには良い感じです。ファンキーに迫るB-1のSail On The Nightあたりは紀の国屋バンドに通じる部分もあり、この手のサウンドが好きな人にはツボなのでしょう。ただ、個人的にはやはりA-2のDaylight Passageが本作のハイライト。イントロのギターとアーベインなキーボード・ワークで一気に持っていかれる泣きのAORバラードです。普段この手のバラード曲はあまり聴かないのですが、この曲に関してはアレンジや歌詞もなかなかに良い雰囲気なので比較的好み。、こうして仕事で疲れた夜に聴くと癒されます。元々のプレス数はそれほど多くないと思うので、正直どこでも見つけられると言った類の作品ではありませんが、もしもどこかで見つけたら聴いてみてください。どちらかと言うとリアルタイム派のAORリスナーにお勧めの作品です。
知っている人は知っている中山美穂の1988年作。僕くらいの年齢だと少し世代が違うので、彼女の印象と言えば、WANDSとタッグを組み180万枚以上のセールスを記録した「世界中の誰よりきっと」くらいしかなく、あいにくアイドル時代の活躍はほとんど知らないのですが、本作はどうやらそんな彼女が少しずつ脱アイドル路線を模索していた時期の作品に当たるようです。なんでもこの年の彼女は1年間で3枚ものオリジナルアルバムを出すという、今の感覚からするとちょっと信じられないハイペースで活動していたようで、本作はその中の3枚目。前作Mind Gameから起用された女性シンガーソングライターの故Cindyをプロデューサーに据えたことが功を奏し、ただのアイドル作品という物差しでは測れない素晴らしい一枚に仕上がっています。そもそも冒頭からライトメロウな雰囲気で始まるA-1のSweetest Loverがいきなり名曲。スロウテンポの曲ながら軽いタッチで作られており、いわゆるバラード的な重苦しさがない非常に都会的なナンバーに仕上がっています。間宮貴子あたりが好きな人なら確実に一瞬で虜になることでしょう。何よりの名曲はA-4のDiamond Lights。東北新幹線で知られる鳴海寛のペンによるブラコン風のライトメロウなミディアムナンバーで、J-AORのお手本みたいなアレンジがただただ気持ちいい至福の一曲です。中山美穂自身の透き通ったヴォーカルも見事なもの。歌唱もさることながら、何より「近所の綺麗なお姉さん」的な歌声が心地よく、まるで空気のようにすっと違和感なく耳に馴染んでいきます。アイドルの歌声としては100点でしょう。ちなみにその他の曲では、後にCindy自身もセルフカバーするA-5の「天使の気持ち」あたりもなかなかの出来。そこそこプレスされたのかCDへの移行期の作品ながら、LPでの入手も比較的容易なので、気になる人は探してみてください。間宮貴子・国分友里恵・二名敦子あたりが好きな人にはお勧めです。
以前このブログでも取り上げ、予想通り紹介から半年後の昨年7月に銀盤化と相成った国分友里恵の1stアルバム「Relief 72 Hours」。本作はそのアルバムと同時か少し後にリリースされたと思われるシングル盤です。A面のタイトル曲は林哲司編曲によるディスコブギーで、こちらは単純にアルバムからのカットなのですが、注目はこっそりとB面に収録されたEasy Love。これが本作を人気盤たらしめる所以、アルバム未収(=現在に至るまで未CD化)な必殺のシティポップスです。そのダンサンブルな展開でアルバム中でも異彩を放っていたJust A Jokeを、全体的な雰囲気はそのままに、もう少しポップかつマイルド、さらにライトメロウ寄りに仕上げたミディアムアップの名曲。サバービア~ライトメロウ以降のJ-AOR好きで、この雰囲気に抗える人はいないと思われる魅惑のナンバーに仕上がっています。作編曲は山下達郎のツアーバンドメンバーとしても知られるギタリストの椎名和夫。アルバム収録曲と異なり演奏者のクレジットがなく、これ以上の情報は分かりませんが、ひょっとしたら同じく達郎バンドのメンバーで、椎名を含め達郎自ら「バンド史上考えうる最高のリズム隊」と評する青山純(ds)や伊藤広規(b)あたりも絡んでいるのかもしれません。椎名以外の二人はアルバムでも2曲ほど演奏参加しているので、その可能性は大いに考えられそうです。主役の国分友里恵自身もコーラスとして達郎バンドに参加しているため、そのように考えるとリーダーの達郎こそ不在なものの、これはほとんど達郎バンドのナンバーそのもの。アルバムがCD化された際、ボーナストラックとして収録されなかったのが非常に悔やまれますが、堀江マミのLoving Youと共に何かのコンピで是非CD化されることを密かに期待しています。当時セールス的に成功しているとは思い難いので、探すのにはそれなりに手間がかかるかもしれませんが、曲自体のクォリティは驚くほど高いので気になる人は是非探してみてください。
ダンス☆マンこと藤沢秀樹が参加していたことで知られる和製ソウルファンクバンドがこのジャドーズ。元々の出自がお笑いグループなのにもかかわらず、音に向かう姿勢は至って真面目で、あいにくセールス的には振るわなかったものの正統派のJ-AORサウンドを聴かせてくれる稀有なバンドです。本作はそんな彼らが敬愛する角松敏生の元を離れ、初のセルフプロデュースに挑戦した1990年の作品。冒頭から増山江威子をナビゲーターとして登場させ、誰でも知ってる「猿みたいな大泥棒」を昔の恋人呼ばわりさせるというちょっとした仕掛けはありますが、いざ演奏が始まってしまえばすぐに角松から受け継いだ都会的な夜のサウンドが展開されます。注目はなんといってもM-4の「東京プラネタリウム」。彼らのナンバーの中でも2ndに収録されたStardust Nightと並ぶJ-AOR屈指のミディアムメロウで、開始数秒を聴いただけで抜群の夜感が伝わる名曲です。夜の首都高速をドライブしているときにラジオからこんな曲が流れたら、なんだかとても幸せな気持ちになることでしょう。今から10年ほど前にクラブ界隈でヒットした流線形の「東京コースター」もそうですが、この「東京○○」というタイトルがまず秀逸。2014年の感性で聴くと、このどこかバブルの面影を感じるノスタルジックな雰囲気がたまりません。まだ僕がとても小さかったころ、色々と旅行に連れて行ってくれた大人たち(=たぶん今の僕と同い年くらい)のカーステから流れていたのがこんな雰囲気の曲だったのを微かに思い出します。おそらくLPはリリースされておらずCDのみですが、別にレアな作品というわけではないのですぐに見つけることが出来るはず。どこでも買える安くて良質な作品なので、気になる方は是非聴いてみてください。
どうも、少しお久しぶりです。先週『add-o-rama』のイベントに参加した後、若干体調を崩し更新が遅れていました。この手のイベントは久しぶりでしたが、個性的な皆様に出会えて非常に楽しかったです。機会があればまたよろしくお願いいたします。さてさて、そんなわけで今日のLPは前回イベント時にもかけた一枚。界隈では有名な早すぎたソウル・ディーヴァ、宮本典子による1984年の作品です。本作、名義こそ宮本典子のものですが実態はフュージョン系バンドのネイティブ・サンで知られる本田竹広(key)を中心としたバンド「本田竹広&ブレイクアウト」の作品としての色合いも濃いようで、彼女の作品の中ではやや異色。以前紹介した「Noriko」のような作品とは異なり歌謡色は薄く、後の結婚相手である中平エイジ(b)のオリジナル曲含め、全ての楽曲が全英語詞によるナンバーになっており、ある意味「日本人の手で作られた洋楽」チックな一枚となっています。人気のB-2、Umi(Suddenly Last Summer)はサザンオールスターズによる和製AOR「海」のカバー。どことなくLemuriaあたりのコンテンポラリー・ハワイアンに通じるサンセットメロウな一曲で、本場のAORと比べても遜色ない素晴らしい演奏を聴くことが出来ます。その他の楽曲でAOR色が強いのは冒頭A-1のAnother Lover。程よく跳ねるリズムと鮮烈なホーンアレンジ、ライトメロウでソウルフルなmimiの歌唱が印象的な佳曲です。ブロウ・モンキーズのIt Doesn't Have To Be This Wayあたりによく似た質感なので、あの手の跳ね系ナンバーが好きな人ならおそらく気に入ることでしょう。ちなみに本作、昨今の再発カタログからは漏れているようですが、どうやら当時CD化されているようなのでCD派の人はそちらを探すのが良いと思います。いわゆるシティポップスの音ではないので和モノ系オンリーのファン向けではないと思いますが、洋楽AORが好きならきっと好みなはず。興味のある方は是非聴いてみてください。