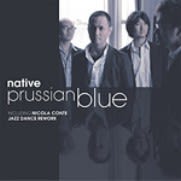ちょうど昨年の同じ頃に少し話題となった作品を、今さらというかかなり遅ればせながら紹介しておきたいと思います。別名義ユニットSoulstanceとしての活動や、Gerardo Frisinaの楽曲製作におけるブレーン的役割で知られる伊Schema所属のLo Greco兄弟。そんな彼らが、自分たちの活動のアナザー・サイドとして2003年にQuartetto~名義で発表した作品に続き、2005年にミラノで吹き込んだのが本作です。Soulstance名義の作品では他のレーベル・メイト同様、いわゆるNu Jazz的な音作りの多い彼らですが、以前ここでも紹介した前作や本作ではオーセンティックなジャズを披露していて、それが何だか逆に新鮮と言うか良い雰囲気。クラブ畑から発信された作品ながら、おそらく年配層にも自然にアピール出来る内容なのではないかと思います。ニコラ・コンテの名作Other Directionsよりも、さらにもう一歩だけモーダルな世界に踏み込んだかのような印象。おそらく数あるSchema作品の中でも、モーダル度という点では本作がトップに位置するのではないでしょうか。Freedom Jazz Dance Book IIに先行収録されたM-4のYes And No(ウェイン・ショーターのカヴァー)が、躍動感と高揚感に満ちたダンサンブルなサンバ・ジャズで人気ですが、今の気分としては断然M-1のタイトル曲が好み。軽快なテンポで演奏されるモーダルなブルース・ナンバーで、まるでスパイ映画のサントラのような少し陰のある雰囲気が抜群に格好いいです。特にGermano Zengaの吹くテナー・サックスが秀逸。他の曲も決して悪くはないものの、この1曲が飛びぬけて素晴らしいために霞んで聴こえてしまいます。こういう雰囲気の曲ってありそうで実はなかなかないんですよね。ちなみに「往年のBasso=Valdambrini楽団のような」という形容を時たま耳にしますが、正直バッソたちよりも演奏はずっと洗練されていると思います。CDのみでのリリースではあるものの、アナログ派の人もチェックしてみるに値する作品。しばらく前に年配層の間でもIdea 6が話題になったことがありますが、同じクラブ発のイタリアン・コンテンポラリーでもこちらの方が内容良いですよ。
CH-Recordというマイナーレーベルに残されたドイツ産ジャズ。キーボーディストのRoby Weberをリーダーとしたヴァイブ入りカルテット編成による73年録音のアルバムです。年代がら純粋なモダンジャズとは言い難く、またウェバーが主に生ピアノではなくエレピをプレイしているので、どちらかと言うと若干ジャズ・ファンク寄りの作品ではありますが、この手のマイナー盤としてはなかなかに好内容なので紹介。このRuby Weberという人の情報があまりないので詳細は分かりませんが、この時代のヨーロピアン・ジャズとしては中々優秀な一枚だと思います。70年代にリュニオンした後のダイヤモンド・ファイブ辺りの肌触りに近い演奏で、ヴァイブとエレピを中心とした柔らかいジャズ。8ビートで若干ジャズ・ロック調の曲やボサノヴァのリズムを取り入れた曲、はたまた正統派の4ビートで心地良くスウィングする曲まで、そのアレンジはヴァリエーションに富んでいますが、基本の演奏能力がそれなりに高いので、どんな曲調のものでもわりと洗練された雰囲気を持っていて良い感じ。以前どこかでも紹介されていたB-2のWork Songなど適度な夜ジャズ仕様となっていて、いわゆるクラブジャズ好きの方にも満足行く内容のものかと思われます。個人的にはA-4のClave-Beatという曲がツボです。取り立てた派手さはないものの、軽快なテンポとマイナーコードで綴られた素敵なボッサ・ジャズ。なおかつビートも打っているので、早い時間のDJプレイには最適と言った趣き。高いお金を払って買うほどのレコードではないと思いますが、もしも安くで見かけてみたら耳を傾けてみても良いかもしれません。ちなみに一見特殊仕様風に見えるジャケットは実は単なる2次元的なデザイン・ワークなのでご注意を。
昨年Raw Fusionから12インチをリリースし、日本のシーンをあっと驚かせたクオシモードに続き、今年は彼らが世界デビュー。以前に2ndアルバムをここでも取り上げたことのある、新世代ジャズ・バンドNativeによる話題の新譜EPです。ちなみにリリースはInfracomレーベルから。数年前に一連の【re:Jazz】シリーズが話題になったことでも記憶に新しい、ドイツのクラブ・ジャズ系レーベルですね。さて、そんな彼らによる(オリジナル作としては)初のワールドワイド・リリースとなる本EPは、昨年国内のみでリリースされたUpstairsというアルバムからの3曲に、2ndアルバムIntentionsからのトラックとお馴染みニコラ・コンテによるリミックスを1曲ずつ加えた5曲構成。オリジナルのメンバーにトロンボーンをゲストとして招き、アルトとの2管で熱い演奏を展開するB-3のStep It!辺り、好きな人も多いのではないでしょうか。エレピ使いではありながらも、その演奏はしっかりとバップ・マナーに沿っているため、モダン派のリスナーにも違和感なく受け入れられるはず。何となく後期のゴイコヴィッチにも近い雰囲気を感じます。ただ、やはり個人的に本作中白眉としたいのは、ニコラ・コンテによるリミックスが施されたA-1のPrussian Blue(Nicola Conte Jazz Dance Rework)。最もリミックスとは言っても、いつもの通りお抱えコンボによる完全な弾き直しではありますけれど…。すぐ次に収められている原曲と聴き比べてみれば分かりますが、今回のリミックスは彼の作品にしてはわりとオリジナルに忠実なカヴァー。しかしながら、そこはやはり御大ニコラのこと。オリジナルにはないヨーロピアンな気品を、まるで魔法のようにこっそりと曲に振りかけています。武骨な雰囲気漂うオリジナルも悪くはないですが、個人的にはこのリミックスに軍配。毎度のことながら、彼の手腕にはさすがとしか言いようがありませんね。オススメ盤です。
80年代初頭のスウェーデンで録音された奇跡のピアノ・トリオ作品。実は何年か前に澤野工房さんから別ジャケでCD再発されていて、以前(1年半くらい前かな)にも一度そちらの盤で紹介したことがあるのですが、今回めでたくオリジナルを手に入れたので再レコメンさせて貰おうと思います。普段ここで紹介しているような60'sのジャズとは少々毛並が違う作品ではあるものの、以前から非常に好きなアルバムなんですよね。「暖かくて柔らかくて美しい」というような形容がとても良く似合う上品な1枚。ある意味では僕が知ってるジャズ作品の中で、最もヨーロッパらしい雰囲気を持ったアルバムかもしれません。今ではハードバップやモーダル・ジャズを中心にジャズを聴いている僕ですが、そもそもヨーロッパのジャズに惹かれていったきっかけって、アメジャズには感じられない、こう言ったエレガントな音色に魅了されていったからなんですよね。A-6のA Cloud In The SkyやB-4のWives And Lovers(バカラック・ナンバー)を筆頭に、全編に渡り本格的に素晴らしい曲に満ち溢れていますが、その極めつけは何と言ってもB-1のSamba For My Friends。かつて一度だけ女性向けに作った自作ミックスCDの一曲目に収録したこの曲は、あまりにも瑞々しすぎる傑作サンバ・ジャズで、澤野工房のホームページの試聴コーナーで触りを聴いた瞬間、そのあまりの気持ちよいメロディーにとんでもない衝撃を受けた作品。音楽の趣味は人それぞれ千差万別ありますが、この曲を嫌いな人って多分この世にいないのではないでしょうか。僕の中では完全に澤野工房クラシック。DJでかけるようなことはおそらくないでしょうが、もしも無人島に持っていくならこういうレコードを選ぶと思います。お洒落な気分に浸りたいOLさんなんかにもオススメ。アナログはレアですが…。
ちょうど2年位前にリリースされたコンピ盤Freedom Jazz Danceに、Was-A-Beeとして参加していたイタリアの男性ヴォーカリストが、このたび前コンピのリリース元と同じSchemaからソロ・デビュー。レーベルのホームページを何気なく見ていても、リリースの随分前から告知をしていたりと、オーナー兼プロデューサーであるLuciano Cantoneの力の入れ込みようが感じられたのですが、事実本国でも売れ行きは好調のようで、先月イタリア国内のみで先行発売されたCDは、既に売り上げが2万枚を突破したとのことです。おそらく日本でもこれから、外資系CDショップなどを中心に猛烈なプロモーションが繰り広げられるのでしょう。Fred Johnsonによる名曲をカヴァーしたA-1のA Child Runs Freeや、パオロ&マルコが手がけたD-1のNever Dieを中心に、おそらくクラブでもヘビープレイされることになるでしょうし、カフェや雑貨屋などのいわゆるお洒落系のスポットではBGMとして重宝されるはず。ただ、僕の評価としては全体的にまずまずと言ったところ。たしかに最近のSchema作品としてはクォリティ高めだとは思いますが、やはり若干のマンネリ感は否めないと言うのが正直な感想です。ただ中には数曲好きなものもあって、例えばB-2のI Can't Keep From Cryin' Sometimeなんかはその例。60'sのヨーロピアン・ジャズ・ワルツそのままのアレンジで、捻りがないと言ってしまえばそれまでですが、僕としては変にクラブサイドにアプローチされるよりは逆にこちらの方が好きです。当時の楽曲に混ぜてDJプレイしても全く違和感がなさそうですしね。そしてもう1曲好きなのはD-2のGig。早くも遅くもない心地良いテンポでスウィングするブルース・ナンバーです。ファブリツィオ・ボッソらの演奏も去ることながら、どことなく込み上げるヴォーカルのメロディー・ラインが非常に僕好みでお気に入り。素敵な夜の終わりを飾るのに相応しい1曲だと思います。おそらくもうしばらくしたら試聴機等にも入ると思うので、興味のある方はそちらでどうぞ。
前作から約1年半ぶりとなるe.s.t.の最新作。このブログをチェックしている人たちにはお馴染みだと思うけれど、一応念のためにもう一度だけ紹介しておくと、彼らはリーダーのEsbjorn Svenssonを中心としたスウェーデンのピアノ・トリオです。最もヨーロッパのコンテンポラリーなピアノ・トリオとは言っても、たとえば澤野工房が発掘してくるような耳障りの良いエレガントなトリオものではなく、その演奏は非常に前衛的な内容なのでご注意を。さて、そんな彼らによる最新作は個人的に今までの彼らの集大成的一枚。これまでも何枚か聴いてきましたが、本作はその中のどれよりも高水準だと思います。とりあえずM-2のタイトル曲が非常に素晴らしい。ピアノ・トリオでの演奏ながら、壮大なスケールと張り詰めた緊張感、そして北欧独特の哀愁を感じさせる演奏に脱帽です。テーマのフレーズも中盤のピアノ・ソロも格好良過ぎ。これまで彼らの最高傑作と思っていたSpam-Boo-Limboを超えた感すらあります。続くM-3のThe Goldhearted Minerもしっとりとした曲調ながら、美しいピアノのフレーズとエレクトロニクスが融合した名曲。軽くボッサなM-6のDolores In A Shoestandや、以前リリースしたSeven Days Fallingを少しアップテンポにしたかのようなM-8のEighthundred Streets By Feet辺りも本当に素敵です。ひょっとしたら今年1番良いアルバムかもしれません。その前衛的なスタイルゆえに誰にでも勧められる類の盤ではありませんが、真の音楽好きならきっとこの素晴らしさが伝わるはず。間違いなく名盤です。
先日ここでも紹介した12インチ、「東京ワルツ」がクラブ界隈でスマッシュ・ヒットとなったホテルニュートーキョーによる待望の1st。ジャケットやタイトルからも分かる通りプログレッシヴな1枚に仕上がっていて、正直なところ僕としては少し意外な感じでした。ただ、だからと言って決して悪いアルバムというわけではなく、むしろ個人的には非常に気に入っている一枚ですね。なんと言うかアコースティックとエレクトリックのバランスが絶妙で、とても洗練された印象を受けます。機械を使った打ち込みサウンドなのに、どことなく生音の優しさも伝わってきて、その辺りの匙加減が非常に上手い一枚と言ったところでしょうか。特にオープニングでもあるM-1のタイトル曲は、エリック・サティのジムノベティあたりを思わせる洗練されたピアノのリフと、ゆるやかに南国の風を運ぶスティール・パンの音色が融合した大人のラウンジ・ミュージック。同タイプの曲だとM-4の空中庭園という曲もなかなか気に入っています。最近いわゆるNu-Jazzと言うと、どれもこれも似たようなサウンドで食傷気味ですが、そんな中にあってこのホテルニュートーキョーのサウンドはかなり好みです。なんと言うかEsbjorn Svensson TrioやChicago Underground Trioにも通じる音響派な雰囲気が良い感じ。決してクラブ向けの曲ではないけれど、たまにはこういう曲に酔うのも悪くないのでは?
一部のマニアの間では微妙に知られている本作は、カナダの女性ジャズ歌手Ginette Renoのライブを、鬼才Michel Legrandが全面的にバックアップした実況録音による一枚。86年と言うかなり新しい年代のレコードながら、その内容はあまりにも素晴らしいビッグバンド・ジャズ・ヴォーカルです。特に見事なまでにルグラン節が炸裂しているA面は、彼の数ある作品の中でもトップクラスにキレたアレンジが抜群。LPに針を落とした後、開始わずか30秒で聴くものを虜にさせる高速ビッグバンドA-1、Quand Ca Balanceがまず鳥肌モノですね。キラキラとめくるめくビッグバンドのアレンジは正に彼の真骨頂と言ったところでしょうか。同タイプながら若干スパイ映画指数が高めなA-3のL'amour En Scieも、ルパンライクな高速4ビートがスリリングなキラー・ナンバー。さらに極めつけはA-2のTo Love。ルグラン自身もヴォーカルで参加しデュエット形式で歌われるこの曲は、なんと「ロシュフォールの恋人たち」のラスト付近で使われていた「夏の日の歌」のセルフカヴァーになっています。おまけに使いにくかったオリジナルに比べ、きちっとしたドラム・ブレイクのイントロが数段DJフレンドリー。もう、この3曲のためだけでも絶対に買ったほうがいい一枚です。カナダ盤オンリーと言うことですが、意外に探せばひょこっと出てきそうなレコードで、値段もそんなには高くないと思います。お洒落系DJはマストですね。オススメ。
最近moderntiquesさんのブログで紹介されていて、気になって購入したのがこの盤。Mike Koskinenという方の曲とスプリットでリイシューされた12インチ盤です。最も僕が聴いているのはもっぱらA面のみなのですけれど…。このリイシューのリリース元となっているJazzpuuは確かフィンランドの再発系レーベルだったと思うのですが、クレジットを見る限り録音自体はストックホルムで行われている模様。Jazz Quintet'60での活動が有名なAllan BotschinskyとNHOP、それから近年Five Corners Quintetにもゲスト参加していたベテラン・サキソニストEero Koivistoinenの参加が目玉でしょうか。75年という微妙な年代とエレピ使いから、全体としてはブラジリアン・フュージョンっぽいアレンジに仕上がってはいますが、各々のソロは相変わらず抜群に格好いいし、曲自体のテンポも高速でノリが良いので、おそらくクラブ・ジャズ好きの方ならばツボだと思います。Boillat=Theraceのハートマークのジャケや、最近では同郷のJukka Eskolaのソロ辺りに近い質感。もしかするとクラブ系のみならずモダン派の方でもいけるかもしれませんね。つい先日されたJudy Bailey Quartet等にも通じる雰囲気かも。リリース自体は微妙に古いのですが、調べてみたところJet Setが最近何枚か仕入れたようです。デッド・ストックでしょうか?まぁ、とりあえず興味があれば騙されたと思って聴いてみてください。
その余りにも挑発的なバンド名が一部筋では有名な、メキシコのジャズ・ファンク~フュージョン・バンドの76年盤。数年前のブリザ・ブラジレイラ・プリモに掲載されていたので、ジャケットに見覚えがある方も多いかもしれません。例によってオリジナルは高価なのですが、メキシコ産のLPということで、値段以前にそもそも市場に出回ることが極めて稀な一枚ですね。それが今回ディスク・ユニオンの企画でCD化と相成ったわけです。もっともこの間のMendez Trio同様に完全な盤起こしなので、CDというフォーマットとは言えど時折気になるノイズは出ますが…。さて、肝心の曲の方ですが基本的には最初にも書いたとおりジャズ・ファンク~フュージョン路線で、スピリチュアルとも取れる側面もちらほら。レア・グルーヴ好きにはこういうのたまらないのでしょうね。そんな中で僕が個人的に気に入っているのはM-5のLa Nina De Los Ojos Verdes。生ピアノではなくローズ使いではありますが、このアルバムの中では最もジャズ度が高い曲で、例えば同時代のMarco Di Marco辺りにも通じるメロウなワルツ・チューン。アメリカやブラジルではなくヨーロッパのジャズに近い質感が好きです。クラブでかけられるような曲ではないけれど、こういう曲は単純に良いですね。ちなみにこの手の企画盤はなくなると探すのが非常に大変になるので、気になる方はあるうちに買いに走りましょう。