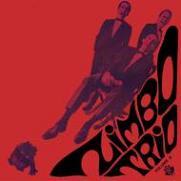深紅のジャケットが美しいジンボ・トリオの66年作。何度か見かけたオリジナルはどれも盤質が悪く、なんとなく購入を控えていたのですが、先日ようやく世界初CD化されましたね。さてさて早速中身の話。まず、帯には「ボサノヴァ黄金時代のジャズ=ジャズ・サンバの代表的ピアノ・トリオ、ジンボ・トリオの最高の1枚がこれ!」などと書かれていますが、個人的にはコレ、どちらかと言えばジャズ・サンバよりもジャズ・ボサの範疇に含まれるのではないかと思います。この辺りの言葉って使う人によって意味が変わってくるので微妙ではありますが、僕の場合だとジャズ・サンバと言うとハードバップ度高めのサウンドを連想してしまうので、そういうのとはちょっと感じが違うかな、と。何と言うか全体的にもっと洗練されたオシャレな雰囲気。ブラジルと言うよりもヨーロッパ、それもドイツ辺りのピアノ・トリオに近い硬質なサウンドが印象的です。イントロ一瞬で優しさに包まれるM-1のKaô, Xangôや、クラシカルなピアノとアフロなビートの好対照が面白いM-2のBocoxeなど、ボサノバ好きはもちろんのこと澤野工房辺りのファンにも気に入って貰えそうな美しい曲がずらり。特にアップ・テンポで演奏されるM-6のSamba Do Veloso(Tempo de Amor)は、間違いなく全編通してのハイライトでしょう。そのあまりに洗練された気高い演奏に、誰もが虜になること請け合いです。またサバービア世代ならば、幻想的なピアノ・ソロで始まるM-10のTristezaもきっと好きなはず。元の曲が良いので、誰がやってもそこそこの内容にはなりますが、数あるカバーの中でもこの演奏はかなりレベルが高い方なのではないでしょうか。ちなみに個人的に気に入っているのはM-7のP'ra Machucar Meu Caração。決して派手な曲ではないものの、アルバム中でも一際センチメンタルかつジャジーな名演で、聴いていて夢見心地にさせてくれる素敵な曲です。今の季節のBGMにも良く似合うのでは。全体的にクラブと言うより部屋聴き用の一枚。まさにAt The Living Roomな雰囲気ですね。なお、静かな曲が多くノイズが入ると成立しないので、盤質の悪いオリジナルよりもCDでの購入をオススメします。
ピアニストのファッツ・エルピディオやテナーのアウリーニョらで構成された、その名もSexteto De Jazz Modernoが63年にRCA Victorからリリースした一枚。調べても出てこなかったので詳細は分かりませんが、この名義でのリリースはおそらく本作のみだと思います。ハウルジーニョやコブラス、それからマシャードらによる諸作のような派手さはないものの、一連のジャズ・サンバの中でも際立ってジャズ度の高い隠れ名盤…というかリズム隊以外は、ほぼジャズと思って頂いても結構です。また収録曲が片面3曲ずつと、比較的ソロが長めの尺となっているのも特徴的。どこか洗練された端正な演奏は、ヨーロッパのジャズなどにも通じるところがあるのではないでしょうか。冒頭A-1に収録されたSamba De Uma Nota Só(One Note Samba)がまず最高。カツカツ打ち込むサンバ・ビートと2管フロントが印象的なミッド・テンポのジャズ・サンバです。続くA-2のBarquinhoやB-1のDesafinadoも同タイプ。どことなくバッソ=ヴァルダンブリーニらが演じたBossa Novaにも通じる「大人の余裕」的サウンドがとてもお洒落ですね。個人的にこういう雰囲気は大好きで、最近は良く似たような盤を探しているのですが、まさか本家ブラジルでここまでの洗練さを持った演奏があるとは思いませんでした。これぞ正に「灯台もと暗し」といったところでしょうか。そして絶対の名曲はラストB-3のLamento。若干スパニッシュ調のメランコリックなジャズ・サンバで、哀愁溢れまくりのメロディーが溜まりません。キャノンボール&セルメンのGroovy Sambaをもう少しアダルトにしたような珠玉の一曲です。ソロも各々水準高めなのですが、特にソロ2番手を務めるアルトのジョルジーニョによるプレイが神がかり的。僕のツボのど真ん中のメロディーです。なお、ヨーロッパではわりと人気があるようで、価格的にもそこそこの値が付いているようですが、日本では一部マニアを除き知られていないレコードなので、もしも見つけられたら安いかも。ちなみに今までBossa Novaというタイトルのアルバムは外れたことが一度もありません。絶対のオススメ盤です。
70年代にMPBシンガーとして一躍人気者になるエリアナ・ピットマンが、その音楽活動の最初期に吹き込んだ一枚。正確なリリース時期はクレジットされていないため不明ですが、おそらく60年代前半の作品だと思います。一応サックス奏者の父ブッカーと共作扱いになっているものの、基本はエリアナ嬢のヴォーカル・ワークにスポットを当てた構成になっているので、実質的にはエリアナのソロ作と言ってしまっても差し支えないかもしれません。ちなみにバックを務めるのはタンバ・トリオ。この手の作品としては古くから世界的に人気のある一枚です。先日ニコラ・コンテが某誌でリコメンドしていたのも記憶に新しいところですね。オリジナルのアナログは非常にレアかつ高額な盤として有名ですが、実は昨年辺りにParadise MastersからこっそりCD化済み。ようやく誰でも普通に聴ける盤となりました。さて、そんな曰くつきの本作。肝心の内容の方はと言うと、タンバ参加と言うこともあり、(良い意味で)やや土っぽさの残るボサノバ~ジャズ・サンバ作品になっています。収録曲中、ジャズ方面から圧倒的に人気なのは、親子で歌うバピッシュなA-2のIt Don't Mean A Thing。ただ、実は意外にその他の曲もなかなか良かったりするので侮れません。特に気に入っているのはA-3のAmor SincopadoとB-2のVens SÓ辺り。どちらもCafe Apres-Midi直系のお洒落なボサノバで、聴いているとついつい苦いコーヒーを飲みたくなる佳曲です。特に後者はパーカッシヴなビートに乗る儚げなヴォーカルが素晴らしく、何となく物悲しい気分になる今の時期のBGMにも良いのではないでしょうか。なお、エリアナ嬢が参加していないインスト作品も幾つか収録されていて、それらの中での個人的ベストはB-6のFesta Na Floresta。イントロ数秒で室内がサウダージ感に包まれるインストゥルメンタル・ボサの名演です。こういう曲、クラブではかけられないかもしれませんが、秋の夜長の部屋聴きという意味では非常に適しているのではないでしょうか。It Don't~のキラーな魅力はもちろん否定しませんが、全体通じて部屋聴きにオススメの一枚。気になる方は廃盤になる前にどうぞ。
もう1枚続けてブラジル盤から紹介。Skindôs Ritmicosなる人物が率いるMr.Samba Bossa Novaなる謎のバンドがRGEからリリースしたEPです。おそらく60年代に吹き込まれたものだと思いますが、録音に至る経緯や他の参加メンバーはクレジットされていないので分かりません。ただ同じくRGEからLPが1枚出ているようで、本作はそこからのシングル・カットということになるそうです。あまりにも安直なコンボ名とは裏腹に演奏自体は非常にレベルが高く、収録された4曲全てがクラブ対応のハード・ジャズ・サンバ。Premium Cutsの鈴木氏も書いていましたが、フロントが2管編成だということも含めて、テイスト的にはルイス・ボンファのBossa Nova+5にかなり似た感じですね。単純に「踊れる」という意味では、むしろこちらの方がレベルが高いかもしれません。どこか怪しげでエキゾチックな雰囲気を醸し出すA-1のConfidênciaがまず最高。ヴィオランと言うよりスパニッシュ・ギターと表現した方がしっくり来る中盤のアコギ・ソロが素晴らしいです。ギロ(だと思います)を加えたリズム隊のキレ具合も絶妙。この辺のラテン・パーカス交じりの高速ビートは、クラブ世代ならば誰しも好きなのではないでしょうか。続くA-2のSamba Do Orfeu(オルフェのサンバ)はピアノの音色が程よいアクセントな名演。こちらもやはりリズム隊がかなり良い仕事しています。レコードを裏返したB-1のChorando Chorandoは、収録曲中で最もパーカッシヴなナンバー。まるでリオのカーニバルを思わせる楽しげな演奏が気持ち良いですね。ラストB-2のBatucadaはメイレレース辺りにも近いオーソドックスなハード・サンバ。フィル・ムーアで有名なあの曲とは同名異曲ですが、ハードバップの影響をガンガンに受けたアレンジで格好良く聴かせます。全曲通じて言えることですが、ソロをたっぷりと聞かせるようなタイプのプレイではなく、テーマのアンサンブルを重視した短尺な曲構成になっているので、その辺りもDJフレンドリーなのではないでしょうか。しかし、これだけの素晴らしい演奏を聞かせる彼ら。どう考えても無名のアーティストではないと思うのですが…。もしも詳細を知っている方がいたら教えてください。
サンサ・トリオの中心的存在であったホセ・ブリアモンチによる68年作。一応リリースはRCAというメジャー畑からですが、あまり見る機会のない一枚なのではないでしょうか。なお、トリオではなく11名というやや大きめの編成での作品で、わりと寛いだ雰囲気の上品なジャズ・ボッサをやっています。ジャケット写真そのままのお洒落サウンドと言ったところ。ちなみに、参加しているのはわりと有名な人なのかもしれませんが、僕が知っているのはトロンボーンのハウルジーニョくらいでした。ヴォーカルとインストが半々くらいの割合で収録されていて、僕が気に入っているのはインストの方。中でもA-4のThe World Goes Onは本作屈指のハイライトだと思います。決して派手な楽曲ではないですが上手く纏まったジャズ・ボッサで、軽快な二管フロントとブリアモンチのピアノ、そして哀愁溢れるヴィオランの音色が良い感じ。また、若干テイストは違うもののB-1のMr.Kingもなかなかの佳曲に仕上がっています。楽しい演奏の中に秘められた儚さがたまらなくサウダージ。普段あまりきちんとしたボサノバを聴かないので、それほど「サウダージ」という感覚に包まれることはないのですが、これはやはりこの言葉でしか表現できない独特の感覚ですね。ルグランのカヴァーになるB-3のWatch What Happensは洒落たヴァイブの音色も素敵なミッド・テンポのボサノバ。聴いていると自然と優しい気持ちになれそうな良い演奏です。それからヴォーカルものでは個人的にA-5のCanto Pra' Amadaがベスト。こちらもブリアモンチのピアノが美しい軽快な曲ですが、ビート的にはしっかり打ってるので使い方次第ではクラブ・プレイも行けるような気がします。と言うか、もしも僕がDJをするなら是非かけてみたいナンバー。夕暮れのカフェなんかにもぴったり合いそうですね。この手のブラジルものの中でもわりとレアな部類に入るレコードだと思いますが、お洒落系の音楽が好きな人には是非聴いてみてもらいたい一枚です。ちょこんと体育座りで腰掛けるジャケットも微かにヨーロッパの香りがしてグッド。ちなみにニコラ・コンテもフェイバリットに挙げてるそうですよ。オススメ盤です。
数多く存在するジャズ・ボサ・ピアニストの中でも、玄人筋からプレイに定評のあるという話のペドリーニョ・マタールが(おそらく)60年代に残した1枚が本作。例によって専門外のため詳細は分かりませんが、聴いた話では彼が残した作品で正統派ジャズ・サンバと呼べるのはこれだけなのだとか。ちなみにリリースは、ジョンゴ・トリオなどでも知られるFarroupilhaレーベルから。複雑なアレンジが施された曲ばかりのため、クラブ的にはやや使いにくいかもしれませんが、その変わりに勢いのあるスリリングな楽曲が一際多く収録されているので、技巧派ピアノを思う存分楽しみたいというような人には打ってつけかもしれません。特にA-1のNeuróticoやA-3のZéro Horaなど、ある意味アブストラクト的とも言える高速ジャズ・サンバ群は、ブロークン・ビーツを通過した現代の耳で聞いても面白いですね。また、A-6のQuem é Homem Náo ChóraやB-2のBalansambaは、テンポこそ速いものの演奏自体はジャズ・ボサ風。イメージとしては、ミルトン・バナナをもう少しハードにした感じとでも言ったところでしょうか。こちらもこちらでなかなか良い感じです。ただ、僕のお気に入りは例によって若干テンポ遅めのキレイな曲。A-4のInútil PaisagemやB-4のPreciso Aprender a Ser Sóのような曲がやっぱりツボですね。どちらも例えば夜景が綺麗なバーのBGMなどに似合う幻想的な曲で、ひんやりと硬質なピアノがムード満点の好演に仕上がっています。甘さのないドライなタッチが都会的。こんなの聴きながらキリっとした白ワインを飲んだら美味しそうですね。B-6でラストを飾るのはアフロな雰囲気漂うジャズ・サンバのBalaiubá Xangô。やはりアレンジは複雑ですが、どことなく壮大な雰囲気がなかなかにグッドです。と言うか全体的にレベルは相当高め。ジャズ・サンバのトリオものはそれほど聴きこんでないので何とも言えませんが、アルバム全体の雰囲気と言う意味では、少なくともこれまで聴いてきたジャズ・サンバ盤の中で一番夜を感じさせる作品でした。特別なキラー曲こそないものの、飽きずに何度も繰り返し聴けそうなアルバム。たまにはこういうのも良いかもしれませんね。
ブラジルの名ピアニスト兼アレンジャーであるアントニオ・アドルフォが64年にリリースした一枚。3D名義でのデビュー作に当たるのがこれです。以前、この翌年に録音されたO-Trio 3D名義でのConvidaというアルバムを紹介したことがありますが、こちらの1stもなかなかの好内容。ゲストとして参加した管楽器陣にスポットを当てた次作とは異なり、当時まだ17歳という若さだったアドルフォのピアノ演奏を存分に楽しめる1枚になっている点がポイントでしょうか。M-1のConsolacaçáoはこの辺りのジャズ・サンバ・トリオでは定番曲。もともとの曲が良いために悪くなりようがないのですが、本作でも勢いあるドラミングに乗せて猛々しくドライブするアドルフォが魅力的な快演になっています。同系統ではジョニー・アルフ作のM-3、Céu E Mar辺りも良い感じ。また、ミッド・テンポで軽快に跳ねるジャズ・ボサ風なM-5のSamba Do Somや、リラックスしたムードで演奏されるM-7のタイトル曲なども水準が高く、いくら若いとは言えハードなジャズ・サンバ一辺倒に陥っていないところも好みです。何よりのお気に入りは、ベースのカチョが渋いヴォーカルを取るM-10のFly Me To The Moon。あえてボサノバのリズムを用いず、ワルツと4ビートを採用したジャジーなアレンジがグッドですね。アドルフォの洒落たピアノ・タッチとカチョのヘタウマなヴォーカルが相まって、夜感と切なさ漂う大人な雰囲気になっているので、これからの人恋しい季節のBGMにも丁度良いのではないでしょうか。おそらく正統派のジャズ好きでも行けるはず。と、言うより僕は初めて聴いたとき、これがブラジル産とは全く気付かず、勝手にスペイン辺りのヴォーカルものかと思っていました。ちなみにアナログはまだそれなりの価格がするようですが、何年か前にサバービア企画で発売された国内盤CDならば、わりと容易に手に入れることが出来ると思います。少なくともブラジル本国で発売されたCDの廃盤を探すよりは遥かに楽。個人的にはブラジルものに興味のない人でも、このFly Me To The Moon名カヴァーのためだけにでも聴いてみて貰いたいアルバムです。もちろんジャズ・サンバ・ファンなら他の曲も必聴ですが…(笑) ヒップなジャケットも素晴らしい名盤。オススメです。
少し久しぶりにブラジル方面の盤から紹介。50年代後半に15歳という若さでデビューし、リオのベッコ・ダス・ガハーファスでも活動していた女性ヴォーカリストが、66年にツアー先のメキシコで残したのが本作です。たしか本国ブラジルではリリースされていなかったと思うので、おそらくメキシコ・オンリーの音源だったはず。同じくブラジル出身のヴァイブ奏者ブレーノ・サウエルを中心としたカルテットをバックに従え、全編に渡りジャズ度高めの寛いだボサノバをやっています。この辺りの音楽は専門じゃないので良く分かりませんが、M-2のCanto De Chegarのような、タンバ・トリオにも通じるジャズ・サンバ系ナンバーが、その道ではわりと人気ナンバーなのではないでしょうか。可愛らしいピアノのイントロで始まり、中盤で怒涛のような高速スキャットに突入するM-4のEstamos Aí辺りも、好きな人には堪らないのでしょうね。ただ、僕個人としてはそうしたアップテンポなナンバーより、実はしっとりとした雰囲気の曲が気に入っていて、特にM-5のNoite Do Meu Bemが大の好み。繊細なピアノに導かれる美しい曲で、どことなくヨーロッパのジャズ、それもEP盤オンリーの激レア盤を思わせる洒落たアレンジが憎い一曲です。中盤以降カツカツと入ってくるドラミングも小気味良く、夜ジャズならぬ夜ボサな名演と呼べるのではないでしょうか。同系統ではM-9のÉ De Manhá~Menino Das Laranjas(2曲のメドレーです)も良い感じ。ちなみにメキシコ・オンリー音源ということもあって、アナログは非常に高額な上、まず見つからない一枚です。少し前にDisk Unionの企画で紙ジャケCD化されたので、素直にそちらを買った方が良いのではないかと。あからさまな盤起こしで若干音質に難はありますが、多分オリジナルを手に入れてもこれくらいのノイズは入るはず。まぁモノがモノだけに許容範囲でしょう。なお、この間のGroove誌でニコラ・コンテが紹介してたレコードのうちの一枚でもありますね。CDの方もいつ市場から消えるか分からないので、もし気になる方は出来るだけお早めの購入をオススメします。
夏の終わりにぴったりな洒落たジャズ・サンバの小品集。ヴァイブとヴィオラン(ガット・ギター)を含む5人組による本作は、64年にMusidiscというレーベルからリリースされたアルバムで、おそらく彼らの唯一のアルバムと思われます。周知の通りこの時代のブラジルにはジャズ・サンバ系グループが多々ありますが、本作のようにヴィブラフォンがリードを取る作品は珍しく、そう言った意味ではわりと貴重な存在なのかも。例のOs Cobrasなどと異なり豪快なホーンがいないため、それほど派手な曲が入っているわけではありませんが、曲調的にもハードな曲ありソフトな曲あり、聴いてて飽きの来ない隠れ名盤なのではないかと思います。DJの方々に人気が高そうなのはB-3のQuintessência。前述Os Cobrasやメイレレースの演奏でジャズ系DJに良く知られた曲ですが、ここではホーンの代わりにヴァイブをリードに用い軽快にカヴァーしていて良い感じです。同じようなハード路線だと、カツカツ打ち込むビートと中盤のワルツへの転調が素晴らしいB-4のDetalhe Do Sambaあたりもなかなか。ただ個人的にはどちらかというとソフト路線の方が好きで、中でもA-4のMoça Do Biquini Azulが一番のお気に入り。ゆったりとしたリズムに上品なヴァイブが転がる洒落た曲で、まるで夏の終わりを思わせるようなセンチメンタルな雰囲気が今の季節に良く似合います。どことなくG/9 Groupを思わせるB-1のTema Felizも最高。可愛らしいヴァイブの音はもちろんですが、IQ高めのピアノがまた気持ち良く、日に焼けた体をそっとクール・ダウンしてくれるような素敵な一枚。オリジナルはそこそこ高価ですが、英whatmusicからCD/LP共に再発されているので、興味がある方はそちらからどうぞ。女の子にもオススメのアルバムです。
久しぶりに和モノのレコードを買ったので紹介。タイトルが少し長過ぎて上に入り切りませんでしたが、「ボサノバ・スタンダード・デラックス」と言う沢田駿吾のLPです。但しこれは70年代の2ndプレス。タイトルとジャケットが変わっているので分かりにくいですが、67年にリリースされた「決定盤!これぞボサ・ノバ」というレコードが本作のオリジナルになります。最近こちらのオリジナル仕様でThinkからCD化もされたので、もしかするとタイトルに見覚えのある人もいるかもしれませんね。さて、そんな本作。オリジナル・2nd共に「いかにも」なジャケットとタイトル、そしてスタンダード中心の収録曲から、つい安易なイージー・リスニング作品を連想してしまいがちですが、これが意外にもジャズ・マナーに則った大人のボサノバ作品となっているので侮れません。中でも白眉はB-2のFly Me To The Moon。自身のレギュラー・カルテットに宮沢昭のフルートを加え、サヒブ・シハブのシャレードを思わせるアレンジで演奏しています。あそこまで武骨な演奏ではないものの、編成的に似通っていることもあり、雰囲気はわりと近いのではないでしょうか。少なくとも僕は、一聴してすぐにサヒブを連想しました。西条孝之助のテナーと宮沢のフルートによる二管の絡みが美しいA-3のDesafinadoも名演。いわゆるハードバップ的な演奏ではないですが、華やいだ夜の雰囲気が良く出ていて、個人的に気に入っています。フロア受けが良さそうなのはB-6に収録された高速ボサジャズのCinnamon And Clove。スパイ映画のテーマのようなスリリングな演奏と、伊集加代子のスキャットが良く合っていて格好いいですね。その他の曲も全体的に雰囲気良いし、あまり和モノっぽさもないので、日本人の演奏に抵抗がある人でもわりと普通に聴けるはず。どちらかと言うとボサノバ好きよりジャズ好き向けという気はしますが、興味があったら是非聴いてみてください。オススメです。