本が好き!な、りなっこのダイアリーです。週末は旦那と食べ歩き。そちらの報告も。
本読みの日々つらつら
梨木香歩さん、『村田エフェンディ滞土録』
『村田エフェンディ滞土録』、梨木香歩を読みました。 
“――そういう世界、知らなくもないけど。あまりにも幼稚だわ。分かるとこだけきちんとお片付けしましょう。あとの厖大な闇はないことにしましょう、という、そういうことよ。” 182頁
苦しいくらい、胸を鷲掴みにされた。物語の舞台は1899年、村田くんの留学先トルコの首都スタンブールである。素直で謙虚な村田くんを取り巻くのは、下宿先のしたたかな鸚鵡や異国の友人たち。そして彼のことをエフェンディ(学問を修めた人物に対する敬称)と呼ぶ、頼もしいムハンマドとディクソン夫人。ともに異国から日本を眺め、志しを確かめ合う同国の友たちだ。
沢山の人たちの考えに触れ、素直に吸収し、いつも謙虚に健やかに思索していく村田くんは、何て言いますか…本当に愛すべき若者です。「鸚鵡に頭が上がらない」などとぼやく姿は、とても微笑ましい。
梨木さんの作品を読んでいるとしばしば、頭が自ずと垂れてくるのです。すごく大切なことがそこに書かれている気がして、居ずまいを正して心を澄まします。もっと凛としよう…と。物語の中に溢れる優しさと厳しさに、胸をうたれます。
遺物の寄せ集めのような建物である下宿先では、互いに異郷の神々たちが小さな喧嘩をします。そんな大らかさも好きです。
そして天才的鸚鵡の存在が、最高です! 素晴らしい!
(2007.5.31)
清水博子さん、『街の座標』
『街の座標』、清水博子を読みました。
“気の重い卒論の題材がすぐそこで日々生産されているのだという事実に、あたまがくらくらして、男にあたりちらしたおぼえがある。近くて明確な距離を介したそこに小説家が居るとも知らずのらりくらりと過してきた時間が、とりかえしのつかない過去として現実に迫り、生活というものにたいしてあらためていくぶん悲観的になったのだ。” 4頁
いったい何なのですかこりは…と、途方に暮れそうなくらい面白かったです。処女作でこの筆力というのも凄いし、エキセントリックさの方向が私の好みすれすれで、そのすれすれ感が堪らなかったです。あともう少しグロだったら放り出す…ていう縁のところを、確信犯的に触られまくったような感じ。
えええ、女の生理をそんな風に描いちゃうの…?とか、かなり生っぽい感覚に晒されたりする一方では、一つ一つの文章が長くてしかも漢字でみっちりしているので、読んでいてその妙なバランスについていけなくて眩暈がする。誰かの作風を彷彿させるなぁ…て、金井美恵子さん。読めば納得です。
“橄欖”をオリーブと読ませているところでは、ルビ好きな私のツボ。言葉遣いも心憎し。
私は卒論の締め切り前1週間を切った頃に高熱を出して寝込んだという経験があり、文字通り熱に浮かされた焦燥感故に忘れがたき思い出です。で、その所為でしょうか…“文学部の卒論”という言葉を見ただけで、ざわざわと胸騒ぎを覚えます。でもこの設定は凄い。凄過ぎる。
同時代の、しかも一冊しか作品を読んでいない作家を卒論に選ぶって、どうなのだろう…。執着があるのかないのかわけがわからない。
ひょんなことからひょんひょんと、主人公と作家の間の距離が異様にリアルに詰められていく展開にも吃驚。もしもそんな目にあったら誰でもパニクったりストーカー化したりするのかなぁ(いや、しないか)。その過程と詳細が面白く、目が離せませんでした。
読み手と書き手の間にあるべき距離、作家の文学性と私生活の間にあるはずの乖離。それを逆手に取ったような作品で、あたしゃやられましたよ。
(2007.5.29)
津原泰水さん、『蘆屋家の崩壊』
本の中で愛好の士に出会って、うひょっと反応してしまいました。旨い豆腐を食うためならば、どこにでも遠征する二人…とな。
『蘆屋家の崩壊』、津原泰水を読みました。
短篇集と言いますか、連作集でした。
冒頭からずいずいと引き込まれて(“隧道”だけに)読み進み、一話目の「反曲隧道」をラストまで読んで、しまったホラーだったのか…と少々腰が退けそうになりましたが、やっぱり面白くてそのままずいずい読んでいました。
所謂ホラーではないのですね。幻想怪奇?ちょっと妖怪? 私には馴染みやすかったですが…。例えば女性が同性として残酷に女を描くのと、男性が異性として残酷に女を描くのとでは、やはり全然違うなぁ…と思い、なかなか興味深かったです。女は女を美化しませんから。
いやううむ、面白かった。程よいペダントリーが織り込まれた諧謔混じりな地の文には、時々くすっ…と笑いがこぼれました。とりわけ「猫背の女」の中の“カチカチ山考”なんて、個人的にはその場でバタ足をしてしまいそうなくらい愉快でした。
もちろんストーリーも堪能しましたし、伯爵と猿渡のとぼけたコンビぶりも可笑しくて、時間を忘れていました。どの話がお気に入りかな?としばし考えてみましたが、なかなか絞れません。「猫背の女」や 「カルキノス」の嗤い、「埋葬虫」の異様美、「水牛群」の幻想美…。「ケルベロス 」はラストが…何だか怖かったのですけれど。
それにしても、豆腐竹輪とか豆腐羹なんて名前がずらずらと出てくる箇所を読むと、ついつい嬉しくて「私も食べたことある~」とか「私のお薦めは燻製豆腐だよ~」などと一人で呟いていたのでありました。
(2007.5.24)
皆川博子さん、『聖女の島』
『聖女の島』、皆川博子を読みました。
“だって、何もかも、元のとおりにしたところから、やり直さなくてはいけませんもの。” 44頁
一目表紙を見てかなりぶっ飛びました(しかもこれは誰…)。物語の舞台となる孤島は、軍艦島がモデルだそうです。
廃墟の中の迷路のような道には、有刺鉄線をからませて作った通行止めがある。廃墟の中に閉じ込められ、大人たちに管理される少女たちの、狂い咲きを強いられて花開いたような早熟で不吉な美しさ。塩に侵され破壊された廃墟と、蕾をこじ開けられた少女たちという、取りあわせの妙とその美意識にしびれます。
妖しく小昏い閉ざされた世界、しのびよりたたみかけてくる悪夢の幻影。なんて巧みに独特な世界をつくり上げてしまうことか…!と、思わず舌をぐるぐる巻く。そうして謎も、ぐるぐる…。大人対子供の水面下における対立。偽善と欺瞞の象徴のような偽家族の存在も、表面上は従順な少女たちの不気味な団結も、いつの間にかザラリとした不穏な感触を伴って、ピタリと読み手に寄り添い取り込んでしまおうとばかりに迫ってきます。おお。
そして、衝撃のラストの素晴らしさと言ったら! 読みようによっては凄く怖くて、ぞうっと背筋が冷たくなります。読みようによってはとても哀しくて、やり切れない読後感に陥ってしまいます。しばし双方の間を揺らいでから、その哀しい…の方に傾いてしまった私は、廃墟の崖から突き落とされたような具合でした。そ、そんなぁ…と。
でもやっぱり、ラストが凄い。もっかい頭に戻って、最初から読み直したくなるくらい。
前半は園長に請われておとずれた修道女、後半は園長藍子の視点で語られています。タイトルの痛烈さが秀逸。
(2007.5.23)
清水博子さん、『vanity』
『vanity ヴァニティ』、清水博子を読みました。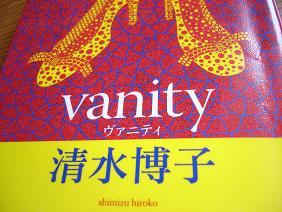
“芦屋川と芦屋のちがい、西宮北口と西ノ宮と西宮のちがい、宝塚と宝塚南口のちがい、甲子園と甲東園を甲陽園と香枦園のちがいを、電鉄会社のちがいとしてしかまだ把握できない。” 35頁
ひょんなことから恋人の実家に住むことになった主人公の画子。一応婚約者候補としての居候なのだが、その恋人の母親は“マダム”としか呼びようがない人物である。対する画子は、上流の奥様なんぞに飼い慣らされるまい…としているかのように見せかけて、実は飼い慣らされるだけの素質さえ持ち合わせてはいない。自分の稼いだお金で気ままな買い物をすることが大好きな、東京の外資系のOLさんである。他愛もない。
関東の直截な感覚と、関西の澱んだ美意識。平行線を辿りながらも一緒に暮していくうちに、時々妙なところで波長が合っていく二人のやりとりが可笑しかった。バトルをしていても時に頓珍漢で、高飛車なマダムさえだんだん憎めなくなっていく。そうだよなぁ、本物のマダムが相手じゃあ、揶揄する気力も萎えるわいなぁ…。
虚栄心は誰にでもある訳だけれど、退きかえしどころはわきまえておきたいものだ。とりわけ富む者とそうでない者とが蔑みあうことは、あまりにも安易でありましょう。…とは言え、「いかり」スーパーでお買い物をすると必ず5桁以内に収まらない(二人分なのに!)なんて話には、私も鼻を鳴らしたくなりましたが。あいや、「いかり」スーパーは好きです。お惣菜とか美味しい。
この作品は、表紙がすっごく好き。草間彌生さんの水玉ハイヒール、いとかわゆし。
(2007.5.22)
服部まゆみさん、『レオナルドのユダ』
『レオナルドのユダ』、服部まゆみを読みました。
“「そのままでは飛ばない」と彼は悪戯を始めようとする悪童のような笑顔を見せ、空に指を向けた。遥か水田の上空に、蛙でも見つけたのか鳶が旋回していた。「あの形ですよ」と言い、また葉を差し出した。”
“ 彼の真似をして僕らは毎回「飛ぶぞ(ヴオラ)!」と叫んで飛ばした。「飛ぶぞ!」「飛ぶぞ! 飛ぶぞ!」「さあ飛ぶぞ!」「さあ飛ぶぞ!」――そして飛んでいるような気分になった。” 23頁
この物語は、二人の人物の一人称によって語られています。フランチェスコの弟の乳母の息子で、フランチェスコの従僕になるジャンと、レオナルドに私怨を持つ毒舌の人文学者パーオロです。人々の賛辞と崇敬の中、神々しい光をあびてすっくりと立っているのがレオナルドならば、その光が生んだ闇の中で憎悪や嫉妬に苛まれる立場にいるのが彼らです。
そしてそんな二人の存在こそが、天才レオナルドの魅力や才能を際立たせていくという、何とも皮肉な構成となっています。あたかも、一人の天才の影に隠れる数多の凡人たち…の略図のようです。
才能と人格は全く別物だと私も思うけれども、正直なところレオナルド・ダ・ヴィンチはやはり、直接描くには大物過ぎるような気がしてしまいます。この物語の中でレオナルドが直接描かれている箇所は意外にもそれ程多くなく、しかもその少ない箇所がとても印象的な場面ばかりなので物足りなくもなく、なかなか巧みな方法だなぁ…と感じ入りました。
特にフランチェスコとジャンが、レオナルドに初めて出会う場面が忘れがたいです。この物語の中ではとりわけ、レオナルドの自然を愛してやまない姿がよく写されていました。まさに一幅の絵のように素敵でした。
文庫版あとがきによると、大幅な改訂がされているそうです。実は物語の途中までは、他の服部さんの作品ほどには楽しめなかったのですが、後半の展開が私にはよかったです。満喫いたしました。
一閃のような強い光と、長く尾をひく深い闇。一人の天才を語り継ぐものたちの物語。
(2007.5.21)
佐藤亜紀さん、『ミノタウロス』
『ミノタウロス』、佐藤亜紀を読みました。
“人間を人間の格好のままにさせておくものが何か、ぼくは時々考えることがあった。”
“それをひとつずつ剥ぎ取られ、最後のひとつを自分で引き剥がした後も、ぼくは人間のふりをして立っていた。” 269頁
いっきに読みました。
第一次世界大戦から内戦時の、ロシア・ウクライナが物語の舞台となっています。内戦に侵された大地、無法地帯と化した町や村々を駆け抜けていくミノタウロスの子ら。感傷を撥ねつける強靭な文体が描き出すのは、命を投げ出したごろつきどもの賭場であり、倫理が全く無力化された弱肉強食のケダモノたちの荒野である…。
心ゆくまで圧倒されました。これほどまでにきつい小説には、なかなか出会えません。
(2007.5.16)
中島京子さん、『FUTON』
読んでみたいと思っていた矢先の文庫化だった。
『FUTON』、中島京子を読みました。
まず『蒲団』の主人公竹中時雄の妻の視点から、アメリカの日本文学者の手によってあらたに書き直された「蒲団の打ち直し」が作中作としてあるのですが、この小説の存在が秀逸でした。絶妙な按配の絡みが堪らない。内と外とが二重写しのようになっていく滑稽さと、主人公たちの格好悪さの中のそこはかとない悲哀と、両方がとても巧みに響き合っています。所謂プロットなるものもしっかりと打ち立てられているのでしょう。これで処女作だというのだから、凄いです。
田山花袋の『蒲団』と言われても、未読の私が思い出せる情報はあまりなくて、「あー、あのモデル問題の。私小説のはしりの…」と、中途半端な記憶の切れ端しかなかったのですが(へなちょこ)、高校の現代国語の担当教師がそのあらすじを、かなり面白おかしく端折って教えてくれたことを憶えています(そういうところだけ記憶力がいい)。その時はちょっと笑いつつ、一生読まないかも…と聞き流していました。こんなに時を経てから、このような形で出会えようとは…。
田山花袋の『蒲団』には興味がなくても、読んでみる気がなくても、この作品の旨味を堪能するには差し支えないかと思います。いやむしろ、『蒲団』って案外面白そうかも…と、興味が湧いてしまうことならあり得ます。きっと、『蒲団』の持つ滑稽さの中の魅力を引き出すことに成功しているのが、この『FUTON』という作品なのでしょうから。
作中作「蒲団の打ち直し」は、そもそもどんな経緯で書かれることになったのでしょうか? うふふ。
終わりがけに近付くと、ほのぼのとした気持ちになれます。私はタツゾウ親父とイズミさんがお気に入りでした。
(2007.5.15)
アントニオ・タブッキ、『インド夜想曲』
須賀敦子さんの訳、タブッキ2冊目。
『インド夜想曲』、アントニオ・タブッキを読みました。
“これは、不眠の本であるだけでなく、旅の本である。不眠はこの本を書いた人間に属し、旅行は旅をした人間に属している。” 「はじめに」より
失踪した友人シャヴィエルを探してインドを旅する主人公。その行く先々で繰り広げられるのは、インドを物語りインドを映すエピソードの数々です。
それぞれに別々の物語に繋がっていきそうなエピソードを、其処此処に惜しげなくとり残していく贅沢さが堪りませんでした。忘れ物をした女泥棒や、猿に見紛う青年占い師。そしてほころびからほろほろと零れるのは、インドの抱えた静かな哀しみです。深い深い時間の澱…。もっと幻想的な描き方をされているのかと思っていた私に、突きつけられるインドの姿。たとえば、病人のしもの世話をする階級のアンタッチャブル。
だが、そうは言っても決して暗い内容ではない。読み手を突き放してくれている、乾いた軽やかさが心地よい。
シャヴィエルがインドで何をしていたのか、なぜ失踪したのか、今はどこにいるのか――。なかなか見えてこない失踪の謎は、まるでミステリのようなお膳立てですが、ふと射す昼の光の中で、いつしか結果と原因が暗転するような、追うものと追われる者の立場が暗転するような、そんな目くらましに出くわしてしまった…。
(2007.5.10)
富岡多恵子さん、『水上庭園』
『水上庭園』、富岡多恵子を読みました。
“ところが、わたしには、理詰めもないかわりにロマンティシズムもありません。ドイツで幾日かEと過しているのは、現世での偶然の出来事にすぎないと思っており、この偶然に、わたしは深く感動しているのです。そういう偶然をのがさず味わいたいとドイツにやってきたのです。夫と暮しているのも偶然です。夫といる日々には、たまたまEが不在なだけです。わたしは、イキモノのなかでことに人間は生れないのがもっともいいと思っていますので、生れてしまった人間はカワイソーな存在だと思っています。こういうことを、Eにどのように説明したらいいのかわかりません。” 205頁
富岡さんの作品はまだあまり読めていないけれど、恬淡とした文体や絶妙な枯れ具合、すこぶる渋い作風が好きです。
恋…とも決め付けられない20年越しの思いを、何故か繋ぎ続け合ってしまった男女が再会を果たしてからの、表面上はあくまでもあわあわとした交流。熱くなることもなく、さりとて執着がないこともない。言葉では上手く説明の付かない、つたない英語を介した二人だけの静かな関係。ゆるりゆるりとした時間に沈み込むような具合になりながら、確かにお互いの魂をゆきかう深い共感に、言葉少なに身を浸す二人。たとえ一歩踏み込もうとしても、どうしても言葉の壁にぶつかることを先に知っている二人の不思議な絆には、何と名づけることも出来やしないのです。
そんな二人の物語に挿入されているのが、Eがかつて彼女に送り続けた書簡の文面でした。20年前の初々しさとひた向きな言葉が詰まった、性急な思いがるる綴られた手紙の数々。決して埋めることの出来ない20年という時間の流れを越えて、22歳のドイツ青年Eの声を運んでくる…。
ほんのりと優しくてさびしいラストが、好きでした。二人の間にあったものは、結局何だったのだろう…?と、しばしもの思いに耽ってしまいます。飾り立てない描き方だからこそ、後ろ髪をひかれる。
(2007.5.8)
| « 前ページ |






