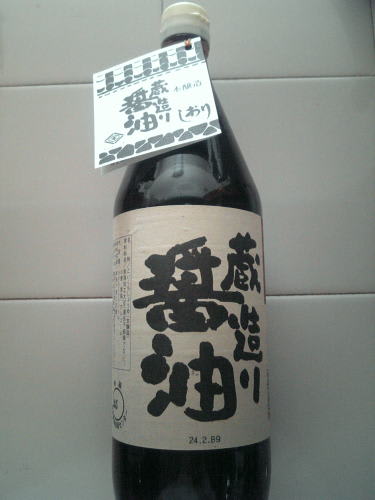染めの道具は洗濯鋏、大小のビー玉、品質切れの小豆、フイルムケース、クリップに箸まである箱本館「紺屋」。
それは多彩なものでいかように使っても構わない。
創造力を膨らませて白いTシャツにデザインしていく。
普段着の上に作業着を装着する。
足は長靴。
手は長いビニール手袋。
完全武装で染めのときに弾ける滴から身体を衛る。
FIXしたら水で絞る。
染めにムラがでないように染料を下地に染みこませるためだ。
一回目の染めに投じる。

静かに沈めていく。
浮かび上がらないように手で押し込む。
ゆっくりとかき回す。
ジワジワと染みこんでいく様子は藍瓶の中だから見えない。
丸い泡がプクと盛り上がった。
エメラルドグリーン色のようだ。
これは酸化の色だという。
3分間、染め込んだら引き上げて手で絞る。
滴が出なくなったら水槽で洗う。

生地に緑色が出なくなるまで洗う。
これも酸化で、そうすると藍の色は発色しないそうだ。
藍染めはアルカリ性だそうだというが頭の中は整理できていない。
この手順は三回するのだが、ラストはとめてあった洗濯鋏などを外した。
全部ではなくてほんの一部にした。
そうするとそこだけが染めが薄くなる。
多少のぼかしがでると思って外したのだがさてさて。
最後の工程はお酢浸け。
フイルムでいえば現像の定着だ。
お酢はアルカリ性。酸化をくい止めるとういうわけだ。
そして水洗い。
かつては前の紺屋川で晒していたのであろう。

できあがりは乾いてからのお楽しみだ。
藍染めの原料となる藍(タデアイ)は裏庭で植生されていることを付け加えておこう。

(H22. 7. 3 SB932SH撮影)
それは多彩なものでいかように使っても構わない。
創造力を膨らませて白いTシャツにデザインしていく。
普段着の上に作業着を装着する。
足は長靴。
手は長いビニール手袋。
完全武装で染めのときに弾ける滴から身体を衛る。
FIXしたら水で絞る。
染めにムラがでないように染料を下地に染みこませるためだ。
一回目の染めに投じる。

静かに沈めていく。
浮かび上がらないように手で押し込む。
ゆっくりとかき回す。
ジワジワと染みこんでいく様子は藍瓶の中だから見えない。
丸い泡がプクと盛り上がった。
エメラルドグリーン色のようだ。
これは酸化の色だという。
3分間、染め込んだら引き上げて手で絞る。
滴が出なくなったら水槽で洗う。

生地に緑色が出なくなるまで洗う。
これも酸化で、そうすると藍の色は発色しないそうだ。
藍染めはアルカリ性だそうだというが頭の中は整理できていない。
この手順は三回するのだが、ラストはとめてあった洗濯鋏などを外した。
全部ではなくてほんの一部にした。
そうするとそこだけが染めが薄くなる。
多少のぼかしがでると思って外したのだがさてさて。
最後の工程はお酢浸け。
フイルムでいえば現像の定着だ。
お酢はアルカリ性。酸化をくい止めるとういうわけだ。
そして水洗い。
かつては前の紺屋川で晒していたのであろう。

できあがりは乾いてからのお楽しみだ。
藍染めの原料となる藍(タデアイ)は裏庭で植生されていることを付け加えておこう。

(H22. 7. 3 SB932SH撮影)