けさの朝日新聞の「オピニオン」ページいっぱいに、
東大名誉教授の篠原一さんのロングインタビューが掲載されていました。
Opinion 歴史つくれるか 民主党政権
東京大名誉教授 篠原一さん
(2010.8.10 朝日新聞)
なお体制移行の途上 討議民主主義活用を
原点回帰必要な首相 部分連合で経験積め
民主党への政権交代を経て、今の状況をどう読み解くか、
「市民の政治学―討議デモクラシーとは何か」(岩波新書) を著した政治学者の視点がおもしろいです。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
篠原一さんの「市民の政治学―討議デモクラシーとは何か」もよかったのですが、
最近読んだ『〈私〉時代のデモクラシー』がけっこうおもしろかったです。
同じ岩波新書です。
ついでに、市民自治、市民参加など地方自治に関心のある方には、
『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』。

とっつきにくいテーマかも知れませんが、基本的なことが書いてあり、
そんなに読みにくい本ではないです。
外は雨。
明日は高山植物のお花が咲き乱れる山に行く予定をしているのだけれど、
想定外の台風で、「宿で温泉三昧」になりそうな気配。
「中高年登山で遭難」なんてことになりたくないし・・・・うーんザンネン。
最後まで読んでくださってありがとう
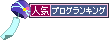
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

東大名誉教授の篠原一さんのロングインタビューが掲載されていました。
Opinion 歴史つくれるか 民主党政権
東京大名誉教授 篠原一さん
(2010.8.10 朝日新聞)

なお体制移行の途上 討議民主主義活用を
原点回帰必要な首相 部分連合で経験積め
民主党への政権交代を経て、今の状況をどう読み解くか、
「市民の政治学―討議デモクラシーとは何か」(岩波新書) を著した政治学者の視点がおもしろいです。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
篠原一さんの「市民の政治学―討議デモクラシーとは何か」もよかったのですが、
最近読んだ『〈私〉時代のデモクラシー』がけっこうおもしろかったです。
同じ岩波新書です。

| 新刊の紹介 2010年4月20日発売です 〈私〉時代のデモクラシー 宇野重規著(新赤版1240)岩波書店 〈私たち〉の政治に希望はあるのか 私たちは今、どのような時代を生きているのでしょうか。政治思想史・政治哲学を専門とする著者は、現代を、一人ひとりが〈私〉意識を強く持ち、他人とは違う自分らしさを追い求める「〈私〉時代」であると位置付けます。そのような社会でデモクラシーはどのような意味を持つのか、そして分断されてしまった〈私〉と〈私〉を結びつけ、〈私たち〉の問題を解決することは可能なのか、が本書のテーマです。 平等意識の変容や新しい個人主義の出現について考察した上で、〈私〉と政治の関係をとらえなおし、「社会」について再考します。議論を進める上で、19世紀フランスの思想家トクヴィル、日本の政治学に大きな足跡を残した丸山眞男、あるいは経営学・マネジメント論で知られるドラッカーまで、多くの研究者の思想が参照されます。 著者は冒頭、「〈私〉とデモクラシーというのは、何だか不思議な組み合わせに見えなくもありません。ふつうデモクラシーというと、出てくるのは「市民」や「国民」、あるいは「人民」や「民衆」などです。……しかしながら、本書では〈私〉こそが、現代デモクラシーを考える上での鍵だと主張したいと思っています」と述べています。政治の混迷の時代だからこそ、もっとも身近な〈私〉の視点から考える必要があるのではないでしょうか。 (新書編集部 安田 衛) ■著者紹介 宇野重規(うの・しげき)氏は1967年生まれ。1996年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。現在、東京大学社会科学研究所准教授(政治思想史・政治哲学)。 著書に『デモクラシーを生きる―トクヴィルにおける政治の再発見』(創文社)、『政治哲学へ―現代フランスとの対話』(東京大学出版会、渋沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン特別賞)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社、サントリー学芸賞)、『トクヴィルとデモクラシーの現在』(共編、東京大学出版会)、『希望学[1]希望を語る―社会科学の新たな地平へ』(共編、東京大学出版会)ほか。 ■目次 はじめに 第一章 平等意識の変容 1 グローバルな平等化の波 2 可視化した不平等 3 「いま・この瞬間」の平等 第二章 新しい個人主義 1 否定的な個人主義 2 「自分自身である」権利 3 自己コントロール社会の陥穽 第三章 浮遊する〈私〉と政治 1 不満の私事化 2 〈私〉のナショナリズム 3 政治の時代の政治の貧困 第四章 〈私〉時代のデモクラシー 1 社会的希望の回復 2 平等社会のモラル 3 〈私〉からデモクラシーへ むすび 参考文献 あとがき |
ついでに、市民自治、市民参加など地方自治に関心のある方には、
『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』。

とっつきにくいテーマかも知れませんが、基本的なことが書いてあり、
そんなに読みにくい本ではないです。
| 『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』 (山本 啓 編集/法政大学出版局) 内容(「BOOK」データベースより) 1990年代後半に入って使われはじめた「ガバメントからガバナンスへ」というキャッチフレーズは何を意味するのか。本書は、公民パートナーシップ、市民参加の可能性、リスク・ガバナンスと自治体、独立行政法人制度、自治体内分権、少子高齢社会の福祉政策、等々のテーマのもとに、ガバメント(政府)とガバナンス(統治)という概念とその関係性を、主としてローカルなレベルにおける「コー・ガバナンス」(共治・協治)への構造転換という視点から問い直す。 |
| 『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』 教授 藤本 吉則 財団法人ふくしま自治研修センターHP これまでも、そして、これからも同じなのかもしれないが、「今は」危機的な状況で、変化しなければならない時代だと考えられている。地方レベルでは、行政資源が限られているなか、ニーズが高まっている公共サービスの質を高めながら如何に提供していくかが、争点として論じられている。 このような問題に関心のある方にぜひともお勧めしたいのが、『ローカル・ガバメントとローカル・ガバナンス』である。私も著者の一人として参加している本であるが、「公共サービスの提供主体の構造転換という問題が日本においても本格的に取り組まなければならない大きな課題のひとつ」とした上で、「ガバメント(政府)とガバナンス(統治)という概念と関係性を、主としてローカルなレベルにおける関係性の構造転換という視点から考えなおしてみよう」との視点から書かれており、東北大学大学院の山本啓教授や北九州市立大学の松田憲忠准教授ら8名の研究者による共著である。 ガバナンス論の入門書ではないため、「そもそもガバナンスって何?」という方にはややとっつきにくい印象があるかもしれない。しかし、公民パートナーシップや市民参加、電子自治体など幅広い分野からローカル・ガバメントとローカル・ガバナンスを論じており、具体的な事例を通じてガバナンスに対する多角的な理解を深めるのに適している本と言えよう。各章とも20ページほどと気軽に読みきれる分量であり、ガバナンスやこれからの地方自治のあり方に関心のある方に読んで頂きたい本である。 |
外は雨。
明日は高山植物のお花が咲き乱れる山に行く予定をしているのだけれど、
想定外の台風で、「宿で温泉三昧」になりそうな気配。
「中高年登山で遭難」なんてことになりたくないし・・・・うーんザンネン。
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね

















