
何の花かわかりますか。スーパーマクロで写しました。左の花の名前は難しいと思います。
ヒント~紫色の5mmぐらいの丸い実が無数になります。?回答は

さて本題です。
我が八千代市には古くから四国霊場八十八ヶ所ミニチュア版があることを[第二回市民企画展「新四国を歩く」図録(以下図録と略します)](編集:八千代市立郷土博物館・むつみ街づくり研究会・村上昭彦 発行:愛宕山貞福寺)で知りました。

そんなわけで4月下旬から5月にかけて新四国八十八ヶ所を廻りました。
図録には10回(10日)で、新四国八十八ヶ所を歩いて廻られたと記載されております。マイブログでもこの順番で札所を掲載しております。
図録によれば、第2回は、飯山満駅から東町・高根・金杉金蔵寺まで歩いて廻られております。
5月4日第14番第81番上飯山満光明寺、第82番本郷地蔵堂を訪れました。
まず、第14番第81番上飯山満光明寺(船橋市飯山満町3-1373)です。
きれいなお寺です。かって車通勤 する時、成田街道の抜け道としてお寺の前の道を利用しておりました。
する時、成田街道の抜け道としてお寺の前の道を利用しておりました。
 光明寺には駐車場があり、
光明寺には駐車場があり、 安心してお参りできます。
安心してお参りできます。

第14番、第81番の大師堂は、境内に隣り合わせにありました。

下は、光明寺多宝塔です。

下の写真は、光明寺の鐘楼と山門です。

次に、すぐ近くにある第82番本郷地蔵堂(船橋市飯山満町3-1447)へ。

本郷地蔵堂は、ゼンリン地図には載っておりませんでした。 近くの番地をたよりに向かいましたがすぐ分かりました。
近くの番地をたよりに向かいましたがすぐ分かりました。 この大師堂だけでした。
この大師堂だけでした。 次回(2回~2)は、第18番飯山満東福寺、第39番高野薬師堂、第35番ゆるぎ地蔵を掲載します。
次回(2回~2)は、第18番飯山満東福寺、第39番高野薬師堂、第35番ゆるぎ地蔵を掲載します。











 テレビ&パソコン専科です。
テレビ&パソコン専科です。






 は最高で、九十九里のパノラマが一望できます。
は最高で、九十九里のパノラマが一望できます。





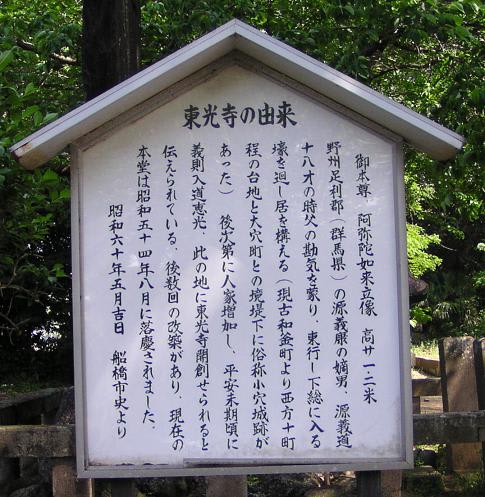

 して撮影しました。
して撮影しました。








 広場ではなかったかと思います。
広場ではなかったかと思います。
 ・雨・
・雨・









 写真では撮れませんでした。
写真では撮れませんでした。






 を見ながら鴨川
を見ながら鴨川 経由で帰途につきました。結構楽しい旅でした。
経由で帰途につきました。結構楽しい旅でした。 それも割れたとたん無くなってしまいました。
それも割れたとたん無くなってしまいました。


 この日は暑く汗だくになりました。
この日は暑く汗だくになりました。







 を見てパスしました。
を見てパスしました。 


 にお参りした大山寺です。
にお参りした大山寺です。

 を飲み、静かに休み
を飲み、静かに休み ました。
ました。







 安くおいしくおすすめの店です。
安くおいしくおすすめの店です。







