Ludwig van Beethoven
Piano Sonatas No.3.5,8,9,19,20,21
Irina Mejoueva

イリーナ・メジューエワさんは、2年計画で現在ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏を進めていますが、CDでもそれを遂行中です。このCDは、その第二弾です。下記に本CDに収められている曲を掲げました。このうち3番、19番、5番、20番、21番は公開演奏で聴きました。
録音は2007年11月、そして今年の4月、5月、7月で、場所は新川文化ホール(富山県魚津市)です。CDの表紙の絵は瀧口周造「私の心臓は時を刻む」(富山県立近代美術館蔵)です。
CDで演奏を聴くには想像力が必要です。具体的に言うと、耳をよく澄ますと右手と左手の動きを聞き分けることができます。当然ですが右手は普通、音階が高いです。
右手はメロディとか、装飾音とか、わりときらびやかで、目立ちます。それに比べると左手は右手での演奏を助ける役割をしています。励ましたり、抑制したり、牽制したり、しかし時には掛け合いのように同じメロディーを変わる番に弾きあったり、一緒に弾いたり、喧嘩したり、仲良くなったりといった感じです。
両手の動きを想像しながら聞くと、楽しいです。
[disc-1]
◆ピアノ・ソナタ 第3番 ハ長調 作品2の3
Ⅰ Allegro con brio
Ⅱ Adajio
Ⅲ Scherzo Allegro
Ⅳ Allegro assai
◆ピアノ・ソナタ 第19番 ト短調 作品49の1
Ⅰ Andante
Ⅱ Rondo Allegro
◆ アレグレット ハ短調 WoO53
Allegretto in C minor, WoO53
◆ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 《悲愴》
Ⅰ Grave Allegro di molto e con brio
Ⅱ Adajio cantabile
Ⅲ Rondo. Allegro
[disc-2]
◆ピアノ・ソナタ 第5番 ハ短調 作品10の1
Ⅰ Allegro molto e cpn brio
Ⅱ Adajio molto
Ⅲ Finale. Prestissimo
◆ピアノ・ソナタ 第20番 ト長調 作品49の2
Ⅰ Allegro ma non troppo
Ⅱ Tempo di Menuetto
◆ピアノ・ソナタ 第9番 ホ長調 作品14の1
Ⅰ Allegro
Ⅱ Adajio
Ⅲ Rondo Allegro comodo
◆ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調 作品53 《ワルトシュタイン》
Ⅰ Allegro con brio
Ⅱ introduzione. Adajio molto
Ⅲ Rondo. Allegretto moderato
著者のひとりであるデウィットさんにいただきました。

サブプライム問題以来、顕在化したグローバル同時不況の全貌と将来予測を豊富な資料と分析によって明らかにした本です。
著者は本書の目的を「(世界同時不況の)メカニズムを解明すること」とし、「まずこの金融危機の根源は、証券化という手法と『影の銀行システム』の崩壊にある。つぎに、信用収縮と景気減速の悪循環のプロセスが金融危機を進行させていく。さらに、この金融危機が深刻なのは、地球温暖化に伴うエネルギー政策の波が重なっていることにある」(p.2)と述べています。
今回の一連の危機は「津波」に例えられています。最初の「津波」は2006年の米国の住宅バブル崩壊。キーワードは「影の銀行システム」です。これは投資ビークルやファンドで債券取引などの資産を運用すれために銀行が設立した特別目的会社からなるシステムであり、これらは取引所を介さない相対(あいたい)の店頭デリヴァティブ取引を行いますが、FRB(連邦準備理事会)やSEC(証券取引委員会)の監督規制が及ばないゾーンであることがポイントです。
「影の銀行システム」の最大の問題点は損失を確定できないこと、したがって危機の構造が見えにくく、ある日突然、金融商品のカタストロフィー(値崩れ)が生じ、システムの崩壊に落着することが起こりうるのです(起こったのです)。
次の「津波」も予見されています。住宅価格の下落、デフォルトの割合の増加による住宅関連証券およびモノラインの格下げを引き金とする住宅関連証券の評価損、信用収縮の結果である企業倒産、さらに資源と食糧のインフレなど、「津波」の予兆をあげるには事欠きません。
信用収縮と実体経済の悪化の悪循環のゆえに、住宅ローンのみでなく、商業用不動産ローン、消費者ローン、自動車ローン、企業融資が焦げ付き始め、危機の加速化による「津波」のエネルギーが蓄積されています。
米国型金融資本主義と市場原理主義者がもたらした今回の危機は、まさに世界を壊すところまできているのです。
著者はこうした状況を嘆いたり、切歯扼腕しているだけではなく、「おわりに-脱出口を見失った日本-」(pp.66-71)では、雇用、年金・医療などの社会保障の立て直し、将来につながる産業政策、すなわち大胆な自然再生エネルギーへの転換や食糧自給率を高める農業支援、東アジアレベルでの通貨や貿易の連携の強化が提唱されています。心強いですね。

清張といえば推理作家、推理作家といえば清張と言うくらいですが、この本は清張の時代小説をとりあげ、ひとつひとつの小説を丹念に分析しています。
清張の時代小説とは「火の縄」「逃亡」などですが、あまり読んだことはありません(実際にこの本を読んだあと、清張の時代小説を探しに近くの書店に行ったが、並んでいませんでした。図書館で捜すか、大きな本屋に行くかしないと簡単に入手できないようです。)従来、あまり取り沙汰されることもなかったそうです。
著者は『小説日本芸譚』『私説・合戦譚』を中心に検討していきます。『芸譚』では「十人の人物の言動のなかに、松本は己の姿をも映し出そうとし」(p.15)、また「松本清張は、実は時代小説の作家だった。それらは”裏芸”だったのかもしれないが、私は”表芸”として見たいのである。理由は一言で言えば、これらの短編の中の人物を一人一人辿ってゆけば、自ずから作者自身の姿が浮かび上がってくるからだ。つまり、これが、ほんとうの”私小説”なのかもしれない」(p.87)とも書いています。
清張にとって余技ではなく、心の平衡を保つために必要であった時代小説の魅力を、著者は「まえがき」で次のように指摘しています、「松本清張の時代物は、真の愛情とは何であるかを問うている。どんなに無惨で酷な話でも、身の震えてくるような情愛が必ずひそんでいる。そのために、情無き者への怒りが読者の胸中に湧いてくるのである」と(p.4)。
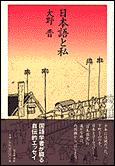
著者は父親に自分のことなど人前で話したりするもんじゃないと言われて育ったらしいのですが、それでも自分のことを書いてみる気になった、とあります(p.11)。
その父は東京深川で砂糖問屋を営んでいました。商売はうまくなかったのですが小学4年生の時に「広辞林」と「字源」を与えてくれ、このこことが言葉に興味をもった自分の原点と確認しています(p.20)。
明治小学校、開成中学での、言葉について教えてくれた個性豊かな印象に残る諸先生との出会い、一高での学生生活と交友、大学での橋本進吉先生への師事を経て、著者は聖泉女学院、学習院大学で教鞭をとるようになりました。
「広辞苑」初版の編集の手伝い、「岩波古語辞典」の編纂(20年かかったと言う)の苦労話。そして65歳にして「ドラヴィダ語辞典」を手にして新たな挑戦が始まりました。日本語の古語と古代タミル語との関係との関係の研究です。
日本語の起源を古代タミル語とする見解は著者を学界で孤立させ、週刊誌上では罵詈雑言を受けましたが、自らの信じる道を進み、国際的な評価も得るにいたりました。
本書はいわば自伝なのですが、同時に日本語がたどってきた過去と現在が見えてきます。
それらが平易で、抑制のきいた、美しい日本語で綴られていて、好ましく思いました。
「科学朝日」編『スキャンダルの科学史』朝日新聞社、1989年

科学(似非科学を含む)と科学者にまつわる26の事件の経緯と顛末です。
誤解だった黄熱病病原菌の発見(野口英世)
幻の錬金術発見(丸沢常哉)
超能力「千里眼」の嘘(山川健次郎)
少壮気鋭の総合自然史学者の心中(北川三郎)
幻想だった脚気菌発見(緒方正規)
血液型の似非科学(古川竹二)
「味の素」で特許取りの契機(池田菊苗)
サイクロトロン破壊事件(ハリー・ケリー)
丙午・大地震襲来騒動(今村明恒)
伝染病研究所移管事件(北里柴三郎)
雛の雌雄鑑別法と男女産み分け論争(増井清)
東京天文台移転事件(一戸直蔵)
心臓移植の是非(和田寿郎)
毒ガスによる中毒(小泉親彦)
弘前・財田・松山事件の血痕鑑定(古畑種基)
若返り療法の怪(榊保三郎)
電気灯による国会議事堂焼失(藤岡市助)
脚気は伝染病説に固執(森鴎外)
実験科学者である文部大臣の自決(橋田邦彦)
占領下日本研究基地化事件(イシドル・ラビ)
理論物理学教授恋愛失脚事件(石原純)
水銀還金事件(長岡半太郎)
ルイセンコ学説事件(徳田御稔)
ペスト感染事件(青山胤通)
長崎大学の医学博士号売買事件(勝矢信司)
定年制と辞職表明事件(田中館愛橘)
心臓移植の和田教授の話は、わたしが子どものころの札幌で聞いたこともある話で、大騒ぎだったのを覚えています。
野口英世、長岡半太郎、池田菊苗、北里柴三郎、森鴎外などは、これは子供のころ偉人伝で知ったのですが、この本ではむしろ偏屈者のように描かれています。どちらも実像とみるべきなのでしょう。人間は「矛盾の統一物」ですから。
本書でとりあげられているスキャンダルは血液型と人間の性格との強い相関関係、錬金術、若返り療法などの怪しげなものもあれば、科学者の先入観、矜持、偏見が作用した事件もあります。人間臭いと言えば言ますね。
しかし、ことが科学の世界の出来事だけに落差が大きすぎる感じです。
『科学朝日』に連載された読み切りもののせいか、面白いのですが、物足りないところも多々ありました。
"おにぎり"なら「ぼんご」 豊島区北大塚2-26-3 03-3910-5617
”おにぎり”で有名なお店が「北大塚」にあります。「ぼんご」です(1960年創業)。JR大塚駅を降りて北口を出て、徒歩3-4分。まっすぐ太いとおりに出て、右折すると見えてきます。
11時から3時までの昼食タイムには、お得なセットメニューがあります。おにぎり2個と豆腐の味噌汁で500円。なめこ汁とのセットだと600円です。
ここの”おにぎり”はあちこちで紹介されていますが、一番の特徴は、注文した”おにぎり”を目の前で握ってくれることです。ふつうのコンビニで売っているものよりは1.5倍くらい大きめです。
使っているお米は、新潟産の「コシヒカリ」、塩は沖縄の天然塩、ノリは有明海苔です。具は30種くらいあるのではないでしょうか? 一個210円です(筋子のみ250円)。
12席ぐらい。カウンターになっていますが、混んでいます。しかし、回転は早いので、注文用紙に書き込んで待てば、すぐに座れます。
東京にもこのようなお店があったのかと、嬉しくなります。一度、お試しください。

吉村昭『ふぉん・しいほるとの娘(下)』新潮文庫、1993年

お稲(その後、「伊篤」と改名)がシーボルトの弟子で伊予・宇和島で医業にたずさわっていた二宮敬作のもとにオランダ語の勉強に赴くところから、彼女の死まで。
この間、文字通り「波瀾万丈」の生涯でした。簡単にまとめると・・・。
シーボルトの娘、お稲は二宮に説得されて医者として身をたてることを決意します。産科の道に進むことになり、岡山にいた石川宗謙に指導を仰ぎます。
ところが、お稲はこの石川に「手ごめ」にされ、タダという女児を出産します。生きる意欲を欠いて、子とともに長崎に戻ります。長崎に寄った敬作に励まされ、お稲は再び医の道へ。そうこうするうち、国外追放されたシーボルトが再来日します。母のお滝とともに感動の再会を果たしますが・・・。
父を尊敬していたにもかかわらず召使の女に手をだす彼に失望し、不本意の日々を送るお稲。その後、宇和島藩の伊藤宗城(むねなり)の厚遇のもとに江戸に出て開業し評判の医師となります。娘のタダ(その後、「高」と改名)の不運な結婚と出産。
お稲はその後、福沢諭吉と邂逅し、医院の創業を勧められます。
激動の時代のなかで翻弄されながらも、自分の生き方を貫き、1903年、長崎で没。享年77。
著者の筆の運びは客観的で、史実に可能な限り即すことをこころがけ冷徹ですが、他面、お稲の内面の葛藤の描写も適切です。
頭のなかでは畏敬していた父シーボルトに対する失望、望まぬ子だったタダへの屈折した愛情、「あいのこ(ハーフ)」といわれながら、逆境にたえ自身の道を進んでいく意思、等々。
この小説では、お稲の人生とともに、流転する時代背景も細かく記述されています。江戸幕府末期の異国船(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、デンマークなど)の来日、外交問題でのシーボルトの動き、開国派と尊王攘夷派の確執、佐幕派と倒幕派の対立、明治維新後の征韓派と内治派の軋轢、東京の文明開化の様子など。
上巻とあわせて圧倒的な読み物になっています。
吉川英治文学賞受賞の大作です。
山本百合子さんの「ベートーヴェン後期のソナタとリストの小品たち」(サロン形式、聴衆22人)
山本さんは、最初にベートーヴェンとリストの時代背景を説明してくれました。
ピアノは18世紀に登場しました。1709年イタリア・フィレンツェでクリストフォリが最初のピアノを製作したといわれています(ヴァイオリン、チェロは16-17世紀にほぼ楽器として完成しましたが、ピアノは遅れました)。以来、イギリスの産業革命、フランスの市民革命を背景に、ピアノは発展していきました。
楽器としてのピアノの可能性を引き出したのがベートーベン、リストです。
ベートーヴェンの初期の作品には当時のピアノの音域としては存在しない部分も書かれています。彼はピアノメーカーがその音を出せるピアノを製作できることを予知していたのです。
1803年、エラール社が納品したピアノは細かなトリルが可能となり、ベートーヴェンは「ワルトシュタイン」を作曲、さらに1817年ー18年に最低音の音域が、F音から4度下のC音まで可能となり、当時の最低音と最高音を響かせる「ハンマークラヴィア」を作曲しました。
40年ほどの時代の差はありますが、リストもピアノという楽器に関心をもち、自宅には6台のピアノがあったといわれています。
そして、いよいよ演奏・・・。曲目は、以下のとおりでした。
◆ ベートーヴェン
① ピアノ・ソナタ 第30番 Op.109
Ⅰ Vivace, ma non troppo
-Prestissimo
Ⅱ Andante molto cantabile ed espressivo
② ピアノ・ソナタ 第31番 Op.110
Ⅰ Moderato cantabile, molto espressivo
Ⅱ Allegro molto
Ⅲ Adagio ma non troppo-Allegro ma non troppo
◆ リスト
③ 「二つの伝説」
④ 「愛の夢」~三つの夜想曲より~
⑤ 「ため息」~三つの演奏会用練習曲より~
⑥ 「ラ・カンパネラ」 ~パガニーニ大練習曲より~
ベートーヴェンのこれらの2曲のソナタは、いずれも簡潔な第一楽章、短くて自由奔放な第二楽章、そしてこの2つの楽章より長い終楽章からなります。
また、これらの2曲の特徴は、音楽用語が斬新な使われカをしていることです。
作品109では、teneramente(愛しむように)、 piacevole(平和に満ちて)など。作品110では、冒頭に con amabilita(愛らしく)、 sanft(やわらかく)と書き込まれています。第三楽章には、「嘆きの歌」Klagender Gesang- Arioso dolenteとあり、さらに二番目のアダージョではPeldedo le forze, dolente(嘆き悲しみで消え入るように)-Ermattet, klagend (人生に疲れ果てて)と表示されています。
以上、山本さんの「授業」のメモです。
リストの曲はみなおなじみのものですが、山本さんは口ずさむように、リズムを体でとりながら、弾いていました。手の動きを追ってみていましたが、「ラ・カンパネラ」は難曲ですね。
深い感動を与えて、演奏は終了しました。午後8時15分。喝采!
初秋の頃、3泊4日で台湾の土を踏みました。

台湾総督府
その前の予備作業として、このブログにも台湾のポイントメモを書き込みました(9月1日、2日、3日、5日、14日の記事参照)。また、伊藤潔著『台湾』(中公新書)を読んで、歴史の勉強もしました(9月26日のブログ記事)。
事前の準備の成果があって、短期間の台湾滞在でしたが、楽しめました。
行程は、成田から台北に入って(日航便で2時間半ぐらい)、バスで台南に向かい(約6時間)、北にあがって台北まで戻って日本に戻るというものです。
本ではわからなかったことをいくつか列挙します。
① セブン・イレブンが多いこと。マミーマートもありましたが、セブン・イレブンが断然多いです。
② セブン・イレブンをはじめお店で買い物をするとレシートをくれますが、このレシートに籤がついています。番号です。日本の年賀状の籤のように、定期的に当選番号が発表され、あたりが出ます。
③ 七福神の「ほてい様」が人気です。お店に入るとこの「ほてい様」が歓迎してくれます。商売繁盛のマスコットのような・・・
④ 鉄道の駅の作りは日本の古い駅に似ています。以前、日本の植民地だったからだそうで、その頃の駅舎がまだ残っていました。また、ここは車は右通行ですが、鉄道だけは左通行です。これも植民地時代の名残とか。
⑤ 台湾ビールは、あっさりして飲み易いです。台中あたりに紹興酒のおいしい地域があり、賞味しました。確かにいけます。
⑥ 全体にまちの建物がくすんでいます。都市づくりもいまいちです。蒋介石は大陸に帰りたくて、いい街をつくることに熱心でなかったのでしょうか? 心ここにあらずだったのでしょうか?
⑦ 「シンクーラ」は、「お疲れ様」の意味。「カキン・カキン」は「早く、早く」。シェシェニーン(有難うの意)と「ニーン」の部分を鼻にかけるように小さく伸ばすと上品に聞こえて、むこうの人はびっくりした顔をします。
かけあしの旅でしたが、印象が強く脳裏に刻まれました。

夜市の様子(台北)
清水俊二『映画字幕の作り方教えます』文藝春秋、1988年
字幕の作成過程はこうです。
まず「シャシン(フィルム)」が到着します。「ツーカン(通関)」を通過すると,「ハコガキ[セリフを選ぶこと]」のための「シシャ(試写)」,「ガイトー(該当)[修正とか処理を加えないと税関を通関しない場面]」があると「ラボ[現像所などの工場]」で「ボカシ」を入れます。
「ハコガキ」が済むと「スパット[スーパー字幕をフィルムのどこからどかまで入れるかを決めること]」にまわし,「デルマド[セリフの始めと終わりの印]」をフィルムに書きこんで,「シャク[セリフの長さ]」をはかり,「リスト[スパッとされたセリフの長さを1巻ごとにわけたリスト]」をつくるのです。「リスト」がきて字幕作成の実際に入り,「ヨミアワセ[セリフの意味、口調のチェック]」に入ります。訂正を重ねて「ケッテーコー(決定稿)」ができます。
これを「カキヤ(書き屋)さん」にまわし,字幕カードに書き,「ヤキコミ[フィルムへのセリフの焼き込み]」。校正を経て「ショゴウ(初号)」が完成。
以上です。隠語を使って的確に説明されています(pp.115-122)。
昭和6年から50余年,2000本の字幕を手がけた著者の「字幕スーパー」人生。この世界では,教えるのは無理で,とにかく字幕作成の練習を重ねるしか上達の術はないとか。(とすると、本の題がおかしいのでは?)
随所に練習用のテキストがあり,模範解答があります。字幕作成は翻訳ではないこと,誤訳を指摘することの愚かしさがよくわかりました。
最後にシビアな話しがありました。「フルメタル・ジャケット」事件です。オリバー・ストーン監督が,一流の字幕ライターである戸田奈津子さんが作成した「字幕」に異議を申し立て(英語が適切に訳されていない、と),別の人があたって落着したことがあったとか。しかし、ピンチヒッターの字幕は、一般向けにはわかりにくいものになってしまいました。「Aクラスのスーパー字幕ライターの仕事が一監督の”芸術的良心”によって拒否されたのである。・・・・私たち字幕屋はこの事をきちんと頭に入れておくべきである」と(p.436)。著者の了解がこれです。


昭和15年。どこにでもある普通の仲睦まじい家族。父の滋はドイツ文学者(坂東三津五郎)、その妻佳代(吉永小百合)。娘が二人いました。初子(志田未来)と照美(佐藤未来)です。家族はそれぞれを「父べえ」、「母べえ」、「初べえ」、「照べえ」と呼び合っていました。
深夜、特攻が野上家のドアを激しく叩きます。佳代がまず出ますが、代わって滋がおそるおそるドアをあけると特攻がズカズカと入り込んできて、彼に縄をかけます。滋は治安維持法違反の思想犯で逮捕されました。時代は日中戦争のさなかでした。
投獄された父。残された家族は、父を思いながら助け合って生きていきます。佳代は、紹介されて小学校の教員の職をえます。
山崎という書生で、滋の教え子だった青年(浅野忠信)が何かと家族のことを心配して、援助します。そんな佳代の家族のところに、父べえの妹のちゃこおばちゃん(檀れい)が手助けに来たり、叔父さんが転がり込んできたり・・・。
しかし、悲しいことが次々に起こります。拷問を繰り返し受け、衰弱した父は獄死します。そして山崎青年のところにも赤紙が・・・・。
戦禍のなかのなかの厳しい条件の下での家族の愛。人と人の結びつきの大切さ。そのことをこの映画は伝えています。
原作は黒澤監督のもとで長くスクリプターを努めた野上照代さんの「父のレクイエム」です。


山口さんの本をもう一冊。前回の『経済再生は「現場」から始まる』と重なる部分がありますが,政府,官庁エコノミストの金融政策批判に力点があります。
著者の本書執筆の第一の動機を「『マネーの世界』へと問題を矮小化したり,『市場原理』なるものに行き過ぎた拘泥りをもつことが,どのような理論的混乱や現実的悲劇を生み出すか,これをあきらかに」することと述べています(p.168)。
この観点からインフレターゲット論からの日銀批判の問題点,不良債権処理の非現実性,ペイオフ解禁の不要性,自己資本比率を基準とする金融行政の陥弄を説いています。
最後に「金融アセスメント(監督官庁に「円滑な資金需給」「利用者の利便」という2つの観点から,金融機関の活動を評価することを義務づけ,その「判断理由」を利用者が入手しやすい形で開示する)」の意義を強調しています。
国民,中小企業化・中小金融機関の側にたって迷走する日本経済の問題点を明るみに出した力作です。

鎖国の江戸時代、1823年に日本の出島に来航したシーボルト。
シ-ボルトはドイツ人でした(当初、オランダ人と偽っていた)、日本の国情調査というオランダ政府の命をうけて来日したのでした。
西洋医学を普及しながら、当時、その海外への持ち出しが国禁だった日本地図、蝦夷・樺太の地図、江戸城の地図など膨大な資料を収集し、本国に搬送しようとしました。世に言うシーボルト事件です。
関連した役人、弟子、通詞、召使いなど約50人が連座、処刑され(地図を渡した幕府の天文方兼書物奉行・高橋影保、徳川家の紋である葵が染め抜かれた帷子を贈った奥医師・土生玄碩、門人の二宮敬作、高良斎、お抱え絵師・河原慶賀など)、投獄されました。
シーボルト本人は折しも本国に帰還する予定の時期でしたが、事実上幕府の命による、国外追放、本国送還となりました(1829年)。
この小説は、シーボルトの来日以降、西洋医学による治療、医学教育をつうじ、長崎の人々、ひいては日本人に慕われたシーボルトとその娘お稲の物語です。
上巻はシーボルト来日から、出島を中心にした医療活動、鳴滝塾での医学の伝授、国情調査、其扇との愛、お稲の誕生、シーボルト事件、離日、お滝(其扇)の結婚、男の子(文作)の誕生、そして蘭学を学ぶためにお稲が長崎を出て伊予国宇和島藩の二宮敬作の所に到着するまでです。物語の核は、彼が遊女とした其扇(そのおうぎ)をしだいにひとりの女性として愛すようになり、お稲という女の子をもうけたことです。
お稲はシーボルトの追放後、オランダ語に興味をもち勉強を始めました。彼女は女性が学ぶことそのものを認めようとしない母親に隠れて勉強を続けましたが、そのような境遇での勉強にあきたらず、義理の父・時次郎の薦めもありシーボルトの弟子で伊予で開業していた啓作に教えを請いに旅立ちます。
印象に残ったのは商館長にともなっての江戸参府143日の旅(1826年)、鳴滝塾という医学塾をつくったこと、日本の植物を集め出島に植物園を作ったこと、などです。
正確で細かい叙述ながら、読者をぐいぐいと引っ張る吉村文学の真骨頂に満足至極の632ページでした。下巻に入ります。
いま、浅草が面白い

浅草と言えば浅草寺(徳川の祈願所)と仲見世。毎日、大変なにぎわいです。
◆今年の秋は、本堂落成50周年記念大開帳です。浅草寺のご本尊聖観世音菩薩像は絶対秘仏のため、これまでご開帳されたことはありません。今回ご開帳されるのは、約1200年前に天台宗第3世座主慈覚大師円仁(じかくだいし えんにん)が謹刻された、前立本尊です。厨子の扉が開かれていて、直接その姿を拝することができます。
また、本堂前には3本の開帳塔婆が立ち、その塔婆からは手綱が渡されています。この手綱は本堂の厨子内の前立本尊の手に繋がり、この手綱を手に取ることで、お開帳の本尊と縁を結ぶことができるとされています。手綱は赤・黄・白・緑・紫の5本あります。
◆関連して「大絵馬寺宝展と庭園拝観」があります。絵馬を見て、滅多に入れない庭園を散策できます。

宮戸川からの観音像の示現以来、1380年の歴史のある金龍山浅草寺。本堂には古くから観音信仰の一つとして絵馬が掲げられました。江戸時代には絵馬堂が建立されました。奉納願主の依頼により、当代一流の絵師が大絵馬を描き、それが掲げられました。現存する絵馬は245点だそうです。
主なものは・・・
二代将軍秀忠や三代将軍家光が寄進した華麗な金蒔仕立ての双神馬、、高橋源吉の「商標感得図」、川辺御楯(かわべみたて)の「長篠合戦賞功」、藤川親明の「石橋」、高嵩谷(こうすうよく)の「源三位頼政の鵺(ぬえ)退治」、鈴木基一の「迦陵頻伽(かりょうびんが)」、三代堤等琳の「韓信股くぐり」、歌川国芳の「一つ家」、鳥居清元の「関羽」などです。
綱吉の描いた「白衣観音」の掛け軸(1705年)もありました。保存状態がよく、きれいです。浅草寺三舟(勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟)の筆による看板(?)もありました。
◆庭園は小堀遠州による回遊式庭園です。池には鯉が泳いでいますし、白鷺が水面すれすれに滑空したりしていて、のどかです。今は紅葉も綺麗です。
◆奥山風景で今半の「牛メシ」を食べました。この奥山風景は江戸情緒をかもしだしながら、珍しいお店がたくさん並んでいます。そして、今は300円で一両の小判と両替し、この小判で買い物ができるのですが、お客さんが多くて小判がなくなってしまったのかひとり1枚だけの交換限定でした。残念。
◆あと、「新富座こども歌舞伎」の舞台がありました。演目は「三人吉三巴白浪・大川端庚申塚の場」でした。口上は6年生の女の子。おとせ、お嬢吉三、お坊吉三、和尚吉三、金貸しの役は、みな小学生です。<おおあたり>
山口義行『経済再生は「現場」から始まる』中央公論社、2004年
著者の山口さんに、3年前に献本を受けました。すぐに読んで、読書ノートに書き込んでおいたものを引っ張り出して、以下に掲げます。
「現場」を重視し,そこに「解」を見出すコンセプトがよいです。眼から鱗がおちました。全体は3章からなっています。
第1章では,帳簿上の「不良債権処理」ではなく,「不良債権減らし」を提唱し,常陽銀行で経営改善支援活動の一環として対象となったある金属加工メーカーの支援,スーパーのM&Aが紹介されています。
第2章では「壊す」のではなく「活かす」という観点から,榛名湖でのワカサギ漁の炭素繊維による再生,大阪産業創造館による企業ネットワークの構築,尾鷲総合病院でのNSTによる地域医療再生の経験について論じられています。
第3章では近時における金融行政の転換,とくに中小・地域金融機関に対する施策の変化が示され,市民参加の新しい金融システム,金融アセスメントの提唱があります。
「現場」第一義主義の視点にたつ鋭い問題提起と先進的な実践の成果をまとめた好書です。










