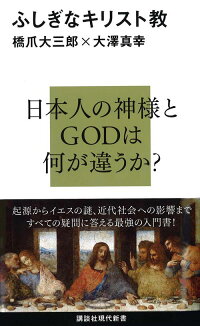わたしの大先輩にあたる著者からいただきました。文字通り、重厚な大著です。読み通すのは大変ですが、まず、ここに紹介します。
・序章
<第Ⅰ部:おいたち・青春・亡命-ヴィーデラウ・ライプツィッヒ・パリ(1857-1890)>
・第1章 少女時代-ヴィーデラウ村
・第2章 青春-ライプツィッヒ
・第3章 亡命-パリでのオシップ・ツェートキンとの生活
・第4章 パリで亡命時代の文筆・演説活動(1857-1890)
<第Ⅱ部:ドイツ社会民主党と第2インターナショナル-シュツットガルト時代(1891-1914)>
・第5章 シュツットガルトでの生活と活動-フリードリヒ・ツンデル/ローザ・ルクセンブルクの出現
・第6章 ドイツ社会民主党の女性政策とローザ・ルクセンブルクとの交友
・第7章 『平等』の編集・内容の変遷、リリー・ブラウンとの論争、クラークの追放
・第8章 第2インターナショナルの女性政策とのかかわり
・第9章 「国際女性デー」の起源と伝搬-米・欧・露、その伝説と史実と-
・第10章 アウグスト・ベーベルの『女性と社会主義』-没後100年に寄せて-
<第Ⅲ部>戦争と革命
・第11章 世界大戦・ロシア革命・ドイツ革命と女性
・第12章 ドイツ共産党とコミンテルンの間で
・第13章 レーニンとクラーラの、「女性問題」と「3月行動」に関する対話
・第14章 レーニン時代のコミンテルンと国際女性運動
・第15章 スターリン時代への移行期のコミンテルンの女性運動のなかで
・第16章 晩年:私的・公的葛藤のなかで
・終章
・あとがき
・補章
1.旅
2.第20回(2013年)社会政策学会学術賞と本書への8本の書評
3.クラーラのはじめての手紙集の出版によせて
4.クラーラのローザ宛、1918年11月17日付け手紙について
5.2017年クラーラ・ツェトキーン生誕160周年、そして未来へ