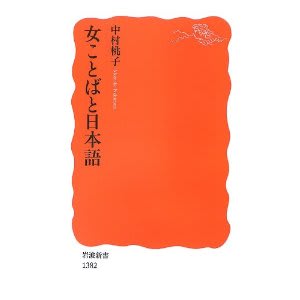
日本語には女性に特有の言葉がある。この「女ことば」とは一体何なのだろうか。著者は本書で多くの人の常識なっている「女性たちが話してきた言葉づかいが自然に女ことばになった」という考え方の問題点を多面的(多様性の承認、規範、知識、価値)に考察している。
具体的には種々の言説をデータとして分析し(歴史的言説分析)、鎌倉時代から第二次世界大戦までの女ことばの歴史をたどりながら、女ことばがつくられてきた道程が明らかにしていく(歴史的言説分析とは、特定の言説が意味をもつようになった政治や経済的な背景を探るという方法)。
その結論は、要約して言えば、女ことばの形成はまず鎌倉時代から続く規範の言説によって女性の発言を支配する傾向が、江戸時代に強化され、さらに現代のマナー本に見られるような女らしさとの結びつきの強調につながっているということ、明治期には近代国家建設という課題のもとで国語理念が男性国民の言葉として形成され対極で「て・よ・だわ」などの具体的な語と結びついた女学生ことばがひろく普及したこと、くだって戦中期には、アジアの植民地の人々同化政策や女性を戦争に動員する総動員体制のねらいとして女ことばが天皇制国家の伝統とされ、家父長制の象徴である「性別のある国語」が強調されたこと、さらに戦後は、占領軍のもとで男女平等政策の推進、天皇制や家父長制の否定のなかで女ことばを自然な女らしさの発露と再定義する言説が普及し、女ことばに日本の伝統を象徴することが期待されるにいたったこと、である。
したがって著者によれば、「日本語には女ことばがある」というとき、それは、実際に日本女性が男性と異なる言葉使いをしているという意味の「ある」ではなく、言語イデオロギーとして言説によって歴史的に形成されてきた、ということなのである、と(結論部分を含め以上、pp.327-8)。
「第1部 『女らしい話し方』-規範としての女ことば」「第2部 『国語』の登場-知識としての女ことば」「第3部 女ことば礼賛-価値としての女ことば1」「第4部 『自然な女らしさ』と男女平等-価値としての女ことば2」。

先日の軽井沢での「メサイア」に刺激を受け、CDでその全曲をとりそろえたかったが、まずハイライトのそれをもとめる。マリナー指揮、アカデミー&コーラス・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのこの盤は、録音もよく、手軽に聴くにはよかった。
ソプラノはエリー・アーメリング、アルトはアンアナ・レイノルズ、テノールはフィリップ・ラングリッジ、バスはグウィン・ハウエルである。
ハレルヤ・コーラスは、毎年度、卒業式で交響楽団が演奏し、グリー・クラブが合唱するのを聴いているので、この曲を聴くと、卒業していった学生のことを思い出す。
ひたすらイエスを称賛するこの曲には、それゆえに勢いと活気がある、このコーラスを聴くと元気がでる。不思議なものだ。この部分は初演のときに、臨席したジョージ2世がこの合唱で感激のあまり立ち上がり、聴衆もこれにならったというエピソードがあり、今でも聴衆が全員起立することもあるのだそうだ。
このCDに収められたもののなかでは、合唱の「われわれはみな羊のように迷って」と、バスとトランペットで聴かせる「ラッパが鳴ると」が好きだ。「われわれはみな羊のように迷って」はヘンデルが合唱書法の粋をつくして仕上げたもので、各パートが華やかに掛け合わされ、最後はアダージョとなってしみじみと結ばれる。「ラッパが鳴ると」は、最後の審判のおりに響くと言われるラッパを模した前奏に導かれ、バスが力強くアリアを歌う。前奏のラッパの動機は、伴奏のなかで絶えず繰り返されるが、これがよい。
この曲は、ヘンデルが1741年、友人ジェネンズが聖書をもとに書いた台本に曲をつけたもので、演奏時間2時間半ほどのこの曲を24日間ほどで書きあげたという。
とまれ、この曲を聴きながら、往く年を惜しむ。

今月5日未明、中村勘三郎さんが亡くなった。歌舞伎界にとっていうまでもなく、演劇界にとって大きな損失だ。わたしが実際に観た勘九郎さんの舞台は、「桂春団治」「夏祭浪花鑑」「法界坊」の3作品。華のある役者だった。
本書は、その勘三郎さんが勘九郎を名乗っていた頃、より正確には勘三郎襲名直前までの活動を、著者のインタビューによって構成した本である。勘三郎さんの生の声であり、その人柄が素直に出ていて、歌舞伎への愛情、古典へのこだわりと革新、観客に向かう姿勢と覚悟、父である先代の勘三郎はじめ先輩への尊敬、野田秀樹さん、渡辺エリさん、大竹しのぶさんなど演劇関係の友人との交流、妻である好江さんとの馴れ初めとその後の結婚生活、二人の息子と後輩への熱いまなざしなどが、くまなく書かれている。
本書から知ることができたのは、勘三郎さんの伝統芸能である歌舞伎への強い想いで、それは例えば、古い資料の読み込みを行って、当たり前のこととして演じられてきたことが、意外とそこに誤解があり、勘三郎さんはその誤解を解きほぐし、かつての役者がいろいろと工夫していたことを掘り起こして演じなおしたことなどである(勘三郎さんはこの例として『藤娘』『京鹿子娘道成寺』『本朝廿四孝』あげている[pp.18-22])。また、歌舞伎は観客に喜んでもらわなければ意味がないとして、盛んに新しい試みをとりいれることに情熱を注いだことも勘三郎さんの功績だった。平成中村座のニューヨーク公演(2004年)、ドイツ、ルーマニアでの公演(2008年)、コクーン歌舞伎(『夏祭浪花鑑』他)など勘三郎さんの活動はとどまるところを知らない展開をみせた。
そうした活動になぜ取り組んだのか、そこにどんな困難があったのか、また成果は何だったのかを、勘三郎さん自身が生の声で語っている。型を守るのではなく、型を破ること、歌舞伎の伝統、リテラシーは守りつつ、他の芸能や文化を取り込み、そこに「化学反応」をおこすこと、それが勘三郎流の歌舞伎哲学だった。
その勘三郎さんの言葉、「走っていれば脛も打つし、傷を負って血もでるよ。でも、人は生あるうちにしか走れない。じっとして考えてばかりいるより、息急き切って走っているほうが、俺の性分に合ってるよ」(p.332)。


長編小説というが異色。筋はある。簡単にいえば女性論説記者の起こした筆禍事件とその顛末。
大手新聞社「新日報社」の記者南弓子(45歳)は論説部に所属していたが、彼女が書いた記事、すなわち元首相が臨んだ水子供養塔除幕式で妊娠中絶と産児制限に対して放った暴言への批判記事が思わぬ波紋をよび、得体のしれない何者かの逆鱗に触れる。新聞社はこの騒ぎを彼女の配置転換でかわそうとするが、彼女はそれに抵抗する。彼女は見えない力の原因究明にたちあがるが、そこからおぼろげにわかったことは新日報社が新社屋用地払下げで政府与党に借りがあり、このことが事件と彼女の配置転換の背景にあるということだった。政府与党は選挙である宗教団体の支援を受けていて、この団体は水子供養で大きな利益を享受していた。
しかもこの団体自体は、内部に与党幹事長を巻き込む組織的抗争をかかえていた。事情に感づいた弓子は、一計を案ずる。元女優で伯母の雅子はかつて首相の田丸と関係があったことを盾に事態解決の交渉へ、弓子の愛人で哲学者の豊崎が妻の友人の紹介で幹事長と交渉へ、弓子の娘千枝が政府首脳に影響力をもつ書家に交渉の橋渡しを依頼に。
それぞれのルートを通じての交渉過程が興味津々に描かれる。事態は落着の方向にむかうが、弓子は記者をやめる決意をする。話の大筋は以上のようであるが、この小説はその筋よりもプロセスに重きがあり、そこでは日本に古くからある贈与の美学、哲学が開陳されたり、首相官邸の描写があったり、論説部の記者のリアルな生き方が示されたり、する。
このあたりは、作者が生来言いたかったこと、知らしめたかったことを、小説に登場する人物の口や眼をとおして語らしめ、描写しているようだ。
主人公、弓子は最後まで魅力的だ。

昨日紹介した「メサイア」の翌日、同じ大賀ホールで「新島学園クリスマスコンサート2012」があった。同校の管弦学部、聖歌隊のクラブが、毎年、ここでクリスマスのイベントとして開催している集いである。今年で4回目とのこと。
プログラムは下記のとおり。クリスマスに関連した演奏、コーラスで愉しめました。とくに、ハンドベルはなかなかのもの。人数が多く、演奏に使うベルも小さいものから大きなものまで多数。学園の取り組みなので中学生もいれば、高校生もいる。練習時間の作り方も大変だったろうと、思った。
音の出し方ただ振るだけでなく、ベルのなかの振り子(クラッパー)をもちあげて弾いたり、鐘(キャスティング)の部分をたたいたりいろいろである。生徒によっては、いくつものベルを扱う子もいて忙しそう。しかし、乱れることなく、しっかりした演奏だった。6オクターブくらいの音程を確保しているようである。こんなに大規模なハンドベルの演奏を聴いたのは記憶にない。
管弦楽は、Sing, Sing, Sing などは演奏に自信がみなぎっていた、ように見えた。指揮者と生徒たちとの信頼関係も演奏に大きな影響を与えるのではなかろうか。曲目によっては、おとなしく、教科書的な演奏もあったが、全体に生徒たちが、この課外活動をつうじて成長しているさまが伝わってきた。拍手をたくさん送った。
新島学園というのは安中榛名にあり、新島襄は上州安中藩の江戸屋敷で生まれことに由来しているそうである。キリスト教にもとづく教育体系が根づいている。管弦アンサンブルは1990年ごろに結成。また聖歌隊は1984年創部、52年の伝統がある。
【第1部:管楽アンサンブル~聖歌隊
・また君に恋してる
・クリスマス・イブ
・Hymm For Child
・Sing, Sing, Sing
・Christmas Song Medley
・讃美歌21第263番 あら野のはてに
・Rockin' Around the Christmas Tree
・上を向いて歩こう
・見上げてごらん夜の星を
【第2部:クリスマスメッセージとハンドベル】
・クリスマス礼拝のように
前奏 When The Saints Go Marching In
・メッセージ&お祈り
後奏 Now The Green Blade Riseh
・あわてんぼうのサンタクロース
・サンタが街にやってくる
・神の御子は今宵しも
・Jingle Bell Rock
・Cradle Songs
・Angels' Carol
・きよしこの夜
クリスマス、軽井沢へ。寒波で気温が低い。サッポロ育ちで寒さに慣れていたはずのわたしにとっても、この寒さはこたえる。しかし、クリスマスにはふさわしい気持ちもする。心がただされる思いである。
わざわざ軽井沢に赴いたのは大賀ホール(ソニー名誉会長大賀典雄が資金を提供して建設、2005年4月開館)でヘンデルの「メサイア」を聴くため。演奏はバッハ・コレギウム・ジャパン。指揮は鈴木雅明さん。
大賀ホール(客席数784)で演奏会を聴くのは初めて、また「メサイア」全曲をしっかり聴くのも初めてである。満席ではなかったが、この時期に、この場所にしては、かなりの聴衆(500人ほど)。有名な詩人の姿をおみかけした他、軽井沢の別荘族と思われる人がちらほら。
大賀ホールは五角形の特色のある建物で、演奏用のステージをとりまくように客席が設けられ、とくに舞台の前方の席は低い。音響が上方に響き、それをこの位置にある席が受け止められるように出来ているのだろうか。
「メサイア」というのは「メシア」(救世主)の英語読み。聖書から歌詞を構成しイエス・キリストの生涯を題材としている。出典はイザヤ書などの預言書を主とし、救世主についての預言を通して、間接的に救世主たるイエスがよみがえる。この演奏会で、今年は素敵なクリスマスになった。
「メサイサ」の歌詞は、欽定訳聖書と『英国国教会祈祷書』 (The Book of Common Prayer, 1662) の詩編から採られている、という。
全体は3部構成。ウィキペディアにその詳細が載っていたので、下記に引用する。 なかでも有名なのは「ハレルヤ」コーラスである。この部分だけ取り出されて、いろいろなところで演奏される。
管弦楽の演奏に従いながら合唱・独唱が繰り返される。演奏時間は約2時間。手許に歌詞があったので、それを見ながら、展開を追ったので、内容もある程度、理解できた。 歌手は実力者が勢ぞろいであった。ソプラノはヨハネッテ・ゾマーさん、第二ソプラノに松井亜季さん、アルトの部分を歌ったのはカウンターテナーのクリント・ファン・デア・リンデさん。テノールに櫻田亮さんと谷口洋介さん、バスにロデック・ウィリアムズさんだった。いずれもそれぞれの分野の実力者である。
演奏会終了後、近くの矢ヶ崎公園の見事なクリスマスのイルミネーション+イベントを見てまわった。メリー・クリスマス。
第1部: メシア到来の預言と誕生、メシアの宣教
- Comfort ye...「慰めよ、わが民を慰めよ…(イザヤ40:1-3)」レスタティーボ・アコンバニャート(以下、単に「アコンパニャート」と呼称)(テノール独唱)
- Every valley shall be exalted...
- 「もろもろの谷は高くせられ…(イザヤ書40:4)」アリ(テノール独唱)
- And the glory of the Lord shall be revealed...
- 「こうして主の栄光があらわれ…(イザヤ書40:5)」 合唱
- Thus saith the Lord of Hosts...
- 「まことに、万軍の主はこう言われる…(ハガイ書2:6-7、マラキ書3:1)」 アコンパニャート(バス独唱)
- But who may abide the day of His coming...
- 「だが、その来る日には、だれが耐え得よう…(マラキ書3:2)」 アリア(アルト独唱)
- And He shall purify the sons of Levi...
- 「彼はレビの子孫を清め…(マラキ書3:3)」 合唱
- Behold, a virgin shall conceive...
- 「見よ、おとめがみごもって…(イザヤ書7:14、マタイ伝1:23)」 アコンパニャート(アルト独唱)
- O thou that tellest good tidings to Zion...
- 「よきおとずれをシオンに伝える者よ…(イザヤ書40:9,60:1)」 アリア(アルト独唱)と合唱
- For, behold, darkness shall cover the earth...
- 「見よ、暗きは地をおおい…(イザヤ書60:2-3)」 アコンパニャート(バス独唱)
- The people that walked in darkness...
- 「暗やみのなかに歩んでいた民は…(イザヤ書9:2)」 アリア(バス独唱)
- For unto us a Child is born...
- 「ひとりのみどりごがわれわれのために生れた…(イザヤ書9:6)」 合唱
- Pifa (Pastoral Symphony)
- パイファ(田園交響曲)
- There were shepherds abiding in the field...
- 「羊飼いたちが夜、野宿しながら…(ルカ伝2:8-11,13)」 アコンパニャート(ソプラノ独唱)
- Glory to God in the highest...
- 「いと高きところでは、神に栄光があるように…(ルカ伝2:14)」 合唱
- Rejoice greatly, O daughter of Zion...
- 「シオンの娘よ、大いに喜べ…(ゼガリア書9:9-10)」 アリア(ソプラノ独唱)
- Then shall the eyes of the blind be opened...
- 「その時、見えない人の目は開かれ…(イザヤ書35:5-6)」 アコンパニャート(ソプラノ独唱またはアルト独唱)
- He shall feed His flock like a shephard...
- 「主は羊飼いのようにその群れを養い…(イザヤ書40:11、マタイ伝11:28-29)」 アリア(ソプラノ独唱またはソプラノ・アルト独唱)
- His yoke is easy...
- 「彼のくびきは負いやすく…(マタイ伝11:30)」 合唱
第2部: メシアの受難と復活、メシアの教えの伝播
- Behold the Lamb of God...
- 「見よ、世の罪を取り除く神の子羊…(ヨハネ伝1:29)」 合唱
- He was despised...
- 「彼は侮られて…(イザヤ書53:3,50:6)」 アリア(アルト独唱)
- Surely He hath borne our griefs...
- 「まことに彼はわれわれの病を負い…(イザヤ書53:4-5)」 合唱
- And with His stripes...
- 「彼の打たれた傷によって…(イザヤ書53:5)」 合唱
- All we like sheep...
- 「われわれはみな羊のように迷って…(イザヤ書53:6)」 合唱
- All they that see Him...
- 「すべて彼を見る者は…(詩編22:7)」 アコンパニャート(テノール独唱)
- He trusted in God...
- 「彼は主にみをゆだねた…(詩篇22:8)」 合唱
- Thy rebuke hath broken His heart...
- 「そしりが彼の心を砕いたので…(詩篇69:20)」 アコンパニャート(テノール独唱またはソプラノ独唱)
- Behold, and see...
- 「尋ねて見よ…(哀歌1:12)」 アリア(テノール独唱またはソプラノ独唱)
- He was cut off out of the land...
- 「彼はいけるものの地から断たれ…(イザヤ書53:8)」 アコンパニャート(テノール独唱またはソプラノ独唱)
- But thou didst not leave His soul in hell...
- 「あなたは彼の魂を陰府(よみ)に捨ておかれず…(詩篇16:10)」 アリア(テノール独唱またはソプラノ独唱)
- Lift up your heads...
- 「門よ、こうべをあげよ…(詩篇24:7-10)」 合唱
- Unto which of the angels...
- 「いったい、神は御使いたちの…(ヘブライ書1:5)」 アコンパニャート(テノール独唱)
- Let all the angels of God worship Him...
- 「神の御使いたちはことごとく…(ヘブライ書1:6)」 合唱
- Thou art gone up on high...
- 「あなたはとりこを率い…(詩篇68:18)」 アリア(アルト独唱またはソプラノ独唱)
- The Lord gave the word...
- 「主は命令を下される…(詩篇68:11)」 合唱
- How beautiful are the feet of them...
- 「ああ麗しいかな…(ローマ書10:15)」 アリア(ソプラノ独唱)
- Their sound is gone out into all lands...
- 「その声は全地にひびきわたり…(ローマ書10:18)」合唱
- Why do the nations...
- 「なにゆえ、もろもろの国びとは…(詩篇2:1-2)」 アリア(バス独唱)
- Let us break their bonds asunder...
- 「われらは彼らのかせをこわし…(詩篇2:3)」 合唱
- He that dwelleth in heaven...
- 「天に座する者は笑い…(詩篇2:4)」 アコンパニャート(テノール独唱)
- Thou shalt break them...
- 「おまえは鉄のつえをもって…(詩篇2:9)」 アリア(テノール独唱)
- Hallelujah...
- 「ハレルヤ、全能者にして主なるわれらの神は…(黙示録19:6,11:15,19:16)」 合唱
第3部: メシアのもたらした救い〜永遠のいのち
- I know that my Redeemer liveth...
- 「わたしは知る、わたしをあがなう者は生きておられる…(ヨブ記19:25-26、コリントコリント前書15:20)」 アリア(ソプラノ)
- Since by man came death...
- 「それは、死がひとりの人によってきたのだから…(コリント前書15:21-22)」 合唱
- Behold, I tell you a mystery...
- 「ここで、あなたがたに奥義を告げよう…(コリント前書15:51-52)」 アコンパニャート(バス独唱)
- The trumpet shall sound...
- 「ラッパが響いて…(コリント前書15:52-54)」 アリア(バス独唱)
- Then shall be brought...
- 「そのとき、聖書に書いてある言葉が成就する…(コリント前書15-54)」 アコンパニャート(アルト独唱)
- O death, where is thy sting?...
- 「死よ、お前の勝利は、どこにあるのか…(コリント前書15:55-57)」 デュエット(アルト・テノール二重唱)、合唱
- If God be for us...
- 「もし、神がわたしたちの味方であるなら…(ローマ書8:31,33-34)」 アリア(ソプラノ独唱またはアルト独唱)
- Worthy is the Lamb...
- 「ほふられた小羊こそは…(黙示録5:12-13)」 合唱
- Amen...
- Amen...
- 「ほふられた小羊こそは…(黙示録5:12-13)」 合唱

映画を観る切り口としてこういうものがあったのだ。確かに映画(製作)にとって衣裳デザインは重要だ。まず、女優、男優を引き立たせなければならない。演技上の個性を際立たせることにも気をつかわなけらばならない。過去の時代を舞台にした映画であれば、衣裳には時代性がもとめられる。ライトがあてられて映えるかどうか、現代ものであれば映画製作時と公開時のラッグに配慮しなければならないケースもあるだろう。予算への配慮、工房の手配、さまざまな課題が衣裳デザイナー、あるいは衣裳担当部門には要求される。考えてみれば当然のことなのだが、これまで映画といえば、ストーリー、監督のコンセプト、俳優の演技にばかり目が向いていて、衣裳にはあまり着目していなかった。
これがわたしだけのことでないことは、映画の衣裳をテーマにした本がほとんどなかったことからもわかる。アカデミー賞でさえ、衣裳デザイン賞が設けられたのは、戦後、1948年(第21回)からである。
本書は、映画(製作)において衣裳デザイナーが果たした役割を正面からテーマにとりあげて論じた異色の作品である。年代順に編纂されている。グレタ・ガルボとエイドリアン、ディートリッヒとトラヴィス・バントン、グレース・ケリーとヘレン・ローズ、ベティ・デイビスとオリー・ケリー、オドリー・ヘップバーーンとジパンシーなどの幸福な関係とともに、女優とデザイナーの確執もいくつか取り上げられている。
話が具体的であるのがよい、たとえば1924年のパリ・オリンピックを扱った「炎のランナー」で、衣裳を担当したミレナ・カルネロはこの作品に登場する人間の全ての衣裳を20年代の古着を再生してつくったという(pp.273-74)。「ウエスト・サイド物語」でジョージ・チャキリスたちがはいていたジーンズは、ダンスが可能なような素材のものでつくられていて、普通のそれではだめだという(p.210)。アイリーン・シャフのアイデアだったそうだ。
他にも多くの懐かしい映画が紹介され(もちろん、衣裳、デザイナーとの関連で)、懐かしかった。「俺たちに明日はない」「華麗なるギャツビー」「ワーキン・ガール」「裏窓」「花嫁の父」「陽のあたる場所」「マイ・フェア・レディ」「シェーン」など。衣裳の視点から見直したい。また、女優も懐かしい人たち。上記以外では、ローレン・バコール、エリザベス・テーラー、リタ・ヘイワース、グロリア・スワンソン、ドリス・デイ、ナタリー・ウッド、ヴィヴィアン・リー、ジ-ン・セバーク、アン・ロスなどなど。
写真が豊富なのもよいが、残念ながら白黒。カラーだったらもっとよかっただろうが、コストの問題があっただろう。著者は映画評論家で有名な川本三郎の妻。繊維工場の娘として育ち、ファッションライターとして活躍していたが、惜しくも2008年6月に亡くなった。

忘年会シーズン、来る。昨晩は、今年初めての忘年会。そろそろそのシーズンだ。職場の忘年会で、RIVIERAというところであった。ここは池袋西口の立教大学のすぐそばで、結婚式場によく使われている。日中、この前を通過すると、ときどきウェディングドレスで着飾った花嫁とあう。一次会はここで、そういう場所だから料理もまずまず。みな8人がけくらいの円卓に座って行儀よく、飲み、そして食べていた。お酒もすすんだ。
そして、二次会。半分く以上のメンバーは引きあげたようだが、われわれのん兵衛はこれでは足らず、「六方」という居酒屋へ。ここには2・3度来たことがある。場所はわかりやすいが、わかりにくい。分かりやすいというのは、池袋駅から地下街のエティカをまっすぐ歩いて、つきあたったら左におれ、地上にあがる(C3出口)。そうすると道路がはしっている(通称、立教通り)ので、その道路の向こう側にすぐある。わかりやすい。わかりにくいというのは、入口が小さく、地下への細い階段を下りていうからで、この界隈で仕事をしている人でも知らない人が多い。
と、話がながくなったが、ここに12・3人ほどで二次会とあいなった。もう食べ物は要らなかったが、ほんとうは家庭料理が安くておいしいのが「六方」であるから、お薦めである。われわれは日本酒をたくさん飲んで、大いに日ごろのの憂さを晴らした。日本酒も豊富なので、その点でもお勧めである。この日は、一ノ蔵、浦霞を所望した。

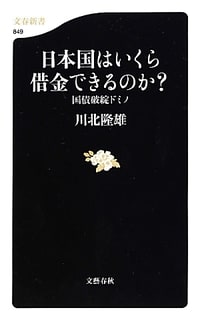
日本の財政が破綻寸前であることは、かなり以前から言われている。今や、世界で最悪である。いろいろな指標でそれを確認できるが、著者はまず政府債務残高の対GDP比に、次いで単年度の財政赤字の対GDP比が重要であるという。前者では日本の財政は200%を超えようとしている。アメリカ97.6%、イギリス90.0%、ドイツ86.9%、フランス98.6%などとくらべても桁違いに高い。EUでやはり財政危機に落ちいってるギリシャでさえ165.1%である。後者でも日本の数字は悪い。この指標で日本は8.9%だが、アメリカ10.0%、イギリス9.4%、ドイツ1.2%、フランス5.7%である。
借金の実額もあがっている。それによると財務省理財局の推計では11年末現在の国の借金総額は954兆4180億円、主計局の推計では12年度当初予算ベースの国の長期債務残高は737兆円(13年3月末)であるという。ものすごい額である。癌は国債の発行に他ならない。国の借金である国債発行額は毎年百数十兆円の規模である。
このような事態に直面しながら、日本財政がまだもちこたえている根拠として、巷間では日本は円を発行できるので国債の償還能力に問題がない、経常収支が黒字基調である、日本は先進国なのでデフォルトは起こりようがない、世界最大の貯金過超国である、この豊富な個人金融資産で国債がほとんど国内で消化されている、などを列挙し、ただちに危険水域に入るわけではないと指摘してきたが、著者はそれらひとつひとつの要因が危うくなってきていることを示し、問題の深刻さを喚起している。
さらに、EU各国の財政危機、ロシア、アルゼンチンのデフォルトおよびアジア通貨危機、アメリカでの国際の格下げの衝撃(2011年8月)との関連のなかで、当該問題を考察し、その行き着く先を展望している。
このままいくと日本の財政は破綻する。時間の問題である。それは7,8年後から10年後というのが著者の予測である(p。226)。その根拠は、「国債など政府債務を国内貯蓄でまかなえるかどうかは、一応個人金融資産1471兆円をベースに考えてよく、まだ317兆円も余裕があるわけだ。問題は、この数字が十分に大きいのかそうでないのか、と言うことである」が(p.157)、2021年には政府債務が個人金融資産を食いつぶすからである(p.226)。

シカゴ学派、リバタリズム(自由市場主義者)で貨幣数量説を唱えた(「インフレは、いついかなる場合も貨幣的な現象だ」)の大御所であるミルトン・フリードマン(1912-2006)は、どういう人物で、どういうことを成したのか?
その思想、考え方には全く同意できまないが、政治・経済の分野で多大な影響力のあった経済学者であったのは事実なので、知っておく必要がある。
米国レーガン政権、英国サッチャー政権の新自由主義的改革の理論的バックボーンであったことは、つとに知られている。
ケインズ流の「大きな政府」に反対し、「小さな政府」を標榜した。資本主義経済が直面した経済不況(恐慌)の治療に、ケインズは財政政策を重視したが、フリードマンは貨幣政策に重きをおいた。
ケインズ政策とは、真っ向から対立している。市場経済、物価の安定、民営化、自由貿易、小さな政府、減税、変動性相場性、税率区分の簡素化、金融政策によるインフレ抑制など多くのメッセージを示した。これらは、現在各国で展開されている経済政策の中心をなすものばかりである。
他に、教育バウチャー制度の導入、麻薬の合法化、福祉削減などの提言も行ったが、違和感はぬぐえまない。
主な著作は「合衆国の貨幣史(アンナ・シュワルツとの共著)」「実証的経済学の方法と展開」「資本主義と自由」「価格理論」「選択の自由(妻との共著)」。
わたしは個人的には、国民経済計算の発展にフリードマンがどのような貢献をしたのかを知りたかったが、本書ではニューヨークの全米経済研究所(NBER)で国民所得関係の仕事をサイモン・クズネッツの助手として遂行していたいたことが簡単に触れられている程度だった(p.57-8)。
経済学の数学利用に関しては、コールズ委員会のようにそれを抽象的で、知的ゲームのように扱う方法論にはくみしなかったようだ(p.79)。MITの数学を駆使した方法論にも批判的だった(p.201)。
フリードマンがチリのピノチエット軍事政権に関与したり、中国、ロシア・ポーランドでの市場経済の推進にひとはだぬいだことは(pp.275-278)、本書でも触れられている。フリードマンがノーベル経済学賞を受賞したさいには、とくに前者の経歴をとりあげて、その受賞に反対する声が大きかったようだ(pp.244-5)。(フリードマンの弟子であるシカゴ・ボーイズが果たした役割についての記述もある[p.243]。)。
1-6章は幼少期から30年代前半、7-19章は学者として円熟期を迎えたシカゴ大学時代、20-24章はメディアで活躍した50年代半ばから晩年まで。巻末にネイサン・ガーデルスによるフリードマンのインタビューがある。
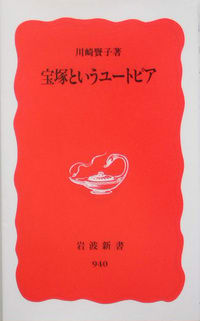
昨日の記事に書いた宝塚歌劇鑑賞のあとに、この本を読む。宝塚歌劇とはいったい何なのか?
宝塚歌劇の魅力を論じた本。叙述(言い回し?)がやや難解なところがある。宝塚歌劇団とは何かをてっとりばやく理解するには、「第5章 宝塚というシステム」を読むのがよい。この章はそれ以前の章とのつながりがなく独立していて、またこの章だけ文章がわかりやすい。
さて宝塚歌劇団であるが、この歌劇団は箕面市有馬電気道株式会社(現阪急電鉄)の小林一三が1913年に梅田発宝塚終点の私鉄沿線の乗客掘り起こし政策の一環として構想し、1914年に第一回公演を立ち上げた。少女ばかりの20人の唱歌隊だった。以来、2004年の創立90周年までに舞台にのぼった生徒の数は4000人を超える。
公演には宝塚音楽学校を卒業した未婚の女性に限られ、男性の役を演じる「男役」と女性の役を演じる「娘役」がいて、独特の表現様式が構築されている。本書では、小林一三の構想にあったイギリス流「田園都市」構想理念、1910年代に華々しく展開された女性論の背景、20年代の大劇場建設(「国民劇」構想)とレビューの登場(「モン・パリ」でのレビュー路線の導入)、30年代におけるスター・システムの導入と男役・娘役の分化、40年代の戦時下占領下の雌伏と女性客の増加、50年代以降のスター育成のさまざまな段階のイベント化、60年代のミュージカル路線の定着、70年代のタカラズカジェンヌとしての<私>のメディア化(「ベルサイユのバラ」ブーム)、近年のファン活動のイベント化の歴史を丁寧に解説している。
初期に岸田辰彌、益田太郎冠者、白井鐵造らが主としてヨーロッパに渡り、舞台づくりが模索されたことは特筆されるべきであり、現在の公演形式が固まるまでには幾多の変遷があったことはおさえておくべきである。
いまの劇団のかたちは、簡単にまとめると次のようになる。まず体制が5組(花・月・雪・宙・星)、各組に80人ほどの演技者、組長、副組長がいる。メンバーは宝塚音楽学校の卒業生。各組に所属しない上級生の「専科」がある。歌劇団スタッフは、演技者の他に、作家・演出家、音楽家、振付、衣裳、美術、大道具・小道具、照明、運営、製作、営業の係員も自前である。ファンも独特の役割をもつ。
宝塚歌劇はレビュー(大きな舞台空間を埋め、多くの観客にアピールする踊りと歌のスペクトル)を特徴とするが、そのレビューについて、著者はこう述べている。「『西洋物』と『東洋のものを西洋風に』演出したものを陳列し展示する『世界』だが、その『源流』はじつはどこにもない。不在の感覚は、遅れて近代化した地域のひとびとの『故郷喪失』の心性に即応し、共振するものである。ノスタルジアの実体的な対象にたどりつくことのできないまなざしは、ユートピア幻想へと折り返される。重要なのは、宝塚レビューの作り手たちが、その仕組みを熟知して大衆を誘惑しつづけたことだろう」と(p.65)。

宝塚歌劇というものを観に行く。全く、未知の世界だ。女性だけが舞台に登場して演技する。男装の女性と娘役の女性。歌舞伎と正反対ということはわかる。しかし、そこまでしかわからない。
映画、舞台の名女優には宝塚出身者が多い。乙羽信子さん、大地真央さん、毬谷友子さん、麻美れいさんなどなど数えきれない。
ともあれ、一度は観るべしということで、有楽町にある東京宝塚劇場(帝国ホテルの前)に出かける。演劇の観客は一般に女性が多いが、宝塚はもっと多い。9割以上が女性。そして、満席だ。
舞台は2部にわかれていて、前半はグランステージ で『JIN-仁-』、後半はショー・ファンタジー。
「JIN-仁-」は村上もとかさんの漫画(集英社)が原作。主人公・南方仁と橘咲の時空を超えた純愛、坂本龍馬との友情をが中心にした話で、現代人が忘れた命の尊さを、時を超え二つの人生を生きた仁の生き方を通して訴ている。ヒューマンドラマだ。
ショー・ファンタジー「GOLD SPARK!-この一瞬を永遠に-」のほうは、雪組トップスター音月 桂が放つ“輝き”の一瞬一瞬を永遠に刻みつけるショー作品。躍動して駆け抜けるダンサーたちのうねりがすごい。
とにかく、舞台づくりが華やか。キラキラ輝く衣装にはめくるめく。素敵な脚線美のラインダンス、美しくとおる声、オケピには生の演奏、階段から降りてくる美女の群れ、パラダイスである。
筋は単純で、「何だこれ?」と思ったところがあったり、セリフが単純すぎる部分もあったが、そういうことに意を介してはだめなようである。単純にこの世界にのめりこみ、愉しむのがいいようだ。

わたしは東京生まれだが、父の仕事の関係で、生後数カ月で札幌市へ。以来、札幌市で幼少、青年期を過ごし、最初の就職もそこだった。子どもの頃、数回上京したが、汽車で24時間以上。大変な道のりで、東京は空間的にも、心理的にも遠かった。しかし、そこでは大好きな大相撲、プロ野球が行われ、正月には雪が積もっていない。子どもの頃のわたしに、東京への憧れや妬ましさが全くなかった、といえばウソになる。
本書はわたしよりもはるかに強く、東京に関心をもち、実際に上京し、そこで作品を書いた作家たちの志をたどってまとめた興味深いもの。登場するのは、斎藤茂吉(山形)、山本有三(栃木)、石川啄木(岩手)、夏目漱石、山本周五郎(山梨)、菊池寛(香川)、室生犀星(石川)、江戸川乱歩(三重)、宮沢賢治(岩手)、川端康成(大阪)、林芙美子(山口)、太宰治(青森)、向田邦子、五木寛之(福岡)、井上ひさし(山形)、松本清張(福岡)、寺山修司(青森)、村上春樹(京都)[漱石は小説「三四郎」の主人公の上京について書かれている。向田は東京出身であるが、子どもの頃転勤で各地を回り、東京がふるさとであったと同時に、憧れの対象だった]。
彼らが、(当時)いかに東京に憧れ、そこで暮らすことを夢見たか。想像力を強く働かせないとわからないが、電車や飛行機で簡単に行くことができる今とは比較にならないことだけは確かである。彼らは東京の何に興味をもち、驚いたのか、それがよくわかる。
上野駅のまばゆさに驚いた茂吉(故郷の夜は漆黒の闇)、停車場、新聞社などの都会の装置(啄木)、大きな図書館(菊池寛)、「ふるさと」への想い(犀星)、軟式野球ボール(ひさし)、早稲田大学の寮(春樹)などなど。
彼らの憧れと志の先にあったのは、近代の文化装置、銀座の匂い、妙なよそよそしさとその対極にある自由、ある種のいかがわしさ、シュールであるが退廃的でもある時代の空気だった。日本の近代文学の黎明期に、東京に憧れた文学者が果たした役割は大きく、彼らの作品はまぎれもなく骨太だった。

山本周五郎の珠玉の短編集。「あとがき」に木村久邇典が「解説」を書いているが、小説の筋を要領よくまとめているだけなので、これは(とくに小説を読む前に)読まない方がよい。
というのも、この文庫におさめられている10編の小説は、読み始めのうちは様子があまりわからず、一体この人はどういう人なのだろう、この件はどうなっていくのだろう、と思わせておいて、それが読み進むうちに次第に事情がわかっていくというつくりになっているし、この作り方が周五郎の短編の魅力のようなので、あらすじがわかってしまって読むのでは愉しみが半減する。筋を自分で追いながら読むべきであり、この作家はそういう力で読者をひっぱっていくのが得意なようだ。
10編の小説はいずれも舞台は歴史的過去であり、江戸時代であったり、平安時代であったりである。個人的には「おさん」「青竹」「みずぐるま」が印象的で、「偸盗」はそうではなかった。
「おさん」は、性の営みのたびに別の男の名前を呼んで陶酔するおさんが、その性のゆえに男を破滅に導き、最後は自分も匕首に刺されて死ぬ。女の業を宿命的に背負って生きたひとりの女。
「青竹」は敵方の大将を討った伊予藩士が恩賞を所望するでもなく、生涯の妻と心に決めた娘の死を知り、墨絵かぶらの旗差物に数珠を描き添えて戦場を死守する逸話。「みずぐるま」は旅芸人の一座のメンバーで、薙刀を使いのうまい太夫の少女が、武家の重職に養女となり、さまざま流転を経験しながら健気に生きていく物語。
その他の「並木河岸」「夕靄の中」「葦は見るいた」「夜の辛夷」「その木戸を通って」「饒舌り過ぎる」も心地よい読後感を愉しめる佳作。

今年は早稲田大学交響楽団(ワセオケ)の創立100周年記念です。その連続演奏会が開催中。第3回目が東京芸術劇場コンサートホールで12月11日にあった。
演奏曲は次の通り。
・ヴェルディ 歌劇「運命の力」序曲
・ストラビンスキー バレエ曲「春の祭典」
・サン=サーンス 交響曲3番 ハ短調 作品78 「オルガン付」
指揮者は大友直人さん、演奏者が多く、音に厚みがある。コントラバスだけで10本。今回は金管、木管が冴えていた。ティンパニも演奏の見事な下支えをしていた。
ストラビンスキーの「春の祭典」、サン=サーンスの「交響曲3番」は、音あわせだけでも大変そうと素人には思えるが、そのような部分はなんなくクリアしていたようだ。とくに、サン=サーンスのほうは、最後のもりあがりが見事だった。
この楽団のHPを見ていたら次の記述があった。難しい(聴くのも、たぶん演奏も)ストラビンスキー「春の祭典」をとりあげた理由がわかった。引用する。
「『未完成」交響曲』よって新たな歩みを始めた『早稲田大学管弦楽団』は、1955年には『早稲田大学交響楽団』へと改称した。1978年9月、早稲田大学交響楽団は第5回国際青少年オーケストラ大会(カラヤン・コンクール)出場のため、初めての海外公演へ出発した。ヴェルディ/「運命の力」序曲を課題曲として、難曲と考えられていたストラヴィンスキー/「春の祭典」を自由曲として高い精度で演奏し、優勝を勝ち取った。これ以来、早稲田大学交響楽団は「春の祭典」と共に世界での評価を高めていった。」と。










