
シェイクスピアに関する著作があり、ポプリ研究家としても知られる著者は、映画監督熊井啓の妻でもあった。
熊井監督の映画は、「忍ぶ川」「サンダンカン八番娼館・望郷」「海と毒薬」「深い河」などは観たが、「天平の甍」「黒部の太陽」は未見である(「破獄」「俊寛」は完成の予定だったが、原作者あるいは監督の死で実現できなかったようだ)。
本書は、著者と熊井啓との出会い、結婚、そして46年の文字どおり一体だった人生を、つづったもの。妻でなければ知ることのできない熊井監督の人柄、映画製作に向かう姿勢、人生観をうかがいしることができる。
同時に、著者自身が自立した女性として、自らの生きる道をみいだし、その分野で大きな仕事をなしとげ、多くの人たち(五所兵之助、岡本太郎、大橋鎭子、辻邦雄、志村喬、森茉莉、田辺聖子、モーリス・メッセダなど)との交流をたもってきたプロセスを知ることができた。ジャン・コクトーへの傾倒、熊井監督が「忍ぶ川」を製作したころの壮絶な病との戦い、などどのページをめくっても真剣な生き方が伝わってきて、いい意味の緊張感をもって著者とかかわることができた。
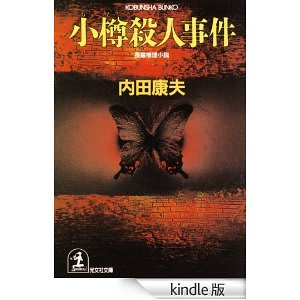
ある広告代理店の依頼で小樽に取材旅行に行くことになった浅見光彦。運の悪いことに、薄明の小樽港に船が入ったところで女性の漂流死体に遭遇する。
女性は勝子という小山内家の人間だった。幕末の頃、蝦夷の開拓のために渡った豪族の末裔である小山内家は小樽では有数の旧家で、かつては大尽といわれたほどの素封家だった。いまではかつての威容はなく、長男章一が跡をついで何とかしのでいるありさまだった。この長男の姉が高島勝子でなかなかのヤリ手で、忍路にクラブをもっていた。章一の妻淑江はわけあって(落ちぶれた津田家を救うために)、本州からここに嫁いできた(勝子は淑江の義理の姉にあたる)。
その淑江は、事情があってかなり年齢の離れたOLの麻衣子を小樽に誘う。息抜きの休暇とおもって飛んできた麻衣子だったが、この殺人事件に巻き込まれ、足止めをくう。さらに勝子の妹俊子が自分の部屋で不審な縊死。勝子、俊子二人の死亡現場には、謎の黒アゲハチョウがそえられていた。
蝶の謎を究明するために光彦と麻衣子は信州・安曇野へ赴く。そこで二人は、淑江のかつての恋人の写真を手にし、彼が自殺していたことを知る。いったい何があったのだろうか。淑江のいまは行方不明の夫、勝子の愛人が絡んで、真相はなかなか見えてこない。地元警察の捜査も暗礁にのりあげ、手をこまねいていたが、光彦は独自の推理を働かせ、聞き取り調査で裏付けをとっていく。その結末は。殺人犯は意外な人物だった。

式年遷宮の伊勢へのお詣りの前に立ち寄った、豊川稲荷。東京からは、「こだま」に乗車して、豊橋で下車、そこからバスで稲荷まで進みました。
曹洞宗の寺院です。広い境内、大きな本殿が印象的でした。正式の寺号は妙巌寺(妙厳寺の本尊は千手観音です)。境内に祀られる鎮守の稲荷(吒枳尼天)が有名なため、一般には「豊川稲荷」の名で広く知られています。日本三大稲荷のひとつです。豊川稲荷は神社ではないのですが、商売繁盛の神として知られており、境内の参道には鳥居が立っています。
嘉吉元年(1441年)、曹洞宗法王派の東海義易によって創建されました。室町時代末期、今川義元が伽藍を整備したといわれています。現存する諸堂は江戸時代末期から近代の再建です。
霊狐塚が有名です。1000体以上の狐の石像です。また、千本幟が参道に、はためいています。参拝者の願い事が書かれています。近隣の名古屋の方の幟が多いですが、埼玉県の久喜市の方のそれもありました。


式年遷宮の伊勢神宮ご参拝のおりに寄ったのが熱田神宮と豊川稲荷。
熱田神宮は、名古屋の市街地にありますが、静寂で緑の多いところです。市民のオアシスになっています。神苑の面積は19万㎡。クス、ケヤキ、アシ、シイ、ムク、イチョウ、クロガネなど広葉樹が多いとか。樹齢千年前後と言われるクスの巨木は有名です。
境内には本宮の他、別宮、12の摂社、31の末社が祀られています。本宮の社殿構造は、明治26年に尾張造りか神明造りに改められ、現在の社殿は創祀1900年記念事業として2009年(平成21年)に造営を終え、10月10日に遷座したものです。
ご祭神は熱田大神。熱田大神は三種の神器の一つである草薙神剣を御霊代とされる天照大神のことです。熱田神宮の創祀は、草薙神剣の奉斎に由来します。
またここには信長塀といわれるものがあります。織田信長が桶狭間の戦いで勝利したさいに、奉納したものです。いまでも、一部がそのまま残っているのです。また、相撲のための土俵もありました。境内の地図があり、土俵をみつけたので、相撲好きのわたしとしては見逃すことができず、探し出して写真をとってきました。相撲はかつて神事だったのです。
この日は(11月30日)、天気もよく、空はよく晴れ、境内は静寂で、気持ちのよい時をすごしました。

おいしいちゃんこ鍋屋さんです。
屋号そのまま、もと関取の玉海力が経営者です。
エレベータを出ると、そこから先はすぐにお店屋さんになっていて、小さい土俵があります。予約していなかったので、大変混んでいて、すぐにはいれませんでした。土俵の前の椅子席で待つこと15分ぐらいでカウンター席につけました。かつての横綱の手形があり、玉海力関の額入り写真があり、完全にお相撲モードです。
店員さんがたくさんいて、きびきび動いています。「俺が好き」のロゴが背中に入った紺色のシャツを店員さんは着ています。なかに、体格のいい店員さん。やはりもと力士でした。芝田山部屋(元横綱大乃国)所属だったとのこと。弟さんが幕下30枚目程まで、あがってきているようです。
クロダイの刺身、しめさばを注文。ちゃんこももちろん。味がよく、ちゃんこなので、鶏肉のだんご、豚バラの他に野菜がたくさん入っています。健康にいい食事です。最近はほtんど口にしたことがないので、この味に懐かしさも感じました。具を食べてしまうと、麺を入れてくれます。ときどき、そばに来て、鍋のなかを覗いて、火加減などみてくれます。まことに親切至極。
若い人が多く、わたしの右も左もカップルでした。みな、ちゃんこに舌鼓です。
相撲のことは、この元お相撲さんに聞くと、なんでも答えてくれます。店員には他に、慶応義塾大学の学生さんも2人いました。

歌舞伎座十二月公演に出かけました。演目は「仮名手本忠臣蔵」です。この演目はもともと、人形浄瑠璃だったもの。いわゆる「忠臣蔵」は、この「仮名手本忠臣蔵」がベースになっています。寛延元年(1748年)8月、大坂竹本座にて初演。全十一段。二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳の合作。元禄赤穂事件を題材としたものです。
「仮名手本忠臣蔵」の「仮名手本」というのは「いろは47文字」で「四十七士」を意味し、「忠臣蔵」は「中心大石蔵之助」を表しています。したがって、「仮名手本忠臣蔵」というのは「大石蔵之助と四十七士の物語」ということになります。
この作品は、「義経千本桜」「菅原伝授手習鑑」とともに歌舞伎の三大名作と言われる演目です。義太夫狂言の傑作としてファンに親しまれています。江戸時代に実際に起こった赤穂浪士討ち入り事件に題材をとり、大星由良之介をはじめとする四十七士の仇討までの人間模様が描かれています。歌舞伎座新開場杮茸落12月歌舞伎では、「5段目」「6段目」「7段目」「11段目」が演じられました。
豪華メンバーです。松本幸四郎、市川染五郎、中村獅童、中村七之助などなど。それから、何といっても坂東玉三郎ですね。ため息が出るような素晴らしい演技とオーラです。
<五段目>
猟師となった勘平は、山崎街道で同志の千崎弥五郎に出会います。そこで勘平は、仇討の資金調達を約束します。おかるの父与市兵衛は夜道で斧定九郎に襲われて殺され、勘平の仇討資金用立てのためにおかるを身売りした前金の50両を懐から奪われます。しかし、その定九郎もイノシシを狙って撃った勘平の銃弾で絶命。誤射した勘平は、あわててその50両を抜き取り、逃亡します。
<六段目>
おかるを引き取りに来た祇園一文字のお才の言葉から、昨晩撃ち殺した者が舅の与市兵衛と思い込む勘平。姑のおかやに詰問された勘平は、罪を認め切腹しますが、ちょうどそこにきていた不破数右衛門と千崎弥五郎か真犯人が定九郎だったことが判明します。勘平の疑いは晴れましたが、仇討の連判に名を連ねることを許されると、安堵して息絶えます。
<七段目>
祇園で遊興にあけくれる大星由良助のところへ、おかるの兄の寺岡平右衛門が訪れ、仇討に加わりたいと願い出ますが、相手にされません。息子の力弥が届けた密書を、遊女おかると斧九太夫に盗み見されたことに気付いた由良之介は、おかるを殺そうとします。それを察した平右衛門は、自ら妹のおかるを手にかけようとしますが、由良之介に止められます。事情を知った由良之介は、おかるに九太夫を殺させ勘平の仇を討たせ、平右衛門を連判に加えます。
<十一段目>
由良之介率いる塩治の浪士たちは、師直の屋敷に討ち入ります。激闘の末、炭部屋に隠れていた師直を追い詰めた浪士たちは、師直の首級をあげ、本懐をとげます。
<五・六段目>
早野勘平 染五郎
斧定九郎 獅童
女房おかる 七之助
母おかや 吉弥
判人源六 亀蔵
千崎弥五郎 高麗蔵
一文字屋お才 萬次郎
不破数右衛門 弥十郎
<七段目>
大星由良之介 幸四郎
寺岡平右衛門 海老蔵
竹森喜多八 松 也
冨森助右衛門 廣太郎
大星力也 児太郎
斧九太夫 錦 吾
赤垣源蔵 亀三郎
遊女おかる 玉三郎
<十一段目>
大星由良之介 幸四郎
原郷右衛門 友右衛門
奥田亭右衛門 宗之助
矢間重太郎 竹 松
冨森助右衛門 廣太郎
大星力也 児太郎
竹森喜多八 松 也
小林平八郎 獅 童

老いをどのように受け入れるかは、人間全体にとっても、個人にとっても、永遠のテーマだ。とくに、90歳をこえる長生きが珍しくなくなった現在、高齢化は社会問題であるとともに、ひとりひとりの問題でもある。尊厳死とか、安楽死とかも日程にのぼるのだろうか。
この映画はこの問題を問いかける。
47年連れ添った夫に先立たれた老いた母イベットは、48才の今は独り身の男アランと一緒に暮らしている。長距離トラックの運転手だったアランはかつて麻薬の密輸に関連して、18か月間刑務所にいたが、いまは出所して再出発を期している。しかし、当面の仕事もなく母のもとに転がりこんで、生活をともにしはじめた。いい仕事はなかなか見つからない。ようやく、就いた仕事は、ごみ処理の分別作業。生きていくには仕方のないところだが、いやいやの仕事であり、生活は貧しい。気晴らしだろうか、ボーリングに興じ、たまたま隣のレーンでボールを投げていた女性クレメンスと親しくなり、ベット・イン。いい関係に発展しそうになるが、所詮、男は可たるべき自分がない。女はそんな男に愛想をすかし、去っていく。
老いた母は、不治の病気をかかえている。悪性の腫瘍で、頭のなかで少しづつ大きくなっている。生活はいまのところ、無理をしなければとくに支障はない。几帳面な性格で、炊事、掃除、洗濯の日常生活はきちっと過ごしていく。ときどき気をまぎらすのはジグゾーパズル。隣人の男性ラルエットとも行き来し、変化には乏しいが、ゆったりと時間が過ぎていっているようだ。
ある日、男は薬をいれてある箪笥の引き出しに書類をみとめる。みると尊厳死を紹介した協会からの書類のようで、母親はサインをしていた。いつか、尊厳死を受け入れることを承諾した書類だった。母は息子のことが心配で、言葉はすくないが、ときどき生活をたてなおすように咎める。ある日、ついに、息子はキレた。母親に怒鳴り声で悪態のかぎりを言い、家を出ていく。
男は友人ラルエットの家に転がり込んでいた。心配してラルエットが家を見に来るが、母親もどうすることもできない。決定的な決裂で、関係の修復は無理そう。そんな時、母は家でかってい愛犬に誤ってネズミ殺しを食べさせてしまった。苦しむ犬をみかねて、連絡でもしたのだろうか男が戻ってくる。犬を必死で介護し、どうやら命はとりとめた。
イベットの病状はさらに進行する。生活もつらそうになってくる。みかねて教会の人が尊厳死の説明にくる。了解する母親。息子とともにスイスの施設に入る。母親はそこで納得して薬をあおぐ。息子と抱きあう、彼女はなきながら最後の別れをつげる。息子も母親をしっかり抱くが、母親は次第に弱って、ついに死んでいく。
ひとつ冷めた眼でみると、イベットの生活はどのように成り立っていたのだろうか。年金はもらっていなかったのだろうか。アランの生活は苦しく、仕事もしていない。となると、イベットがもらっていたかもしれない年金は当面、必要ではなかったのだろうか。その辺が、ストーリーでは全然、問題になっていなかった。現実的すぎる話かもしれないが、少々、気になった。
1時間47分ほどの映画。画面はたんたんと流れていくが、場面の切り替えはうまい。思いがけなくシーンの切り替えがあり、観客はそこで切り替わった場面をゆっくり考える時間を共有できる。おしつけがましいところのない展開だ。
最後の場面。亡くなった母を施設の人たちが車で、火葬場にだろうか、運んでいく。そして男がうつる。何も語らず、しかし、たばこをふか、追憶でもしているのだろうか。それが数分続き、FIN。深い余韻を残して映画は終わった。
原題は”Quelques heures de printemps”、直訳すると「春の数時間」です。
・ヴァンサン・ランドン(アラン)
・エレーヌ・ヴァンサン(イベット)
・エマニュエル・セニエ(クレメンス)
2013年セザール賞4部門(主演男優賞、主演女優賞、監督賞、脚本賞)ノミネート

伊勢神宮は、今年、式年遷宮でにぎわっています。わたしは、神道とも仏教とも無縁ですが、日本文化を理解するうえで、一度は伊勢神宮を観ておきたいと思い、でかけました。
想像以上の人の波です。観光バスで、次々と人がおしよせています。地元の方の話によると、初詣のおり以上とのこと。
鳥居から入って、宇治橋を渡り、右ににおれて進みます。人の流れについていくという感じです。火除橋を渡って手水舎で清め、さらに五十鈴川御手洗で心身を清め、正宮に向かうのです。そのあと、荒祭宮などをお参りします。
式年遷宮は20年に一度、正宮をはじめ、お社を建て替えること。それが長い長い歴史のなか、もう2000年以上も続いているようです(途中、中断あり)。なぜ、20年に一度かについては、諸説があるようですが、建て替えの技術が世代継承されるのに20年ほどかかる「からというのが真実に近いようです。建て替えといっても、それ自体が神事とむすびつけられながら行われるので、時間がかかるようです。ここでは、時間の流れが、都会とは全然、違うのです。
伊勢神宮は天照大御神を祀る内宮と豊受大神を祀る外宮とに分かれています。さらに別宮や摂社・末社・所管社など全部で125社があります。これらを総称して、伊勢神社というのです。
その起源は、神話から始まります。「日本書記」には、皇女の倭姫命が天照大御神の鎮座する地を求めて旅をし、伊勢を選んだということになっています。その後、雄略天皇が夢の中で、天照大御神から「豊受大御神を呼び寄せるように」との神託を受け、豊受大御神が丹波から山田原に迎えられたのです。ここは全国に5000社ほどもある神社の本宗です。
外宮からお詣りして、バスで10分ほどかけて内宮に移動、そこでなかをひとまわりしますと小一時間かかります。森林のなかにあるので、ひんやりした空気のなか、森林浴を楽しめます。
外宮、内宮をひとわたりお詣りしたあとは、「おかげ横丁」に入ります。ここも雑踏でした。いろいろなお店があり、歩くだけでも面白いです。和太鼓をたたいている勇壮な場面もありました。
伊勢神宮には、新幹線で行きました。車中から富士山が、それはきれいでした。豊橋でおり、豊川稲荷に行き、そのあと熱田神宮へ。一泊して伊勢に入ったのです。車中からみた富士山の写真も掲載します。時間の推移と逆ですが、次回は豊川稲荷と熱田神宮を紹介します。


カイユボット展が東京駅八重洲口に近いブルジストン美術館で開催されている(10月10日ー12月29日)。
カイユボット(1848-1894))は印象派の画家ですが、あまり知られていません。日本では近年、人気がでてきたようです。それで展覧会が開催されたのでしょう。
しかし、本国のフランスでは、モネ、ルノワールと並ぶ代表的な印象派の画家です。1876年の第2回印象派展以降、5回にわたってこの展覧会に参加しました。画家として有名なのはもちろんですが、当時まだ評価の定まらなかった、印象派の仲間の作品をコレクションしたことでも知られています。
作品の対象としては、近代都市パリの風俗、風景、イエールやジュヌヴィリエといったパリ近郊の自然が選ばれました。新興ブルジョアジーと労働者にも、まなざしを向けました。
展示場のなかの作品では、「自画像」「室内、窓辺の女性」「ギュスターヴと犬のベルジェール、カルーゼル広場」などが印象にのこりました。よく知られた「ヨーロッパ橋」もありました。
展示場の床に、当時のパリの地図があり、どこで印象派展が行われたなどの案内がありました。現在のパリの街並みとほとんど変わっていないことが確認できます。
それと弟マルシャル・カイユボットが撮影した写真もたくさんありました。貴重です。










