長く、閲覧、ありがとうございました。
わたしの日々の様子は、FB 岩崎俊夫 でお知らせしています。
 今しがた、原田眞人監督・脚本『駆け込み女・駆け出し男』をさいたま新都心の「MOVIXさいたま」で観てきました。井上ひさし原案の話題作です。 ときは天保12年、老中・水野忠邦の天保の改革が進行中。当時、離縁を希望する女が駆け込む寺がありました。鎌倉の東慶寺という尼寺で、幕府公認の駆け込み寺でした。 その東慶寺へ、ふたりの女が命からがら逃げ込んできます。ひとりは日本橋唐物問屋・堀切屋三郎羽左衛門(堤真一さん)のめかけ「お吟」(満島ひかりさん)、もうひとりは七里ガ浜・浜鉄屋の主人(武田真治さん)の妻鉄練り職人の「じょご」(戸田恵梨香さん)。ふたりはそれぞれのいわく付きで東慶寺に駆け込む途中で、出会い、互いに身の上をしって一緒に駆け込んできたのです。 同時にひとりの男・中村信次郎が東慶寺をめざしてきました。お吟とじょごが追ってと勘違いしたこの男は、駆け込み前に意思表示を聞き取り調査する御用宿の女主人・源兵衛(樹木希林さん)の甥っ子でした。この甥っ子は滝沢馬琴を尊敬する駆け出しの戯作者であり、医者の見習いです。滝沢馬琴さんは、名優山崎努さんが演じています。 お吟もじょごも怪我をしています。駆け込み寺に駕籠でかけつけたお吟は、途中で、駕籠担ぎに襲われ、大けがを。鉄練り職人のじょごは、顔にやけどのなまなましい跡が。医者のはしくれである信次郎は、二人に懸命に治療にあたります。
今しがた、原田眞人監督・脚本『駆け込み女・駆け出し男』をさいたま新都心の「MOVIXさいたま」で観てきました。井上ひさし原案の話題作です。 ときは天保12年、老中・水野忠邦の天保の改革が進行中。当時、離縁を希望する女が駆け込む寺がありました。鎌倉の東慶寺という尼寺で、幕府公認の駆け込み寺でした。 その東慶寺へ、ふたりの女が命からがら逃げ込んできます。ひとりは日本橋唐物問屋・堀切屋三郎羽左衛門(堤真一さん)のめかけ「お吟」(満島ひかりさん)、もうひとりは七里ガ浜・浜鉄屋の主人(武田真治さん)の妻鉄練り職人の「じょご」(戸田恵梨香さん)。ふたりはそれぞれのいわく付きで東慶寺に駆け込む途中で、出会い、互いに身の上をしって一緒に駆け込んできたのです。 同時にひとりの男・中村信次郎が東慶寺をめざしてきました。お吟とじょごが追ってと勘違いしたこの男は、駆け込み前に意思表示を聞き取り調査する御用宿の女主人・源兵衛(樹木希林さん)の甥っ子でした。この甥っ子は滝沢馬琴を尊敬する駆け出しの戯作者であり、医者の見習いです。滝沢馬琴さんは、名優山崎努さんが演じています。 お吟もじょごも怪我をしています。駆け込み寺に駕籠でかけつけたお吟は、途中で、駕籠担ぎに襲われ、大けがを。鉄練り職人のじょごは、顔にやけどのなまなましい跡が。医者のはしくれである信次郎は、二人に懸命に治療にあたります。  駆け込み寺に入るには作法があり、駆け込むにいたった経緯の聞き取り調査が行われるのです。源兵衛は番頭の利平(木場克己さん)とその女房・お勝(キムラ緑子さん)の前で、彼女たちのこれまでの経緯を聞き取り、ふたりはお寺に入ることを許されます。 駆け込み寺に入ってくるものには、いろいろな人がいて、それぞれのわけありの人生があります。男社会で、封建社会。女たちはトタンの苦しみを背負ったひとばかり。幕府側からの陰謀もうごめいています。 天保改革の頃の江戸時代の様子、駆け込み寺・東慶寺の果たした役割、その内部の秩序がよくわかり、俳優さんたちもみな渾身の演技で、大満足の映画でした。
駆け込み寺に入るには作法があり、駆け込むにいたった経緯の聞き取り調査が行われるのです。源兵衛は番頭の利平(木場克己さん)とその女房・お勝(キムラ緑子さん)の前で、彼女たちのこれまでの経緯を聞き取り、ふたりはお寺に入ることを許されます。 駆け込み寺に入ってくるものには、いろいろな人がいて、それぞれのわけありの人生があります。男社会で、封建社会。女たちはトタンの苦しみを背負ったひとばかり。幕府側からの陰謀もうごめいています。 天保改革の頃の江戸時代の様子、駆け込み寺・東慶寺の果たした役割、その内部の秩序がよくわかり、俳優さんたちもみな渾身の演技で、大満足の映画でした。  ・大泉洋 (中村信次郎)・戸田恵梨香(鉄練り じょご)・樹木希林(三代目柏谷源兵衛)・堤真一(堀切屋三郎右衛門)・山崎努(曲亭馬琴)・満島ひかり(お吟)・内山理名(戸賀崎ゆう)・陽月華 (法秀尼)・キムラ緑子(お勝)・木場勝巳(利平)・神野美鈴(おゆき)・武田真治(重蔵)・北村有起哉(鳥居耀蔵)・橋本じゅん(近江谷三八)・山崎一(石井与八)・女貸本屋(高畑淳子)・でんでん(為永春水)
・大泉洋 (中村信次郎)・戸田恵梨香(鉄練り じょご)・樹木希林(三代目柏谷源兵衛)・堤真一(堀切屋三郎右衛門)・山崎努(曲亭馬琴)・満島ひかり(お吟)・内山理名(戸賀崎ゆう)・陽月華 (法秀尼)・キムラ緑子(お勝)・木場勝巳(利平)・神野美鈴(おゆき)・武田真治(重蔵)・北村有起哉(鳥居耀蔵)・橋本じゅん(近江谷三八)・山崎一(石井与八)・女貸本屋(高畑淳子)・でんでん(為永春水)
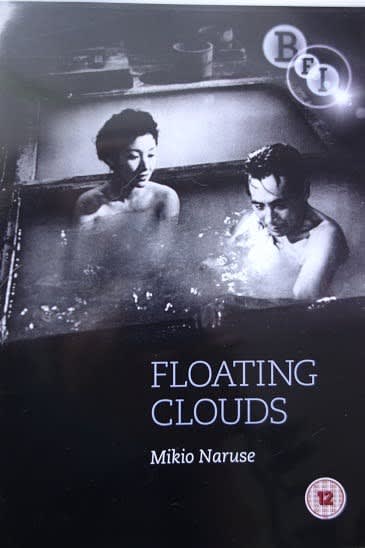










これも韓国映画らしい作品。

貧しい家庭環境のなかに生きる主人公ワンドゥギ(ユ・アイン)は、世をななめにみて、反抗的な高校生生活をおくっている。父親は脚が不自由で、街頭での踊りから入る収入で、どうにか暮らしている。母親はいない(らしい)。住んでいるところは、バラックのよう。このようなところが、現在の韓国にもあるrのだろうか。貧しい人たちが密集して暮らしている。喧嘩、罵声が絶えない。
ワンドゥギの通って高校は夜間高校だろうか。この担任の名前はドンジュ(キム・ユンスク)。ワンドゥギの家のすぐそばに住んでいて、ワンドゥギの生活にしじゅう介入してくる。しかし、ドンジュは粗野で、ガサツな教師にみえるが、きわめて人間臭い。
ワンドゥギとこの教師とのやりとり、確執、人間的交流がこの映画の中心になってるが、ワンドゥギを囲む人は他にもたくさんいて、教室の仲間、優等生の女子学生ユナ、もうとうにいなくなっていたと思っていたフィリピン国籍の母親(イ・ジャスミン)、画家らしいかヤジ暴言の隣人、ドンジュが恋心をいだいた画家の妹で武侠小説を書いているというホジュン(パク・ヒンジュ)。
ドラマの語源は、ギリシャ語。「葛藤」という意味合いだ。その意味で、この映画は、ホントのドラマだ。ワンドゥギと教師ドンジュ、父親との葛藤。久しぶりに再会した父母の葛藤、ワンドゥクと成績優秀なユナとの葛藤。それらの葛藤のなかに、ユーモアがあり、ペーソスがある。強がってみたり、小心になったり。みながみな小さい空間でぶつかりあい、ののしりあいながらも、次第に心をとけあわせ、信頼が形成され、一歩づつ人生を進んでいく。共感をもって鑑賞した108分だった。


 パリの高級アパルトマンに住むフリーダ(ジャンヌ・モロー)。ひとり暮らしで、気難しい。彼女はエストニア人で、かつては同郷のひとたちとの交流もあったが、いまは絶えている。 彼女のアパルトマンには、ステファン(パトリック・ピノー)という中年の男性がときどき様子をみに来ている。ステファンはかつては、フリーダと愛人関係にあったようだ。ステファンは、フリーダからプレゼントしてもらったカフェでオーナー。カフェはそこそこ繁盛している。 そのステファン。フリーダが高齢化し、ときどき大量の薬を飲むような行動を取り始めているので、家政婦にきてもらうことを考え、つてをたどって、アンヌというエストニアに住む中年女性に、依頼。彼女は母に死なれ、鬱屈した日々を過ごしていたが、このパリでの仕事にかけることにする。 気難しいフリーダは彼女に相談なく家政婦を雇ったことが気にくわなく、生真面目なアンヌを無視したり、嫌がらせをしたり。朝食には、クロワッサンと紅茶が習慣だったが、それを用意できないアンヌに腹をたてる。アンヌはスーパーでクロワッサンを買い、これをフリーだのもとに運ぶが、「こんなプラスチックのようなものを食べれるか。パン屋で買いなさい」と、紅茶をわざと床にこぼしながら言う。 アンヌはここでの家政婦に自信をなくし、故郷に帰ることを決意し、ステファンに相談をもちかけるが、なだめられ、考え直す。 このあと、エストニア人のかつての仲間がフリーダの部屋に再会に来たのを悪罵で追い返したり、フリーダとアンヌとの確執が強まったり、弱まったりといろいろあるが・・・・。さて、その結末は。 あっけないと言えばあっけない、ラストシーン。 この映画では会話が多くなく、パリのすばらしい光景(エッフェル塔、凱旋門、ルーブル、街並み)がたっぷりスクリーンに浮かび上がり、アンヌが帰郷を決意して深更、パリの街をキャリングケースをひきまわしながら歩き回るシーン、など静か。会話以外の空白部分で、監督が伝えようとするものが、ゆっくり伝わってくる。わかりにくいと言えばそうなのだが、これもフランス映画独特のありようだ。 主演のジャンヌ・モローは、映画製作時(2013年)、85歳。「死刑台のエレベータ」「恋人たち」「小間使いの日記」でのかつての美貌の面影はあるが、それでも年輪はかくせない。いい味を出していた。 原題は、「エストニア人のパリ」。「クロワッサンで朝食を」の邦題では、この映画の本質はみえてこず、台無しになっているが、興業的には仕方がないところか。
パリの高級アパルトマンに住むフリーダ(ジャンヌ・モロー)。ひとり暮らしで、気難しい。彼女はエストニア人で、かつては同郷のひとたちとの交流もあったが、いまは絶えている。 彼女のアパルトマンには、ステファン(パトリック・ピノー)という中年の男性がときどき様子をみに来ている。ステファンはかつては、フリーダと愛人関係にあったようだ。ステファンは、フリーダからプレゼントしてもらったカフェでオーナー。カフェはそこそこ繁盛している。 そのステファン。フリーダが高齢化し、ときどき大量の薬を飲むような行動を取り始めているので、家政婦にきてもらうことを考え、つてをたどって、アンヌというエストニアに住む中年女性に、依頼。彼女は母に死なれ、鬱屈した日々を過ごしていたが、このパリでの仕事にかけることにする。 気難しいフリーダは彼女に相談なく家政婦を雇ったことが気にくわなく、生真面目なアンヌを無視したり、嫌がらせをしたり。朝食には、クロワッサンと紅茶が習慣だったが、それを用意できないアンヌに腹をたてる。アンヌはスーパーでクロワッサンを買い、これをフリーだのもとに運ぶが、「こんなプラスチックのようなものを食べれるか。パン屋で買いなさい」と、紅茶をわざと床にこぼしながら言う。 アンヌはここでの家政婦に自信をなくし、故郷に帰ることを決意し、ステファンに相談をもちかけるが、なだめられ、考え直す。 このあと、エストニア人のかつての仲間がフリーダの部屋に再会に来たのを悪罵で追い返したり、フリーダとアンヌとの確執が強まったり、弱まったりといろいろあるが・・・・。さて、その結末は。 あっけないと言えばあっけない、ラストシーン。 この映画では会話が多くなく、パリのすばらしい光景(エッフェル塔、凱旋門、ルーブル、街並み)がたっぷりスクリーンに浮かび上がり、アンヌが帰郷を決意して深更、パリの街をキャリングケースをひきまわしながら歩き回るシーン、など静か。会話以外の空白部分で、監督が伝えようとするものが、ゆっくり伝わってくる。わかりにくいと言えばそうなのだが、これもフランス映画独特のありようだ。 主演のジャンヌ・モローは、映画製作時(2013年)、85歳。「死刑台のエレベータ」「恋人たち」「小間使いの日記」でのかつての美貌の面影はあるが、それでも年輪はかくせない。いい味を出していた。 原題は、「エストニア人のパリ」。「クロワッサンで朝食を」の邦題では、この映画の本質はみえてこず、台無しになっているが、興業的には仕方がないところか。




