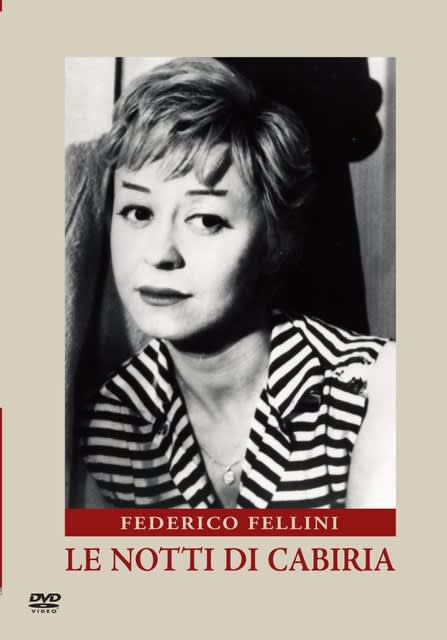この映画は、現時点で互いが相手に対する関心を失っている夫婦関係を中心に、結婚前の二人、結婚直後の二人が同じ旅路をたどりながら、二つの過去の関係を交錯させ、男女が、とりわけ夫婦が結ぶ絆の表と裏とを描いた作品である。ストーリー展開のなかで時間が現在と過去の間を頻繁に行き来し、しかし演技や会話はつながっていることがあるので、そのつもりで見ていないと筋が分からなくなってしまう。この点を注意すれば、話の展開は非常に面白く、身につまされる。フランスの田園風景を背後にした、一組の男女の移ろいやすい愛をテーマに扱った、見ごたえのある作品である。
話しの筋立ては、 三三歳の建築家、マーク・ワレス(アルバート・フィニー)と妻ジョアンナ(オードリー・ヘプバーン)との一組の夫婦がたどった十二年間の愛の軌跡である。現在、中過去、大過去での二人の愛が巧みに交錯されて話が展開して行くが、話の中心は現在である。若さだけで財産も何もないが無邪気にいつもよりそい、愛を確認しながら明日にむかって生きている結婚前の二人。社会でのポジションが確立し、仲睦まじい結婚直後の二人。社会的地位は獲得したが、愛の輝きを失なってしまった現在の二人。カメラは三つの時間を自在に往来し、時代を経て変化していく愛の危うさを明るみにしていく。
マーク・ワレスとジョアンナは、二人が初めて知り合った地、フランスを自動車旅行をした。仕事で世話になっているサン・トロペのモーリスに会いに行くのが目的であった。ワレス夫妻は、熱烈な恋愛で結婚し、外見こそリッチな生活を送っていたが、夫婦仲はしっくりいっていなかった。ジョアンナはこの旅行も結局、モーリスに遠隔操作され、他人につきあわされて自分たちの生活がないと嘆いていた。相手を理解しあおうという心の余裕はとうに消え、離婚の話も会話にのぼる。マークは仕事一点張り、妻を大邸宅と高級車などで満足していればいい存在としてしか見ていない。それにも拘わらず他方では何を与えても満足しない嫌味な女、と軽蔑していた。ジョアンナは、望むものを得ていないという不満足でフラストレーションがたまっていた。その一番の原因は、マークが自分に関心をもたなくなったことにあった。自動車旅行の間も口喧嘩、揶揄と皮肉は絶えない。
かつて、二人の出会いは偶然だった。ひょんなことからヒッチ・ハイクをすることになった二人。安宿に泊まってひもじい思いをし、海岸で日向ぼっこするなど、無邪気に付き合っているうちに恋心が芽生えて結婚した。
結婚後、二人が知人のマンチェスター夫妻とドライブ旅行をしている場面。夫のハワードは計算づくの人間。ドライブ中も運転距離を正確に計算し、旅行にかかった経費も緻密に勘定するタイプの男性。妻のキャシーは、かつてマークと関係があった。娘が一人いたが、大変にわがままだ。自分の意見がとおらないとキーを抜いて車を止め、それを投げ捨てて、大人たちを困らせた。そのような家族に愛想をつかし、ジョアンナとマーク夫妻は共同の旅行を中止した。家族というものの、やりきれなさを感じたのだった。
自動車旅行の末、リゾート地に着いた二人だが、マークは妻を放りだして、卓球に興じた。夫に無視され、退屈で不満が一杯のジョアンナは、知人に紹介されたデビットという男性と遊び、一夜をともにした。マークはそのことに気づき、ムカつきながらことの次第を追求した。ジョアンナにとってデビットは気のおけない存在であったが、くつろぐことのできない。一時の男にすぎなかった。彼女は結局、マークのところに戻ってきた。「戻ったわ」「楽しんだ?」「おかげであなたが恋しかった、ほんとよ」「君は僕を傷つけた、傷つけたあげく戻ってきた」。そのような断片的な会話が交わされる。
オドリー・ヘップバーンが演ずるジョアンナのプレタポルテの衣装が楽しい。また、小道具としての「パスポート」の使い方にセンスを感じる。マークはしばしばパスポートの所在が分からなくなって慌てるが、ジョアンナはそれをしっかり管理している。
恋人、夫婦、家族、女と男のつながりは、時とともにその形は変わり、危うい。危うい関係で綱渡りしながら、二人は再び同じ方向を向いて歩んで行く。
オドリーは巧みに屈折した感情を表現し、難しい大人の演技をこなした。アルバート・フィニーは、イギリスの舞台出身の名優。複雑で起伏のある男女の感情の葛藤が見事に演じられた。