
作家であり、精神病医師である著者の自伝。長編小説を得意とし、自伝的小説に『永遠の都』『雲の都』などがあるが、これらの小説のどこがフィクションでどこが実際にあったことなのかを種明かししようという企みもあって、この本が出来上がったようである。実際には編集者が著者に質問し、それに対して著者が丁寧に、正直に答え、それに註をつけ、写真を示し、年譜を補って、結果としてありのままの自伝になった、と「あとがき」にある。
戦前、戦後の大事件を背景に(最初の記憶は2・26事件)、著者のたどってきた道のりがよくわかる。小説を書きたかった、それも長編小説を、というのは著者の若いころの凄まじいともいえる読書、トルストイ、ドストエフスキー、モーパッサン、バルザック、ハーディ、ホーソーンなどを読破した賜物である。医学の道に入り、精神医学を専門とする。
この間、セツルメント活動にのめりこみ、マルキシズム、キリスト教に触れる。拘置所での死刑囚、無期懲役囚とのヒアリング、フランス給費留学生の経験も(サンタンヌ精神医学センター、フランドル地方サンヴナン村の精神科の病院)、著者の文学の世界の構築の滋養となった。精神病理学の専門分野での業績も豊かである。ヤスーパース、フロイトなどとの格闘の軌跡は興味深い。
いわゆる「文壇」とは距離をおきつつ、しかし大岡昇平、遠藤周作、大江健三郎、辻邦生、立原正秋、高井有一、土居健郎などとの交流がかなり細かく書かれている。目標とする文学は、リアリズムを前提とした長編小説、そして、首都東京の履歴を描くこと。
辿り着いて、キリスト教徒となる(「いかにしてキリスト教徒となりしか」)。本書は妻の死から始まり(自身の心臓病)、父、母の死で結ばれている。

中ほどに書評が35本。その前後に「評論気分」と「随筆的気分」「推薦および追悼」「解説する」のカテゴリーでくくられた文章がならんでいる。
著者は小説家であり、文芸評論家であるが、つい先日、亡くなられた。合掌。
この人の文章は、型どおりでなく、自由闊達で、月並みなところが全くなく、精神の動き方が独特だ。個性的で面白い。
一番最後の「わたしは彼女を狙ってゐた」というのは、著者が毎日新聞の書評欄の顧問役を務めていたとき、女性の書評の書き手として、米原万里さんを狙っていたのだが、他の新聞社に取られてしまったということを書きながら、米原さんの書評のすごさを、あますところなく書き込んでいる。「米原万里は本に惚れるたちである。知的好奇心に富み、本に対して機嫌がいいのだろう。これは高級な生命力のあらはれだ」と褒めている。「本に対して機嫌がいい」という表現が素敵だ。
書評というジャンルの文化性を数か所で論じている。いい書評を書く文化がまだまだ日本には育っていないという。
夏目漱石の「坊ちゃん」に「清という下女」が出てくるが、清は坊ちゃんの生母ではないか、そう理解すると話の辻褄があう、という創見を開陳している。これもユニーク。
「辞書的人間」は、辞書への畏敬が表明され、辞書を愛する人の話だ。著者もそのひとり。
井上ひさしの演劇をたいそう讃えている。竹田出雲、黙阿弥と並ぶほどの劇作家と激賞している(p.255)。当然だろうが、その評価の視点が卓抜だ。井上作品のなかから3つあげるとすると、「雨」「化粧」「父と暮らせば」だという(p.123)。「ロマンス」には「花やかな仕掛け」があるという。ヴォードビルという要素をうまく使っているというのだ。「じつにおもしろい。楽しめるし胸をうつ」と書いている(p。120)。
著者はその井上さんと石川淳と一緒に連句を愉快に遊んだ思い出をつづっている(p.195)。その連句を俳句、俳諧の関連をまじえた解説には目をさまさせられた。そういうことだったのかと。俳句は連句の発句だったそうで、正岡子規がその発句を俳句に格上げさせたとか。了解した。
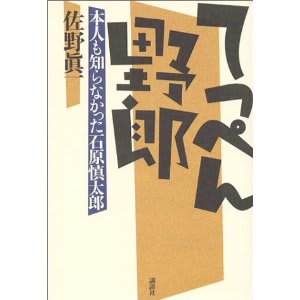
石原慎太郎氏(以下、敬称略)は現役の東京都知事。その評価は賛否両論。しばしば不規則発言で物議を醸す。本書はその東京都知事の半生、人柄、成してきたことの全てを明らかにしている。
全体のボリュームもさることながら(本文470ページ)、父親である潔の生涯、弟で俳優として国民的支持を得た裕次郎とのかかわり、彼のとりまき、家族のこと、芥川賞を受賞した「太陽の季節」の顛末、政界の暴露的記述など質的にも厚みがあり、現存の人物を丸裸にした内容も濃く、よくここまで書けたと驚くばかりである。
まず、父親潔の生涯が面白かった。愛媛県長浜町で生まれた潔は、大正の初期に山下汽船に店童として入社、以後、豪胆、磊落な性格で昭和初期の樺太、小樽で材木を輸送する摘み取り人夫の斡旋などに従事。慎太郎、裕次郎は父の転勤とともに小樽、逗子と海のある街で生活する。小樽のあたりの記述は、わたし自身、地理的な感覚があるので、吸い込まれるように読んだ。
この父親の生活、性格は良くも悪くも慎太郎のその後の礎になったと推測され、著者はそれゆえに潔に関する叙述に破格のページを割いて、「第一部:海の都の物語」分析的記述をしている。
次いで、焦点が慎太郎その人に絞られ、「太陽の季節」が芥川賞を受賞する前後の話が「第二部:早すぎた太陽」で展開される。表面的かつ一時的に左翼活動に傾斜したこと、「太陽の季節」の評価の二分となかずとばずのその後、、裕次郎との強い関係(コンプレックス)、「無意識過剰」との評論家江藤淳の評価、三島由紀夫の好意的支援などわたしがしらなかったことが多く書かれている。著者のすさまじい取材の成果である。
「第3部:てっぺんへの疾走」では政治家に転身し、参議院全国区でのトップ当選(300万票,1968年)、参議院議員を辞職し衆議院選挙に出馬、当選(1972年)、運輸大臣として竹下内閣に入閣(1987年)、東京都知事選での勝利と再選(1999年、2003年、[さらに本書の範囲を超えるが2007年])と続く。この本は2003年に出版されたのだが、この時点では、慎太郎は首相への道に向かう岐路にあったが、その可能性が低いとの見通しで終わっている。予感はある程度的中したわけである。
著者はいまもある慎太郎の若いころからの変身ぶりをあげつらう見方を否定し、その座標軸は動いていないこと、変わったのは慎太郎ではなく、戦後日本ではなかったのかと、問うている(p.195)。そして慎太郎が意外と抹香くさく、輪廻転生が渦巻く世界を抱えていること(p.266)、彼が書く文章にしばしば露見するノー天気なほどの率直さ、それ自体が危険なわかりやすいイデオロギー(pp.325-326)、人々の耳目を集めることにプライオリティーの重きをおいた独特のポピュリズム(p.430)、「中心気質」で「大きな餓鬼大将」(p.469)など、徹底的なまでにその思想と人格が掘り下げられている。
「短気、わがまま、粘りのなさ、骨おしみ、非寛容、オカルト世界への傾斜、加齢と成熟を拒む幼児志向、。これに強烈な国家意識という指摘を加えれば、そこに等身大の石原慎太郎像がほぼ浮かび上がる。(p.468)/何度も述べてきたように、慎太郎は約半世紀にわたって出ずっぱりでやってきた。それは、彼が非凡な才能を持っているがゆえだとはいえても、必ずしも超一流であることを意味しない。逆に、彼は俗受けする、というより俗受けすることしか腐心しない二流の人物だったからこそ、大衆の人気を獲得しつづけたともいえる。慎太郎は『てっぺん』に登りつめられるのか。それは、慎太郎を見つめてきた大衆が、時代と自分を映してきたように見える鏡を、相変わらず眺め続けていくのか、それとも国家に収斂する鏡を断ち割って生きようとするのか、それを自らに問いかけることにも重なる(pp.469-79)」、これが著者の結論である。

白洲正子は、1980年頃から俄かに脚光をあびる存在となった。「いまなぜ白洲正子なのか」。この問いに対する答は、本書を読むかぎり、正子の生き方そのものが日本人が生きるための「羅針盤」、そしてもう少しひらたく言えば日本人の「モデル」であり、その存在と生き方が時代閉塞の状況のなかで「一陣の涼風」「精神安定剤」となったということにつきる。
正子(1910-1998)の出自はは伯爵家(樺山家)、4歳にして能の世界にふれ(梅宮三郎・六郎兄弟の「猩々」)、二世梅若実に弟子入り、大正時代も末、14歳になった大正13年にアメリカに留学、白洲二郎という伴侶を得て、昭和、平成を生きぬいた。多彩な世界に遊び、それは能、骨董、着物、花、職人芸、和歌などに及ぶ。
交友関係は広い。本書の「青山学院にて」の章で書かれているように、青山二郎、河上徹太郎、小林秀雄、永井龍雄、大岡昇平がその中心で、酒を交わして談論風発、そこから佳きものを汲み取った。近衛文麿、吉田茂、健一、西園寺公一(公望の孫)、細川護貞(細川家第17代当主)、北大路魯山人、大野晋、三宅一生、多田富雄などともみな知り合いの関係にあった。
「いかにすべきわが心」(西行)をテーマに、自らが掘り当てるべき井戸をさがし(夢中になれるものを探すの意)、模索の青春を送って、たどりついたのが日本人のアイデンティティを極め、書き記し、「日本の美の定点観測者」となることであった。お嬢様でありながら、破天荒に、思うがままに生き、その生き方そのものが、1990年以後の先が見えない日本の進路にとって新たな道標として採りあげられたということだろう。白洲二郎・正子に焦点があたったのが、まさにそういう日本のそういう時期にあたっていた。
『能面』(求龍堂)、『かくれ里』(新潮社)、『きもの美-選ぶ眼・着る心』(徳間書店)、『心に残る人々』(講談社)、『花と幽玄の世界-世阿弥』(宝文館出版)、白洲正子著作集』(全7巻・青土社)、『梅若実実聞書』は、その成果、結晶である。本書は著者(「週刊朝日」編集長、朝日新聞編集委員を経て文筆家)が晩年の正子に直接取材することでなった作品。
正子を「拝金主義にまみれる前の時代の日本を知る数少ない生き証人」「日本女性の古典」と讃えている。
*明日からフランス・パリに行きます。その間、過去のブログ記事を再掲します。自動予約処理です。
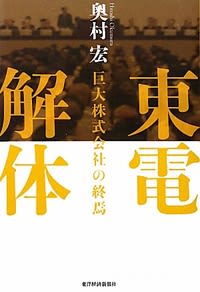
東京電力の解体に賛成の人も、反対の人も、読んでいただきたい本である。
昨年3・11の東日本大震災は、福島原発に甚大な被害をもたらし、いまなお放射線被害は拡大している。汚染された土壌の廃棄、1号機から4号機までの完全な廃炉までに要する時間は数十年、半世紀以上かかるのではなかろうか。
「安全神話」を単純に信仰していた人々、あるいは危険性を故意に隠蔽してきた人々は論外であるが、懸念されていた事態は目の当たりの現実となった。事後処理は途方もない規模のものである。
筆者はこれまでの研究で、現代の法人資本主義、会社本位主義の在り方に警鐘をならしてきた人であるが、3・11の事態に直面し、意を強くして大規模化した企業の解体、法人資本主義からの脱却を主張している。「東電たたき」が重要なのではない。今回の福島原発問題に、東京電力という大独占株式会社に現代の法人資本主義、会社本位主義の矛盾が象徴的にあらわれているので、東電の過去・現在・未来を議論し、その解体の方向を模索して、現代資本主義、大独占企業の帰趨に決着をつけ、そのための知恵を出し合いましょう、と言うのが全体の論旨である。
日本の原子力政策の問題点、電力産業成長の経緯、東京電力の果たしてきた役割な重要な論点が随所に出されているのでそれはそれとして押さえておくべきであるが、問題を散漫にすることなく今回の問題に限定すれば、問題の所在は多くの人命を失わしめた東電の刑事責任が問われていないこと、東電があまりにも大きすぎてつぶせないとの認識が蔓延していること、原子力損害賠償支援機構をたちあげ銀行救済のために巨額の血税を投入したこと、などである。
巨大独占企業の存在そのものが、日本の政治・経済・社会の御荷物になってきている。東電の国有化には、展望がない。採るべき方向は、電力会社の地域独占の廃止、発電部門、送電部門、配電部門の分離、そして発電部門に関しては水力、火力、原子力のいずれの発電所ごとに独立した会社にすること、さらに関係会社はすべて独立させ、小さな組織に改編していく、原子力発電は止める方向でエネルギー問題を展望していくことである。
東電が株式会社形態をとっている限り、その自己変革は期待できない。政府の命令で進めるしかなく、政府が先頭にたって企業改革を推進するしかない。既存勢力には即刻退場してもらい、御用学者、お抱え記者にも退陣勧告。法人資本主義にかわる新しいシステムを構築できる人々、彼らによって遂行される政治がいま必要であり、いまがそのための絶好の機会というわけである。
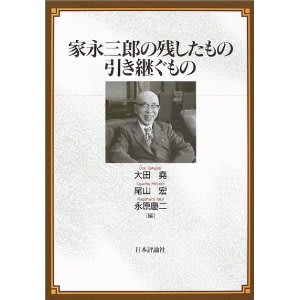
教科書裁判闘争で偉大な役割を果たした家永三郎先生の人と業績を回顧し、さらにその運動を継承した実践を展望した好著。 編集者は太田堯さん、尾山宏さん、永原慶二さんだが、編者を含め40人が原稿を寄せている。
通読して、家永三郎先生の精神的遺産の巨大さ、教科書裁判の歴史的意義の深さ、その後の運動の広がりの多様さと広範さに驚嘆する。
家永教科書裁判は1965年、家永三郎(1913-2002)が一学者、一国民として現行教科書検定制度が違憲違法であるとして、国(文部省)を相手取って起こした裁判である。以降、第二次訴訟提訴(1967年)、第三次訴訟提訴(1984年)を経て、1997年8月29日の最高裁第三小法廷判決をもって終結した。
三度の提訴を通じて、地裁から上下級10カ所の担当裁判所から10件の判決を出させた。中身としては検定制度の適用違憲をいうもの(杉本判決)、検定制度の恣意的な運用を批判するもの(畔上判決)、検定制度は合憲とするが、個々の検定処分の行き過ぎをとがめるもの4件などがある。
この裁判が歴史的に大きな意義をもったのは、検定制度の合憲性を問うにとどまらなかったこと、換言すればそれを教育をめぐる闘い、憲法問題にまで高めたことにあった。
全体は2部3グループ構成であ。第Ⅰ部「家永三郎先生の精神と学問の今日的意義」で主に理論的な側面を記録した文章が、第Ⅱ部「自由・平和・民主主義を求めて-家永三郎先生の遺志と活動の継承」で実践的な側面からの文章が並んでいる。全体がとても重視していてどの文章にも感銘を受けたが、家永史学について論じた「家永史学を支えるもの(江村栄一)」、家永先生が勤務していた東京教育大学での闘いについて書かれた「東京教育大学闘争における家永先生(大江志乃夫)」、家永先生の憲法論の意義をあつかった「家永憲法論の業績と特質(小林直樹)」、杉本判決の積極的な意味を浮き彫りにした「家永先生の『高尚な生涯』と教科書裁判の意義(太田堯)」「家永教科書裁判と教育学(堀尾輝久)」「家永教科書裁判の今日的意義(尾山宏)」から多くのことを学んだ。
国家と教育の関係を問い直し、精神の自由を前提する子どもの学習権[文化的生存権]とそれを中核とした国民の教育権と教育の自由論を展開し、国家は教育内容や教科書記述に立ち入ってはならないことを明示的に述べた杉本判決の意義は、教育にたずさわるものとして忘れてはならないものである。
他に2・3の論稿には検定内容の具体的やりとりが紹介されているが、検定内容のあまりのお粗末さにあきれてしまった。教育の反動化は強まっている。教育現場の一部にみられる荒廃には目に余るものがある。両者は無関係でない。家永先生が残された遺産の継承しそれを深化させることは、わたしたち国民一人ひとりの課題である。

井上ひさし(1934-2010)というと「ひよっこりひょうたん島」のイメージが強すぎ、またその後、たくさんこの人が書いた演劇をみたがひとつひとつの作品の位置を押させていず、いきおいこの作家についての知識は断片的だった。本書はそこに筋道をつけてくれ、この巨人が成した生涯の仕事の大きさが圧倒的に読者に迫ってくる。
著者は本書を、井上ひさしが「巨大な知の発行体」であったこととの指摘から初めている。そして座右の銘が「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに」だったことを紹介。
生い立ち(山形県生まれ)、父の死(農地解放運動で検挙され病死)、母の手一つで育つも、貧困のた東北のあちことを転々とし、15歳のときに仙台の児童養護施設に入園。上京し上智大学に入学、授業にはほとんどでず浅草のストリップ劇場「浅草フランス座」で進行係の役でアルバイト。この間、あちこちの懸賞小説に応募。その後、放送作家として活躍。てんぷくトリオの座付作家に。
熊倉一雄さんのアドバイスで放送作家から劇作家の道へ。「日本人のへそ」が評価された他、「ブンとフン」「十一匹のネコ」「道元の冒険」など問題作、話題作を次々に世におくる。「手鎖心中」で直木賞。その後の活躍ぶりはよく知られたことだが、わたしは井上さんの小説家としての力量をいままであまり知らなさすぎた。というか読んでもいなかった。反省。とくに「吉里吉里人」が圧巻なようだ。
こまつ座旗揚げ後は、遅筆堂を自他ともに認めつつも、劇作で快進撃が続く。「頭痛肩こり樋口一葉」「国語元年」、昭和庶民三部作(「きらめく星座」「闇に咲く花」「雪やこんこん」)、「藪原検校」「しみじみ日本乃木大将」、ヒロシマ・シリーズ(「父とl暮らせば」「紙屋町さくらホテル」)などなど。テレビドラマでは「四千万歩の男」(伊能忠敬)。
さらに社会的活動として、ペンクラブ会長、九条の会呼びかけ人、生活者大学校(1988年スタート)などをこなした。文句のつけようがない博覧強記、怪物だ。著者はこうした井上さんの歩んだ道を年譜を編むようにたんたんと綴っている。
井上さんが亡くなって2年足らず。短期間でこのような大著が出てきたことに率直に驚き、感動した。

青木繁と坂本繁二郎、同時期に同じように久留米藩の下級士族の家に生まれ、家を継ぐ義務をもち、絵描きを志していた頃には、活動をともにしました。
しかし、青木はいくつかの今日も高く評価されている作品を遺しましたが、坂本が注目されるにいたったのは戦後の20年間ほど。坂本は一時、梅原龍三郎、安井曽太郎と並び称されたものの、その作品は忌憚のない眼で評価すると凡庸でした。
坂本は青木に深いコンプレックスをもち、そのことを生前は隠し続けようとしました。
著者の主張はごく簡単にまとめれば以上のようですが、著者は美術評論家でないにも拘わらず、全編を通じてその洞察力には驚かされました。
著者によれば夭折した青木の全盛期は短く、「優婆尼沙土(ウパニシャッド)」「黄泉比良坂(ヨモツラサカ)」「威弥尼(ジャイミニ)」「海の幸」「輪廻」「エスキース」「天平時代」「海」などの作品ですが、画壇や鑑賞者を意識した作品は見劣りがするばかりか、正視に堪えないものもかなりあるようです。
「わだつみのいろこの宮」も清張の評価にかかってはあまり高くないです。
青木が福田たねと恋愛関係に入り子どもまで生まれながら、家族と養育を省みず、故郷での父の死と家督を継がなければならず、しかし貧困のなかで身を持ち崩し、病に倒れ、早世しました。
青木はその天才を一時線香花火のように輝かせ、日本美術史上に必要不可欠な画家となりました。
著者による青木とその作品の分析は非常に興味深いです。青木の一部の作品に特徴的なフォービズム的傾向(p.50)、上野図書館に通って得たにわか勉強の結果としての単純なミス(pp,48-49)、青木の作品を「明治の浪漫主義」と結びつけた評価の浅薄さ(p.60)、などなど。
著者は青木の作品、生き方の対極で、坂本のそれを検証していますが、その作品に見るべきものはなく、20代に意気込んで書いた哲学的文章はドイツ哲学の自己流の非論理的な焼きなおしにすぎず、フランス留学の成果もなく、坂本繁二郎が日本美術史上から落ちても何の影響もない、と断じています(わずかに版画の作品のみ褒められています)。
問題なのは、坂本が青木に凄まじいコンプレックスをもち、結果として事実関係を歪めた表現をとったり、くだらないケチをつけたりしたこと、生前の青木の能面・狂言面・伎楽面のデッサンを秘匿し公にしなかったこと(それらは坂本の死後発見された)、また一部の美術評論家が坂本を必要にもちあげたことでした。
清張の透徹した分析力は、日本美術の分野でも健在でした。

草笛光子さんの自叙伝です。
読者に語りかけるように,内弁慶だった少女時代,松竹舞踏音楽学校時代,ミュージカルとの出会い,芥川也寸志との結婚・離婚,舞台での役者としての仕事感が綴られています。
「シャーリー・バレンタイン(ひとり芝居)」は余程,気にいったのでしょう,紙幅を多く割いて,舞台に立つにいたった経緯,稽古風景,反響が書きこまれています。
映画(ポーリン・コリンズ主演)が大変面白かったので,彼女のひとり芝居は観たかったとつくづく思いました。

著者「あとがき」によると、幕末から明治にかけての混乱と変動の時代に果敢に生き、行動した人々はたくさんいて、彼らは多くの失敗と挫折を繰り返し、試行錯誤を重ね、なおそこにも前途に燭光を見出し、時代の先駆けになろうとしたようです。
本書は、そうした人たちに長年関心を抱き続けてきた著者が2009年が横浜開港100年にあたったことを切っ掛けにこの地で上記の活躍をした21人に絞り、列伝風にまとめたものです。横浜が選ばれたのは、自身は横浜に生まれ育ったから、とのことです。
「海浜を埋め立てた速成の人口の活舞台に、われこそはと自己を恃み、あるいは乾坤一擲の運命を賭して、多くの若者がいっせいに流入してくるという光景は、史上類例のないことであり、破天荒なドラマの生まれないほうが不思議である」(p.303)と著者は書いています。
それでは、その21人とはどのような人々なのでしょうか。「Ⅰ 黒船から押し寄せた変革の波」では、7人が取り上げられている。J・C・ヘボン(伝導医師・ローマ字創始)、中川嘉兵衛(食肉業・製氷事業)、仲居屋重兵衛(生糸貿易商)、若尾逸平(生糸商)、下岡蓮杖(写真家・画家)、原善三郎・原三渓(生糸商・文化事業)。
「Ⅱ 開化の潮流に掉さす先駆者」に登場するのは、次の8人。内海兵吉・打木彦太郎(製パン業)、五姓田芳柳・五姓田義松(洋画家)、高島嘉右衛門(事業家)、岸田吟香(新聞創始者・事業家)、田中平八(生糸商・相場師)、メアリー・E・キダー(女子教育家)。
「Ⅲ 風雪の時代を駆け抜けた人々」には、次の6人がラインナップです。前島密(郵便事業)、早矢仕有的(商社創業)、堤磯右衛門(石鹸製造)、大谷嘉兵衛(製茶業)、雨宮敬次郎(相場師)、快楽亭ブラック(噺家)。
メアリー・E・キダーはフェリス女学院の創設者。早矢仕有的は現在の「丸善」の創業者であ(pp.228-230)、その有的にはハヤシライスの元祖説(p.236)もあるといいます。大谷嘉兵衛は太平洋に海底電線敷設に貢献した人物です(pp.267-279)。
本書に載っている人物は、それぞれに魅力的であり、もっと知りたいと思ったことがすくならずありましたが、巻末の参考がそのために役立つでしょう。
また、珍しい写真がたくさん掲げられています。著者はどのようにこれらを集め、取捨選択したのでしょうか。本づくりの観点から、興味をもちました。

経済学史研究者の第一人者であった小林昇[1916-2010](敬称略、以下同様)が昨年6月に93歳で逝去されましたが、その学問業績と人となりの回想記で、29人の方が執筆しています。
二部に分れ、Ⅰ部では研究者による小林昇の業績の評価と再検討です。通読すると、小林の研究の守備範囲、内外での評価、研究内容を理解できます。Ⅱ部では小林の研究以外の文学、短歌、こけし蒐集にまつわる回想である。小林の人柄、研究姿勢、研究仲間との交流、弟子との接し方が丁寧に回顧されています。一番最後に、娘さんである松本旬子さんが「父と母の思い出」を書いています。
わたしは経済学史の分野のことは門外漢でわからないのですが、この回想記を読むと、この分野でどのようなことが、どのように問題となってるのかを概観することができました。もっとも、それは小林昇の業績をとおしてのことですが。
小林が対象とした研究分野は、19世紀イギリス重商主義、リスト、スミスの研究であり、それをさして「デルタ」と呼ばれていたようです。関連して、タッカー、スチュアート、ヒューム、マルクスがとりあげられ、論じれました。
研究の方法は「試行錯誤的往反」というもので、研究対象である経済学者の理論と思想の徹底的な「相対化」であり、経済史を扱いながら経済学史を評価し、また逆連関的方向で捉えなおすというもののようです。
わたしなりの言い方をするならば、「試行錯誤的往反」とは、ある理論的基準で対象となる経済学者の思想なり考え方を絶対的に評価するのではなく、それらがおかれた経済社会状況のなかでとらえ評価し、また経済学者の眼をとおしてその時代の状況をとらえ、その思考的往復、循環をつうじて問題の所在を浮き上がらせ、論じていくという方法、といえるのではないでしょうか。
経済学史家として小林は現代資本主義の難問に対する政策的提言を行うことをストイックに控えていたようですが、根底には経済成長至上主義に批判的であり、達成された経済水準の維持に重きをおいた政策展開を構想していたようです。
小林はまた、文体に気を使った人のようで、自己の文体をもって自己の著作を書くことを信条とし、日本の社会科学者、とくに経済学者のいくたりがそうしているか、と疑問をもっていたとのことです。
小林は短歌が玄人はだであったことは、その著『山までの街』で知っていましたが、この回想記にもそのことに触れた記述が随所に見られました(歌集に『歴世』などがある)。また、こけしの蒐集でも相当な蓄積があったらしく、「東京こけしの会」で活動をし、エッセイもしたためていたようです。価値あるこけしのコレクションは、西田記念館に寄贈されました。

「大塚史学」で著名な大塚久雄(1907-96)。タイトルに「人と学問」とありますが、その学問については多少なりとも知識がありましたが、「人」の部分に関してはあまり知りませんでした。本書はその人と学問をトータルにバランスよく解説しています(丁寧に説明され、無駄な記述がなく、すっきりしています)。
その大塚久雄は京都に生まれ、父は湯浅蓄電池(株)の重役であり、6人兄弟の3番目でした。三高まで進んだのですが、大学は東京帝大経済学部に入学しました。京都の高校にいながら大学を東京に選んだのは、三高の教授山谷省吾が「若い時には一度広い世界を見ておくことも悪くはない」と言う言葉が大塚の脳裏に強く残ったからのようです(p.21)。
学生時代に内村鑑三、矢内原忠雄らと邂逅し影響を受けました。父親がマックス・ウェーバーの『社会経済史原論』を買い与えてくれたことがあったにもかかわらず、その頃はまだ関心をもてなかったようです(大塚がマックス・ウェーバーに沈潜していくのは、東大助手の2年目にハンブルク大学のジンガーが東大に客員教授としてきて、その薫陶を受けてからです[pp.37-39])。時代の空気からマルス経済学に関心をもつようになりました。とくに河合栄治郎教授の勧めがあったようです。
他方、肺尖カタルを患ったり(p.24)、また左脚の膝の関節リウマチが原因で大腿から下を切断し(p.69-74)、また戦後は3回、肺の手術を受け(p.89-95)、肉体的にはかなり過酷な人生でした。
マルクス主義者は戦中、厳しい監視のもとにあり、検挙、投獄されるものが多く、大塚の周囲も例外ではありませんでした。苦難のなかで東京大学に職を得て、戦後は経済史研究の分野で大きな貢献をしました。
大塚の生涯の仕事は膨大でこれらをひとくちにまとめることは到底無理ですが、あえてここでキーワードのみを示すならば「前期的資本」範疇の確立、株式会社発生史研究、「局地的市場圏」概念の提示などです。
著者は『大塚久雄著作集』(第Ⅰ期全十巻)[岩波書店]刊行で、編集者の仕事にたずさわったおりに大塚久雄から聞いたことをメモとして保管していたものを、時代背景を加えて整理したものです。付録として大塚久雄の「資本論講義」が掲げられていますが、これは大塚が東大退官後、国際基督教大学に着任し、そこでの卒業論文指導ゼミナールで資本論をとりあげ、南大塚の自宅でその講義を行ったときのテープを、おこしたものです。2回分で、商品論、貨幣論あたりのマルクス「資本論」の解説です。これらをどう読まなければならないかが、比較的わかりやすく説かれています。さらに、巻末には詳細な「論文発表年譜」が掲げられています。

ゲーテの言葉に、行き先に迷ったら原点に戻れ、というのがある。3・11以降、日本丸は何を目指すのか、どのような航海をすればよいのか。3・11前後で、風景を、生活を観る目が変わった。
大地震と、原発事故の前の日本はどこかおかしかったのだ。大地震対策の不備、原発安全神話、浮ついていた。被災地の荒涼とした風景、日に日にあきらかになる放射能被害の実情をまのあたりするにつけ、遅ればせながら狂った現代社会再認識し、狂気が常識化していたことを反省せざるをえない。
本書編集のリーダー格であった坂本龍一さんは、3・11に遭遇して言葉を失い、音楽の無力さを感じ、大きな喪失感をもった。時間の経過のなかで、友人、知人とフェイスブックをとおして「3・11以降だからこそ胸にひびいていた言葉」(p.7)を「たくさんの文章や本をあげていくなかで、それを本にしようという話が起こり、・・・多くの人に共感してもらえる読書案内」(p.10)にしたのが本書である。
茨木のり子、竹村真一、セヴァン・カリス=スズキ、ローレン・トンプソン、中井久夫、寺田寅彦、丸山真男、伊丹万作、小田実、鶴見俊輔、吉部園江、スベトラーナ・アレクシエービッチ、手塚治虫、ダニエル・クイン、菅啓次郎、先住民族指導者の文章が連ねられているが、いずれも深く考えさせられるメッセージだ。
チャップリンの「独裁者」をとおして主客が逆転した現代社会の価値観について論じた丸山真男の「現代における人間と政治」、無責任感覚がが社会に蔓延していく構造を読みといた伊丹万作の「戦争責任者の問題」、市民運動の基本は「いくら何でもひどすぎる」という思いでデモ行進に集まることと語る小田実の「『われ=われ』」のデモ行進」、チェルノブイリ原発事故の悲惨さを市民感覚で告発したスベトラーナ・アレクシエービッチの「チェルノブイリの祈り」がとくに印象に残った。
手塚治虫の「アトムの哀しみ」、寺田寅彦の「津波と人間」も一読に値する。
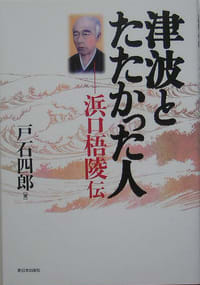
浜口梧陵(1820-1885)という大きな仕事をした人でありながら、あまり知られていない人物の生涯を平易に紹介した本です。あまり知られていない人とはいえ、古い小学校の教科書にのっていた話「稲むらの火」(原典は小泉八雲の「生ける神」)のその人といえば、知る人ぞ知るということらしいです。
その話とは、ある海辺の村を襲った大津波を庄屋の五兵衛がいち早く察知し、刈り取った大切な稲むら(稲の束)に火を放って村人に知らせ、おおぜいの命を救ったというものです。[この話、本当に農家の貴重な財産である稲むらだったかは疑わしく、実際にはすすき、または脱穀後の稲藁だったのではないかと、著者は推測しています(p.61)]。
この五兵衛が浜口梧陵その人であり、紀州広村・現和歌山県広川町での実話ということのようです。
著者は浜口梧陵のこの逸話を彼の生涯のなかで再考し、この人物を再評価しようとして、この書をあらわしました。
通読すると浜口梧陵なる人物は、醤油醸造業を営む浜口儀兵衛家(現・ヤマサ醤油)当主で、七代目浜口儀兵衛を名乗り、紀州と江戸を行き来した豪商でした。ただ商人だったというだけでなく、儒教思想をふまえ、経世済民のもと社会福祉(とくに医療支援)、社会事業(広村防波堤の敷設)で大きな仕事を成しとげました。
また、藩政改革、教育事業でも多大な貢献があり、故郷の広村に私塾(その後耐久社と改称)を開設し、共立学舎設立に奔走しました。
蘭医・関寛斎、勝海舟、福沢諭吉と交流があり、広い交友関係がありました。政府駅逓頭、和歌山県大参事、国会開設建言総代、県議会初代議長などを歴任しました。経営者として、社会活動家として、江戸末期から明治初期の激浪のなかを駆け抜け、生き抜いた偉人とのことです。

NHK BSハイビジョンの番組「100年インタビュー/作家・劇作家 井上ひさし」(2007年9月20日)をもとに原稿をつくり、単行本化したものです。インタビュアーは、堀尾正明さん。この番組は見ました。本の内容はほとんどそのままです。
目次をみると、生い立ちから、父のこと、母のこと、文学との出会い、懸賞応募から劇作家の道に入っていった経緯、そして笑いとは何か、文学とは何かについての井上流哲学が開陳されています。
数々の名作を世に問い、評価をうけ、蔵書の数は20万冊という凄い人なので、語られる一語一語に重みがある。そして、井上さんのいいところはそれを難しいことばではなく、わかりやすい言葉で説明してくれるところです。それが、この本での大きな文字になって、示されています。
・情報をどんどん入れて知識になり、知識を集めて知恵をつくっていく、どんな仕事もきっと同じはず。(p.28)
・頑張ればひかりが見えてくる。(p.42)
・初日の幕が開いて、お客さんが拍手して「いい芝居でした」「感動しました」「笑いました」と言ってくれるのが何よりの報酬。(p.78)
・笑いとは、人間が作るしかないもの、それは、一人ではできない、人と関わって、お互いに共有しないと意味がないものである。(p.88)
・明日命が終わるにしても、今日やることはある。(p.94)
・自分が使いこなせる言葉でものを考えることが大切。(p.98)
・「それ、わかりませんので教えてください」と無知のふりをして聞き返せばいい。やっぱり無知が一番賢いのです。(p.104)
・手が記憶する。記憶した手で新しいことを作っていく。(p.110)
最後に「100年後の皆さんへ、僕からのメッセージ」が掲げられている。100年後の地球が人間がどうなっているのかを心配しつつ、100年前のわたしたちががんばっていい世界を手渡したい、というような内容です。ときどき、井上さんが生きておられたら、福島原発のことなどはどう受けたとられるのかを知りたいです。井上さんの故郷は、福島に比較的近い、山形川西町ですから・・・。









