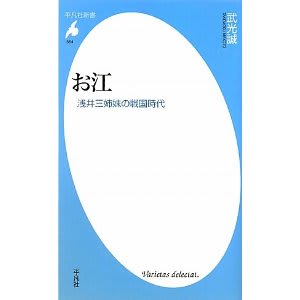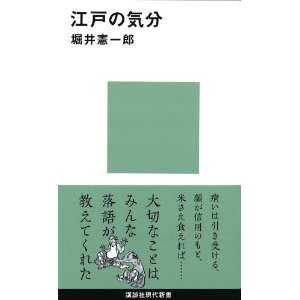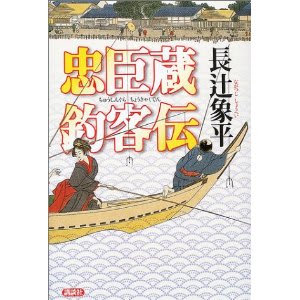本文の一番最後の文章、「米を語る。それは水を語ること、緑を語ること、土を語ることであり、相撲をはじめとする民族文化を語ることであり、日本文化の土台と特性を語ることであり、「地方」を語ることであり、地球環境を語ることであり、そして、日本人のアイデンティティを語ることであった」(p.222)。これが結論です。
冒頭では著者の不満が書かれています。「吉野ヶ里」遺跡から始まり、この遺跡の発見当時のフィーバーぶりはともかく、そこにかつて栄えた集落と文化があるとき、忽然と消え、その消滅が米の問題と重ね合わせて論じられなかった、と。
日本人との米とのつきあいの問題を軸に、新田開発、治水(水抜き、溜池)、堰、条理制、用水、干拓、埋め立て、森林、治山、砂防、客土について、著者は大きな視野で論じていきます。 「水田はダムである」という言葉に象徴される富山理論です。
壮大な日本文化論であり、それは日本の土地制度上の大改革を「大化の改新」「太閤検地」「地租改正」という長い歴史のなかに鳥瞰しつつ、全国を津々浦々めぐって得た地理学的知見に見事に凝縮しています。
ほとんど無名に近い土木の天才の存在にも驚かされました。また、「文明とは余剰生産物の結果」(p.110)などのテーゼが出てくるかと思えば、土地の測量との関連で和算の話が出てきたり、宮本ユリ子のおじいさんである福島県典事で安積開拓の父・中条政恒(p.154)、新渡戸稲造の兄である著名な土木技術者・新渡戸七郎(p.158)が登場したり、「米」を基点に縦横な展開には感心しました。
おしまい。