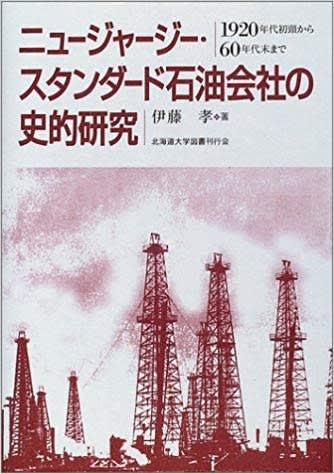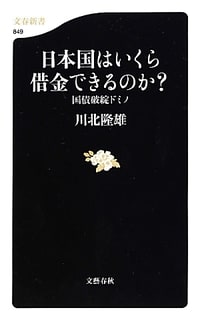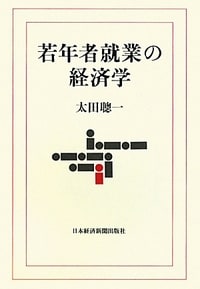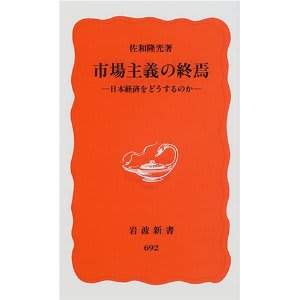わたしが注目してみていた個別銘柄で一時堅調だった任天堂、カプコン、トヨタ、JR東海、モルファ、アカツキ、日東電工、ソフトバンクグループなどみな大幅下落です。
日本時間0時5分現在、NYダウ平均は832ドル下落、ナスダックは237ドル下落です。
下記のような記事がありましたので、掲載します。
**********************
東京五輪中止なら損失7.8兆円=新型コロナ影響試算―SMBC日興
<2020/03/06 18:56時事通信>
SMBC日興証券は6日、新型コロナウイルス感染が7月まで収束せず、東京五輪・パラリンピックが開催中止に追い込まれた場合、約7.8兆円の経済損失が発生するとの試算を公表した。国内総生産(GDP)を1.4%程度押し下げ、日本経済は大打撃を被るという。
SMBC日興は、新型ウイルスの世界的な感染拡大が7月まで長期に及ぶ場合は五輪開催中止の可能性が高いとみている。五輪に絡む損失では、宣伝や輸送といった大会運営費に加え、訪日客を含む飲食・グッズ購入など観戦関連支出で計6700億円とはじいた。新型肺炎の感染拡大が収まらず、国内消費のほかサプライチェーン(部品供給網)の依存度が高い中国を取引先とする輸出入減少などの影響と合わせると、損失総額は7.8兆円程度に上ると見込んだ。