
本書は科学の発達とその成果が、人間に幸福をもたらす半面、戦争に利用される可能性があり、後者の危険性に警鐘をならしたもの。科学は本来「中性」であるが、それを利用する人間の理性が問われるということである。ノーベル自身、また受賞者のピエール・キューリーは、新しい発見が人類に害毒も福利ももたらす諸刃の剣であることを示唆し(デュアルユース)、その懸念を表明していた。(ドイツの化学者で化学賞の受賞者だったフリッツ・ハーバーは第一次世界大戦中に毒ガスを開発しユダヤ人虐殺に手をかし、悔恨ももたなかったという。こうした科学の悪用の例は枚挙にいとまがない)
著者は同時に、資本の巨大な力が人間の理性を翻弄することにも注意を喚起している。為政者によって科学者が総動員され、戦争に協力させられてしまうのがこれである。原子爆弾を完成させた一大プロジェクトであるマンハッタン計画、ベトナム戦争のためのジェーソン機関などをあげている。現代科学、とくに自然科学は、膨大な投資があたりまえになり、そのことに科学者が振り回され、即効性のある、また実用的な成果が求められ、タコツボ化した研究室で、世の中の動きに関心をもたない研究者が育っている。著者はそのことを憂えている。
著者は科学者の勇気ある行動の例も多数あげている。核廃絶を訴えたラッセル=アインシュタイン宣言(1955年)、核兵器廃絶を掲げるパグウォッシュ会議の開催(1957年)などである。
冒頭が面白い。ノーベル賞を受賞したおりに、「あまりうれしくない」と発言したことがマスコミに取りざたされたこと、またノーベル賞受賞の記念スピーチに戦争のことに触れた部分があり、これに対してクレームをつけたものがいた、というエピソード(?)を紹介している。前者に対しては、ノーベル財団の受賞通知の態度が権威主義的でカチンときた、後者に対してはむしろノーベルの精神からしてそのことに触れないこと自体がおかしい、と述べている。著者の精神は健全である。
本書には、著者自身の戦争体験(5歳のとき自宅に不発焼夷弾が落下)、反戦運動、組合運動の経験に触れながら、科学者が過去に戦争に果たした役割を詳細に紹介、分析している。また、戦争体制に向かってまっしぐらに進む安倍政権に対して、また憲法九条を反故にする動きに対して、さらに軍学協同、産学協同へ邁進する科学界の傾向に、厳しい批判を行っている。しかし、進行する事態を悲観的に見ているのではなく、この方向には必ず「やりすぎ」を止める動きが出てくると確信しているところが印象的であった。
いたるところで恩師の坂田昌一の世界観、科学論をひいて、著者がそれを自らの人生の研究の指針としていたことがわかる。その坂田が言っていたことは「科学者たるまえに人間たれ」ということであった。
本書の構成は、以下のとおり。
「第一章:諸刃の科学-「ノーベル賞技術」は世界を破滅させるか?」「第二章:戦時中、科学者は何をしたか?」「第三章:「選択と集中」に翻弄される現代の科学」「第四章:軍事研究の現在-日本でも進む軍学協同」「第五章:暴走する政治と「歯止め」の消滅」「「原子力」はあらゆる問題の縮図」「第七章:地球上から戦争をなくすには」
なお、著者の物理学受賞理由はウィキペディアによると、下記のようである。本書では紹介されていないので、付け加えておく。
小林と益川の功績は、もしクォークが3世代(6種類)以上存在し、クォークの質量項として世代間の混合を許すもっとも一般的なものを考えるならば、既にK中間子の崩壊の観測で確認されていたCP対称性の破れを理論的に説明できると示したことにある。
クォークの質量項に表れる世代間の混合を表す行列はカビボ・小林・益川行列と呼ばれる。N.カビボは1963年に2世代の行列理論を提唱し、小林・益川の両者は3世代混合の理論を1973年に提唱した。
発表当時クォークはアップ、ダウン、ストレンジの3種類しか見つかっていなかったが、その後、1995年までに残りの3種類(チャーム、ボトム、トップ)の存在が実験で確認された。
現在KEKのBelle実験およびSLACのBaBar実験で、この理論の精密な検証が行われている。これらの実験は小林・益川理論の正しさを実証し、小林、益川は2008年、ノーベル物理学賞を受賞した。
数学史がなぜ必要なのか? 著者はこたえています、まず「学問の遂行にはその歴史的過去に通ずることが重要」であるからであり、次いで過度に抽象的になった現代数学の意味内容を充実化させることが必要だからである、と。この説明は冒頭の部分にあり、「リー群論」を例に出していますが、実は本書の課題である「近代微分積分学」の歴史そのものが、数学史が必要な所以の例証になっています。
「近代西欧数学の象徴であり、今日の科学技術革命の基礎である」微分積分学の端緒は、17世紀後半の無限小記号代数解析です。
もう少し詳しく言うと、近代の微分積分学の誕生は、ニュートン、ライプニッツによってなされた、アルキメデスの無限小幾何学の記号代数的言語よる無限小代数解析への転換が前提としてありました。
すなわち、無限小記号代数解析(微分積分学の基本定理の発見)はニュートン、ライプニッツの包括的な数学的天才によって提示されたのですが、それは古代ギリシャのアルキメデスによる「パラボラの求積法」という遺産(帰謬法的な幾何学的思考方法)の、ヴィエト、デカルト的記号化(アラビア数学である代数にもとづく)がなければありえなかったというのです。
このあたりの数学史の展開は、この学問のダイナミズム、醍醐味を味わわせてくれます。
余滴:数学上の思想的革命は「古代ギリシャにおける公理論的体系の発見」「17世紀の微分積分学の定式化」「19世紀初頭の非ユークリッド幾何学の形成」。
東京大学大学院数理科学研究科での講義録のハイライトを一般読者向けに書き直したものだそうな。しかし、難しかった。やれやれ。
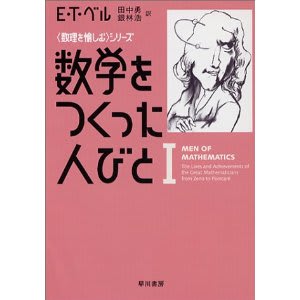
数学の歴史で大きな貢献を成した学者の何人かの名前は、知っています。教科書で習った人では、ピタゴラス、アルキメデス、ニュートン、パスカルぐらいは、誰でもしっています。彼らの業績もそれなりに言うことはできます。ピタゴラスであれば「直角三角形のピタゴラスの定理」、アルキメデスなら「アルキメデスの原理」、ニュートンは「万有引力の法則」、パスカルは確率論といったところでしょうか。
ただ、彼らがどういう人だったのか、その業績がどういう過程で生まれたのか、などはほとんど知られていないし、多くの人は知ろうともしないです。
本書は、数学の巨人たちのあまり知られていない伝記です。原書が出版されたのは1937年、相当古いです。原題は「ツェノンからポアンカレにいたる大数学者の生涯と業績」。1953年に、イギリスのペンギンブックスで2分冊本として出版され、その前半分だけが1943年に日本語訳で刊行されました。日本語全訳は、1962年に東京図書から出ました。
数学が退屈なものではなく、「大なり小なり、精神の劇的なドラマだということを、本書ほど鮮やかに描き出したものは少ない」(p.12)と「訳者挨拶」に書かれています。早川書房の文庫版では3冊に分かれていて、その第1冊に登場する数学者は以下のとおりです。
ツエノン、エウドクソス、アルキメデス、デカルト、フェルマ、パスカル、ニュートン、ライプニッツ、ベルヌーイ家の人々、オイラー、ラグランジュ、ラプラース、モンジュ、フーリエ。ツエノン、エウドクソス、アルキメデスは古代ギリシャの数学者です。それから、フランス人が多いのに気づきます。
数学の概念と結び付けて紹介すると、アルキメデス、ニュートンは微積分学、フェルマは無限論、パスカルは確率論、デカルトは解析幾何学などです。数理物理学や天文学との関係で、近代数学が発展していくさまには、今回、認識をあらたにしました。
数学者はそれぞれに個性的な生き方をしている。相互の論争があった。それぞれが生きた時代がまだ科学の光が弱い、宗教の権威としきたりが支配的な蒙昧の社会だったことも頭に入れておかなければなりません。当時の権力者との微妙な関係もありました。
そのような時代に生きながら、有る人は才能を十分に開花させたが、有る人は才能をもてあまし、不本意な人生をおくったのです。数学の天才の誰もが変人、奇人だったわけではありません。ニュートンが行政官としても仕事をなしたとは驚きましたが、デカルトの最期などはさびしい限りでした。

書棚に未読のまま置かれていた。何故、この本を買ったのか、記憶がない。しかし、以前から自然科学のわかりやすい本には、関心があったので、きっとそういう関心でもとめたのだろう。
ガリレオ(1564-1642)の生涯と業績を平易に解説したもの。知らないことはたくさんあったが、アリストテレスの自然観、天体の運動に関するプトレマイオス体系に疑問をもち、観察と数学を使って自然科学の道を開いたこと、すべての問題を、重さ、距離、時間そして速度のような基礎的量でまとめようとしたこと(p.83)でそれが可能になったこと、という叙述が印象に残った。
ガリレオはコペルニクス的な地動説を唱えたこと(ティコ・ブラーエの体系との格闘)、物質の運動に関心をよせ、自由落下の法則(s∝t^2,v∝t,1/2vt=s,ここでvは速度、tは静止状態から計った時間、sは静止状態から落下した距離、∝は「比例する」という意味)、慣性の法則(硬く滑らかな球が、硬く滑らかな水平面上に置かれ、静かに押されるとき、この球が加速したりあるいは減速したりする理由がない、直線上の運動は「保存」される)などの解明に貢献があった。地動説では、当時の教会の教義に反しために、異端の宣告を受け、幽閉されたことは、よく知られていて、本書にもそのことがしっかり書かれている。
著書として『星界からの報告』『二大世界体系についての対話(天文対話)』『新科学対話(機械学、および地上運動に関する2つの新科学についての対話、および数学的証明)』があり、イタリア語で書かれた(ラテン語ではなく)。ガリレオの仕事はフランスではマリン・メルセンヌやデカルトに、イギリスでは数学者ジョン・ウォリス、司教ジョン・ウィルキンス、化学者ロバート・ボイルに影響を与えた。

本書は,1900-50年にかけて,日本の数学発展に貢献した高木貞治(1875-1960)の没後50年を記念して書かれている。高木貞治は,代数的整数論とりわけ類体論の権威。
類体論(るいたいろん,class field theory)の名前の由来は,1930年ごろに考案されたヒルベルトの「類体」による。
*「類体」の用語を始めて使ったのはハインリッヒ・ウェーバーで,彼は「楕円関数の虚数乗法により供給されるある特別な相対アーベル数体をとりあげ,それを『類体』とした[本書140ページ]」。
高木貞治の学問業績とその背景を、本書によりながら簡単に紹介したい。
パリで開催された第2回国際数学者会議(1900年)でヒルベルトが示した数学上の未解決の23の問題のうち、第9問題「任意の数体における一般相互法則の証明」と第12問題「アーベル体に関するクロネッカーの定理の,任意の代数的有理域への拡張」を解いたのが高木貞治である。
高木は上記の2つの数学上の難問を解いたが、後者については1901年に書かれたガウス数体の虚数乗法論に関する論文(「複素有理数域におけるアーベル数体について[学位論文])で部分的に解決,さらに1920年に書かれた「相対アーベル数体の理論」「任意の代数的数体における相互法則」で最終的な結論を出した。さらに同年9月シュトラスブルクで開催された第6回世界数学者会議で発表した(153-154ページ)。
本書は,高木の出生(岐阜県大野郡数屋村)から,三高,東京帝大を経て,近代日本の数学が確立されるまでにいたった経緯を,研究経歴,研究活動と研究仲間との親交をたどりながら,その学問的貢献とともに解説したものである。(巻末に年譜があります)
高木の貢献を数学的に解説した個所を理解するのは難しいが,全体的な流れをつかむことが大切。数学に特化した本でなく,多くのエピソードをまじえて読みものとして構成されていることは,以下の章建てをみるとわかる。
・序章:故郷を訪ねて
・第一章:金栗初めて開く-岐阜から京都へ
(1)一色小学校
(2)二つの生誕日
(3)岐阜中学校から三高へ
(4)近代日本数学の源流-金沢の関口開」
・第二章:二人の師:河合十太郎と藤澤利喜太郎
(1)第三高等中学校
(2)初代数学教授菊池大麓
(3)帝国大学の数学講義
(4) 藤澤利喜太郎の洋行
・第三章:自由な読書にふける-数論の海へ
(1)藤澤セミナリー
(2)アーベル方程式をめぐって
(3)洋行ベルリンへ
・第四章:後るること正に50年-類体論の建設
(1)ゲッチンゲンへ
(2)類体論への道
(3)世界大戦をはさんで
・第五章:日本人の独創性-高木貞治の遺産
(1)『解析概論』の誕生
(2)ヒルベルトとの再会
(3)過渡期の数学
(4)晩年の日々
・終章:高木貞治と岡潔
「高校生向けに」と称してコラムが設けられ,「二次方程式と複素数」「平方剰余の相互法則」「レムニスケート関数」「アーベル方程式」「アーベル数体と代数的整数論」などの説明がある。
著者の高瀬正仁氏は専攻が多変数函数論で,現在九州大学大学院数理研究院準教授。

フェルミ推定の実践。
フェルミ推定というのは、ある数量的問題をそれほど難しくない計算手続き(ほとんど加減乗除)で概算し、答を出すというもの。例えば日本の総世帯の車の保有台数をもとめる問題。日本の総人口1億2800万程度しか知識がないとしても、そこから世帯数、一世帯当たり車の保有台数が推定でわかるから、約7000万台前後と推定できる。
上記は簡単、本書ではもう少しフェルミ推定問題に適した、ある意味で驚くべき問題がカテゴリー別に(生活編、コミュニティ編、エコロジー編)列挙されている。
問題は次のようなもの。あなたが知っている言葉の数、1年で出るゴミの量、バスの重さ、月の重さ、1つの都市にいるピアノ調律師の人数、クルマをひっぱるのに必要なハエの数、嵐と原子爆弾とではどちらが威力があるか、などなど。
ただ知っておくべき公式はいくつかあるようで、それは球の体積、球の表面積、速度のエネルギーの求め方など。フェルミ推定は、座ったままで、変数間の数量的連関を、必要最小限の計算式で推定するところに妙味がある。著者はこれを数学脳(ギーグ)と呼んでいる。
宝くじ関連の面白い箴言があった、曰く「宝くじ券の購入料は統計を知らない人が払う税金である」と。なるほど。
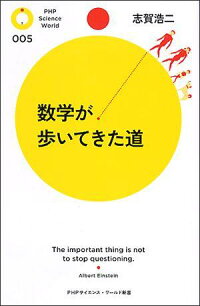
数学の遠大な歴史系譜の基軸をおさえた啓蒙書です。それは以下の目次を一瞥するだけで分ります。
・序章:聞いてみたいこと
・第1章:深い森へ(1.円周率、2.ピタゴラスの定理、3.平行線の公理、4.ツェノンの逆理)
・第2章:近世に向けての旅立ち(1.中世から近世へ、2.火薬と大砲、3.コンパス、4.活版印刷、5.時計)
・第3章:ヨーロッパ数学の出発(1.デカルトの方法、2.ニュートンの「プリンキピア」、3.ライプニッツの無限小量)
・第4章:数学の展開(1.開かれた社会へ、2.バーゼル問題の解と「無限解析」、3.オイラー無限のなかの算術、4.無限小量の批判)
・第5章:関数概念の登場(1.変化するもの、2.関数・グラフ・極限)、3.微分ー関数への作用、4.積分-関数のひろがり、5.微分と積分-数学の2つの方向)
・第6章:解析学の展開(1.テイラーの展開と因果律、2.複素数、3.正則性、4.波立つ変化)。
円は完全な図形と考えられるのに、円を数の世界にうつしだした円周率πはどこまでも規則性のない数の列が続いていく、そこに暗示されるのは数の無限性と神秘性であるという話から始まり、数学が「線分計算」と「比を用いた数の計算」とは切り離して考えなければならないことの認識を「ピタゴラスの定理」によって取り込んだことが確認されています。古代ギリシャ数学は、このとき数の神秘の扉を開いたのでした。
思惟の世界に淵源をもつ数学はその後、イスラム世界で代数学を誕生(9世紀)させ、近世に入ってデカルトを経て微分・積分学が形成され(変化のなかに時間を見、後者を数学のなかに取り入れたニュートン力学と変化のモナド[単子]の存在を見たライプニッツの数学)、両者の数学を統一させた関数と変数概念によって解析学へと展開されていきます。
さらにガウス、アーベル、ガロア、リーマンなどの天才の業績を経て、概念がさらに純化され実数から複素数に移行します。
ここに至って数学は、時間のない抽象の中で因果律が成立する世界に到達します。20世紀の数学は抽象数学として再びイデアの世界に回帰することになるのです。
2000年有余の数学の歴史逍遥の旅がここにあります。
数学的展開、古典からの引用があり、内容は決して易しくはありません。

著者は京都大学原子炉実験所の研究者です。原子力研究という夢をもって大学に入学しましたが、直後にその道の選択が間違っていたことを知ります。1970年10月に女川町で開催された原発反対集会に参加して、反原発の研究者として身をたてることを決意しました。なぜ原子力の研究を専門にしていながら、原子力に反対し続けるのかを本書で明らかにしたと書かれています。
私は本書を読んで、人類は原発というなんともやっかいなお荷物をか抱えこんでしまったものだと愕然としました。
冒頭から前半は、放射線の恐ろしさが書かれていて、ただ恐怖をあおるというのではなく、核分裂の構造、メカニズムが易しく解説されているので、その怖さを実感します。
あわせて、①核分裂反応の意味や(ウランが中性子と結合して燃えるのが核分裂反応、複数個の中性子は外にとびだして連鎖反応する)、②ウランはその大部分が「非核分裂性ウラン(ウラン238)」で、「核分裂性ウラン(ウラン235)」はわずかしか存在しない、③ウラン235を集める作業がウラン濃縮と呼ばれる、④ウラン238を「核分裂性ウラン(ウラン239)」に変換して得られるのがプルトニウムという、⑤濃縮ウランやプルトニウムを生み出す工程で出てくるゴミが劣化ウランで、それはほとんどタダでつくられたようなものでアフガン、イラクなどで劣化ウラン弾として使われた、ということが次々と解説されています。
さらに多くの誤解、たとえば日本は唯一の被爆国、化石燃料の埋蔵量に限界があるので原子力は不可欠、原発は二酸化炭素を排出しないのでクリーンといった常識が、誤った情報であることを説得的に解説しています。なぜかは一読してください。
原発というお荷物を人類が抱え込んでしまったとわたしが痛感したのは、それはいったん事故にみまわれるとそのコストがばかにならないこと、使用済核燃料がその処理方法を完全に見いだせないまま世界的規模で現在も累積しつづけている、原発の熱効率は意外と悪く、またその温排水で海洋の温度をあげることに結果していること、などを知ったからです。
廃棄物の処理ではアルファ線核種であるプルトニウムが扱われますがその危険性はウランの比でないこと、多くの原子力発電所で計画されているウランにプルトニウムを混ぜた混合酸化物燃料(MOX)を使用する方法(プルサーマル)が問題の多いものであること、さらに高速増殖炉がきわめて危険であること(高速中性子を使うため制御が難しい)、などの指摘は重要です。
ただ、著者は原子力からは簡単に足を洗えること、現在の原発を即刻停止しても困らないことを述べ、(やや楽観的なようにも思いつつ)展望を失うことのない結末にしています。それが救いでした。
<目次>
1章:被爆の影響と恐ろしさ
2章:核の本質は環境破壊と生命の危険
3章:原子力とプルトニウムにかけて夢
4章:日本が進める核開発
5章:原子力発電自体の危険さ
6章:原子力に悪用された二酸化炭素地球温暖化説
7章:死の灰を生み続ける原発は最悪
8章:温暖化と二酸化炭素の因果関係
9章:原子力からは簡単に足を洗える
10章:核を巡る不公正な世界
11章:再処理処理場が抱える膨大な危険
12章:エネルギーと不公正社会

本書を通読して印象に残ったのは、自然科学の対象が自然であるが、別の観点からみれば人間も自然の一部であり、そうであるならば自然科学によるる自然認識は自然の自己認識に他ならないという考え方です(自然自体の自己反映活動)。このコンセプトが全体の基調にありますが、実際の叙述はもっと具体的です。
概要は以下のとおりです。
自然科学の論理と方法にはそれを生み出した文明の基礎にある自然観の反映がある。また、逆に新たな科学の発展が自然観の転換をもたらしてきた。自然科学の在り方と自然観は双方向的である。
とりあげられている自然観は、①数学的自然観、②原子論的自然観、③機械論的自然観(デカルトが提唱)、④力学的自然観(ニュートン力学)、⑤階層的自然観(物質と力)、⑥進化論的自然観、⑦量子論的自然観である。
17世紀以降の近代科学の成立までには、アリストテレスの目的論的自然観が支配的であった。後者にとってかわった近代自然科学の特徴はその成立期から成熟期まで「絶対化」の論理、すなわち近代科学の理論体系が絶対的時間・空間、不変実体の原子・元素、絶対的空虚で不動の真空、および絶対的自然法則、因果律に基づく必然的決定論などといった絶対的概念で構築されていた。
これに対し、20世紀以降の相対性理論と量子論に象徴される自然科学は相対概念に重きが移り、この相対化の論理とは個別的に分離把握されていた絶対概念(時間、空間、物質)を変化と相互連関のうちに捉え直すという認識の方法である。
この科学の認識革命、概念転換によって自然観の転換も引き起こされ、現代科学の自然観の柱は、階層的自然観(原子論的自然観に対置)、進化論的自然観(機械論的自然観に対置)、数学的自然観である。また、ミクロ世界の運動を支配する普遍的理論である量子力学の成立は、それまでの自然認識を根底から覆すものであり、現代科学の共通の基盤になっている。
本書ではこうした自然観の変遷の様が、物理学の進歩・発展をたどりながら解説されています。古代ギリシャの科学者、哲学者(アリストテレス、プラトン、パルメニデス、ピュタゴラス)から始まって、ニュートン、デカルト、ケプラー、オイラー、ベルヌーイ、マックスウェル。マイケルソン、モーレイ、アインシュタイン、ボイル。ホイヘンス、ノイマン、ゲーデル、ハイゼンベルグ、ド・ブロイなど有名な科学者の業績が丁寧に(したがって、門外漢には難しいところが多々ある)紹介されています。
自然の無限の奥深さ、自然科学のそれが実感できる好著です。

本年、鈴木章、根岸栄一両氏がパラジウムを触媒とする有機化合物のクロス・カップリングの業績でノーベル化学賞を受賞しました。このところ日本の科学者の受賞が目立ちます。そのことに刺激されて本書をひもときました。
表題どおり、1901年に設置されたノーベル賞の一世紀の歴史です。ノーベル賞が設置された理由、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞の流れ、候補者の選び方、日本の受賞者の業績の解説が要領よく、分り易く説明されています。
ノーベル賞がよき伝統を保ってきた理由として、選考プロセスが公平、厳密で、秘密が厳しく守られていること、賞金の額が高いこと、外部資金のもちこみなどを原則的に断ってきたことなどがあげられています。
第一回の生理学・医学賞の受賞者に北里柴三郎が最も近いところにいたにもかかわらず、結果的に受賞できなかったこと、野口英世が何度も候補者にあがったこと、湯川秀樹、朝永振一郎の業績の意義の大きさ、また本書が書かれたのは2002年であすが小柴教授、小林・益川教授の受賞が予測されていることなど、興味深い記述が随所にあります。
物理学賞の系譜にみられる量子力学、素粒子論の発展、化学賞で近年では分子生物学(遺伝子とDNA)が隆盛をきわめていること、生理学・医学賞では人類の病気との闘いを追跡できることなど、普段触れることができない自然科学領域の動きが新鮮に感じられました(さらに、自然科学三賞の流れは、ドイツが科学者を輩出した時期からそれがアメリカに移っていく傾向、賞が原理・原則と真理の発見に与えられ方向から応用科学の方向へ移ってきていることなども)。
経済学賞が特別な位置にあるとの指摘、時々奇妙な受賞が話題になる平和賞への著者の見解も参考になります。

宇宙全体は何から構成されているのか。地球以外のどこかに生命は存在するのか。20世紀半ば以降の宇宙科学の発展は目覚ましいものがありましたが、根源的なことがまだわかっていないらしいです。
本書は宇宙科学の最前線を、対話形式でわかりやすく説く良書です。宇宙論の課題を説明するとき、キーワードは「暗黒」だそうです。「暗黒物質」「暗黒エネルギー」等々。
「暗黒物質」とは正体は不明だが、可視光を含め、電磁波(光)でその存在を直接見ることができない物質のことです。宇宙の構成は、この暗黒物質と暗黒エネルギーが96%を占めるというのだから驚きです。
この話から始まって、銀河系、銀河群のなかの地球の位置、星、銀河までの距離をどう測るのか、星の一生の決まり方、太陽の年齢と内部構造、物質の歴史、宇宙の起源、太陽系外の星の惑星の発見(1995年)、その画像での確認(2008年)、惑星をもつ星の条件と広がっていきます。
著者の専門は恒星物理学、天体分光学ですがその専門分野の立場から宇宙の成り立ちを書いてみたということです。
『全国商工新聞』(2009年6月15日~2010年4月12日)に連載された「星博士の星から見る宇宙」をもとに加筆、再構成されたものです。

数学で愉しもうという趣向ですが、わかりやすいところとわかりいくいところとがあり、理解度はまだら現象です。
全体は、序章を含めて5部。「はじめに-優雅な果実 何でこんなところに数学が?」「第一部:頭脳と数学の出会うところ」「第二部:物の世界を数学する」「第三部:人の世界を数学する」「第四部:真理の数学」。
著者の解説を借りて、各部の内容を紹介すると、第一部では、心の混乱を整理するのに、数学がぜひとも必要なことが示されています。第ニ部ではものごとをはっきり見るのをさまたげるもののうち、物質的な現実自体の状況からくるものを探っています。第三部では、数学がいかに「公平さ」などという人間的な問題に光をあてているかを味わおうとしています。最後の部では、本書の中心をなし、数学がさまざまな道をつうじて原因と結果、証拠と証明、真理と美とのあいだにある意外な基本関係が示されること、またしばしば実際に示していることが述べられています。美と真理とは同じコインの両面というわけです。
相関関係と因果関係とをとりちがえてはいけないこと、「平均」概念には慎重に接近すべきことなどよく知られていることが指摘されています。また数学の魅力がその本質的、内在的論理の真理性であるにもかかわらず、その世界でも矛盾が避けられないことをゲーデルが証明したこと、ワイルズが証明したフェルマの定理、宇宙の構造を理解するのに必要な「雑音」の除去など、面白く豊富な話題がたくさん紹介されています。
ダレル・ハフの『統計でウソをつく法』[1954](高木秀玄訳、講談社ブルーバックス)は、統計の問題を考えるさいには欠かせず参照される名著であるようです(p.79)。
法則の認識に果たすパターン認識の役割について述べられている箇所は、有益でした。著者はこの点に関連して、「科学が特に優れているのは、何といってもいわゆるパターン認識だろう」「パターンが繰り返すという事実から、私たちは自然の法則を公式化することができる」と指摘しています(p.107)。
原題は"The Universe and The Teacup"

今年6月13日午後7時51分(日本時間)、満身創痍の小惑星探査機「はやぶさ」(全長約31メートル、直径約2.5メートル、重量140トン)が宇宙から帰還しました。
厳密に言えば、探査機そのものは大気圏突入後燃焼、小惑星「イトカワ」(Sタイプ[石灰質中心]惑星)の表面から採取したカケラが入っているかもしれないカプセルのみが切り離され、オーストラリアのウーメラ沙漠に着地したのです。
2003年5月9日に内之浦宇宙空間測候所で打ち上げられて以来、7年ぶりです。当初は4年で帰還の予定でした。トラブルが相次ぎ、一時、帰還が諦められたこともありました。宇宙航空研究開発機構(JAXA)、宇宙科学研究所(ISAS)の快挙、ひいては日本の宇宙科学界全体の誇りになる快挙です。
なぜなら、「はやぶさ」はその探査飛行で既に始めての成果を次々に出してきましたし、また最大の目的であったサンプルリターンに成功していれば、太陽系宇宙誕生の秘密が明かされるかもしれないからです。
本書はその全行程をドキュメンタリータッチの読み物にしてあります。
帰還にさいしては報道で大きくとりあげられ、衆目の知るところとなりました。一般には小惑星(太陽の周りをまわっている小惑星は、現在わかっているだけで27万個)「イトカワ」からの採石(といってもミクロン単位のゴミほどにも小さい粒子)があったのかなかったのかが焦点となっていますが、今回の「はやぶさ」ではイオンエンジンが推進力であること、地球からの軌道を離れるのにスィングバイという方式でのいわば省エネ方法を使ったこと、地球に送ってきた膨大な量の写真など大きな成果が既に出ています。ここに注目しないといけません。
また、大きなトラブルを次々と克服したことも特筆しなければなりません。その手法に関しても科学的貢献がありました。トラブルとは具体的には、イオンエンジンAの故障と停止(2003年5月27日)、3基のリアクションホイール(姿勢制御装置)のうちの一基の故障(2003年8月15日)、行方不明になった超小型探査ロボット「ミネルバ」(2005年11月12日)、イトカワへの一回目のタッチダウンで「はやぶさ」の状況が不明になったこと(2005年11月20日)、燃料漏れで姿勢が安定せず、通信が途絶したこと(2003年11月26日)、イオンエンジン自動停止状態(2009年11月4日),等々です。
数えきれないトラブルに対して冷静な、粘り強い、チームワークのよい探査活動への従事が、成功につながったことが、本書を読むとよくわかります。
「小惑星へ行こう」の呼びかけ賛同者88万人の名前をIC技術で作成した50枚のチップをイトカワに置いてきたという話、2度目のタッチダウンで「レーザー高度計」から「近距離エーザー高度計」への緊張感ある転換、そして着地の話、2005年9月燃料切れで息もたえだえの「はやぶさ」との通信途絶と奇蹟的回復の話、「はやぶさ」地球帰還直前にスーパーエンジニアである川口さんが神社詣でをした話、どれもこれもドラマチックな話の連続で興味つきません。

岩波新書のなかでも古典的名著といわれている本です。戦前1939年初版で、改訂版が1956年、再改訂版が1979年。わたしの手元にあるのは1994年に刊行されたもので、79刷(通算)とあります。
内容は本の表題にあるとおりですが、実は2つの話が盛り込まれています。ひとつは文字通り数字の零(ゼロ)がいつ、いかなる形で発見されたのかということ。もうひとつは、連続という問題をどのように考えるかと言うことです。
まず前者(「零の発見-アラビア数字の由来-」)について。
数字の零(ゼロ)はインドで発見され(6世紀頃)、計算数字と記録数字に分類可能な記数法がその淵源としてあるという話です。インド記数法を使えば10個の数字だけで、あらゆる自然数を自由に書き表すことができ、加減乗除の計算もすこぶる簡単にできます。わたしたちにとっては当たり前になって、とくに疑問も感じないインド記数法はソロバンや桁の取り方などで、古代から試みられたさまざまな工夫のなかから残った遺産です。人類の文化史上の巨大な一歩でした。
関連して、有理数と無理数、無限級数の和、対数の問題にも言及があります。
後半(「直線を切る-連続の問題-」)では、ギリシャに始まった数学の歴史が平易に論じられています。無理数の問題、時間と連続などの概念、点と線、微分と積分の考え方、また古代ギリシャ人の関心にあった幾何学の難問のひとつ、与えられた円と等しい面積をもつ正方形をるくることができるか、定規とコンパスで作図可能かといった問題が興味深く説明されています(与えられた円と等しい面積をもつ正方形は存在するが、定規とコンパスだけでは作図は既に不可能であることが証明されています)。
数学を学ぶことの面白さが伝わってくるいい本です。

猿橋賞という、女性の自然科学者たちの功績をたたえ、彼女たちの存在を世に伝え、女性を励ますことがその目的である賞があります。地球化学者であった猿橋勝子が勤務先の気象研究所の退官記念のお祝いに贈られた資金をもとにつくられました。
その猿橋勝子(1920-2007)の生き方の軌跡をまとめたのが本書で、第四回猿橋賞を受賞した物理学者の米沢冨美子さんが著しました。企画は5人の猿橋賞受賞者で練られたとのこと。
猿橋勝子は1920年3月22日東京生まれ、電気技師であった父・邦治と母・くのの一人娘で、9歳離れた兄がいました。第6高女を卒業後生命保険会社にいったん勤めましたが、向学の志が強く帝国理学専門学校に入学(東京医専にも合格したが、面接官であった著名な吉岡彌生の横柄な態度に嫌気がさし、入学せず[この事情は本書51-55ページに詳しい])、在学中から中央気象台で研究を始めましたが、ここで生涯の恩師とでもいうべき三宅康雄にであいます。
理専卒業後、大手町にあった中央気象台で正規の研究官として研究するようになり、オゾン層の解析から地球科学の研究に関わるようになります。さらに海洋における炭酸物質の測定問題に挑み、微量拡散分析装置を自ら開発、「天然水中の炭酸物質の挙動」で理学博士(東京大学)が学位授与されました(1957年)。
猿橋の業績としては、1962年のサンディエゴにあるカリフォルニア大学スクリップス海洋研究所でのセオドア・フォルサム博士との放射能分析に関わる「分析測定法の精度競争」での成果がつとに有名です。猿橋の微量分析の方法が国際的認められることとなる契機となりました。
猿橋は自らの研究成果に立脚し、人生の後半には核実験による放射能汚染の実態を訴えました。また日本学術会議会員として女性として初めて選らばれ、女性科学者の地位の向上と改善に貢献しました。
著者は「エピローグ」で書いています、「人間・猿橋勝子を一つの言葉で表すなら、「直向き(ひたむき)」であろう。/何に直向きであったかのか。生きることに。科学に。自分の哲学に」と(p.109)。









