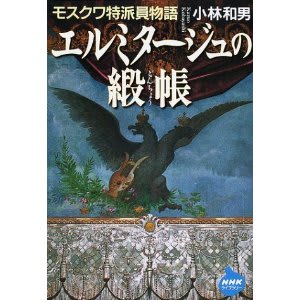
「エルミタージュの緞帳」とは? 世界三大美術館のひとつエルミタージュ美術館には、ほとんど知られていないし、見た人もいないが劇場があり、その正面の舞台にはロマノフ家の紋章である金色の王冠を戴いた「双頭の鷲」が入った緞帳がかかっているらしく、「エルミタージュの緞帳」とはそれを指しています。
この緞帳は19世紀の画家で、一時マリンスキー劇場の芸術監督をしていたアレクサンドル・ゴロヴィンとその弟子による作らしく、ソ連時代にはこの緞帳は表目に薄い幕が張られ、約70年もの間、破壊されることなく、存続してきた、とのことです。
1991年にソ連が崩壊し、エルミタージュ美術館は表面の薄い幕を剥ぎ、ロマノフ王朝のシンボルが再現されました。
本書はソ連崩壊からエリツィンが登場したロシアの政治と社会の現場報告ですが、その話の内容の象徴にこの緞帳が標題に採用されたわけです。(この書の最後のエッセイの表題は、「エルミタージュの緞帳」です)。
著者は冒頭で述べていますが、中学生から高校の頃、ソ連による人類初の人工衛星打ち上げに衝撃を受け、ロシア語を東京外国語大学で学び、NHK入社。70年にモスクワ駐在特派員となり、取材活動に。しかし、直後からこの社会主義国への期待が幻想であったことに気づきました。
社会主義国ソ連の問題点はいまでは周知であり、一般的には、過度の中央集権制、ノメンkラトゥーラが跋扈した官僚制度国家であったことが崩壊と解体の原因であったことになっています。
本書はジャーナリストによって書かれたものなので、話が具体的であり、リアルです。ペレストロイカがパンスト論議から時始まったこと、ゴルバチョフに大きな期待が寄せられながら軍部に対する統制がきかず、保守化したこと、エリツィンがゴルバチョフを失脚させたものの権力をとったとたん、権力にあぐらをかき、同じ轍をふんだこと、ソルジェニーツィンの取材での失望、画家レーピンの歪曲された実像、チャイコフスキーコンクール(1994年)の舞台裏などなど。
コスイギン外相、ロストロポーヴィッチ、サハロフ博士など大物への取材内容も興味深いです。
著者は「何かといえば共産党独裁政権下の特権階級を批判し」てきたのですが、自身その特権的な恩恵に浴してきたことも十分自覚していて(p.237)、ロシアとロシア人の一筋縄ではいかないしたたかさ、懐の深さをにも熟知し、そのことが文章の端々に感じられ、面白い読み物でした。
板橋区立美術館で「池袋モンパルナス展」が開催されています。来年の1月9日までです。板橋区立美術館に行くには、JR池袋駅から地下鉄有楽町線に乗り換え、「地下鉄赤塚」で下車、そこから徒歩ですと25分ぐらいです。一本道を道なりに歩いていけるので、迷うことはありません。バスも走っていますが、運動のため、往復歩きました。
池袋モンパルナスとは、今から約80年前、現在の池袋駅を中心とする一帯に、アトリエ付き住宅があったところです。借家人募集のビラや口コミで集まった画学生、靉光(あいみつ)、麻生三郎、寺田政明ら画家、評論家、詩人、演劇関係者などが集い、喫茶店、酒場で芸術論を交わされたそうです。その中の1人、詩人小熊秀雄はこの集落を芸術の都パリのモンパルナスをイメージしつつ「池袋モンパルナス」という詩とエッセイを残し、その由来で池袋モンパルナスの名があります。
1930年代半ばになると、軍靴がせまりきて、画家たちのあるものは召集を受け、従軍しました(兵隊や画家として)。この時期、若い画家たちの間で流行したシュルレアリスム風の絵画は、戦時中の文化や思想の統制により発表ができなくなりました。
この池袋モンパルナスについては、宇佐美承の名著『池袋モンパルナス』(集英社)があり、本ブログでも、2009年2月15日付で紹介しました。
今回の展示会では、1930~1940年代を「池袋モンパルナス」で過ごした画家、寺田政明、古沢岩美、井上長三郎、鳥居敏文と彼らが交友関係にあった画家、詩人の作品が展示されていました。また、池袋美術家クラブ、独立美術協会、新人画会、創紀美術協会などの活動もしのばれます。
アトリエ村に暮らした画家、吉井忠の日記の一部が紹介されています。寺田政明、麻生三郎、詩人の高橋新吉らの名前も散見される吉井の日記からは、池袋モンパルナスの日々の生活が読みとれます。
地味ではありますが、いい展示会でした。
 ←小熊秀雄「夕陽の立教大学」
←小熊秀雄「夕陽の立教大学」
 ←吉井忠「二つの営力」
←吉井忠「二つの営力」
 ←長谷川利行「水泳場」
←長谷川利行「水泳場」
 ←麻生三郎「男(自画像)」
←麻生三郎「男(自画像)」

著者「あとがき」によると、幕末から明治にかけての混乱と変動の時代に果敢に生き、行動した人々はたくさんいて、彼らは多くの失敗と挫折を繰り返し、試行錯誤を重ね、なおそこにも前途に燭光を見出し、時代の先駆けになろうとしたようです。
本書は、そうした人たちに長年関心を抱き続けてきた著者が2009年が横浜開港100年にあたったことを切っ掛けにこの地で上記の活躍をした21人に絞り、列伝風にまとめたものです。横浜が選ばれたのは、自身は横浜に生まれ育ったから、とのことです。
「海浜を埋め立てた速成の人口の活舞台に、われこそはと自己を恃み、あるいは乾坤一擲の運命を賭して、多くの若者がいっせいに流入してくるという光景は、史上類例のないことであり、破天荒なドラマの生まれないほうが不思議である」(p.303)と著者は書いています。
それでは、その21人とはどのような人々なのでしょうか。「Ⅰ 黒船から押し寄せた変革の波」では、7人が取り上げられている。J・C・ヘボン(伝導医師・ローマ字創始)、中川嘉兵衛(食肉業・製氷事業)、仲居屋重兵衛(生糸貿易商)、若尾逸平(生糸商)、下岡蓮杖(写真家・画家)、原善三郎・原三渓(生糸商・文化事業)。
「Ⅱ 開化の潮流に掉さす先駆者」に登場するのは、次の8人。内海兵吉・打木彦太郎(製パン業)、五姓田芳柳・五姓田義松(洋画家)、高島嘉右衛門(事業家)、岸田吟香(新聞創始者・事業家)、田中平八(生糸商・相場師)、メアリー・E・キダー(女子教育家)。
「Ⅲ 風雪の時代を駆け抜けた人々」には、次の6人がラインナップです。前島密(郵便事業)、早矢仕有的(商社創業)、堤磯右衛門(石鹸製造)、大谷嘉兵衛(製茶業)、雨宮敬次郎(相場師)、快楽亭ブラック(噺家)。
メアリー・E・キダーはフェリス女学院の創設者。早矢仕有的は現在の「丸善」の創業者であ(pp.228-230)、その有的にはハヤシライスの元祖説(p.236)もあるといいます。大谷嘉兵衛は太平洋に海底電線敷設に貢献した人物です(pp.267-279)。
本書に載っている人物は、それぞれに魅力的であり、もっと知りたいと思ったことがすくならずありましたが、巻末の参考がそのために役立つでしょう。
また、珍しい写真がたくさん掲げられています。著者はどのようにこれらを集め、取捨選択したのでしょうか。本づくりの観点から、興味をもちました。
今回はブレストン・コートに宿泊したので、活動範囲は、ほとんどハルニレテラスに終始しました。まず、食事。朝食はブレストン・コートでしたが、夕食はハルニレテラスに並ぶお店、SAWAMURA、川上庵などです。
昨日の画像のクリスマスツリーは、そこにあったものです。ツリーはいくつか設置されていました。もうひとつを下に掲げます。自分の写真で撮ったものです。

さらに、ここには普段はみられないメリーゴーランドが設置されていました。子どもたち用でしょうが、大人も馬に乗ることができます。夜はライトを浴びて、それは綺麗です。昼と夜のメリーゴーランドの写真を下に掲げます。


日中はピッキオで、山に入り、焚き火をたいてチョコレートフォンジュを楽しみました。久しぶりに薪を割り、煙にいぶられながらの焚き火体験。
木々の先をみあげると、冬の小鳥たちが鳴いていました。双眼鏡を貸してくれ、観察を試みましたが、野鳥たちが警戒してしまうのか、なかなかその姿をみせてくれません。
最後に「星野温泉」。ここでは以前にも入浴したことがありますが、今回はゆず湯になっていて、浴槽には数百個のゆずが浮き、いい香りでした。この時期の軽井沢は大変に冷えますので、温泉で温まるのは最高です。
今年は軽井沢に何度も足を運びました。軽井沢は避暑地のメッカですが、もうだいぶ前から、冬季にも観光客を呼ぼうというわけで、スキー、クリスマスなどのイベントを開催しています。大賀ホールでの演奏会も見ものです。
中軽井沢の星野リゾートのあたりは、クリスマスのデコレーションが華やかだということで、今年はここでイブを挟んだ数日を過ごしました。
天候に恵まれ、滞在中は快晴。とくに最終日は、くもひとつないピーカン。遠くに望む浅間山が貴婦人のようなたたずまいで、自然の懐の深さをあらためて感じました。とは言っても、空気は冷たく、とくに夕方になり太陽が沈むと、気温は零下になります。厳しい寒さです。

宿泊は、ブレンストン・コートのコテージです。ドアにはリースが掲げられていました。(写真参照)

夕方には高原教会で、イブの催しもの、佐久市から小学生の合唱団がきて、クリスマスソング。そのほか、聖歌隊の合唱、ハンドベルによる演奏など、イベントが続いていました。また、石の教会ではイベントこそないものの、周囲の光のデコレーションは、静謐のなかの大人の華やかさといった感じでしょうか。
何と言ってもすばらしいのは、ブレストン・コートのまわりに2000個もならぶランタンに入ったろうそくです。あたり一面で輝いています。そして木々には、ここにも照明が上手に配置され、クリスマスツリーが立ち、冷えた空気のなかにほんもののクリスマスを祝う人々の気持ちが満ち溢れていました。教会関係者によってリボンが、そして柊の葉を細工したものが訪問客にくばられ、温かなコミュニケーションの演出がありました。


経済学史研究者の第一人者であった小林昇[1916-2010](敬称略、以下同様)が昨年6月に93歳で逝去されましたが、その学問業績と人となりの回想記で、29人の方が執筆しています。
二部に分れ、Ⅰ部では研究者による小林昇の業績の評価と再検討です。通読すると、小林の研究の守備範囲、内外での評価、研究内容を理解できます。Ⅱ部では小林の研究以外の文学、短歌、こけし蒐集にまつわる回想である。小林の人柄、研究姿勢、研究仲間との交流、弟子との接し方が丁寧に回顧されています。一番最後に、娘さんである松本旬子さんが「父と母の思い出」を書いています。
わたしは経済学史の分野のことは門外漢でわからないのですが、この回想記を読むと、この分野でどのようなことが、どのように問題となってるのかを概観することができました。もっとも、それは小林昇の業績をとおしてのことですが。
小林が対象とした研究分野は、19世紀イギリス重商主義、リスト、スミスの研究であり、それをさして「デルタ」と呼ばれていたようです。関連して、タッカー、スチュアート、ヒューム、マルクスがとりあげられ、論じれました。
研究の方法は「試行錯誤的往反」というもので、研究対象である経済学者の理論と思想の徹底的な「相対化」であり、経済史を扱いながら経済学史を評価し、また逆連関的方向で捉えなおすというもののようです。
わたしなりの言い方をするならば、「試行錯誤的往反」とは、ある理論的基準で対象となる経済学者の思想なり考え方を絶対的に評価するのではなく、それらがおかれた経済社会状況のなかでとらえ評価し、また経済学者の眼をとおしてその時代の状況をとらえ、その思考的往復、循環をつうじて問題の所在を浮き上がらせ、論じていくという方法、といえるのではないでしょうか。
経済学史家として小林は現代資本主義の難問に対する政策的提言を行うことをストイックに控えていたようですが、根底には経済成長至上主義に批判的であり、達成された経済水準の維持に重きをおいた政策展開を構想していたようです。
小林はまた、文体に気を使った人のようで、自己の文体をもって自己の著作を書くことを信条とし、日本の社会科学者、とくに経済学者のいくたりがそうしているか、と疑問をもっていたとのことです。
小林は短歌が玄人はだであったことは、その著『山までの街』で知っていましたが、この回想記にもそのことに触れた記述が随所に見られました(歌集に『歴世』などがある)。また、こけしの蒐集でも相当な蓄積があったらしく、「東京こけしの会」で活動をし、エッセイもしたためていたようです。価値あるこけしのコレクションは、西田記念館に寄贈されました。
だいぶ前に行ったおでん屋さん「大凧」を紹介します。上野にあります。本ブログ(2011年11月28日付)に載せた別のおでん屋「多古久」の近くにあります。「大凧」の名前の由来はわかりません。お店の入口の上に「大凧」がつってありますが、屋号との関係でわかったのはそこまでです。席は30席ほどです。

閉店直前に飛び込みました。すでに「出来上がった」客が数名、テンションが高く、お酒の瓶、ビルのジョッキの空き瓶を前に談論風発の様子。
わたしは軽めのお酒とおでんのネタを注文。しかし、ネタの多くは売り切れで、好みのシラタキ、牛筋はなく、それで、はんぺん、卵などを注文して溜飲をさげました(?)。ジャガイモを頼んだところ、もうそれはかなり溶けていて小さめ。マスターは「サービスです」とお皿にとってくれました。
冬の夜はなべ物が、とくに伝統のおでんが身体が温まり、歓迎です。ポトフという料理がありますが、あれは西洋のおでんですね。と言ったら、違うという人がいます。しかし、わたしは今でもそう思っています。
ポトフを最も簡単に作るには、鍋に水をはって、コンソメの塊をひとつ入れ、あとは、骨付きの鶏肉、ソーセージ、ベーコン、キャベツ、人参、ジャガイモ、豆腐、セロリを入れて煮込むだけでかなり美味しいものができます。時間がないとき、あるいは野菜のかけらが冷蔵庫に残っているときはそれらを次々と入れて、火を通して食べます。わたしは個人的にはセロリは絶対に入れたい食材ですが、あとはあまりこだわりません。
話がおでんからポトフになってしまいましたが、そんな会話をしておでんを楽しみ、このお店をあとにしました。

表題は本書のなかの一章の標題からで、本書全体でキライな言葉について論じているのではありません。

本書で紹介されている、キライナ言葉、あるいは言葉の使い方に著者が合点がいかないとして挙げているおは、「体調をくずす」「ふれあい」「慎重な姿勢」「させていただきます」「じゃないですか」「あげる」「いやす」「いやし」「○○感」「まちづくり」「いのちとくらし」「思い出をつくる」「参加、交流、感動」などなど。キライな言葉の傾向はわかります。
本書はそれ以外にも、知的欲求を満たしてくれる箴言、警句、苦言、提言がたくさんあります。「電話を入れる」という言い方はおかしいが、いつ頃からそういう言い方が普及し始めたのか。「白兵戦」とはどういう意味なのか。辞書をひけばわかるのか?いつから使われた言葉なのか。「ミイラとりがミイラになる」の語源は?(語源は不明とのこと)。「ピンからキリ」というとき、ピンが上等なのか、キリが上等なのか?(「ピンからキリ」は「最初から最後まで」という意味で、どちらが最高で、最低なのかは意味していない)。
野球が好きなわたしは、戦中に敵性語である英語は使ってならないということで、「ストライク」を「よし」、「ボール」を「だめ」とコールしたと逸話に関するコメントが面白かったです。結論から言うと、当時は六大学野球が全盛の時代で、そこではこういうことはなかったようです。
「ストライク」を「よし」、「ボール」を「だめ」とコールしたのは「職業(プロ)野球」でそれもごく一時期に使われていたにすぎなかったようです。くわえて「職業(プロ)野球」は当時マイナーだったので(今からは考えられないが)、社会的に大きな意味をもったことではなかったようです。そのうち、戦火は厳しくなり野球どころではなくなったのはよく知られているとおり。
この他にも「実家」の本来の意味、「和夫」という名前はかつてあまりなかった、そもそも「和」をどうして「カズ」と読むのか、など意表を突く問題提起があって、このシリーズはやめられない。シリーズ本は「まだまだあるようだ。(この本は『週刊文春』に連載されていたのだそうである。

世田谷パブリックシアターで、「欲望という名の電車」(青年座)の舞台が演じられています。ブランチ役は、高畑淳子さん、妹のステラ役には神野美鈴さん、ステラの夫役には宅間孝行さん、ミッチ役には小林正寛さんが出演しています。
ストーリーは先日紹介した、テネシー・ウィリアムズ作、鳴海四郎訳です。原作を読んだときに、感想を述べたように、これをどのように劇にするのか、なかなか想像力がわかず、それゆえに愉しみにしていました。映画(ビビアン・リー、マーロン・ブランド出演)は観たのですがかなり前のことで、記憶が不確かでした。
高畑さん、神野さんの女優ふたりがいい演技でした。
「欲望」という電車に乗って「墓場」駅で降り、妹のステラの家にころがりこんだブランチ。ベルリーブの大農園に育った彼女は父が死んですべてを失い、教師をしていましたが、少年に手をだして追われ、ニューオリンズの街に来たのでした。
なかばアル中状態、そして粗野なスタンレーとステラとの同居で気まずい生活をしいられ、常にスタンレーに脅かされる日々。そして最後はそのスタンレーと・・・・・・。精神錯乱になって病院に入るにいたります。高畑さんの演技には鬼気迫るものがありました。
神野さんも入魂の舞台で、実際に涙を流しながらの演技でした。
・作 テネシー・ウィリアムズ
・訳 鳴海四郎
・演出 鵜山仁
・音楽・演奏 小曽根真
・ブランチ・デュボア 高畑淳子
・ステラ・コワルスキ 神野美鈴
・スタンレー・コワルスキ 宅間孝行
・ハロルド・ミッチェル 小林正寛
・ユニス・ハベル 山本道子
・スチーブ・ハベル 塾一久
・パブロ・ロビンス 川辺邦弘
・医師 金内喜久夫
・黒人女/メキシコ女/看護婦 津田真澄
・集金の青年 宇宙
・演奏 小曽根真
大宮にあるおいしいお店を探しています。みつけたのがこの店「つけめん102」(さいたま市大宮区桜木町2-446小島ビル1号館1F)です。JR大宮駅の西口を出て、徒歩15分ぐらいにあります。ネットでの評判がよかったので、行ってみました。ネットの口コミはあてにならないものもありますが、慣れてくると、まじめに書き込んでいるものと、そうでないものとを見極めることができるようになります。
この店の規模がよくわからなかったのですが、かなりの人が並んでいました。カウンターの席しかなく、15席くらいでしょうか? 並びは20人ぐらい、聞くと30分程で席につけるということだったので、また来るのもやっかいなので、待つことしました。

この店は千駄木にある「つけめんTETSU」の姉妹店のようで、TETSUを「テン・ツー」を読み変え、それに数字をあてはめて「10と2」、それで「102」だそうです。
つけめんというのはあまり食べたことはありませんが、濃厚に見える、しかし意外とあさありしているスープに太めの麺をつけて食べます。ネットの口コミに書かれていたように、おいしいつけめんでした。


若い人が威勢よく、うまく連携しながら働いています。お客も若者が圧倒的でした。

著者は作家北杜夫(斎藤宗吉)の娘で歌人斎藤茂吉の孫、茂吉の妻は輝子です。著者にとっては祖母にあたります。その輝子の生涯、生き方を孫娘の眼でエッセイ風にまとめのがこの本です。
輝子は浅草にあった精神科の病院の医師、斎藤紀一の娘でした。茂吉は14歳の頃に山形県南村山郡金瓶村(現在の上山市金瓶)からでてきてこの親戚の医師のところに転がりこみ、養子となりました。
茂吉と輝子は幼馴染みでしたが、茂吉31歳、輝子18歳のときに結婚。二人の仲は決してよいとはいえず、生涯で18年間、別居生活がありました。もともと輝子は活発な少女でしたが、茂吉死後、猛女ぶりを発揮します。
海外旅行です。89歳で亡くなるまでに海外渡航数97回、世界108カ国を訪れました。その中には79歳で南極、80歳でエヴェレスト山麓、81歳でエジプト、83歳でアラビアなどが入っています。
著者はその海外力熱に浮かされた輝子の猛女ぶりとそれに振り回された叔父、茂太夫妻、父宗吉とその妻の様子を面白可笑しく書き綴っています。
父である北杜夫さんのことも、すでに本人が公にしていることばかりですが、躁鬱病の顛末を中心に描写しています。一番悔やんでいるのは、著者が小学校1年生から大学4年までにつけていた日記を、就職が決まったときに、「燃えるゴミ」にだし、この世からなくなってしまったこです。
ただ、輝子死後、輝子から著者に海外から宛てたかなりの枚数の絵葉書がでてきたようで、そのことをエピローグで紹介しています。また、著者は成城大学出身ですが、卒業論文に歌人としての斎藤茂吉をとりあげたとか。しかし、その内容は構成だけが示され、どんなものになったのかは書かれていません。たいした論文にはならなかったと推測できます(何となく、そのような匂いがする著者の書きっぷりからわかるのです)。

こんなに言葉にこだわったら二進も三進もいかないのではないか。しかし、こだわらないで過ごしていたら能天気すぎはしまいか。とにかく、言葉、漢字の蘊蓄の書です。
例えば、「大臣」という語。これは「王様の家来」という意味。したがって、日本は「天皇」という名の皇帝がいる国だから「大臣」という語を使うのはまだしも(それでも象徴天皇制なのだから、「王様の家来」というのは憲法規定から言えばおかしいです。著者はそこまで言っていませんが・・・)、フランスの外務大臣、ドイツの農業大臣という言い方はおかしいのではないかとうのです。中国の「外交部」のことを「外務省」というのは変ではないか、と書かれています。
「内閣」の「閣」は小部屋の意、したがって「内閣」は厳密に言えば「秘書室」という程度の意味だそうです。なるほど。
明治の初めまで日本人の男子の名前には「実名」と「「名乗」があり、前者は公家、武家の男子が元服のときにつける名で、訓で読み、読み方はどうでもよかったそうです。「名乗」は通称で音で読むのだそうです。それで徳川慶喜は「けいき」であって、「よしのぶ」が正しいことにはならないそうです。西郷「隆盛」とその弟「従道」は明治になってから間違いでその名になったそうです。
「円」はなぜ「YEN]なのか。それは「円」は「えん」と発音されたのではなく、「いぇん」だったからだそうです。アイウエオの「エ」は平安時代からずっと江戸時代まで「イェ」と発音されていたからで、明治4年5月の太政官布告「新貨条例」で日本の貨幣単位を「円(圓)」とすることが定められたときには、「円」のローマ字表記は「YEN」だったらしいです。
日本の暦と西暦は年の変わり目も違うし、一年の日数、月数も時々違い、ひと月の日数も違うので「文久二年(1862)」といった表記は正しくないのだそうです。
さらに時代小説など読むと、江戸時代の人たちの会話に」、当時絶対使われていなかった「連絡」とか「報告」といった言葉がでてきてぎょっとしたこともあったらしいです。
いやいやいろいろなことを学びました。

わたしたち子供時代の食生活は、今とまるで違います。バナナは高級品でしたが、今はそうではありません。クジラの肉のカツは、豚のトンカツより安かったらしく、よく食卓に出ましたが、いまはレアです。
こういう話を始めたらきりがないのでやめますが、スキヤキはめったに食べることのできないメニューでした。一年に何回、食べることができたでしょう。数回で、御馳走でした。子供たちはあらそって牛肉をさがし、すぐに鍋から「売り切れ」となりました。今の子は、スキヤキはとくに好きではないのではないでしょうか。また、それほどぜいたくな料理ではありません(もっとも高級な牛肉にはなかなか手が出ませんが)。
というわけで、子供時代の御馳走だった「スキヤキ」には郷愁もあり、いまでもときどき食べたい料理です。
前置きがながくなりましたが、極上の「スキヤキ」屋さんが銀座にあります。スキヤキだけではなく、神戸牛を食べることができる老舗と言ったほうが正確でしょう。神戸牛ステーキ処「牛庵」(中央区銀座6-13-6:03-3542-0226)です。
スキヤキは、大変おいしいです。まず、牛脂で鍋にてりをつけ、ここに牛肉を広げ、割り下を注ぎます。このあたりまでは、給仕の方が手伝ってくれます。溶いた卵に焼けた肉をつけ、ひとくち口に入れると懐かしさがこみあげてきます。そう、この味、この味。
次いで、玉ねぎ、シイタケ、筍、春菊、豆腐を順に加え、スキヤキがスキヤキらしくなっていきます。
美味しく、しかし値段はリーズナブル。最後はつけものと白いご飯、そして赤だしの味噌汁、いい時間を過ごしました。
すきやきは家庭で鍋をつつくのもいいですが、数年おきにここを訪れ、本場の味に舌鼓をうちます。
ごちそうさまでした。

銀座のいいBARを一軒、紹介します。”BAR FOUR SEASONS”(中央区銀座4-13-12 伊藤ビル4F:03-3563-0808)です。綺麗なBARで、もうすぐ開業7年目ということでした。クリスマスが近いせいか、ドアにはリースがかかっていました。
BARですからカクテルといきたいところですが、わたしはいつもウィスキーです。ボウモアとマッカランを注文。眼の前のバーテンダーさんが女性で、話をしているうちに北海道出身、高校時代に札幌にいたということで、さらに話を進めていくと、何とわたしが住んでいた琴似八軒にいたこともあったとのことで、驚きました。帯広市が故郷のようです。
家にかえってこのBARのHPをのぞくと、その方が紹介されていました。そこには、次のようなことが書き込んでありました。
帯広市にあった「カクテルバー真藤」を2004年に閉め、このBARのメンバーである勝亦誠さんとともに「BAR FOUR SEASONS」を開いたとのこと。それまでの経験を活かし、季節に合わせて北海道の食材なども取り入れて、客をもてなすことをしたいとのことです。何でも第3回 ビーフィーター インターナショナル バーテンダー コンペティション(ニューヨーク)で総合優勝し、第28回 全国バーテンダー技能競技大会(名古屋)でも総合準優勝した人のようです。おみそれしました。
20席ぐらいのカウンターがあり、奥にはグループで飲める席もあります。かなり人気のお店のようで入れ替わり立ち替わりお客さんがきていました。

東京文化会館で、早稲田大学交響楽団・第192回定期演奏会がありました(11月30日)。指揮は山下一史さんです。
まず、会場に着いて、その人の多さに驚きました。OB、OG、関係者が多いのでしょう。かく言うわたしは関係者でも何でもなく、この交響楽団のファンにすぎません。会場はこの会館の大ホールでしたが、満席でした。
演奏曲目は、R.シュトラウスの「アルプス協奏曲・作品64」「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら・作品28」「ホルン協奏曲第1番・変ホ長調・作品11」でした。「アルプス協奏曲」は、シュトラウスがアルプスをイメージして作った交響詩です。いろいろな楽器が個性を発揮して、曲が成り立っています。テーマがアルプス登山の一日ですから、夜明けから以下のような標題が並びます。
《夜/日の出/登り坂/森へ/滝にて/まぼろし/花咲く草原にて/牧場にて/藪と茂みに抜け、道に迷って/氷河にて/危険な瞬間/頂上にて/ヴィジョン/霧が立ち上る/太陽が自然に陰っていく/エレジー/嵐の前の静けさ/雷と嵐、下山/日没/エピローグ/夜》
学生さんの演奏は素晴らしかったです。そのことを言ったうえで、ただわたしは交響詩と言うのはやや苦手です。作品に初めからテーマがついているのが交響詩の普通の形ですが、これが時々邪魔になります。ここは嵐の場面、ここは夜明けといわれても、そう聴こえない時もありますし、どうしてこれがそのテーマなの、ということもあります。そういう思考錯誤が、作品をきくときにわずらわしくなることがしばしばだからです。
「ホルン協奏曲」は、いい曲です。この協奏曲は古典派やメンデルスゾーン、シューマンに影響を受けていたシュトラウスの初期の作品です。古典的な3楽章構成です。シュトラウス18歳の作品と知って驚きました。いまではモーツァルトの協奏曲に次ぐ演奏頻度の高い作品です。
ホルンはベルリンフィルの主席ホルン奏者、シュテファン・ドールさんがゲスト出演でした。ドールさんのホルンが素晴らしかったです。ふくよかな、暖かい、深い音色を、聴衆が満喫していました。ホルンの伸びやかな音が気持ちよく耳に入ってきます。









