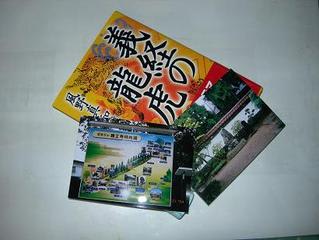佐渡情話 夏めく風や たらい舟
おけさ・たらい舟・尖閣湾(君の名は) みんな悲恋な話です。
そんな悲しい恋はいやですが、何故か日本人の心にのこり大事に育っていくのですよね。 民話の里では、山椒太夫・夕鶴・他、 文楽人形芝居もあります。
つゆ晴れ間 民話うまれる 情の島
おけさ笠をかぶり たらい舟にのりました、この笠って、盆踊りは無礼講、武士・町人・無宿人 誰が踊っているのか分からない様にかぶったんですって、今年の町内会の盆踊りこれ被って踊ろうかしら、よけい目立つかしら?。
顔隠し 無礼講だよ 盆踊り
今BS再放送で朝、「君の名は」やってまーす。忙しい時間なのに誰が見るの? 海中透視船のりました、想像していた日本海とは違った穏やかな海です。

君の名を 問えばキスゲが なびく湾
ここのキスゲの種類忘れましたが、丈は短く土の無い岩肌から潮風にまかせ、揺れてます。
自分へのみやげはなんたって佐渡の地酒、「北雪」の五種類飲み比べです、これからの暑い夏を乗り越えるには、これが一番楽しみでーす。
最後にきて、芭蕉の面影 消えました、まぁいいか、出雲崎で待っていてくれるとおもいます。
旅装解き 地酒に酔いし 想う佐渡
おけさ・たらい舟・尖閣湾(君の名は) みんな悲恋な話です。
そんな悲しい恋はいやですが、何故か日本人の心にのこり大事に育っていくのですよね。 民話の里では、山椒太夫・夕鶴・他、 文楽人形芝居もあります。
つゆ晴れ間 民話うまれる 情の島
おけさ笠をかぶり たらい舟にのりました、この笠って、盆踊りは無礼講、武士・町人・無宿人 誰が踊っているのか分からない様にかぶったんですって、今年の町内会の盆踊りこれ被って踊ろうかしら、よけい目立つかしら?。
顔隠し 無礼講だよ 盆踊り
今BS再放送で朝、「君の名は」やってまーす。忙しい時間なのに誰が見るの? 海中透視船のりました、想像していた日本海とは違った穏やかな海です。

君の名を 問えばキスゲが なびく湾
ここのキスゲの種類忘れましたが、丈は短く土の無い岩肌から潮風にまかせ、揺れてます。
自分へのみやげはなんたって佐渡の地酒、「北雪」の五種類飲み比べです、これからの暑い夏を乗り越えるには、これが一番楽しみでーす。
最後にきて、芭蕉の面影 消えました、まぁいいか、出雲崎で待っていてくれるとおもいます。
旅装解き 地酒に酔いし 想う佐渡