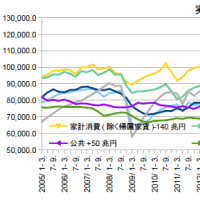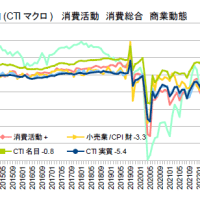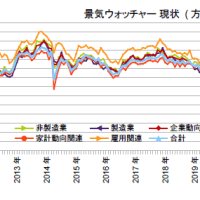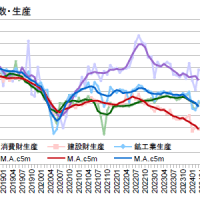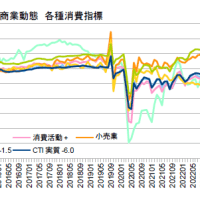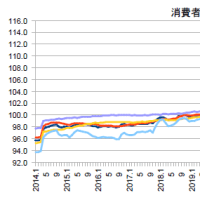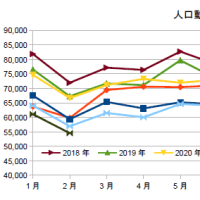今日は近未来フィクションである。2017年、東京大学は、ついに秋入学制に踏み切った。意外だったのは、一部の主要大学がこれに追随しなかったことだ。これは、後の悲惨な結末を暗示するものだった。
旧帝大のうち、北海道、東北、九州の各大学が追随しなかったのは、地元高校と県当局からの強い反対が背景だった。豊かでない地方の高校生にとって、秋入学までの無駄なギャップイヤーの期間は経済的に負担が重く、進学のチャンスを摘んでしまうと訴えたのである。海外の留学生の便宜より、地元の高校生を大切にして欲しいというのは、もっともな話だった。大学側は東大に遅れることに不安もあったが、数年は様子を見ることで妥協した。
早稲田大と慶応大が追随しなかったのも、東大にとって予想外であった。もともと、私学は、ギャップイヤーによって、半年間も入学金などの収入が先延ばしになるのは痛かった。春秋入学制という半身の構えで対応し、果たして秋入学制が成功するかどうか、結果を見てからでも遅くないというのが最終方針になったのである。
秋入学制は、新聞や経済界といった、「グローバル人材」などという抽象的な言葉で喜ぶ人たちには評判が良かったが、やってみると、専門家が危惧していたことが、次々と現実になっていった。第一は、秋入学制にしても、優秀な外国人の留学生が大して増えなかったことである。優秀な留学生が日本に集まりにくいのは、入学時期よりも、教育内容の問題だったからである。
その反面、弊害は大きかった。海外の有名大学が、「どうせギャップイヤーを空費するなら我が大学へ」と、営業攻勢をかけてきたのである。これまで東大が抑えてきた、東京の高所得層に属する最優秀の高校生をゴッソリと持っていかれてしまった。また、伸びしろが大きく素質のある高校生は、東大より、東北大や九州大を選ぶようになった。両大は、国際化は、学部でなく、大学院でするというアピールにも努めた。
他方、私学の雄は、「ギャップイヤーのムダを考えれば、私学の学費も高くない」と強調し、首都圏の中所得層のできる高校生を奪いにかかった。東大合格レベルの生徒には、奨学金を充実することも忘れなかった。結局、東大は、わずかな留学生と引き換えに、日本人の最高の学生の多数を失ってしまった。まさに、抽象的な理念に溺れて学区制度を敷き、優秀な生徒を失って没落した、かつての日比谷高校の二の舞になったのである。
東大の失敗の理由は何だったのだろう。答えは簡単だった。日本人の高校生という、自分たちにとっての最大の顧客のことを、ちっとも考えなかったからである。そもそも、自分たちの方針に皆が付いて来るという驕りがあり、顧客はもとより、競争者も戦略を変えてくるとは思ってもいなかったのだ。こうして、社会に多大な迷惑をかけ、日本の教育を衰退させて、壮大な実験は終わったのである。
※冒頭を書き損じておったので、謹んで訂正します。
(今日の日経)
先端医療の実用化早く。マンションにスマートメーター。大学開国・内向き変える好機に。アジア輸出が黒字を左右。円売り権利が示す変調。コンビニ売上高1.7%増。百貨店は減。陶酔の賞味期限・梶原誠。経済教室・回復軌道へ・センター予測・愛宕伸康。
旧帝大のうち、北海道、東北、九州の各大学が追随しなかったのは、地元高校と県当局からの強い反対が背景だった。豊かでない地方の高校生にとって、秋入学までの無駄なギャップイヤーの期間は経済的に負担が重く、進学のチャンスを摘んでしまうと訴えたのである。海外の留学生の便宜より、地元の高校生を大切にして欲しいというのは、もっともな話だった。大学側は東大に遅れることに不安もあったが、数年は様子を見ることで妥協した。
早稲田大と慶応大が追随しなかったのも、東大にとって予想外であった。もともと、私学は、ギャップイヤーによって、半年間も入学金などの収入が先延ばしになるのは痛かった。春秋入学制という半身の構えで対応し、果たして秋入学制が成功するかどうか、結果を見てからでも遅くないというのが最終方針になったのである。
秋入学制は、新聞や経済界といった、「グローバル人材」などという抽象的な言葉で喜ぶ人たちには評判が良かったが、やってみると、専門家が危惧していたことが、次々と現実になっていった。第一は、秋入学制にしても、優秀な外国人の留学生が大して増えなかったことである。優秀な留学生が日本に集まりにくいのは、入学時期よりも、教育内容の問題だったからである。
その反面、弊害は大きかった。海外の有名大学が、「どうせギャップイヤーを空費するなら我が大学へ」と、営業攻勢をかけてきたのである。これまで東大が抑えてきた、東京の高所得層に属する最優秀の高校生をゴッソリと持っていかれてしまった。また、伸びしろが大きく素質のある高校生は、東大より、東北大や九州大を選ぶようになった。両大は、国際化は、学部でなく、大学院でするというアピールにも努めた。
他方、私学の雄は、「ギャップイヤーのムダを考えれば、私学の学費も高くない」と強調し、首都圏の中所得層のできる高校生を奪いにかかった。東大合格レベルの生徒には、奨学金を充実することも忘れなかった。結局、東大は、わずかな留学生と引き換えに、日本人の最高の学生の多数を失ってしまった。まさに、抽象的な理念に溺れて学区制度を敷き、優秀な生徒を失って没落した、かつての日比谷高校の二の舞になったのである。
東大の失敗の理由は何だったのだろう。答えは簡単だった。日本人の高校生という、自分たちにとっての最大の顧客のことを、ちっとも考えなかったからである。そもそも、自分たちの方針に皆が付いて来るという驕りがあり、顧客はもとより、競争者も戦略を変えてくるとは思ってもいなかったのだ。こうして、社会に多大な迷惑をかけ、日本の教育を衰退させて、壮大な実験は終わったのである。
※冒頭を書き損じておったので、謹んで訂正します。
(今日の日経)
先端医療の実用化早く。マンションにスマートメーター。大学開国・内向き変える好機に。アジア輸出が黒字を左右。円売り権利が示す変調。コンビニ売上高1.7%増。百貨店は減。陶酔の賞味期限・梶原誠。経済教室・回復軌道へ・センター予測・愛宕伸康。