ジャズの演奏を聴いていて、最近つくづく感じるのが、走るリズム・セクション。人間のやっていることだから、機械のように正確にリズムを刻む事は不可能だし、現実に出来るとすれば、テクノになってしまう。おおよそ、人間がやる演奏としては不自然になってしまう。(テクノを否定する訳ではなく、その機械的不自然さが、テクノでは十分生かされていることは理解しています。)リズムマシンでも1980年代後半だったか、Rolandから人間的なリズムの揺れを再現するマシンが出たことがあり、それを買ったんだけど、使いこなせなかった記憶がある、トホホ。機械も未だに捨てられずに持ってる。
Running bassとは、Walking bassとも言い、コードの主音、もしくは五度の音などコードの構成音、以外の音を繋いで演奏する演奏法。ポール・マッカートニーもAll my lovingなんかでやってて、中学の時、気に入ってました。
私がここで言っているのは、リズムが必要以上に早くなるリズム・セクションについての話です。リズム・セクションはピアのトリオなど、バックを勤める人達のこと。Art Pepper meets the Rhythm Sectionという有名なCDがあるが、これはArt Pepperという有名なプレーヤーが、Miles Davisのバック(リズム・セクション)を勤めていたRed Garlandのピアノトリオと演奏したから付けた名前。この辺りはジャズをご存じの方なら良く知ってらっしゃる話。ついでに言うと、この時、Art Pepperは麻薬が切れていて、体調は最悪の状態だったとか。でも、演奏は素晴らしいの一言。脱線ばかりでごめんなさい。
最近、リズムが早くなるプレーヤーを聞く機会が割とあり、何処まで早くなるのが許容出来るかという話。
アップテンポの曲は一流のプレーヤーが演奏しても、初めより終わりの方が早くなってる事って結構ある。乗ってくると、早くなる。聞いている方も不自然さは感じない。何故か??徐々に早くなるから。
最近聞いたドラマーはアップテンポの曲では、大概突然早くなる。ドラムソロを採ると又早くなる。ドラムソロが終わると、ある程度他のプレーヤーは早くなったテンポに合わせるけど、あまりに不自然なため、同じテンポにならないので、少しテンポが遅くなる。要するにリズムが伸縮する。ジャズでは、アドリブがどうのこうのと皆さんおっしゃるが、実はリズム・キープがうまく行っている事が前提になるのが基本。この基本が守られていないと、ジャズのスウィング感が損なわれる。このプレーヤー、以前から、好きになれなかったが、ここ一年、誰にも解る突然のランニング!!!フライングと言っていいかも。ジャズでは、ベースのリズムが少し先行してドラムがその少し後にビートが付くことになり、グルーブ感を出すという。その逆をやられた日には、聴衆はたまらない。不愉快で。
さて、フライング リズムセクションのプレーヤーの心理はどんな物か、いろんな専門家に聞いてみたけど、ある人は、早くなるのを全然気にしてないからだろう、という答え。ある人は、バラードの時は良いから、そういうプレーヤーでも選ぶんじゃないか、との答え。実は、多くの専門家には、走るプレーヤーが誰か、共通の認識があるようです。どんなプレーヤーを選択するかは、リーダーの責任だし、フライング・ドラマーを選んでリーダーをした人の評価が下がってもかまわないのかも知れないけど、音楽が職業である以上は、必要最低限の技術は満足されないといけないのでは??と、あんまり真剣になって本当のことを書くと、途端に嫌がられるので、これ以上は書きませんが、走りすぎるプレーヤーは、たまに同業人から指摘されることもあろうし、自分の演奏、録音採って、反省の糧にするのも良いと思います。自分がリーダーになってやっているのなら兎も角、バンドに迷惑を掛けるのはいけません。このレベルのプレーヤーがアメリカ当たりで通用しないことは明らかですが。そうそう、私が指摘したプレーヤーに対して、まだ、ジャズを聴き始めて1年生くらいの子が、聞き苦しいと言ってました。要するに、最も基本的で、且つ重要な事のひとつがリズムキープってこと。聴衆も、その程度のことは解って、ジャズライブを聴けば、プレーヤーはセレクトされてくるんじゃないかとも思います。ついでに言うと、日本のドラマーはモダンジャズでトレーニング、スイング苦手と言う言い訳。これも、言い訳として通用しません。アメリカなどのプレーヤーは、デキシー、スウィングからモダン、超モダンなどに至るまで幅広いトレーニングを受けています。しっかりしたリズム感を持っています。一定レベル以上の人に言えることなんでしょうが。
因みに、私は、走る人は、元々のリズム感がそうである人は別にして、多くは、長期にわたるアルコールの多量摂取が原因のひとつではないかと考えています。今や、ジャズ演奏は、麻薬打って、酒飲みまくってというふしだらな生活で維持出来る程、簡単な技術では無くなっているように思います。
ジャズに重要なのは、一拍の深さ、なんてよく聞きます。走りすぎは、一拍が浅くなります。ついでに申し上げておくと、私は・・・、走ります。でも、アップテンポの曲は指がおっつかず、走ることはありません、なんちゃって。所詮はアマチュア、これが最大の言い訳です。
Running bassとは、Walking bassとも言い、コードの主音、もしくは五度の音などコードの構成音、以外の音を繋いで演奏する演奏法。ポール・マッカートニーもAll my lovingなんかでやってて、中学の時、気に入ってました。
私がここで言っているのは、リズムが必要以上に早くなるリズム・セクションについての話です。リズム・セクションはピアのトリオなど、バックを勤める人達のこと。Art Pepper meets the Rhythm Sectionという有名なCDがあるが、これはArt Pepperという有名なプレーヤーが、Miles Davisのバック(リズム・セクション)を勤めていたRed Garlandのピアノトリオと演奏したから付けた名前。この辺りはジャズをご存じの方なら良く知ってらっしゃる話。ついでに言うと、この時、Art Pepperは麻薬が切れていて、体調は最悪の状態だったとか。でも、演奏は素晴らしいの一言。脱線ばかりでごめんなさい。
最近、リズムが早くなるプレーヤーを聞く機会が割とあり、何処まで早くなるのが許容出来るかという話。
アップテンポの曲は一流のプレーヤーが演奏しても、初めより終わりの方が早くなってる事って結構ある。乗ってくると、早くなる。聞いている方も不自然さは感じない。何故か??徐々に早くなるから。
最近聞いたドラマーはアップテンポの曲では、大概突然早くなる。ドラムソロを採ると又早くなる。ドラムソロが終わると、ある程度他のプレーヤーは早くなったテンポに合わせるけど、あまりに不自然なため、同じテンポにならないので、少しテンポが遅くなる。要するにリズムが伸縮する。ジャズでは、アドリブがどうのこうのと皆さんおっしゃるが、実はリズム・キープがうまく行っている事が前提になるのが基本。この基本が守られていないと、ジャズのスウィング感が損なわれる。このプレーヤー、以前から、好きになれなかったが、ここ一年、誰にも解る突然のランニング!!!フライングと言っていいかも。ジャズでは、ベースのリズムが少し先行してドラムがその少し後にビートが付くことになり、グルーブ感を出すという。その逆をやられた日には、聴衆はたまらない。不愉快で。
さて、フライング リズムセクションのプレーヤーの心理はどんな物か、いろんな専門家に聞いてみたけど、ある人は、早くなるのを全然気にしてないからだろう、という答え。ある人は、バラードの時は良いから、そういうプレーヤーでも選ぶんじゃないか、との答え。実は、多くの専門家には、走るプレーヤーが誰か、共通の認識があるようです。どんなプレーヤーを選択するかは、リーダーの責任だし、フライング・ドラマーを選んでリーダーをした人の評価が下がってもかまわないのかも知れないけど、音楽が職業である以上は、必要最低限の技術は満足されないといけないのでは??と、あんまり真剣になって本当のことを書くと、途端に嫌がられるので、これ以上は書きませんが、走りすぎるプレーヤーは、たまに同業人から指摘されることもあろうし、自分の演奏、録音採って、反省の糧にするのも良いと思います。自分がリーダーになってやっているのなら兎も角、バンドに迷惑を掛けるのはいけません。このレベルのプレーヤーがアメリカ当たりで通用しないことは明らかですが。そうそう、私が指摘したプレーヤーに対して、まだ、ジャズを聴き始めて1年生くらいの子が、聞き苦しいと言ってました。要するに、最も基本的で、且つ重要な事のひとつがリズムキープってこと。聴衆も、その程度のことは解って、ジャズライブを聴けば、プレーヤーはセレクトされてくるんじゃないかとも思います。ついでに言うと、日本のドラマーはモダンジャズでトレーニング、スイング苦手と言う言い訳。これも、言い訳として通用しません。アメリカなどのプレーヤーは、デキシー、スウィングからモダン、超モダンなどに至るまで幅広いトレーニングを受けています。しっかりしたリズム感を持っています。一定レベル以上の人に言えることなんでしょうが。
因みに、私は、走る人は、元々のリズム感がそうである人は別にして、多くは、長期にわたるアルコールの多量摂取が原因のひとつではないかと考えています。今や、ジャズ演奏は、麻薬打って、酒飲みまくってというふしだらな生活で維持出来る程、簡単な技術では無くなっているように思います。
ジャズに重要なのは、一拍の深さ、なんてよく聞きます。走りすぎは、一拍が浅くなります。ついでに申し上げておくと、私は・・・、走ります。でも、アップテンポの曲は指がおっつかず、走ることはありません、なんちゃって。所詮はアマチュア、これが最大の言い訳です。










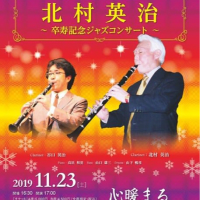
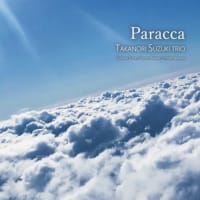

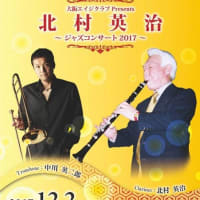












いつものHiro様らしからぬ痴的(失礼!)ではなく知的な内容に感嘆しております!
「Art Pepper meets the Rhythm Sectionという有名なCD…この時、Art Pepperは麻薬が切れていて、体調は最悪の状態だったとか。でも、演奏は素晴らしいの一言、…今や、ジャズ演奏は、麻薬打って、酒飲みまくってというふしだらな生活で維持出来る程、簡単な技術では無くなっている…」
大昔の「Jazz」は「庶民が踊るための音楽」という側面をかなり持っていたと思います。そこから完全に脱却させ、「聴くための音楽」にしたのがチャーリー・パーカー、ディジー・ガレスビーでありマイルス・デイビスなどでありました。しかしながら「旧来の悪癖」とは縁が切れず、若くしてその才能を破滅させた天才も多く存在します。上記のCD、「Art Pepper meets the Rhythm Section」を聴いても解るように「Jazzと麻薬」は無関係というより、麻薬(Drug)はJazzというアメリカの代表的文化の発展を阻害するものではないでしょうか…?
Jazzが「男女混淆の場」から姿を消した時、Jazzは「風俗」から「芸術」に変わったのだと思います。
今回の記事も、ここ一年間考え続けていたことを、ここに記載してあります。走るドラム、これが本題です。遅れがちなドラムも困るのですが、走りすぎるのも困る、高い評価を得ている(????)プロのドラマーに走る人がいるのは、意外です。こういうプレーヤーとプレーしていると、ビックリするほど始めと終わりでリズムが違います。ただ早くなるだけならまだマシだけど、早くなったり、遅くなったり。
なんでも評論家さんにはこういう人のプレイを一緒に聞いて、是非コメントを貰いたいと思います。
ただ、ジャズが踊るための音楽から、Bebapになり、聞くための音楽(早くて踊れない!)になったのがゲイジツ、というのはいかにもありきたりのコメント!では、ウィンナ・ワルツはゲイジツではないんでしょうか。私はスウィング・ジャズも十分な音楽性、芸術性を感じますが。
多忙な日常生活の中で、高いお金を払って、走るドラム、走るリズムセクションは、もう聞きたくない、というのが本音です。
さて、なんでも評論家さんは々お考えですか???????
「ただ、ジャズが踊るための音楽から、Bebapになり、聞くための音楽(早くて踊れない!)になったのがゲイジツ、というのはいかにもありきたりのコメント!では、ウィンナ・ワルツはゲイジツではないんでしょうか。私はスウィング・ジャズも十分な音楽性、芸術性を感じますが。」
私はウィンナ・ワルツや、日本で云ういわゆるスウィング・ジャズに芸術性がないなどとは片言隻句も書いてはおりませんのでよろしく誤解なきようお願いします。
20世紀のアメリカで最も偉大な芸術家(と私は考えていますが)デューク・エリントンも「スインなどグしなけりゃ意味ないね
ありきたりの意見ではいけませんでしょうかね…?
「奇を衒った書込み」など”意味ないね
走るドラマーが、”技術に定評の有る”と論評される様では日本(関西??)ジャズ界も危ういですね!?。