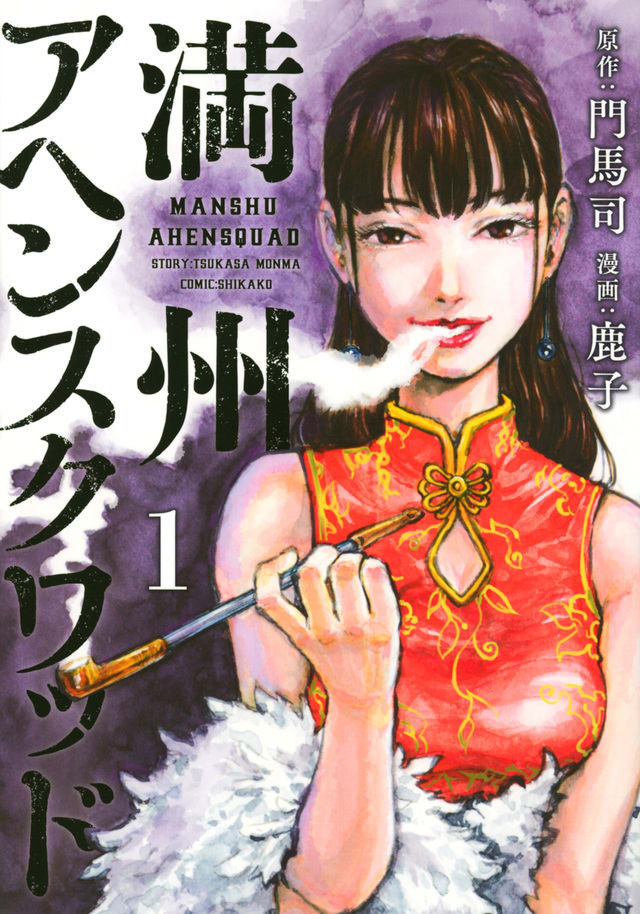最近こそあまり読まなくなっていたが、一時はかなり好きだった方。
学生時代に田名角栄氏のロッキード事件裁判を巡る論争を当時の『朝日ジャーナル』誌上で読んだのが、最初だったと思う。




後に大好きな作家となったハルバースタムの名を知ったのは、この『アメリカジャーナリズム報告』だったと記憶している。
特に感銘を受けたのがこの2冊↓


科学/サイエンスに対して、ジャーナリズムの立場からまっすぐに切り込んでいく姿勢は尊敬に値するものだったと思う
とりわけアメリカの宇宙飛行士たちに対して、「宇宙で神の存在を感じたか?」と質問し、
「今まで沢山のインタビューを受けてきたが、そんな質問をされたのは初めてだ」
という答えを引き出したのは、彼のジャーナリスト人生の中でもハイライトの一つに数えられるものだったのではないか。
その後も何冊か。

もう10回以上は読み返し、愛読書の一つとなったのがこれ↓

進路に、いや人生に悩む若者諸君にぜひ一読を勧めたい本(^^)。
一番最近読んだのが、武満徹へのインタビュー集を元にまとめたこれ↓

かなり前から武満への取材を進めていたのは知っていたが、いざ本になってみるとこれがもの凄い大作(驚)!
読み応え十分で、素晴らしい内容だった。
人生の半分以上を読書に費やしてきたのではないかと思われるほどの有名な読書家で、彼の読書生活そのものが本になったこともあった。

ひたすらに「知」を追い求めて来た立花さん。
途中で挫折してきたこの本を読み返しつつ、ご冥福をお祈りいたします。

合掌。