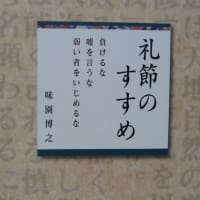第2273号 27.03.19(木)
.
静後万物を見れば、自然に皆春意あり。『近思録』
.
心を静かにして、そののちに天地間の万物を見ると、どこもかしこも春の陽気が立ち込めて、生き生きと発育するすがたが目前に現われてくる。その気分こそ、仁者の心に一致する。(程伊川のことば)299
.
【コメント】またまたテロが発生しました。チュニジアに旅行していた日本人の方が3名ほど犠牲になったそうです。
何故殺し合いをしなければならないのでしょうか。大変悲しいことです。衷心より哀悼の意を表したいと思います。
.
こういった事件は今後も大なり小なり起り得るような気が致します。出来れば危険が予想されるところへは行かない方が賢明ではないでしょうか。
.
このブログで菅原兵治著『農士道』をご紹介していますが、「農家では金をかけずに楽しむ得る風流な趣が味わえる」とありますが、多くは急ぎ過ぎているような気がするのですが、如何でしょう。
.
先般は、ある国家権力者が「核」の準備をさせていたというようなことが報じられましたが、やがて現実となることがありうるかもしれません。だからお互いを理解すべく努力し菅原兵治先生が提唱する生き方が風情があるような気がするのですが。
.
折角この世に生を得たのですから、人生の真の喜びを味わってもらいたいため、私は子どもたちに『南洲翁遺訓』を教えているのです。
-----------------
『大学味講』(第110回)
.
味 講
.
(一) 康誥に、周の武王が弟の康叔を衛の国の諸侯として封ずる時に、これに対して与えた書に、「先王文王は、克くつとめて徳を明らかにした」---だから汝もよく徳を磨いて、不明にならないようにせよ---というのであります。
.
(二) 次に、さかのぼって前朝の殷の歴史にこれを求め、書経の太甲篇から引用しているのであります。それは湯王の没後、嗣王太甲が即位した時に、名相伊尹がこれを求めた書の最初にある「先王はこの天の明命を顧み----」という言葉を引用しているのであります。
この太甲は、湯王の嫡長孫であるが、最初は身が修まらなかったので伊尹がこれを戒めたのであるが、「先王湯王は、天命を受けて、前朝夏の暴君桀王を伐って天子の位についたのであるが、常に天より授かった明らかな命(即ち天命)を顧みて、一刻といえども、それに反することのないようにと、よくつとめられました。しかるにもしあなたが、それを忘れて怠るようなことがあれば、前朝の夏のような運命に陥るでありましょうから、戒めなければなりません、というのであります。
-------------------
『論語』(第210)
.
子、匡に畏す。曰はく、文王既に没したれども、文茲に在らずや。天の将に斯の文を喪ぼさんとするや、後死の者斯の文に与るを得ず。天の未だ斯の文を喪ぼさざるや、匡人其れ予を如何せん。
.
孔子が匡で大難にあって殺されそうになった時、孔子は落ちつきはらって次のように言った。聖人の周の文王によって盛大を極めたが、その文王はもう既に亡くなってしまっている。文王の亡き後の文明の道の伝統は、このわたしの身に伝わっていないであろうか。
もしも、天の神がこの文明の伝統を滅亡させてしまうつもりなら、文王の後に生れたこのわたしは、文王の作った文明の道を学び得ることはできなかったであろう。
しかし幸いにも、わたしは文王の教えを学び、その道を体得している。もし天の神が、まだこの文明の伝統をほろぼさないつもりならば、文明の修得者であるこのわたしは、きっと天の神がお守りくださるだろう。天の加護のあるこの私を、匡人如きものが一体どうしようとするのか。断じて指一本わが身にふれることはできまい。
--------------
百人一首
.
御垣守 衛士の焚く火の 夜は燃え
昼は消えつつ 物をこそ思へ 【大中臣能宣朝臣】49
.
静後万物を見れば、自然に皆春意あり。『近思録』
.
心を静かにして、そののちに天地間の万物を見ると、どこもかしこも春の陽気が立ち込めて、生き生きと発育するすがたが目前に現われてくる。その気分こそ、仁者の心に一致する。(程伊川のことば)299
.
【コメント】またまたテロが発生しました。チュニジアに旅行していた日本人の方が3名ほど犠牲になったそうです。
何故殺し合いをしなければならないのでしょうか。大変悲しいことです。衷心より哀悼の意を表したいと思います。
.
こういった事件は今後も大なり小なり起り得るような気が致します。出来れば危険が予想されるところへは行かない方が賢明ではないでしょうか。
.
このブログで菅原兵治著『農士道』をご紹介していますが、「農家では金をかけずに楽しむ得る風流な趣が味わえる」とありますが、多くは急ぎ過ぎているような気がするのですが、如何でしょう。
.
先般は、ある国家権力者が「核」の準備をさせていたというようなことが報じられましたが、やがて現実となることがありうるかもしれません。だからお互いを理解すべく努力し菅原兵治先生が提唱する生き方が風情があるような気がするのですが。
.
折角この世に生を得たのですから、人生の真の喜びを味わってもらいたいため、私は子どもたちに『南洲翁遺訓』を教えているのです。
-----------------
『大学味講』(第110回)
.
味 講
.
(一) 康誥に、周の武王が弟の康叔を衛の国の諸侯として封ずる時に、これに対して与えた書に、「先王文王は、克くつとめて徳を明らかにした」---だから汝もよく徳を磨いて、不明にならないようにせよ---というのであります。
.
(二) 次に、さかのぼって前朝の殷の歴史にこれを求め、書経の太甲篇から引用しているのであります。それは湯王の没後、嗣王太甲が即位した時に、名相伊尹がこれを求めた書の最初にある「先王はこの天の明命を顧み----」という言葉を引用しているのであります。
この太甲は、湯王の嫡長孫であるが、最初は身が修まらなかったので伊尹がこれを戒めたのであるが、「先王湯王は、天命を受けて、前朝夏の暴君桀王を伐って天子の位についたのであるが、常に天より授かった明らかな命(即ち天命)を顧みて、一刻といえども、それに反することのないようにと、よくつとめられました。しかるにもしあなたが、それを忘れて怠るようなことがあれば、前朝の夏のような運命に陥るでありましょうから、戒めなければなりません、というのであります。
-------------------
『論語』(第210)
.
子、匡に畏す。曰はく、文王既に没したれども、文茲に在らずや。天の将に斯の文を喪ぼさんとするや、後死の者斯の文に与るを得ず。天の未だ斯の文を喪ぼさざるや、匡人其れ予を如何せん。
.
孔子が匡で大難にあって殺されそうになった時、孔子は落ちつきはらって次のように言った。聖人の周の文王によって盛大を極めたが、その文王はもう既に亡くなってしまっている。文王の亡き後の文明の道の伝統は、このわたしの身に伝わっていないであろうか。
もしも、天の神がこの文明の伝統を滅亡させてしまうつもりなら、文王の後に生れたこのわたしは、文王の作った文明の道を学び得ることはできなかったであろう。
しかし幸いにも、わたしは文王の教えを学び、その道を体得している。もし天の神が、まだこの文明の伝統をほろぼさないつもりならば、文明の修得者であるこのわたしは、きっと天の神がお守りくださるだろう。天の加護のあるこの私を、匡人如きものが一体どうしようとするのか。断じて指一本わが身にふれることはできまい。
--------------
百人一首
.
御垣守 衛士の焚く火の 夜は燃え
昼は消えつつ 物をこそ思へ 【大中臣能宣朝臣】49