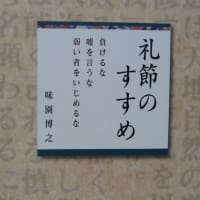第2529号 27.11..30(月)
.
東隅已に逝けども、桑楡(そうゆ)晩(おそ)きに非ず。『古文眞宝』
.
少年の日はすでに過ぎ去ったが、老年にはまだ時間がある。これからでも遅くない。(王勃「縢王閣序」555)
.
先般、地さん(当時105歳)の心意気をご紹介しましたが、私は100歳まで26年ございます。生死は天のしからしむる所だと思ってはいますが、やりたいことは、荘内南洲会様にある文献のご紹介でございます。これからでも遅くはないという心境で臨みたいものです。
.
20年位前読んだ『農士道』は難解を究めましたが、現在ブログでご紹介しながら、こんな素晴らしい本であったかとワクワクしながら、読んでいます。
.
昨日ご紹介した中に、
.
〈すめらみくにのもののふは------黒田藩の俊傑加藤司書が、いみじくも唱破したこの今様こそは、日本武士の荘厳たぐひなき「仕」の精神を明示せるもの、苟も日本農士として、日本国土に奉仕せんとする者に、亦此の至誠を以て仕ふる處がなければならぬ。祖神の霊の宿ります瑞穂國の大地に打込む一鍬一鍬に籠むる力! そは決して一日労働すれば何十銭の労銀を獲得する為のみの故に働くのだといふ様な、労働商品的な努力とは賽壤(さいじょう)天地の差ある聖なる勤労である。----「仕事」である。是れ實に日本精神の職業的顕現にして、「仕事する」眞精神は實に此処に在らねばならぬのである。〉
.
これを書いて、小・中学校の頃、母につれられて畑に行き、鍬を握って畑に打込んだことが回想されます。菅原先生みたいに、学術的に私たち双子に檄を飛ばした分けではありませんでしたが、大体似たようなことをいったという記憶がごさいます。そういった意味では、現今の超スピードの社会変化は考え物だと私は思っています。
.
人間の真の幸せは、テレビコマーシャルがいう、見てくれと、おいしいものを食べることだけではないと思います。大いに働いて、一風呂浴びて漢籍を繙くところにこそあるのではないでしょうか。少なくとも私はそのようにしているつもりです。だから元気なのです。今の所は。
--------------
『臥牛菅恒秀』(第67回)
.
当時、水戸から、あるいは関西から江戸に潜入した浪士群はおびただしいものであったが、少数の荘内藩の警備隊では江戸の秩序を守りぬいたのは、松平、菅の優れた統率指揮によることはいうまでもないが、それと同時に江戸市民の積極的な協力によることも多かった。それは荘内藩の警備隊の行動がきわめて厳正であったことや、同じ暴行武士を取締るにしても、破廉恥の行動のない者は、あくまでも武士の面目を重んじて取扱ったが、破廉恥な行為があれば何人でも容赦なく取扱い、その処分の寛厳が、身分の尊卑を問わないことに、江戸ッ子は大いに共感したからであった。『ウワバミよりもカタバミがおそろしい』と無頼の徒は荘内藩を恐れはばかり、江戸ッ子は『江戸の団十郎、荘内の権十郎』とほめたたえ、松平権十郎の錦絵が売り出されたほどであった。
※カタバミ。荘内酒井氏の紋章。
※※団十郎。歌舞伎の名優市川団十郎。
-------------------
『論語』(第460)
.
柳下恵士師となり、三たびしりぞけらる。人曰はく、「子未だ以て去る可からざるか。」曰はく、「道を直うして人に事へば、焉に往いてか三たびしりぞけられざらん。道を枉げて人に事へば、何ぞ必ずしも父母の邦を去らん。」
.
柳下恵が裁判官になって、三度免職された。そこである人が『こんなにしばしば退けられるのだから、もう大抵にして此國を去り、他国へ行って身を立てたがよさそうなものではないですか。』と言った。
すると柳下恵が言うには、『私がやめられるのは、正道を守って殿様や大夫に迎合した御奉公をしないからです。此の調子では今の世の中にどこの國へ行ったって三度や四度免職されないでしょうか。もし正道をまげて御奉公するくらいならば、何を好んで父母の國たる此國を立ちのきましょうや。ここでそういう御奉公を致します。ともかくも私としては正しきを行ひさえすればよいので、免職されるか否かは私の知ったことではありません。』
.
農士道の訓戒といい、論語の訓戒といい、考えさせられる問題だと思います。最近の裁判を拝見し、首を傾げることがあるのは私だけでしょうか。その国にはその国の、天が与えた使命、生き方があると思うのです。農士道が教える「ひの本」精神でなければならないと考えますが、私が間違っているでしょうか。
-------------
『農士道』(第344回)
.
今之を農業的に更に深く考察するに、農業といふ仕事を「本」の原理と末の原理の両面より見れば如何になるか。一応之を究むる必要がある。前述の通り「ひの末」原理はすべてものを分裂的、対立的に見る處から、農業上に於ても、「人間」と「土地」とを亦対立的に分裂して見て、「人間」が「土地」を征服して、これより成るべく多くの利益を獲得し----極限すれば搾取せんと考える様になる。之に対して「本」の原理に立って考ふれば、すべてものを総合的大和的に見、随って「他」と対立せる「我」を主張して我執排他に出づることを戒むるが故に、「人間」と「土地」とを対立的に考ふる事をせず、「人間」が「土地」に没我奉仕して----厳密に謂へば、佛家の、佛家の所謂「入我我入」の教の如く、人間が土地の中に没我し、土地が亦人間の中に没我する一体大和の境地に至って至誠勤労するといふ事になる。
-------------
.
東隅已に逝けども、桑楡(そうゆ)晩(おそ)きに非ず。『古文眞宝』
.
少年の日はすでに過ぎ去ったが、老年にはまだ時間がある。これからでも遅くない。(王勃「縢王閣序」555)
.
先般、地さん(当時105歳)の心意気をご紹介しましたが、私は100歳まで26年ございます。生死は天のしからしむる所だと思ってはいますが、やりたいことは、荘内南洲会様にある文献のご紹介でございます。これからでも遅くはないという心境で臨みたいものです。
.
20年位前読んだ『農士道』は難解を究めましたが、現在ブログでご紹介しながら、こんな素晴らしい本であったかとワクワクしながら、読んでいます。
.
昨日ご紹介した中に、
.
〈すめらみくにのもののふは------黒田藩の俊傑加藤司書が、いみじくも唱破したこの今様こそは、日本武士の荘厳たぐひなき「仕」の精神を明示せるもの、苟も日本農士として、日本国土に奉仕せんとする者に、亦此の至誠を以て仕ふる處がなければならぬ。祖神の霊の宿ります瑞穂國の大地に打込む一鍬一鍬に籠むる力! そは決して一日労働すれば何十銭の労銀を獲得する為のみの故に働くのだといふ様な、労働商品的な努力とは賽壤(さいじょう)天地の差ある聖なる勤労である。----「仕事」である。是れ實に日本精神の職業的顕現にして、「仕事する」眞精神は實に此処に在らねばならぬのである。〉
.
これを書いて、小・中学校の頃、母につれられて畑に行き、鍬を握って畑に打込んだことが回想されます。菅原先生みたいに、学術的に私たち双子に檄を飛ばした分けではありませんでしたが、大体似たようなことをいったという記憶がごさいます。そういった意味では、現今の超スピードの社会変化は考え物だと私は思っています。
.
人間の真の幸せは、テレビコマーシャルがいう、見てくれと、おいしいものを食べることだけではないと思います。大いに働いて、一風呂浴びて漢籍を繙くところにこそあるのではないでしょうか。少なくとも私はそのようにしているつもりです。だから元気なのです。今の所は。
--------------
『臥牛菅恒秀』(第67回)
.
当時、水戸から、あるいは関西から江戸に潜入した浪士群はおびただしいものであったが、少数の荘内藩の警備隊では江戸の秩序を守りぬいたのは、松平、菅の優れた統率指揮によることはいうまでもないが、それと同時に江戸市民の積極的な協力によることも多かった。それは荘内藩の警備隊の行動がきわめて厳正であったことや、同じ暴行武士を取締るにしても、破廉恥の行動のない者は、あくまでも武士の面目を重んじて取扱ったが、破廉恥な行為があれば何人でも容赦なく取扱い、その処分の寛厳が、身分の尊卑を問わないことに、江戸ッ子は大いに共感したからであった。『ウワバミよりもカタバミがおそろしい』と無頼の徒は荘内藩を恐れはばかり、江戸ッ子は『江戸の団十郎、荘内の権十郎』とほめたたえ、松平権十郎の錦絵が売り出されたほどであった。
※カタバミ。荘内酒井氏の紋章。
※※団十郎。歌舞伎の名優市川団十郎。
-------------------
『論語』(第460)
.
柳下恵士師となり、三たびしりぞけらる。人曰はく、「子未だ以て去る可からざるか。」曰はく、「道を直うして人に事へば、焉に往いてか三たびしりぞけられざらん。道を枉げて人に事へば、何ぞ必ずしも父母の邦を去らん。」
.
柳下恵が裁判官になって、三度免職された。そこである人が『こんなにしばしば退けられるのだから、もう大抵にして此國を去り、他国へ行って身を立てたがよさそうなものではないですか。』と言った。
すると柳下恵が言うには、『私がやめられるのは、正道を守って殿様や大夫に迎合した御奉公をしないからです。此の調子では今の世の中にどこの國へ行ったって三度や四度免職されないでしょうか。もし正道をまげて御奉公するくらいならば、何を好んで父母の國たる此國を立ちのきましょうや。ここでそういう御奉公を致します。ともかくも私としては正しきを行ひさえすればよいので、免職されるか否かは私の知ったことではありません。』
.
農士道の訓戒といい、論語の訓戒といい、考えさせられる問題だと思います。最近の裁判を拝見し、首を傾げることがあるのは私だけでしょうか。その国にはその国の、天が与えた使命、生き方があると思うのです。農士道が教える「ひの本」精神でなければならないと考えますが、私が間違っているでしょうか。
-------------
『農士道』(第344回)
.
今之を農業的に更に深く考察するに、農業といふ仕事を「本」の原理と末の原理の両面より見れば如何になるか。一応之を究むる必要がある。前述の通り「ひの末」原理はすべてものを分裂的、対立的に見る處から、農業上に於ても、「人間」と「土地」とを亦対立的に分裂して見て、「人間」が「土地」を征服して、これより成るべく多くの利益を獲得し----極限すれば搾取せんと考える様になる。之に対して「本」の原理に立って考ふれば、すべてものを総合的大和的に見、随って「他」と対立せる「我」を主張して我執排他に出づることを戒むるが故に、「人間」と「土地」とを対立的に考ふる事をせず、「人間」が「土地」に没我奉仕して----厳密に謂へば、佛家の、佛家の所謂「入我我入」の教の如く、人間が土地の中に没我し、土地が亦人間の中に没我する一体大和の境地に至って至誠勤労するといふ事になる。
-------------