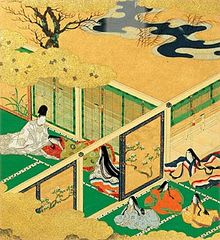高校時代の「地理」の先生が「バイカル湖は地球のヘソ」と言われていたのを今も覚えています。
ロシアのイルクーツクという都市の近くに「ヘソのように」存在する「バイカル湖」は、地球上で一番深度がある湖だそうで、一度は行ってみたい場所のひとつでした。
縁って私自身は1988年以来、中国の内モンゴル自治区へ行く機会が毎年のように出来て、ここ21年間にたぶん23回は内モンゴルへと足を運んでいることになります。
そのきっかけになった「内蒙古地球学校」と称するプロジェクトの準備段階から、なにやら「モンゴル族」が私たち日本人のルーツではないかと思うようになっていました。
例の「蒙古班」と呼ばれる、赤ちゃんのお尻にある「青いしるし」が、いかにも日本人がモンゴル族に近い存在だということがわかります。
ある人から借りた「日本人の源流」と称する松本先生という医学博士の著書を読んでいると、何と「バイカル湖」のほとりに住む「ブリヤートモンゴル族」の人たちの血液型分布が、日本人の血液型分布に一番近いことが分かりました。
それ以来、私自身の内モンゴル行きは、まるで「お盆の里帰り」のようになっていて、毎年夏に「この指たかれ」方式で友人、知人だけでなく、新聞やインターネット告知なども含めて、毎回数人から十数人と行く「モンゴルツアー」が続いたのでした。
今年は、ついに内モンゴルからの留学生で、現在名古屋大学大学院で研究生として頑張っている古くからの友人のB君と、あの憧れでもあった「バイカル湖」周辺のブリヤートモンゴル族に出会うための旅にでることになったのです。
NHKスペシャル「日本人はるかな旅」では、2001年のDNA鑑定の結果、「日本人はバイカル湖畔のブリヤート人との共通点が非常に多い」とされ、朝鮮人、南中国人、台湾人などと共通する特徴を持ったのが各一体だったのに対して、ブリヤート人は30人近くが共通していたという。
あるワークショップ、「縄文人はシベリアからやってきた」でも、縄文人の20数体のミトコンドリアDNAの内、17体がシベリアのバイカル湖周辺に住むブリヤート人と同じだということがわかったとされている。
現在のブリヤート人は、ロシア、モンゴル、中国に住み、ロシア連邦内の人口は43万6千人と少ないが、ブリヤート共和国の全人口の約1/4を占め、特にバイカル湖の東側に住む者が、固有の文化と伝統を重んじた生活を続けているが、西側の住民はロシア人との混血化が進んでいるらしい。
ブリヤート族の住居はモンゴル族の住居「ゲル」にあたる木造のユルト(ロシア語の円形移動式テント)で、ブリヤート共和国の国旗は、モンゴル国旗にも歴代採用されているソヨンボからとった天体を表すシンボルがあり、自治州の旗にも天体や太陽が描かれていて共通している。
「日本人のルーツ」を探る旅が近づいている。
ロシアのイルクーツクという都市の近くに「ヘソのように」存在する「バイカル湖」は、地球上で一番深度がある湖だそうで、一度は行ってみたい場所のひとつでした。
縁って私自身は1988年以来、中国の内モンゴル自治区へ行く機会が毎年のように出来て、ここ21年間にたぶん23回は内モンゴルへと足を運んでいることになります。
そのきっかけになった「内蒙古地球学校」と称するプロジェクトの準備段階から、なにやら「モンゴル族」が私たち日本人のルーツではないかと思うようになっていました。
例の「蒙古班」と呼ばれる、赤ちゃんのお尻にある「青いしるし」が、いかにも日本人がモンゴル族に近い存在だということがわかります。
ある人から借りた「日本人の源流」と称する松本先生という医学博士の著書を読んでいると、何と「バイカル湖」のほとりに住む「ブリヤートモンゴル族」の人たちの血液型分布が、日本人の血液型分布に一番近いことが分かりました。
それ以来、私自身の内モンゴル行きは、まるで「お盆の里帰り」のようになっていて、毎年夏に「この指たかれ」方式で友人、知人だけでなく、新聞やインターネット告知なども含めて、毎回数人から十数人と行く「モンゴルツアー」が続いたのでした。
今年は、ついに内モンゴルからの留学生で、現在名古屋大学大学院で研究生として頑張っている古くからの友人のB君と、あの憧れでもあった「バイカル湖」周辺のブリヤートモンゴル族に出会うための旅にでることになったのです。
NHKスペシャル「日本人はるかな旅」では、2001年のDNA鑑定の結果、「日本人はバイカル湖畔のブリヤート人との共通点が非常に多い」とされ、朝鮮人、南中国人、台湾人などと共通する特徴を持ったのが各一体だったのに対して、ブリヤート人は30人近くが共通していたという。
あるワークショップ、「縄文人はシベリアからやってきた」でも、縄文人の20数体のミトコンドリアDNAの内、17体がシベリアのバイカル湖周辺に住むブリヤート人と同じだということがわかったとされている。
現在のブリヤート人は、ロシア、モンゴル、中国に住み、ロシア連邦内の人口は43万6千人と少ないが、ブリヤート共和国の全人口の約1/4を占め、特にバイカル湖の東側に住む者が、固有の文化と伝統を重んじた生活を続けているが、西側の住民はロシア人との混血化が進んでいるらしい。
ブリヤート族の住居はモンゴル族の住居「ゲル」にあたる木造のユルト(ロシア語の円形移動式テント)で、ブリヤート共和国の国旗は、モンゴル国旗にも歴代採用されているソヨンボからとった天体を表すシンボルがあり、自治州の旗にも天体や太陽が描かれていて共通している。
「日本人のルーツ」を探る旅が近づいている。