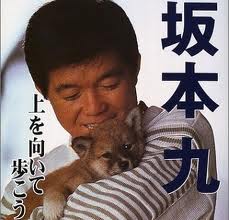通産省時代から経済産業省に31年間勤務し上級官僚だった、古賀茂明氏(57歳)が遂に昨日9月26日に役所からの再三再四の退職勧告を受け入れて退職を余儀なくされ、たった5分足らずの手続きで毎日の様に勤務していた建物を去ったのである。
民主党政権への政権交代が実現した頃から、民主党の主張する政治主導で従来の官僚主導からの脱皮を図って、公務員制度改革や上級官僚たちの政府支援の外郭団体などへの、いわゆる「天下り禁止」などの改革を進めるにあたって、役人である省庁の人間が改革の意思を持たないと出来ないとの大きな壁があったのだが、古賀氏はそうした壁を取っ払うべき手法と熱意を持った官僚のひとりとして、「行政改革」と「公務員制度改革」に率先して働く改革の人であったらしい。
しかし、民主党政権が誕生した2009年秋のすぐ後に、なんと財務省官僚などの強い意向が働いたとされている抵抗があって、当時の仙石官房長官などが彼の経済産業省での仕事ぶりと国会での対応や発言などに反旗を翻して、彼を無任所の経済産業省官房付きという窓際族に左遷してしまったことに事は始まっているのである。
彼が一体何をしたのか?は、多様な憶測や報道がなされているのだが、結局ははっきりとした根拠はわからないままに、省庁の主な官僚たちの圧力や批判、人事に対する提言などから、民主党政権のリーダーシップを握る閣僚たちから、彼は外した方が良いとの対応が生まれて、現内閣に引き継がれたようで、野田新首相も枝野経済産業大臣もほとんど罷免に近い、彼の退職を容認したという過程が見受けられるのであった。
昨日から今日にかけて、各テレビ局は一斉に国家公務員でなくなった当の古賀茂明氏をゲストに招いたり、電話インタビューしたりと大忙しなのだが、まだ何故彼が役所を去らなければならなかったかの明確な因果関係と実際の問題点は説明されているとは言いがたいのである。
つまり、政治家主導、官僚の言いなりにはならないと言って誕生した民主党の政権運営にとって、古賀氏のような公務員制度改革を実践しようとする実力者が邪魔になったという、皮肉な結末と言っても過言ではないような顛末がそこには潜んでいるようで、表向きは「改革」を主張し、マニフェストにも明記していた公務員制度改革をはじめとした一連の旧態依然とした、自民党政権時代からの障壁とでも言うべき壁を壊すどころか、守ることが自分たちにとっても利があるとの見方、身の処し方に終始しているといった実態が見え隠れしている。
こうした改革や変化に抵抗する力とは一体何なんだろうか。
日本社会だけでなく、人間社会においては必ず「変えなければ」と思っている人たちと、「今のままでいいのでは」と思っている人たちがいるものだが、実はその変化や改革をなそうとする時に、その抵抗をするのは必ず「今のままでいいのでは」と思っている人たち、すなわち「改革される」ことによって自分たちの身分の保障や仕事が見えなくなるという不安や恐れを抱く人たちがいるのである。
政治家だけではないが、改革には犠牲や血を流さなければならないとまでは言ってはいるが、実際のところは多くの犠牲者や課題を新たに背負ったり、責任を追求される立場は出来るだけ回避して、平穏無事に過ごしたいという「普通の感覚」が優先されるらしく、政治家とて人間であるゆえに、知らず知らずの内にそういった自己防衛のわ方が勝っていて、少数派の行動や言動を抹殺してでも、多数派の意向を重視してしまうといった蛮行に出てしまうものなのだろう。
今回の古賀氏の更迭に近い事件は、まさに「改革」という名を掲げながら「改革しない」という民主党政権そのものの実態を浮き彫りにしたと言ってもいい事象であり、野田新内閣のスタートに少なくとも改革、前進を期待している国民の多くの失望感が聞こえてきそうな事件となったと言えよう。
経済産業省を退職した古賀茂明氏に対して、テレビマスコミを中心として、「今後の活躍に期待する」といったメッセージが多く語られてはいるが、本来ならば公務員制度や公務員給与および退職金、天下りなどの改革を自らが実態をよく知るものとして改革にメスを入れていくという立場での官僚であっていただきたかったはずなのに、近い将来は次官候補とまで言われていた古賀氏を政府は切ったことで、外国メディアや首脳からも「日本は改革の意思がない」とまで言われているのである。
さて、私たちの日常生活においても、よく似た事象がいっぱい存在しているのではないだろうか。
必ずしも少数派が正しいとは言わないけれど、表向きは民主主義の日本社会だが、多くの場合は「今のままでいいのでは」と言った意見や何も考えない、何も新たな挑戦やリスクは負いたくない人々の多数派のために、多くの場合は「改革」や「変える」ことすら難しいといったケースや場面が多いと思われるのである。
ましてや、改革に熱心な人や言動を切るといった手段で、その場を取り繕ったとしても、いずれその実態はよけいに悪くなって、もっと大きな犠牲や血を流さなければならないといった大苦境がやってくることは間違いないのではないだろうか。
一番難しいと思うのは、組織の存続を優先して、一人の職員や官僚の意見や身分は簡単に切ってしまうことができるといった、目に見得ない風潮、習慣、伝統などと言われる慣例ではないだろうか。
冷静沈着に考えて、「この国を少しでも良くする」という目標に向かって行動する人、考える人たちが増えなければ「この国は変わらない」という絶望がそこにはあるようである。
民主党政権への政権交代が実現した頃から、民主党の主張する政治主導で従来の官僚主導からの脱皮を図って、公務員制度改革や上級官僚たちの政府支援の外郭団体などへの、いわゆる「天下り禁止」などの改革を進めるにあたって、役人である省庁の人間が改革の意思を持たないと出来ないとの大きな壁があったのだが、古賀氏はそうした壁を取っ払うべき手法と熱意を持った官僚のひとりとして、「行政改革」と「公務員制度改革」に率先して働く改革の人であったらしい。
しかし、民主党政権が誕生した2009年秋のすぐ後に、なんと財務省官僚などの強い意向が働いたとされている抵抗があって、当時の仙石官房長官などが彼の経済産業省での仕事ぶりと国会での対応や発言などに反旗を翻して、彼を無任所の経済産業省官房付きという窓際族に左遷してしまったことに事は始まっているのである。
彼が一体何をしたのか?は、多様な憶測や報道がなされているのだが、結局ははっきりとした根拠はわからないままに、省庁の主な官僚たちの圧力や批判、人事に対する提言などから、民主党政権のリーダーシップを握る閣僚たちから、彼は外した方が良いとの対応が生まれて、現内閣に引き継がれたようで、野田新首相も枝野経済産業大臣もほとんど罷免に近い、彼の退職を容認したという過程が見受けられるのであった。
昨日から今日にかけて、各テレビ局は一斉に国家公務員でなくなった当の古賀茂明氏をゲストに招いたり、電話インタビューしたりと大忙しなのだが、まだ何故彼が役所を去らなければならなかったかの明確な因果関係と実際の問題点は説明されているとは言いがたいのである。
つまり、政治家主導、官僚の言いなりにはならないと言って誕生した民主党の政権運営にとって、古賀氏のような公務員制度改革を実践しようとする実力者が邪魔になったという、皮肉な結末と言っても過言ではないような顛末がそこには潜んでいるようで、表向きは「改革」を主張し、マニフェストにも明記していた公務員制度改革をはじめとした一連の旧態依然とした、自民党政権時代からの障壁とでも言うべき壁を壊すどころか、守ることが自分たちにとっても利があるとの見方、身の処し方に終始しているといった実態が見え隠れしている。
こうした改革や変化に抵抗する力とは一体何なんだろうか。
日本社会だけでなく、人間社会においては必ず「変えなければ」と思っている人たちと、「今のままでいいのでは」と思っている人たちがいるものだが、実はその変化や改革をなそうとする時に、その抵抗をするのは必ず「今のままでいいのでは」と思っている人たち、すなわち「改革される」ことによって自分たちの身分の保障や仕事が見えなくなるという不安や恐れを抱く人たちがいるのである。
政治家だけではないが、改革には犠牲や血を流さなければならないとまでは言ってはいるが、実際のところは多くの犠牲者や課題を新たに背負ったり、責任を追求される立場は出来るだけ回避して、平穏無事に過ごしたいという「普通の感覚」が優先されるらしく、政治家とて人間であるゆえに、知らず知らずの内にそういった自己防衛のわ方が勝っていて、少数派の行動や言動を抹殺してでも、多数派の意向を重視してしまうといった蛮行に出てしまうものなのだろう。
今回の古賀氏の更迭に近い事件は、まさに「改革」という名を掲げながら「改革しない」という民主党政権そのものの実態を浮き彫りにしたと言ってもいい事象であり、野田新内閣のスタートに少なくとも改革、前進を期待している国民の多くの失望感が聞こえてきそうな事件となったと言えよう。
経済産業省を退職した古賀茂明氏に対して、テレビマスコミを中心として、「今後の活躍に期待する」といったメッセージが多く語られてはいるが、本来ならば公務員制度や公務員給与および退職金、天下りなどの改革を自らが実態をよく知るものとして改革にメスを入れていくという立場での官僚であっていただきたかったはずなのに、近い将来は次官候補とまで言われていた古賀氏を政府は切ったことで、外国メディアや首脳からも「日本は改革の意思がない」とまで言われているのである。
さて、私たちの日常生活においても、よく似た事象がいっぱい存在しているのではないだろうか。
必ずしも少数派が正しいとは言わないけれど、表向きは民主主義の日本社会だが、多くの場合は「今のままでいいのでは」と言った意見や何も考えない、何も新たな挑戦やリスクは負いたくない人々の多数派のために、多くの場合は「改革」や「変える」ことすら難しいといったケースや場面が多いと思われるのである。
ましてや、改革に熱心な人や言動を切るといった手段で、その場を取り繕ったとしても、いずれその実態はよけいに悪くなって、もっと大きな犠牲や血を流さなければならないといった大苦境がやってくることは間違いないのではないだろうか。
一番難しいと思うのは、組織の存続を優先して、一人の職員や官僚の意見や身分は簡単に切ってしまうことができるといった、目に見得ない風潮、習慣、伝統などと言われる慣例ではないだろうか。
冷静沈着に考えて、「この国を少しでも良くする」という目標に向かって行動する人、考える人たちが増えなければ「この国は変わらない」という絶望がそこにはあるようである。