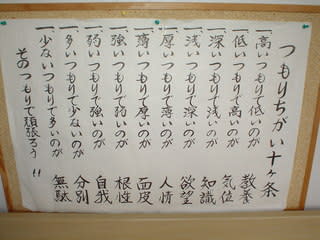藤沢から鎌倉までは、あの有名な江ノ電こと「江ノ島電鉄」が、非常にいいロケーションの中を昔ながらに走っていて、視察に訪れる鎌倉まで約三十分で行けるというのに、議会公務のため少し遠回りは許されないと事務局の許可がでなくてJRで行くという。
いくら公務とは言え特別な費用がかかるわけではないので、湘南の海沿いと町並みを走る、情緒ある路面電車のような風情のある私鉄で行こうと、再度事務職員と共に提案してみたが却下されてしまった。
そこで私自身は早起きして朝食前に、せっかくの江ノ電に私的に乗車しようと考えたのである。
早朝6時前に起きて、身支度して藤沢駅6:25発の鎌倉行きに稲村ヶ崎までの往復切符を買って乗車したのである。
愛用のデジタルカメラを持参して、江ノ電の写真を何枚か撮影してブログに掲載しようと思っているので、乞うご期待あれ!である。
しかし自宅のパソコン入力環境と全く違うホテルのパソコンからの入力で原稿は送れるが写真の掲載が不可能なため、帰宅してからの写真の掲載となる。
行政視察の機会は年に2、3度あって、他市や他の地方、地域の自然や町並み、ロケーションを見て行政課題を感じることも多くあるので、観光旅行のような時間はないが、移動の選択肢としてのアクセスを選ぶことなどはあってもいいのではないかと私は思うのである。
人は、どんな職業、業務であっても、仕事の現場だけではなく、その移動経路や移動時間に感じる感性がきっかけとなる仕事への刺激などが、結構あるものではないだろうか。
私は公人としての公務の途中に、違う地方、地域の町並み、自然、人の行き来などを見て、多くの示唆や発想を得ることがあるのである。
ぜひ杓子定規に公務の遂行だけを考えるのではなく、余裕のある移動時間や移動の経路で、議会議員としても私人としても感じる何かが大変大切なのではないでしょうか。
旅先のホテルでの深夜のパソコン入力によるブログ原稿の送信なので、十分まとまった内容になっていないが、ご容赦いただきたいと思います。
それでは、またガリバー旅行記としてのコメントをお届けする時に、今回の議員研修の成果としての報告をさせていただきたいと思っています。おやすみなさい。
さて、翌日自宅に帰って早速、江ノ電の写真をと思ったのだが、デジカメのバッテリーが切れたために、藤沢から稲村ヶ崎へ往復で、早朝の江ノ電に乗車したのに、藤沢に戻ってから携帯の写真を撮ったにすぎなかった。
これは失態と一時は思ったが、すぐに写真ではなく、車内、車外の様子を、自分の目で見て、感じて、頭に記憶することの大切さを、返って久しぶりに教えてもらった感じで、よーく観察することが出来た。
鎌倉の私立の小学校に通学する児童たちと高校生達の車内での様子や遊び、そして読書の様子など、際立って賢さと現代の子どもたちの気質や流行の一端をも感じることができたのは、江ノ電に往復45分ほど稲村ヶ崎まで往復したお陰であった。
湘南海岸は曇り空で天気は良くなかったため、太平洋の眺望は決して遠くまでは見通せなかったが、涼しい海風を感じることの出来た、旅先での早朝の約一時間であった。
いくら公務とは言え特別な費用がかかるわけではないので、湘南の海沿いと町並みを走る、情緒ある路面電車のような風情のある私鉄で行こうと、再度事務職員と共に提案してみたが却下されてしまった。
そこで私自身は早起きして朝食前に、せっかくの江ノ電に私的に乗車しようと考えたのである。
早朝6時前に起きて、身支度して藤沢駅6:25発の鎌倉行きに稲村ヶ崎までの往復切符を買って乗車したのである。
愛用のデジタルカメラを持参して、江ノ電の写真を何枚か撮影してブログに掲載しようと思っているので、乞うご期待あれ!である。
しかし自宅のパソコン入力環境と全く違うホテルのパソコンからの入力で原稿は送れるが写真の掲載が不可能なため、帰宅してからの写真の掲載となる。
行政視察の機会は年に2、3度あって、他市や他の地方、地域の自然や町並み、ロケーションを見て行政課題を感じることも多くあるので、観光旅行のような時間はないが、移動の選択肢としてのアクセスを選ぶことなどはあってもいいのではないかと私は思うのである。
人は、どんな職業、業務であっても、仕事の現場だけではなく、その移動経路や移動時間に感じる感性がきっかけとなる仕事への刺激などが、結構あるものではないだろうか。
私は公人としての公務の途中に、違う地方、地域の町並み、自然、人の行き来などを見て、多くの示唆や発想を得ることがあるのである。
ぜひ杓子定規に公務の遂行だけを考えるのではなく、余裕のある移動時間や移動の経路で、議会議員としても私人としても感じる何かが大変大切なのではないでしょうか。
旅先のホテルでの深夜のパソコン入力によるブログ原稿の送信なので、十分まとまった内容になっていないが、ご容赦いただきたいと思います。
それでは、またガリバー旅行記としてのコメントをお届けする時に、今回の議員研修の成果としての報告をさせていただきたいと思っています。おやすみなさい。
さて、翌日自宅に帰って早速、江ノ電の写真をと思ったのだが、デジカメのバッテリーが切れたために、藤沢から稲村ヶ崎へ往復で、早朝の江ノ電に乗車したのに、藤沢に戻ってから携帯の写真を撮ったにすぎなかった。
これは失態と一時は思ったが、すぐに写真ではなく、車内、車外の様子を、自分の目で見て、感じて、頭に記憶することの大切さを、返って久しぶりに教えてもらった感じで、よーく観察することが出来た。
鎌倉の私立の小学校に通学する児童たちと高校生達の車内での様子や遊び、そして読書の様子など、際立って賢さと現代の子どもたちの気質や流行の一端をも感じることができたのは、江ノ電に往復45分ほど稲村ヶ崎まで往復したお陰であった。
湘南海岸は曇り空で天気は良くなかったため、太平洋の眺望は決して遠くまでは見通せなかったが、涼しい海風を感じることの出来た、旅先での早朝の約一時間であった。