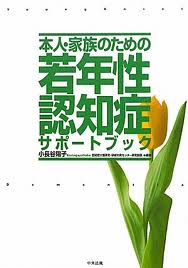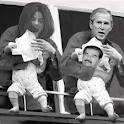三日前に突然、石原慎太郎都知事が記者会見し、任期半ばまだ2年以上を残して都知事を辞任し、石原新党なるものを結成して、再び衆議院選挙に政党条件を満たせば比例区で立候補して、日本の没落を救うために戦うのだと公表したのである。
80歳に先日なったばかりなのだが、どうやら自民党の総裁選挙で息子の石原伸晃当時幹事長が安倍新総裁の再出馬に負けてしまい、野田民主党も安倍自民党もだらしないから、自分が最後のご奉公をすると粋がって第三極の結集を目指して親分になるという、相当思いあがった宣言をしたと感じた。
芥川作家として太陽族などと言われた時代の落とし子であったのだが、石原裕次郎の兄ということもあって絶大なる支持者に支えられて、東京から衆議院議員に当選し、参議院議員とあわせて25年の国会議員表彰を受けて、その国会での演説で国会議員を辞職することを宣し、その後東京都知事を3期12年務めて、昨春に引退かと思われたのに再び「やる」と出馬、当選したのにも関わらず、中途半端に「投げ出す」結果となった。
国会議員としても環境庁長官や運輸大臣という大臣経験はあるが、当時「青嵐会」と称した非常に右翼的な思想を背景にした施策を目指していたし、自民党の中でも特異な存在だったのだが、国会議員、都知事という政治家として権力を行使する立場から、障碍者や中国、韓国などアジア諸国の人々、またホームレスや社会的弱者に対して、とても差別的な言動や行動をとるというおっさんであったと記憶している。
今回の新党結成に向けてのスローガンでも、憲法を米国に押し付けられた憲法と断言し、世界に名だたる平和憲法を全く評価せず、新憲法を制定すると語り、つまり軍隊を持ち戦争の出来る日本、アメリカにでも追従せずに軍事力で対等に交渉できる国にしたいらしいし、原発についても当然必要との見解を示している。
政策面での考え方や個人の人格をとやかく言うつもりはないが、どう見ても現在まで政治家として生きてきた人と言うよりも、自分は芸術家気取りで、自分より偉い者はいないと思っている、やたら上から目線ばかりのお爺さんなのである。
田中真紀子現文部科学大臣に言わせば、間違いなく「老害」の如く語られていたし、平沼赳夫氏を代表とする「立ち上がれ日本」と合流する形で、現職の国会議員5人以上という政党条件をクリアして、次の総選挙にのぞむらしいが、平均年齢はゆうに70歳を超える「超老人政党」の誕生となるのである。
ともかく、記者会見でも苦笑いしながら、「なんでこんな年寄りがやらなければならいないのか」、「もっと若い奴が出て来い!」と言いながら、多くの記者に取り囲まれてのインタビューを楽しんでいる様子であり、橋下「日本維新の会」や渡辺「みんなの党」、また河村名古屋市長の「減税日本」などとの連携、連帯を目指しているらしいが、まったく期待するところはない。
80年の人生で、政治的には晴れ舞台におられたが、新東京銀行の大失敗や東京オリンピック誘致運動の挫折なども含め、東京都知事としての功績もあまりなく、ただ威勢のいい勝手なええとこの坊ちゃんが、間違って直木賞など貰ったものだから、調子に乗ってしまって、ここまで自分が一番偉いと思ってしまう爺さんになってしまった感が否めない方である。
ようやく始まった臨時国会で、野田首相は衆議院本会議での施政方針演説をし、問責決議をした自民党、公明党などの反対で、参議院では演説ができなかったらしいが、施政方針演説などは1度でよく、肝心なのは国民のための政策推進の実質的議論と法案の成立であり、総選挙をめぐる解散要求などの攻防はやめ、国民目線の国会に早く戻して税金泥棒の国会議員と批判されない役割を、ちゃんと果たしてほしいものである。
新党や既成政党とか○○党に期待なんか、とっくに国民の多くはしていません。ましてや老害的政治家の出番はもううんざりです。新党を作ったり、幾つになっても立候補するのは自由ですが、国民、有権者を舐めたらアカンぜよ。
80歳に先日なったばかりなのだが、どうやら自民党の総裁選挙で息子の石原伸晃当時幹事長が安倍新総裁の再出馬に負けてしまい、野田民主党も安倍自民党もだらしないから、自分が最後のご奉公をすると粋がって第三極の結集を目指して親分になるという、相当思いあがった宣言をしたと感じた。
芥川作家として太陽族などと言われた時代の落とし子であったのだが、石原裕次郎の兄ということもあって絶大なる支持者に支えられて、東京から衆議院議員に当選し、参議院議員とあわせて25年の国会議員表彰を受けて、その国会での演説で国会議員を辞職することを宣し、その後東京都知事を3期12年務めて、昨春に引退かと思われたのに再び「やる」と出馬、当選したのにも関わらず、中途半端に「投げ出す」結果となった。

国会議員としても環境庁長官や運輸大臣という大臣経験はあるが、当時「青嵐会」と称した非常に右翼的な思想を背景にした施策を目指していたし、自民党の中でも特異な存在だったのだが、国会議員、都知事という政治家として権力を行使する立場から、障碍者や中国、韓国などアジア諸国の人々、またホームレスや社会的弱者に対して、とても差別的な言動や行動をとるというおっさんであったと記憶している。
今回の新党結成に向けてのスローガンでも、憲法を米国に押し付けられた憲法と断言し、世界に名だたる平和憲法を全く評価せず、新憲法を制定すると語り、つまり軍隊を持ち戦争の出来る日本、アメリカにでも追従せずに軍事力で対等に交渉できる国にしたいらしいし、原発についても当然必要との見解を示している。
政策面での考え方や個人の人格をとやかく言うつもりはないが、どう見ても現在まで政治家として生きてきた人と言うよりも、自分は芸術家気取りで、自分より偉い者はいないと思っている、やたら上から目線ばかりのお爺さんなのである。
田中真紀子現文部科学大臣に言わせば、間違いなく「老害」の如く語られていたし、平沼赳夫氏を代表とする「立ち上がれ日本」と合流する形で、現職の国会議員5人以上という政党条件をクリアして、次の総選挙にのぞむらしいが、平均年齢はゆうに70歳を超える「超老人政党」の誕生となるのである。
ともかく、記者会見でも苦笑いしながら、「なんでこんな年寄りがやらなければならいないのか」、「もっと若い奴が出て来い!」と言いながら、多くの記者に取り囲まれてのインタビューを楽しんでいる様子であり、橋下「日本維新の会」や渡辺「みんなの党」、また河村名古屋市長の「減税日本」などとの連携、連帯を目指しているらしいが、まったく期待するところはない。

80年の人生で、政治的には晴れ舞台におられたが、新東京銀行の大失敗や東京オリンピック誘致運動の挫折なども含め、東京都知事としての功績もあまりなく、ただ威勢のいい勝手なええとこの坊ちゃんが、間違って直木賞など貰ったものだから、調子に乗ってしまって、ここまで自分が一番偉いと思ってしまう爺さんになってしまった感が否めない方である。
ようやく始まった臨時国会で、野田首相は衆議院本会議での施政方針演説をし、問責決議をした自民党、公明党などの反対で、参議院では演説ができなかったらしいが、施政方針演説などは1度でよく、肝心なのは国民のための政策推進の実質的議論と法案の成立であり、総選挙をめぐる解散要求などの攻防はやめ、国民目線の国会に早く戻して税金泥棒の国会議員と批判されない役割を、ちゃんと果たしてほしいものである。
新党や既成政党とか○○党に期待なんか、とっくに国民の多くはしていません。ましてや老害的政治家の出番はもううんざりです。新党を作ったり、幾つになっても立候補するのは自由ですが、国民、有権者を舐めたらアカンぜよ。