
昨年5月、府中市美術館に<東京・ソウル・台北・長春-官展にみる-それぞれの近代美術>という企画展を見に行きました。(→関連過去記事。)
以来にわかに朝鮮・韓国美術づいた私ヌルボ、昨年6月には朴寿根(パク・スグン)の生地・楊口(ヤング)の朴寿根美術館を訪れ、8月にはソウルの美術館巡りの旅をしてきました。
※6月の楊口等への旅行についてはコチラが関連過去記事、といえるかどうか? 続きでちゃんとした記事を書こうと思ったのですが、思っただけで今に至ってます。8月の旅行記録は→コチラの記事参照。
そして今。4月4日(土)~5月8日(金)神奈川県立近代美術館葉山館で<ふたたびの出会い 日韓近代美術家のまなざし―『朝鮮』で描く>展が開催されています。
※公式サイト→a href="http://www.moma.pref.kanagawa.jp/public/HallTop.do?hl=h">コチラ。また→コチラの報道用資料には、本展の第1~5章の内容、関連企画等が15点の画像付きで紹介されています。
・・・ということで、さっそく初日に行ってきました。
横浜からだと少し遠くて、約1時間くらいかな? 前来たのが2010年夏の「浜田知明の世界展」だったからもう5年にもなります。昼前に着きましたが、最寄りのバス停どころか建物自体も憶えてない・・・
 。
。展示室に入って最初に目にとまったのは和田三造「朝鮮総督府壁画画稿」。そして藤島武二「花籠」。どちらも、昨年府中市美術館で見た作品です。著名な日本人画家では、他に土田麦僊・山口蓬春・岡田三郎助等々。藤田嗣治が1912年新婚旅行で朝鮮総督府病院長だった父を訪ねて訪朝したのを機に描いたという「朝鮮風景」という作品もあります。(上記の報道用資料参照。)
また、代表的な朝鮮人画家たちの作品も。高羲東(コ・フィドン)「程子冠をかぶる自画像」、李仁星(イ・インソン)「窓辺」、金重鉉「巫女図」等も府中市美術館で展示されていた作品です。それ以外に、先月ドキュメンタリー映画「ふたつの祖国、ひとつの愛 ~イ・ジュンソプの妻~」で観たばかりの李仲燮(イ・ジュンソプ)「旅だつ家族」や、彼と同様生前は不遇で死後高い評価を受けるようになった上述の朴寿根(パク・スグン)「赤ん坊をおぶった少女」、あるいは李快大(イ・クェデ)「自画像」といった作品も並んでいます。

【図録の表紙は李仲燮(イ・ジュンソプ)「旅だつ家族」。この分厚く内容豊富な図録が2,400円(税込)とはゼッタイお得! 】
上記のように日朝の有名な画家や作品も多い中で、ヌルボがとくに注目したのは第2章<近代「朝鮮」の風景>~第3章<近代人の日常>に数多く展示されている日常の風景や人物を描いた作品です。たとえばヌルボと同じ徳島県人の加藤松林人の作品はその代表例です。
事前学習もなく来ましたが、このあたりに差しかかって昨年の<東京・ソウル・台北・長春-官展にみる-それぞれの近代美術>とは明確に異なったこの展覧会のコンセプトといったものがわかりかけてきました。これらの日常の風景や人物を描いた作品には、作家自身の自然な感性、風土やそこで生活する人々へ親和感といったものが感じられます。そんな<地べたからの目線>で描かれた
それは「官展」といった上からの枠組みの中で制作された作品とは対照的です。
そういえば、タイトルからして美術家のまなざし>と、美術家個人の視点が中心におかれていますね。
※このような美術作品を鑑賞する視点とは関係なく、1910~40年代当時の朝鮮の風俗、自然の風物や都市の景観等を見るだけでも興味深いものがあります。たとえば、南大門の横を牛車が通ったり(金山平三「南大門」(1917))、平壌の大同江で洗濯をしていたり(吉田博「大同門」(1937))、杉浦非水のリトグラフ「京城三越 新館落成」(1929)というのもあります。
上述した本展の企画意図等については、直接携わった方たちの話をその後伺うことができました。
初日に行ったのは、午後に1930年代に文化学院で学んだという98歳(!)の画家・金秉騏(キム・ビョンギ)さんの特別講演会があったからでした。翌5日には四谷三丁目の国際交流基金ビルで関連行事として「複層―日韓近代美術家たちのまなざしが開く新たな地平」と題したシンポジウムが午前10時~午後5時開かれ、これにも参加。
両日ともオープニング・レセプション、交流会にも出席したりしていろいろな方と話をすることができました。連日の盛りだくさんのメニューの上、そもそもレセプションに顔を出すなんてのも初めてのことで緊張したりして、とにかくすごく疲れましたが、それ以上にとても興味深く勉強になる話を聞けた上、いろいろな方と知り合い、話をすることができたのは大収穫でした。その内容については続きに回します。










![韓国内の映画の興行成績 [8月11日(金)~8月13日(日)] ►「コンクリートユートピア」は期待してよさそう! ►日韓の港町のヤクザ文化(?)と「野獣の血」等のこと](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6a/11/92d870b3e7abfcf50b59506f39b0cba6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月28日(金)~7月30日(日)] ►「密輸」に続いて「ザ・ムーン」が公式公開前に10位にランクイン ►<サメのかぞく体操>って知ってますか?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/c5/5e7496d2812629ef25604c3e9779b3f4.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月21日(金)~7月23日(日)] ►期待できそう! リュ・スンワン監督の新作「密輸」 ►最近観たドキュメンタリー「世界のはしっこ、ちいさな教室」は良かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/a0/12b1fedcdd7d44e3b5ae4cdde7c52ed4.jpg)
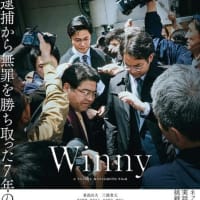
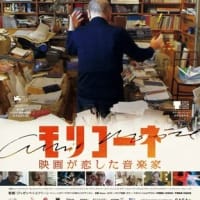
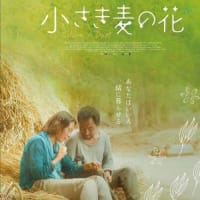
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/97/23df6cbf19458fe4f08e5af9d4969562.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/58/a7/37839be4ca432b6c9dabb103a6fa31b6.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [7月14日(金)~7月16日(日)] ►韓国でも「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE」の勢いがスゴイ! ►ハンガリーのアニメ「ピノキオ」ねー・・・](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/71/b9/cb7ffe184f0640f4c629be5ba1de9724.jpg)
![韓国内の映画の興行成績 [6月30日(金)~7月2日(日)] ►韓国映画「君の結婚式」の中国版リメイク、韓国で上映! ►ウェス・アンダーソン監督の新作「アステロイド・シティ」、期待していいかな?](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/00/81/b0850e17282a4b2ef3dd13867cfce7de.jpg)
山口蓬春のスケッチの線の確かさにほれぼれしましたが、安藤義茂の一連のスケッチに感動しました。
正にヌルボさんがおっしゃるー「これらの日常の風景や人物を描いた作品には、作家自身の自然な感性、風土やそこで生活する人々へ親和感といったものが感じられます。そんな<地べたからの目線>で描かれた」ーその地で生活する人々への温かな共感を感じました。
そして色々な課題を飛び越えるアートの持つ力のすごさに今日は改めて気付かされました。
館長トークがあったのですが日本の朝鮮に対するオリエンタリズムや民族を超えた芸術家同士の感応。学芸員の李さんからも話があり本当に行ってよかったです。李さんがおっしゃるように韓日どちらの絵かにわかに断ずる事が出来なくてこれが本当の姿なのだと思いました。韓国でもこの展覧会が開催される事を願います。
柳の言う朝鮮の悲哀という見方だけでは一面的なのだなと実感しました。
これからじっくり、楽しみながら図録を見ます。
また歴史博物館の「大京城府大観」 これ今度ソウルに行ったら絶対に買い求めてきます。
浅川伯教の住んだ所など探る際の参考になりそうです。漢字表記も有難いです。
何時も有難うございます。
府中の官展の展覧会逃したのはざんねんでした。これから過去記事拝読いたします。
4日は、作者が「日本人 「朝鮮」在住者」=緑 のように色によって分けられていることにも気づきませんでした。また岡本一平「朝鮮漫画行」(1928)、細木原青起「朝鮮漫画(1909)のようなおもしろそうな本にも目がとまりました。前回には行かなかった図書室にも行って関連図書を数冊ザッと見てきました。 ※「別冊太陽 韓国朝鮮の絵画」とか、吉川凪「京城のダダ、東京のダダ」等。金惠信「韓国近代美術研究 植民地期「朝鮮美術展覧会」にみる異文化支配と文化表象」と金英那「韓国近代美術の百年」は横浜市立図書館にあるので以前目を通しました。
李美那さんのキッチリした話し方とその内容には友人も感じ入ってました。 あっと驚く紹介記事は →コチラ
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=76778&thread=01r04
・・・なのですが、もしかしてご存知でしたか?
美術館を出てから近くにある葉山しおさい公園で昭和天皇が採集したウミウシ等を見て帰ってきました。
おふたりづれだったのですね。来ていらっしゃるとは考えもせず、作品と解説に集中していたのではっきり覚えていないです。年のせいかもしれませんが。
李美那さんのお父さん有名な方だったんですね。ご紹介頂き有難うございます。写真落ち着いて見えますが実物はもっともっと若い!
しかも韓文でお話まであったとはこちらも行けずに残念でした。
絵を見て作者名を見て、その反対もあったのですが繰り返す中で自分も民族の境界を容易に超えていた事に(ちと大袈裟ですか)感激しました。
あの後、閉館まで私も図書室で粘り、府中の図録を見ました。参考本の吉川凪さんは読んでいます。
植民地時代の絵画作品を集めている「黄正洙」さんはどんな方なんでしょうか。
一度韓国でコレクションを見てみたいものです。
それから楊口のミュジアムにも行ってみたいです。あの時の記事覚えていましたがお酒の事が印象に残り(笑) ミュジアムは見事記憶に残っていませんでした。
ブログアップ楽しみにしています。