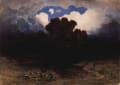ロシアの小説を読んでいた相棒が、そういう記述があると言って、訊いてきた。
「チマルさん、セロフって画家、知ってる?」
知ってるよ、有名だよ、セロフ。特に、桃を持った女の子の絵がさ。
「そう、それそれ!」
その箇所を読んでもらったけど、う~む、やっぱり小説家の眼というのは、対象をどこまでも深く掘り下げるもんだな。
その絵、タイトルが桃で、女の子も実際桃を持ってるんだけど、この桃が全然、桃色じゃないんだよね。その代わりに女の子の服が桃色なんだよね。で、女の子の頬っぺたが、桃毛まで生えた熟れた桃みたいな頬っぺたなんだよねえ。……
ヴァレンティン・セロフ(Valentin Serov)。両親はともに作曲家。が、父親は早くに死んでしまい、未亡人はちっちゃなセロフ坊やを連れてヨーロッパへ移る。
で、パリでは同地に遊学中の、かの有名なロシア人画家レーピンと交流。レーピンはセロフ少年を大層可愛がったとか。
まもなく母子は、鉄道王マモントフに招かれて、アブラムツェヴォの芸術家村に移る。そこで再びレーピンから、否、レーピンと言わず多くの最良の画家たちから、セロフは絵を学ぶ機会を得る。
こんな幸運に恵まれたら、画才は伸び放題に伸びるしかない。セロフ少年は歳上画家らと競うなか、モデルの外観を素早く、確実に捉える早熟のデッサン力を身に着ける。ああ、のどかで楽しいアブラムツェヴォの生活よ!
アカデミーに入学するが、パリへの旅行でフランス印象派を知ったセロフは、陽光が斑な光と影のハーモニーとなって画面に揺れる、色明るく鮮やかな、それでいてナチュラルな肖像画を描くようになる。
上記の「桃と少女」の絵はその最初の作品で、ロシア印象派の始まりと言われる。マモントフの娘(多分)を描いたもの。
フランス印象派など何のことやら、という当時のロシア画壇では、旧来からのリアリズム手法の画家たちが、あの斑点では画廊が梅毒に感染してしまう、とかなんとか、ブーブー文句を言ったとか。
でもまあ、この感覚的な、新しいスタイルの人物画で、セロフは当時最も成功した肖像画家となった。著名な知識人、文化人たちを数多く描いている。
画風の冒険はあまりなかったけれど、移動派や芸術世界派にも参加し、1905年、血の日曜日事件の際には、抗議の意味でアカデミーを脱退、民主的信条を表明した。立派、立派!
画像は、セロフ「桃を持った少女」。
ヴァレンティン・セロフ(Valentin Serov, 1865-1911, Russian)
他、左から、
「子供たち」
「村」
「十月、ドモトカノヴォ」
「フィンランドの農場」
「バレエ・シルフィールドを踊るアンナ・パブロワ」
Related Entries :
コンスタンティン・コロヴィン
移動派
アブラムツェヴォ派
芸術世界派
Bear's Paw -絵画うんぬん-