世界をスケッチ旅行してまわりたい絵描きの卵の備忘録と雑記
魔法の絨毯 -美術館めぐりとスケッチ旅行-
光の詩人




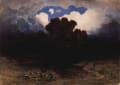

旧ロシア諸国を旅行して以来、TVロシア語講座なんかを観ている相棒、講師の恭子先生が、極東美術館にあるクインジの絵を紹介しているのを知って、
「チマルさん、クインジって画家、知ってる?」と訊いてきた。
知ってるよ、結構有名だよ。
アルヒープ・クインジ(Arkhip Kuindzhi)。移動派の風景画家なんだけれど、ちょっと変わってるんだよね。光の描写が独特で、光を帯びた風景が両腕を広げてこちらを抱きすくめようと迫ってくるような、幻惑的にロマンチックな情感があるんだよねえ。移動派の幅を広げた画家の一人だと思うな。
生まれは黒海北方の内湾アゾフ海のほとりの町。貧しい靴屋の家に生まれ、おまけに両親とも幼少時に亡くしたクインジは、子供の頃から転々として働いた。
なので正規の美術教育は受けず、もっぱら独学で絵を学んだというのだが、それでもアカデミーの授業に出入りし、海景画家アイワゾフスキーの教室で修行している。海はクインジの故郷であり、原風景(多分)。
この間、アカデミー内で結成された移動派にも参加。アカデミーを離れるとフリーの画家となり、ヨーロッパを周遊して各国美術館の巨匠に学ぶ。
そんなふうにして培われたクインジの絵だけれど、その画風は移動派のものとも、古典的巨匠らのものとも随分と異なる。
基本、写実なのだが、濃密な色彩と鮮鋭な明暗が独特の光の印象を醸している。絵が光を放っているようで、奇妙と言えば奇妙なのだが、そこは画家の処理が巧みなのだろう、その奇妙さは却って幻想的で、ロマン派チックな静謐と神秘の叙情へと高められている。簡素な風景に、画家が与えた永遠のイリュージョン。
この光と大気の独特の効果を駆使した画風は画壇の評判となり、彼のギリシャ系の名前の響きのエキゾチックさも加わって、驚嘆の的となって大衆の人気を得たという。誰によるのか、クインジの呼称は「光の詩人」。
私の感想としては、クインジは「光の詩人」というよりは「光の魔法使い」だな。それも、錬金術師のような類の魔法使い。
が、同僚画家たちだけは、クインジの錯覚を催す色彩に騙された気になったらしい。最も欲しい側からは評価を得られず、クインジはオープンに作品展示する場をすべて放り出してしまう。あるいは、将来才能が衰えてゆくのを見せたくない、とその最高潮で引っ込んだともいう。以後は、ごく親しい友人にしか絵を観せなかった。
後年アカデミーで教鞭を取り、ニコライ・レーリヒ(Nicholas Roerich)、コンスタンティン・ボガエフスキー(Konstantin Bogaevsky)、アルカージイ・ルィロフ(Arkady Rylov)、ウィリヘルムス・プルヴィティス(Vilhelms Purvitis)ら、優秀な弟子たちの才能を育んだが、アカデミーに抗議した生徒たちを支持して首になった。
が、その後も個人的に弟子たちを教え続け、彼らのヨーロッパ周遊費まで拠出。当のアカデミーにも、その利子を若い画家たちのために、と多額の贈与をし、死の前年にはクインジ美術協会を設立、絵と財産を寄贈した。
光の詩人は、ちゃんと金の使い方も知っていた。立派、立派!
画像は、クインジ「冬の森の月光の斑点」。
アルヒープ・クインジ(Arkhip Kuindzhi, 1842-1910, Russian)
他、左から、
「夜」
「北部」
「ステップ」
「破波と雲」
「エルブルス山」
Related Entries :
イワン・クラムスコイ
イワン・シシキン
ワシーリイ・スリコフ
ヴィクトル・ヴァスネツォフ
イサーク・レヴィタン
アレクセイ・サヴラソフ
ミハイル・ネステロフ
アルカージイ・ルィロフ
ニコライ・レーリフ
ウィリヘルムス・プルヴィティス
移動派
Bear's Paw -絵画うんぬん-
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 古き貴族の美... | 青薔薇は散らず » |






