かなり前から中東情勢を学んできて、最も驚いてきたことを改めて書いてみる。こういう国が存在して、しかもここがイスラム過激派支援を含めてイスラム原理主義運動に最も大きい影響力を行使してきたとすれば、イスラムテロは無くならぬわけだと、改めて考え込んできた次第だ。世界第2位の原油埋蔵量を誇る王制国家サウジアラビアのことである。以下の抜粋は、『「対テロ戦争」とイスラム世界』(板垣雄三編 岩波新書)から。この抜粋をみただけでも、現在の対テロ戦争に至るまでの重要な歴史的背景の一つが理解できると感じた所である。
『 閉鎖空間サウジアラビア
サウジアラビアは総人口約二〇〇〇万人の約三分の一は、外国人である。・・・・
サウジ人は世界でも最も閉鎖的な「国民」であり、サウジアラビアは現代の「秘境」のひとつでさえある。サウジ国内に住む外国人は、サウジ人の家に住み込む外国人の召使たちでさえ、必要最小限の仕事上のコミュニケーションを除いて、サウジ人とのプライベートな交流はほとんど無い。サウジ政府が用意したお仕着せのプログラムに従う場合を除けば、テレビは言うに及ばず、新聞ですら、外国人記者に報道ビザがおりることはなく、民間人向けの観光ビザも存在しない。サウジ社会、サウジ人の実態は、闇の中である』(156ページ)
『 イスラム原理主義運動のスポンサー
一九八〇年代以降、イスラム主義運動の最大のスポンサーは、サウジアラビアをはじめとする、クウェート、カタル、アラブ首長国連邦などの湾岸産油国であった。非王制アラブ諸国および欧米の治安関係者、イスラム運動家の間では周知の事実であり、公然の秘密であった。中でもサウジアラビアの役割は質量ともに他を圧していた。
しかし冷戦構造下では、西欧諸国において、こうした湾岸産油諸国のイスラム主義武装闘争派支援は黙認された。というのは保守的な王制の湾岸産油国は、西側世界への石油の供給源であり、ソ連の影響を強く受けたエジプト、シリア、イラク、リビアなどのアラブ社会主義諸国に対抗して同地域におけるアメリカとイスラエルの利権を護るための「敵の敵」、すなわち「友好国」だったからである。また非王制アラブ諸国にとっても、湾岸産油国は総計一〇〇〇万人近くの大量の出稼ぎ労働者の受け入れ先であり、経済支援国でもあるので、公然たる名指しの非難は避けねばならなかった。結果として湾岸諸国のイスラム主義支援を口にすることはタブーとなった。
こうして八〇年代を通じて、「イスラム原理主義テロ支援国家」の悪名は、おりしも現れた共通の敵、「反米、反王制、反アラブ国家」であるイラン・イスラム共和国に全て押し付けることが、湾岸諸国ー西欧ーその他アラブ諸国の共謀によるイメージ/情報操作戦略となったのである。』(同書156~157ページ)
『 同時多発テロ事件の余波
アメリカはこれまでも再三、「テロリスト」の支援の中止を求めてきたが、サウジアラビアは言を左右して、アメリカの要求を拒否してきた。その対応にかねてより苛立っていたアメリカは、事件直後に、これまでのタブーを破り、実行犯たちの大半の国籍がサウジアラビアであるとの情報をリークし、あまつさえサウジ王族がビン・ラーディンを支援しているとまで明言した。・・・「親米国・サウジアラビア」という幻想は雲散霧消した。』(159ページ)
『 サウジアラビアと人権
そもそも犯罪者の公開処刑、女性の外出禁止、女性教育の制限、異教徒の宗教活動の禁止など、アメリカがタリバーン政権打倒のための武力行使の口実としてあげた「人権侵害」はそのまま文字通り、サウジアラビアにも当てはまる。サウジアラビアの首都リアドでは、中央モスクの前の広場で金曜集合礼拝の後に公開処刑が実行されており、女性には運転免許証は発行されず、親族の同行なしには旅行も許されず、男女共学の中等・高等教育機関は存在せず、国内には一軒の教会、シナゴーグ、仏教・ヒンドゥー教寺院の存在も認められず、聖書や十字架を持ち込んだだけでも国外退去処分になる。
武力によるタリバーン政権打倒に込められたアメリカのメッセージは、サウジ王家にとっては、火を見るよりも明らかであろう』(160ページ)
死刑制度が存在し、女性の社会進出が著しく遅れていて、かつ、国のアイデンティティー固守に拘るせいか移民許可を極端に嫌っているなどの特徴だけを取れば、わが国と似ていると思うのは僕だけだろうか。それが、宗教原理主義と島国性という全く別の淵源によるものであると見てさえも。世界の近代史を見れば分かるように、このいずれもがお上が強かった封建時代の特徴なのである。
『 閉鎖空間サウジアラビア
サウジアラビアは総人口約二〇〇〇万人の約三分の一は、外国人である。・・・・
サウジ人は世界でも最も閉鎖的な「国民」であり、サウジアラビアは現代の「秘境」のひとつでさえある。サウジ国内に住む外国人は、サウジ人の家に住み込む外国人の召使たちでさえ、必要最小限の仕事上のコミュニケーションを除いて、サウジ人とのプライベートな交流はほとんど無い。サウジ政府が用意したお仕着せのプログラムに従う場合を除けば、テレビは言うに及ばず、新聞ですら、外国人記者に報道ビザがおりることはなく、民間人向けの観光ビザも存在しない。サウジ社会、サウジ人の実態は、闇の中である』(156ページ)
『 イスラム原理主義運動のスポンサー
一九八〇年代以降、イスラム主義運動の最大のスポンサーは、サウジアラビアをはじめとする、クウェート、カタル、アラブ首長国連邦などの湾岸産油国であった。非王制アラブ諸国および欧米の治安関係者、イスラム運動家の間では周知の事実であり、公然の秘密であった。中でもサウジアラビアの役割は質量ともに他を圧していた。
しかし冷戦構造下では、西欧諸国において、こうした湾岸産油諸国のイスラム主義武装闘争派支援は黙認された。というのは保守的な王制の湾岸産油国は、西側世界への石油の供給源であり、ソ連の影響を強く受けたエジプト、シリア、イラク、リビアなどのアラブ社会主義諸国に対抗して同地域におけるアメリカとイスラエルの利権を護るための「敵の敵」、すなわち「友好国」だったからである。また非王制アラブ諸国にとっても、湾岸産油国は総計一〇〇〇万人近くの大量の出稼ぎ労働者の受け入れ先であり、経済支援国でもあるので、公然たる名指しの非難は避けねばならなかった。結果として湾岸諸国のイスラム主義支援を口にすることはタブーとなった。
こうして八〇年代を通じて、「イスラム原理主義テロ支援国家」の悪名は、おりしも現れた共通の敵、「反米、反王制、反アラブ国家」であるイラン・イスラム共和国に全て押し付けることが、湾岸諸国ー西欧ーその他アラブ諸国の共謀によるイメージ/情報操作戦略となったのである。』(同書156~157ページ)
『 同時多発テロ事件の余波
アメリカはこれまでも再三、「テロリスト」の支援の中止を求めてきたが、サウジアラビアは言を左右して、アメリカの要求を拒否してきた。その対応にかねてより苛立っていたアメリカは、事件直後に、これまでのタブーを破り、実行犯たちの大半の国籍がサウジアラビアであるとの情報をリークし、あまつさえサウジ王族がビン・ラーディンを支援しているとまで明言した。・・・「親米国・サウジアラビア」という幻想は雲散霧消した。』(159ページ)
『 サウジアラビアと人権
そもそも犯罪者の公開処刑、女性の外出禁止、女性教育の制限、異教徒の宗教活動の禁止など、アメリカがタリバーン政権打倒のための武力行使の口実としてあげた「人権侵害」はそのまま文字通り、サウジアラビアにも当てはまる。サウジアラビアの首都リアドでは、中央モスクの前の広場で金曜集合礼拝の後に公開処刑が実行されており、女性には運転免許証は発行されず、親族の同行なしには旅行も許されず、男女共学の中等・高等教育機関は存在せず、国内には一軒の教会、シナゴーグ、仏教・ヒンドゥー教寺院の存在も認められず、聖書や十字架を持ち込んだだけでも国外退去処分になる。
武力によるタリバーン政権打倒に込められたアメリカのメッセージは、サウジ王家にとっては、火を見るよりも明らかであろう』(160ページ)
死刑制度が存在し、女性の社会進出が著しく遅れていて、かつ、国のアイデンティティー固守に拘るせいか移民許可を極端に嫌っているなどの特徴だけを取れば、わが国と似ていると思うのは僕だけだろうか。それが、宗教原理主義と島国性という全く別の淵源によるものであると見てさえも。世界の近代史を見れば分かるように、このいずれもがお上が強かった封建時代の特徴なのである。










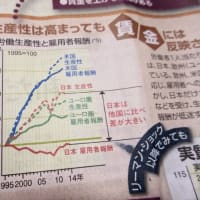
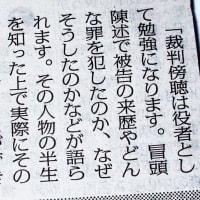






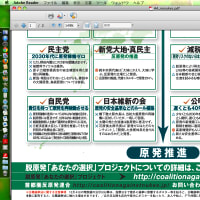





知ってはいたが、こういうサウジアラビアは、現代世界の化石国に見える。アメリカが唱える「自由と民主主義の抑圧」の典型国もかくやと、こんな国でもと言ってはなんだが、国家主権は保証されているのである。国家主権は侵害されてはならないのだ。例え北でも、これを侵害したら国民が塗炭の苦しみを舐めるのである。イラクを見よ、シリアを見よ!
ただし、こういう国が大金持ちとして存在し、その金とアメリカの支援とを受けて有形無形周囲各国に干渉するのでは、まるで「憎まれっ子、世にはばかる」ではないか。イスラム原理主義騒動が止まないわけである。アルカイーダの創始者ビンラディン自身がサウジの王族で、彼には多大なサウジ資金も流れていたらしいのだが。
とこう考えてさえ、こんな国の主権も守られねばならないのである。ただし、ある国の防衛問題に触れた時、集団安保体制ということで、国連公認の自衛権発動はありうるのだろう。
そしてまた、こんなサウジアラビヤとの友好国なんて、邪な国に決まっている。だって、現代世界に生きている人間として、もの凄い抵抗感を持たざるをえないからである。
「サウジ=悪い国」。ここへの侵略は許せないが、批判は自由である。日本も、こんな国からは手を引くべきである。そして、批判はしてあげよう。