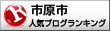先日、市原特別支援学校で開かれた「ミニ集会」に参加しました。
今回のテーマは「特別支援学校の防災」。
私は、以前議会で「特別支援学校を障害者の福祉避難所に」と訴えました。
福祉避難所とは、高齢者や障害者など、災害弱者に配慮した避難所の事です。
特に知的障害者の場合、一般の避難所ではパニックになって大声で走り回るなど、単にハード的なバリアフリーでは解決できない問題が起こり、滞在が困難になる事例がとても多いのです。
もし普段通いなれている学校が福祉避難所に指定されていれば、少なくとも児童生徒やその家族の不安が大幅に解消されることは間違いありません。
市原市では、現在いくつかクリアしなければならない課題はあるものの、市と学校双方で協定の締結に向けて協議中です。
さて、
ミニ集会で講演してくださった東京都立矢口特別支援学校元PTA会長の石塚由江さんの言葉で、特に印象に残ったのが
「受援力」。
私は初めて聞く言葉でした。
一般的には、「災害時に地域がボランティアを受け入れるための環境や知恵」を指すようですが、
この言葉を障害者に当てはめると、例えば
普段から身の回りの事や障害の特徴、接し方などを記したカードやファイルを用意しておく、
隣近所と親しくして、障害の事も伝えておく、
災害時にすぐに障害者とわかるような目印を身に着ける、
など。
石巻のある支援学校では、障害者バッヂの普及率が震災前の20%から震災後は100%に跳ね上がったそうです。
身の安全の前にはプライバシーもへったくれもないのですね。
それから、「これは面白い!」と思わず膝を打ったのが、
東金特別支援学校の教師が、子供たちに地震の時に取るべき行動をなんとか身に着けてもらいたいと考案した、
「あたりまえ体操 防災バージョン」

お笑いコンビ「COWCOW」の、あのネタですね(^^)
河北新報社がさっそく取り上げた記事は、こちら。
『子どもの防災意識養うユニーク教育 「あたりまえ体操」防災バージョン』
防災の基本は、一にも二にも自助(自分で自分の身を守ること)。
これは健常者も障害者も変わりはありません。
そういう意味で、この日の参加者がとても少なかったのは、なんとも残念ではありました。
今回のテーマは「特別支援学校の防災」。
私は、以前議会で「特別支援学校を障害者の福祉避難所に」と訴えました。
福祉避難所とは、高齢者や障害者など、災害弱者に配慮した避難所の事です。
特に知的障害者の場合、一般の避難所ではパニックになって大声で走り回るなど、単にハード的なバリアフリーでは解決できない問題が起こり、滞在が困難になる事例がとても多いのです。
もし普段通いなれている学校が福祉避難所に指定されていれば、少なくとも児童生徒やその家族の不安が大幅に解消されることは間違いありません。
市原市では、現在いくつかクリアしなければならない課題はあるものの、市と学校双方で協定の締結に向けて協議中です。
さて、
ミニ集会で講演してくださった東京都立矢口特別支援学校元PTA会長の石塚由江さんの言葉で、特に印象に残ったのが
「受援力」。
私は初めて聞く言葉でした。
一般的には、「災害時に地域がボランティアを受け入れるための環境や知恵」を指すようですが、
この言葉を障害者に当てはめると、例えば
普段から身の回りの事や障害の特徴、接し方などを記したカードやファイルを用意しておく、
隣近所と親しくして、障害の事も伝えておく、
災害時にすぐに障害者とわかるような目印を身に着ける、
など。
石巻のある支援学校では、障害者バッヂの普及率が震災前の20%から震災後は100%に跳ね上がったそうです。
身の安全の前にはプライバシーもへったくれもないのですね。
それから、「これは面白い!」と思わず膝を打ったのが、
東金特別支援学校の教師が、子供たちに地震の時に取るべき行動をなんとか身に着けてもらいたいと考案した、
「あたりまえ体操 防災バージョン」

お笑いコンビ「COWCOW」の、あのネタですね(^^)
河北新報社がさっそく取り上げた記事は、こちら。
『子どもの防災意識養うユニーク教育 「あたりまえ体操」防災バージョン』
防災の基本は、一にも二にも自助(自分で自分の身を守ること)。
これは健常者も障害者も変わりはありません。
そういう意味で、この日の参加者がとても少なかったのは、なんとも残念ではありました。