★ 島おこし 奄美カレー ★
むしむしと暑い季節になってきましたね。
食欲も落ち気味になる、
そんなときにはスパイスを利かせた料理にしませんか?
奄美大島の島おこしのシンボルとして、
特別栽培された生うこんをベースにした
カレールーはいかがでしょう。
左から、ちびっこ・甘口・中辛。
ちびっこは幼児向き、甘口は小学低学年向きです。


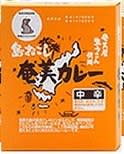
カレーの黄色はターメリックの色であり、
日本では「うこん」と呼ばれる香辛料なのです。
見た感じは生姜に似ています。


古来から奄美では、
うこんを食用・染色・薬として
広く用いていたそうです。
奄美の「島おこし」を思案していた
奄美島立会物流センターが、
このうこんに着目したのが始まり。
そして、うこん…ターメリック…カレー…という発想により、
カレーを作りたいと考え、1
985年、試行錯誤の末に
島おこし 奄美カレーが誕生したのだそうです。
大自然豊かな奄美大島産の
生うこん(ターメリック)を主な原料に
作られたのが奄美カレーなんですね。
奄美カレーは で注文できます。
で注文できます。
今日が注文締め切りなんです!
急いで~(もしかして明日の朝でも間に合うかも・・・・)
おまけの話
天竺舎もうこんを栽培してます。
誰か高知産うこんを使ったカレールーを作りませんか。。。。
むしむしと暑い季節になってきましたね。
食欲も落ち気味になる、
そんなときにはスパイスを利かせた料理にしませんか?
奄美大島の島おこしのシンボルとして、
特別栽培された生うこんをベースにした
カレールーはいかがでしょう。
左から、ちびっこ・甘口・中辛。
ちびっこは幼児向き、甘口は小学低学年向きです。


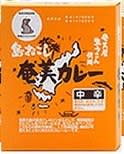
カレーの黄色はターメリックの色であり、
日本では「うこん」と呼ばれる香辛料なのです。
見た感じは生姜に似ています。


古来から奄美では、
うこんを食用・染色・薬として
広く用いていたそうです。
奄美の「島おこし」を思案していた
奄美島立会物流センターが、
このうこんに着目したのが始まり。
そして、うこん…ターメリック…カレー…という発想により、
カレーを作りたいと考え、1
985年、試行錯誤の末に
島おこし 奄美カレーが誕生したのだそうです。
大自然豊かな奄美大島産の
生うこん(ターメリック)を主な原料に
作られたのが奄美カレーなんですね。
奄美カレーは
 で注文できます。
で注文できます。今日が注文締め切りなんです!
急いで~(もしかして明日の朝でも間に合うかも・・・・)
※井上スパイスのスパイスは不定期扱いとなりますので、この機会にぜひご注文ください。
おまけの話

天竺舎もうこんを栽培してます。
誰か高知産うこんを使ったカレールーを作りませんか。。。。















 会員Hさん夫妻さんの声
会員Hさん夫妻さんの声






 がついてます。
がついてます。
 理事長 丸井一郎です。
理事長 丸井一郎です。




 こんな手間をちょっと加えるだけで出来上がりのランクがアップします!
こんな手間をちょっと加えるだけで出来上がりのランクがアップします! 最初にニンニク(薄切り)を加えると大人の味
最初にニンニク(薄切り)を加えると大人の味 



 最後に合わせて盛る。この場合前後にオリーブ油を足すとまた格別。
最後に合わせて盛る。この場合前後にオリーブ油を足すとまた格別。 乾燥トマトが美味しかった
乾燥トマトが美味しかった

 ♪
♪ TONTON有機農場のショルダーベーコンお好みの量を薄切りにし、弱火で炒めて脂を出す。
TONTON有機農場のショルダーベーコンお好みの量を薄切りにし、弱火で炒めて脂を出す。 鍋は厚手のステンレスがよい。
鍋は厚手のステンレスがよい。 厚さ5~7ミリに輪切りにしたジャガイモを加え、蓋をして弱火で加熱する。
厚さ5~7ミリに輪切りにしたジャガイモを加え、蓋をして弱火で加熱する。 上の面まで火が通ったら(完全でなくていいです)、裏返して蒸し煮にする。蓋をせずに焼き色をつけてもよい。
上の面まで火が通ったら(完全でなくていいです)、裏返して蒸し煮にする。蓋をせずに焼き色をつけてもよい。








