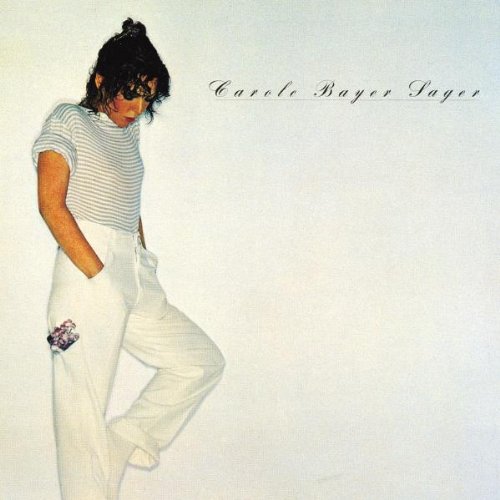老いた両親の介護のために、25年ぶりに故郷・帯広にもどった。主夫で、介護士で、看護師で、ケア・マネージャー補佐で、洗濯夫で、料理人で、買い物係で、庭の草取りジジイで、お掃除おじさんのような生活がつづいている。寝たきりになってしまった母、認知症初期の九十近い父親。このふたりの介護を、ひとりでやる事態に至った。じつにヘヴィーな日々、これこそ、ハード・デイズ&ナイツだね。
優雅に帯広散歩というわけにいかないが、スーパーマーケットへの道すがら、道端の草木にみとれる。ひさしぶりにみる北海道・道東の木々、草花は新鮮だ。長く暮らした関東と北海道では、植物相がまったく違う。関東は亜熱帯の北限、ここは亜寒帯の南限ともいえる。おなじ種類の植物でも、ちがう種といっていいほど大きさが違う。