国技・大相撲の幕内に142年間
出身力士を輩出し続ける青森県
と昨日書いた
まだ江戸幕府の世の安政3年、
西暦でいえば1856年に生まれた
一ノ矢が、入幕して以来ずっとで、
横綱に鏡里、初代若乃花、栃ノ海、
二代若乃花、隆の里、旭富士と6人。
大関には貴ノ浪、さらに関脇安美錦、
小結舞の海、高見盛ら名力士多数。
誤解を避けるべく添えると、
一ノ矢は生まれが江戸時代で
入幕したのは明治16年。
そこからのほぼ一世紀半である。
2位は茨城県の43年連続だから
圧倒的にもほどがある!
今は違うと思うけれど、
青森には土俵のある校庭が多かった。
逆に、なくなった影響か、
かつての「王国」は風前の灯で
今は幕内に尊富士、たった一人。
伊勢ケ浜部屋の彼の出身が
「五所川原」だ。

そう主題は「ごしょがわら」で
相撲ではないのだ。が
昨日も触れた『うっちゃれ五所瓦』は
相撲漫画!
週刊少年サンデーにかつて連載され、
平成元年度の小学館漫画賞受賞作。
神奈川の武蔵山高校が舞台で、
主人公・五所瓦角以外は、
柔道部、レスリング部、応援部に
囲碁部と個性豊かな(?)
寄せ集めで日本一を目指す!
よくあるパターンではあるが、
最大のライバル田門泰造(黒島高校)、
丙馬一郎(杉田工業)ら周辺人物も
巧みな作りで、面白い作品だった。
様々なスポーツの特徴を生かし
一競技に集約させる手は
他でも見るわけだけれど。
当時はまだ広がっていなかった
「多様性」に通じていたのかぁと、
久しぶりに『うっちゃれ〜』の
頁を巡りながら、ふと。
さて。
五月場所初日に18歳の貴花田が
大横綱千代の富士をくだした1991年。
その3日後にウルフ引退となった年に
連載を終えた『うっちゃれ〜』だが、
30年の時を超えた2023年に
『うっちゃれ五所瓦〜粘り腰編』を
ビッグコミックでスタートさせた。
⋯⋯知らなかった。

同年三月場所では、昭和以降初めて
〈横綱大関不在〉となった相撲界。
「ヒーロー誕生」を期す想いか?
あの五所瓦が土俵で闘う物語が還ってきた。
他のメンバーは・・・
柔の道に戻った清川薫が
世界選手権で銀メダリストとなり
五輪でさらに輝くメダルを目指す!
囲碁部だった雷電五郎は
おまわりさんに。
関内孝之はプロレス技での
白星が多かったが、
職業としてもプロレスラーを選んだ。
応援部だった難野一平はサラリーマン
・・・とそれぞれの道を歩んでいる。
現在も連載中。
昨日のブログで、父の故郷が五所川原で
筆者は生まれも育ちも神奈川だとも
綴ったけれど、そんなわたしが
生れた年が1966で、丙午(ひのえうま)。
上述の登場人物に「丙馬」と
縁が多い漫画だったりもする。

作者なかいま強は1960年沖縄出身で、
かのえね(庚子)なのに、
何故に「五所瓦・神奈川・丙馬」なのか?
そして来年の十二支十干が〈丙午〉だ。
女が男を食らうと謂れ、
極端に子が少ない60年に一度の巡り。
少子化でただでさえ生まれない
「未来の宝」は、またもや激少なのか!
もうそんな迷信はうっちゃられるのか










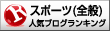



 耳に懐かしい津軽弁を堪能。
耳に懐かしい津軽弁を堪能。

 熱血高校相撲漫画だ
熱血高校相撲漫画だ
























 その日は生憎の雨。
その日は生憎の雨。





















