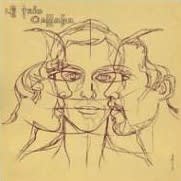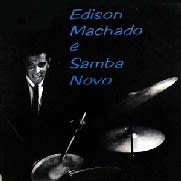少し久しぶりの紹介となるブラジル盤。しかも、これまで多く紹介してきたジャズサンバ系の盤ではなく、いわゆるバランソと言われるジャンルのもの。Maestro Cariocaなるコンポーザーが、自身のバンドを率いてバランソ専門レーベルであるEquipeに残した1枚です。録音時期はクレジットに明記されていないので分かりませんが、おそらく70年前後ではないでしょうか。全体的に華やかなホーンを中心に据えた構成になっていて、時に男女それぞれによるコーラスを交えながら、軽快なテンポで突き進む楽しげな仕上がりになっています。女性Vo.によるA-2のMorena Boca De Ouroや、例のForma盤でVictor Assis Brasilも取り上げていたA-3のFeitico Da Vilaなど、この手のバランソ中でも最高峰と思われる名演がズラリ。このレーベル特有の音抜けの良さも手伝って、本家ブラジルの土臭いサウンドと言うよりも、ヨーロッパで録音されたライブラリー作品のような一種のエレガントさを秘めているのがポイントですね。そして何と言っても極めつけの名曲はA-1のNa Cadencia Do Samba。一聴しただけでは、普通にウミリアーニやピッチオーニ辺りのチネ・ジャズと間違えてしまいそうな、哀愁と気品と情熱が同居したジャズ・サンバ名作です。Angel Pocho Gattiによる人気曲Kashbaにも近い雰囲気で、まさにクラブプレイのためにあるようなダンサンブルな一曲。これで盛り上がらなければ嘘でしょう。ちなみにこのEquipeというレーベル、本作以外では例のSergio Calvalhoによる白盤やWhat Musicから再発されたJulinhoの唯一のアルバムなんかもリリースしています。正統派ブラジル音楽ファンだけでなく、クラブジャズ好きも何気に要チェックですね。
こんなものまでCD化されてしまうなんて…。ブラジルのサキソニストHector Costitaによる1964年の隠れ名盤。たとえばOs Cobrasのメンバー辺りと比べれば、ジャズ・ボッサ界の中でも極端に知名度が低い彼ですが、意外にもその活動歴は長く、他のミュージシャンのサイドメンとして地味ながらも活躍していたそう。たしか最近紹介したセルメンのジャズ・ボサ盤にも参加していたはずです。さて、本作はそんな彼による珍しいリーダー作。エディソン・マシャードやセバスチャン・ネトらをサイドメンに迎えて、かなり本格的なハードバップをやっています。おそらく当時の他のハード・ジャズ・ボッサの名盤と比べても、際立ってジャズ度が高いと感じるはず。Horace SilverのカヴァーとなるM-5のTokioや、流麗な高速ジャズ・サンバであるM-10のTem Doなど秀逸ですが、個人的に本作中で白眉とさせてもらいたいのはM-1のLe Roi。どこか呪術的でアフロな雰囲気が漂うミディアムのブルース・ナンバー。要所要所での3拍子への転調も華麗にキマっています。トム・ジョビンの名曲を夜ジャズ風にアレンジしたM-2のInsensatezやM-4のVivo Sonhandoも文句なしの完成度。ちなみにオリジナルはFermataというマイナー・レーベルからリリースされていますが、今回はSom Livreからの復刻となっています。何度かオリジナルを買おうとしたこともあるのですが、安い盤でもないので躊躇していたところに来ての嬉しい再発。ブラジル・ファンのみならずジャズ・ファンにもオススメの一枚です。
周知の通り後にブラジル音楽の伝道師として世界に羽ばたいていくことになるセルメン。本作はそんな彼がブレイクする数年前の1964年にPhillipsからリリースされた一枚です。セルメンというとブラジル音楽とソフトロックを組み合わせたような独特のアレンジの曲が有名で、各国に多くのフォロワーを生み出したポップス界の名アレンジャーというイメージが強いですが、実はそのキャリアのスタートはれっきとしたジャズ・ピアニスト。「ベッコ・ダス・ガハーファス」にあったナイト・クラブで夜な夜なピアノを弾いていたという過去を持つ人だったりします。ちなみに当時そこに集まっていた誰も彼もが、今ではジャズ・ボッサ界の伝説的人物ばかり。と言うわけで、本作もまた参加メンバーが凄いことになっています。ハウルジーニョやエディソン・マシャード、セバスチャン・ネトなどを含む3管セクステット編成での録音。もちろん悪いわけがありません。Os Cobrasやメイレレースのアルバムにも引けを取らないブラジル産ハードバップ。特にA-5のPrimitivoやB-5のNeurotico辺りはヨーロピアン・ジャズとも相性が良さそうな高速ジャズ・サンバ。あまり「らしさ」は感じられませんがジョビンによるアレンジが素晴らしいです。そして、個人的なお気に入りはA-4のDesafinado。ボサノヴァのスタンダードとして有名な曲ですが、数あるカヴァーの中でも5本の指には入るであろう名演。夜感漂うジャケットも素敵ですね。セルメンの作品ってだけでコアなジャズ・ファンには見落とされがちですが、そんな先見だけで敬遠するのはもったいなすぎる一枚。再発は良く見るので、是非一度聴いてみてください。ジャズ・サンバとしてのみならず純粋にジャズとして見ても文句なしに格好いい一枚ですよ。
1960年代のブラジルを代表するトロンボーン奏者Raulzinho(ハウルジーニョ)が、Sanbalanco Trioをバックに従えて吹き込んだハード・ジャズボッサな一枚。それなりのマニアの方でないと彼の名前には馴染みがないかもしれませんが、実は参加している作品は結構多く、有名どころだとTenorio Jr.の例のアルバムなんかにもいる人です。と言うか当時のブラジルにおけるジャズ・ボッサ人脈では、彼以外にトロンボーン奏者っていなかったのではないでしょうか。そんな風にすら思えるほど、当時の作品においてトロンボーンと言えば彼の名がクレジットされています。正確なことは分かりませんが、いずれにしろこの楽器において彼に匹敵する実力者が当時いなかったことだけは間違いなさそうですね。それくらい圧倒的にトロンボーンの扱いが上手いです。バルブをスライドさせて音を出す楽器で何をどうやったらこんな音が出るのか、はっきり言って超絶技巧過ぎて意味が分かりません。アルバム全編において人並み外れた素晴らしい演奏を堪能できますが、そんな中で彼の実力が最も如何なく発揮されているのが、M-1のタイトル曲。例によってブラジル産ハードバップとも呼べそうな高速ジャズ・サンバなのですが、ここでの彼のトロンボーン捌きはまさに神業というしかない代物。Sambalanco Trioによる強烈な援護射撃も相まって、この手の作品の中でも抜群の輝きを放った1曲です。とにかく始めから終わりまで両腕握りっぱなしの熱い演奏。ブラジル好きはもちろんハードバップを愛する若者にこそ聴いて欲しい1曲です。
今さらですが衝動買いしてしまったので紹介。世界中で今現在も売れに売れまくっている本作は、セルジオメンデスによる約10年ぶりの新譜です。ヒップホップ界の人気者であるBlack Eyed PeasのWill.I.Amをプロデューサーとして迎えて作られたアルバムで、巷では「ヒップホップとボサノヴァの融合」だなんて触れ込みで紹介されているのをよく見かけますね。まぁどちらかと言うと「ブラジル音楽のヒップホップ的解釈」と言った方が適切かと思いますが、要するにセルジオ・メンデスを売れ線のヒップホップ的な音作りで全面的にプロデュースして完成したのがコレということです。従って豪華(?)な客演陣を含め基本的には商業的な雰囲気が見え隠れする1枚で、あまり個人的に好きなタイプのアルバムでもないのですが、要所要所で見せるMPB~コンテンポラリー・ブラジリアン風味のアレンジが秀逸で、ついつい我慢できずに購入してしまいました。2枚あるLPの内で最もMPB傾向が高いSide 3が一番のお気に入り。ブラジル・ヒップホップ界からMarcelo D2を迎えたボサmeetsヒップホップのC-1、Samba Da Bencao(ピアノが綺麗過ぎ!)に始まり、フリーソウル度高めのメロウMPBなC-2のタイトル曲、それから大人のヒップホップとでも呼べそうなC-3のLoose Endsまで、この面に関しては本当に文句の付けようのない素晴らしい出来。他の曲はともかく、この3曲のためだけに買っても損はないアルバムかと思います。まぁどこの試聴機にも入っていると思うので、まずは試聴からどうぞ。
何気に久しぶりの紹介となるジャズボッサもの。ピアノのDon Salvador、ベースのSergio Barroso、それからドラムスのEdison Machadoによるピアノトリオ、その名もRio 65 Trioによる66年の2ndアルバムです。彼らと言えば、1stに収録されたMeu Fraco e Cafe Forte(濃いコーヒーを)という曲が良く知られていて、この2ndの方はあまり話題に上がることがないような気がしますが、だからと言って聴かないというのでは少し勿体無い気がするので紹介させてください。さて、まだまだ荒削りな演奏ながら、そのダイナミックさが魅力の1stと比べて、幾分洗練された1枚に仕上がっているのがこの盤の特徴。冒頭を飾るM-1、Cartao De Visitaのようなハード・ドライヴィングなジャズ・ボッサも収録されていることはいますが、基本的にはもう少しお洒落系と言うかソフト路線でまとまっています。M-2のDeve Ser BonitoやM-5のPonte Aereaあたりにその傾向が顕著ですね。今の気分的にオススメなのは、M-4のApeloとM-12のSeu Encanto。前者はゆったりとしたマイナーコードのボサノヴァ、後者はいわゆるジャズ・ワルツの佳曲。どちらも夜感漂うモーダルなナンバーなので、クラブシーンにおける昨今のモダンジャズ・ムーブメントにも対応可かと思われます。もちろん彼らのテーマであるM-10のRio 65 Temaなんかも最高。これからの暑い季節を乗り切るには、こういった洒落たジャズボッサなんかいかがでしょうか。
このジャケットが既にそこそこ有名なので、少し知識のある人ならばジャケを見るだけでピンと来るでしょう。そしてこの手のインスト系ジャズ・ボッサを熱心に聴いている人にとっては、もはや定番中の定番と言えるのがこの作品。ピアニストのFernando Martinsを中心としたブラジルのトリオが、渡仏中の68年にリリースしたSaravahに残したLPです。たしかブラジル本国での録音作はなかったと思うので、これが彼ら唯一のアルバムと言うことになるはず。オープニングを飾るA-1のBerimbauから高速ジャズ・ボッサで気持ちよく駆け抜けてくれます。自作となるA-3のBiaやCafe Apres-Midiのコンピに収録されたB-5のMuito A Vontadeも同様の疾走ジャズ・ボッサ・チューンでオススメ。個人的に気に入っているのはジョビンをカヴァーしたA-5のEstrada Do Sol。いわゆるブラジルのピアノ・トリオと言ってしまえばそれまでなのですが、Tamba TrioやSambalanco Trioなどの他コンボに比べるとやはり洗練度が違います。間違いなく、フランスで録音されたということが影響しているのでしょう。あまり話題には上がらないA-2のNao Tem Solucaoや、A-4のNascenteのようなモーダルなバラードも美しくて気に入っています。この辺りがやはりブラジル録音では出せない独特の味わい。ちなみにオリジナルは結構レアですが、Dare-Dareからの再発はわりとよく見かけます。再発なら値段も安いのでオススメですね。
ブラジル(と言うかジャズ・ボッサ)を代表するドラマー、Edison Machadoによる60年代のCBS盤。一部のブラジル音楽マニアの間でカルト的人気を誇る本作は、ほとんどジャズ・ボッサ・オールスターズと言えそうな最高の面子で録音された大傑作。J.T.MeirellesにPaulo MouraにRaulzinho、さらには伝説のピアニストTenorio Jr.までもが参加していると言えばブラジル音楽に心得のある方なら、そのメンバーの凄まじさが分かるはずです。そしてそれらを操るEdison Machadoのドラムがまた抜群に素晴らしい。A-3のAboioからしてClarke = Boland Big Bandばりの強烈なラテン・ジャズなのですが、その本領が発揮されるのはB面。もはやこの辺りのホーン入りジャズ・ボッサでは定番のB-1のQuintessenciaカヴァーに始まり、B-2のSe Voce Disser Que SimやB-3のCoisa N°1、さらにはB-4のSoloなど息をも尽かさぬ高速ジャズ・ボッサの連続の前にはただただ呆然と立ち尽くすばかり。Art Blakeyのアルバムを引き合いに出すまでもなく、ドラマーのリーダー作と言うのは得てしてフロア向けのものが多いですが、そのような中でもこのアルバムはダントツ。あまりの格好よさの前にため息しか出ません。ちなみに現在は廃盤ですが、アナログ・CD共に数年前に正規で再発出ています。僕が持っているのはこの再発アナログですが、今となってはなかなか見かけないですね…。
今から2年ほど前に英What Musicから再発された本作は、ブラジル音楽コレクター達に幻の一枚と噂される激レア盤。トランペット奏者であるJulinhoことJulio Barbosaが、唯一残したリーダー作として知られている作品です。全編インストのジャズ・ボッサなのですが、最近よく僕が紹介しているような「ブラジルのハードバップ」的演奏ではなく、比較的ラウンジーで落ち着いた雰囲気の演奏が繰り広げられています。全体的に気品があり、どことなくヨーロッパ的な匂いもチラホラ。B-3のTema Pro Gaguinhoや続くB-4のMenina Florを始め、気持ち良さの中にも少しばかりの陰影を秘めた大人な曲が多数収録されている好盤。今日みたいに曇り空の午後にはこういうレコードをかけながら、のんびりと過ごすのもいいかもしれません。全体的に速すぎず遅すぎずといったテンポの曲ばかりで、正にAt The Living Room的な名盤と言えるでしょう。そしてジャズDJに人気があるA-5のCaminhandoはやはり飛び切りの名曲。ややアップ気味なテンポの中を駆け抜ける、哀愁に満ちた三管のテーマが美しいです。フロアをがんがんに盛り上げるというタイプの曲ではないでしょうが、うまくプレイすればとても気持ちよく踊れそうなジャズ・サンバ。言うまでもなくユーロ・ジャズなんかとの相性も最高です。オリジナルはともかく再発はわりとどこにでも売っているので、チェックしてみてください。ちなみにCDでもリリースされているようです。
数ヶ月前からディスク・ユニオンなどを中心に話題となっていたブラジル音楽の大型リイシュー企画が遂にお目見え。残念ながらアナログでのリイシューはなく、全25枚全てがCDのみでの発売となりますが、だからと言って見逃すのではもったいなさ過ぎる好企画です。で、その25枚の中でも特にジャズ・ファンに評価されそうなのがこの盤。Sambossa 5による65年の1stアルバムですね。サバービアやプレミアム・カッツで紹介されている2ndもかなり内容が良いそうなのですが、こちらの1stも充分に素晴らしい。ジャズ・ボッサと言ってしまっては語弊がありそうなくらい、60年代ハードバップからの影響が色濃い熱い演奏が全編で繰り広げられています。MeirellesやOs Cobras辺りの音が好きな人にはストライクでしょう。一般にピアノ・トリオが圧倒的に多いジャズ・ボッサの中で二管クインテット編成と言う点や、全ての曲が短尺で2~3分で終わるところもフロア的にはポイント高いと思います。M-2のDiagonalをはじめ格好いい佳作揃いの1枚ですが、個人的に最も気に入っているのはラストに収録されたM-12のTensão。ヨーロッパのハードバップなんかとも相性が良さそうな高速調のモーダル・ジャズ・ボッサ。こういう曲はもはやブラジルのハードバップと呼んでしまって構わないと個人的には思っているのですがどうでしょう。ボサノヴァのゆるい感じが好きな人が、こういうの好むとも思えないし…。ジャズファンにこそオススメの1枚です。