国会が衆参でねじれ状態にあると、報道は面白おかしく書き立てているが、これまでの日本の政党のあり方が幼かったのだともいえる。所属政党の決めたことは何が何でも賛意を示し、他党の意意見には、はなから否定してかかる。これは、与党が衆議院と参議院どちらでも必ず多数を占めていた、戦後のしばらくは除きかつてなかったことである。
与党と野党と言う縛りを前提に取り組んできた国会運営が、民主主義の成熟を遅らせててしまったと言える。もうひとつ悪しき慣行として、党議拘束がある。党内で決めたことは何が何でも従えという、日本特有の”おらが党”なる帰属意識が党議拘束の根底にある。この党議拘束を巨大化して、議員に押し付ける結果になったのが、小選挙区制である。
小選挙区制度の下では、党の意向に逆らって出ることができなくない。一人しか公認されることがない。更に、政党助成金を党が管理する中で、とても党の意向に逆らうことなどできない。自らの意志を主張できない、持たない国会議員ばかりになってしまう。
選挙に勝つためならなんでもやる。デタラメをおうが夢物語を主張しようが特定の団体のいいなりになろうが、何としても議席を得た党が与党になる。小沢一郎の手法がここにある。幹事長が全てを掌握し、配下に置く手法である。
今回のねじれ現象は、こうした従来の形、国会の在り方を見直すいい機会である。ヨーロッパに限らず、どこでも政党相互の妥協や案作成に論戦や論議は常態である。
最初から、与党や野党との枠の中でしか論議できないのは、与党や野党の経験しかない政党の未体験ゾーンに差しかかっている。政党の立場しか主張できない未熟な日本の政党は、国民を優先できない。今日本の民主主義が転換点に立っていると言える。










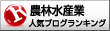
















テレビ番組では複数の党が議員定数削減を公言するが、99%不可能なことを平気で言う。これを国会で認めることはあり得ない。
落選するとただの人と言われるように、議員であるが故の権力と特権に酔いしれている人種がみずから身を引くなどの発想は生まれない。
ねじれ国会も期待したいが、衆参議員が専門家として機能しているのだろうかという疑問がわき上がる。もしかして、学生運動の延長上に日本の政治があるのかと思うと身の毛がよだつ。
国民の未来を真剣に考えている国会議員がどれほどいるのだろう。議員数削減を言う議員は許せない。せめて、議員歳費を半額、特別支給は不要と宣誓する国会議員がいればとりあえず投票することにしたい。