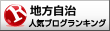昨夜北海道地方で放送された、クローズアップ北海道「TPPで乳製品ピンチ”強い酪農”を目指せ」は、大型化に対する警告の番組であった。番組の冒頭では、十勝の大型酪農家、番組では900頭搾乳している、と報告されていた。
巨大な牛舎と、搾乳施設には圧倒されました。これほど大きな牛舎にするには、餌の主体が購入資料になってしまう。配合飼料(輸入穀物のことである)は、毎日100万円を超すと説明していた。きっと円安で相当のダメージを受けるに違いない。
 牧場の方は、TPPが入ってくれば存在すらできないと、作業の手を休めながら語っていた。このような巨大な酪農業は、外部資本への依存度が高く、ちょっとしたことで傾いてしまう。
牧場の方は、TPPが入ってくれば存在すらできないと、作業の手を休めながら語っていた。このような巨大な酪農業は、外部資本への依存度が高く、ちょっとしたことで傾いてしまう。
番組のほとんどは、足寄の放牧酪農を主体にやられている方の、経営形態を展開していた。ほとんど穀物を給与することなく、外に出て牧草地の草を食べさせていた。この方は牛舎すら持っていない。簡易な雪風を防ぐようなハウスしかない。
牧場主は、「TPPが入ってきてもこのスタイルを続けます」と、何の危機感もなく答えていた。本人は大学を出てから、ニュージーランドに実習に行き、放牧だけで搾ることを学んでいる。設備投資も経費も極力抑えられている。外部資本の依存はほとんどない。当然環境に左右されるために、規模も小さく一頭当たりの搾乳量も少ない。
この30年ほどで、日本の酪農は大きく変わった。一頭当たりの乳量は倍ちかくになったが、給与穀物量は倍以上になった。給与供物はほとんどがアメリカからの輸入されたものである。この10年ほどで穀物価格は倍近くなったが酪農家は気が付いていない。円高で酪農家はそれほど高くない穀物に依存し続けてきた。
穀物多給酪農家では、当然病気も多発する。三産も搾れない。放牧酪農は、マイペース酪農と言われていることが多く、この人たちのところでは病気は少なく、五産ほど搾ることになる。
大型酪農は、設備投資や維持の経費が膨大な金額になる。おまけに大量の穀物を給与する。酪農家の労働時間も、年8000時間を超える膨大なものとなる。牛も頻繁に病気になってくれる。周辺産業にとってはまことにありがたいしシステムなのである。
大型酪農は、今回自民党政府が奨励する「意欲ある農家」と分類され、マイペー ス型や放牧主体の酪農家は、改善意欲がない農家に分類されることになる。大型酪農家が世界の資源を浪費して、環境悪化と食糧問題の元凶になっていることは、この国の政府は問わないのである。
ス型や放牧主体の酪農家は、改善意欲がない農家に分類されることになる。大型酪農家が世界の資源を浪費して、環境悪化と食糧問題の元凶になっていることは、この国の政府は問わないのである。
更に、酪農家の経営質や労働量のことなども問わないのである。アベノミックスでこれまで以上に、農家が債務を抱えることになる。
左に<マイペース酪農交流会>をアップしました。