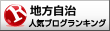結構色々な報道やネットから情報を拾っているつもりでいるが、知らなかったことがあまりに多い。すっかり決着がついていたと思っていた、カネミ油症事件であるが、原爆症や水俣病と同様の経過をたどっていたのである。
カネミ油症事件とは、45年まえに何の瑕疵もない一般国民の台所に忍び込んだ、猛毒のダイオキシンである。食用油の生産過程で混入した、PCBであるが現在はダイオキシンと分類されている。
この被害者たちが、一時の補償にとどまることなく継続的な、補償を求め昨年救済法が成立した。被害から44年経過していた。ご多分に漏れず、カネミ油症事件でも被害者認定で、いまだに決着がついていないのである。
ダイオキシン物質の特徴として、次世代に引き継がれる恐怖がある。現実に被害者の母親から、症状として引き継いでいる2世たちがいる。しかし、血液検査をしても全く異常を見出すことができないため、カネミ油症の認定患者にはならないのである。
日本では救済法が成立しても、可能な限りその範囲を狭めるのである。ほぼ同様の油症事件が起きている台湾では、親が患者なら子供にもその対象を広げて認定しているのである。
こうした日本政府の姿勢は、原爆症や水俣病についても同じことが言える。原爆症については、アメリカの見解あるいは指示のもとで、7日間を過ぎ現地にいた人は認めなかったことに始まり、地域を限定する作業は延々と続けられた。それがようやく昨年枠が外れた。
水俣病についても、血液検査の結果で認定患者を絞り込んだ。現実の症状がある人たちは、救済されることがなかったのである。アスベスト被害も同様である。被害者が声を上げ、多くの場合亡くなられてから、工場周辺の人たちの認定に腰を上げたのである。
その他数限りない、薬害事件はいずれの場合も加害者擁護に国家は動いている。原発による放射能被害者や被害地域も同様に、最小限にとどめようとし、加害者擁護とみられる動きを見せる。
不特定多数の人たちが被害者となった事件の場合、日本という国では最小限に留めようと国家権力は動くのである。慰安婦問題も集団自決についても同様の力学が働いている。