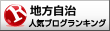何度も何度も都会の人たちが、一票の格差を裁判所に持ち込む。国会議員の持ち票に差があるというのである。意味合い的には解らなくもないが、これは都会の人たちの一方的な理屈にすぎない。人間の数がこの世界を支配しているのではない。
日本の土地のほぼ70%は山林であり人がほとんど住んでいない。都会と称されるところは、僅か5%を占めているに過ぎない。5%のところに日本の75%が住んでいる。彼らが一斉に、人間の数に応じて権利を主張したらこの国は終わってしまう。ましてやそれを民主主義と言うのな ら、新鮮な空気と酸素を供給し水や食料を供給する、過疎地はたまったものでない。
ら、新鮮な空気と酸素を供給し水や食料を供給する、過疎地はたまったものでない。
中選挙区時代、北海道五区は衆議院議員定数が5名であった。五区とは、十勝と釧路と根室と網走支庁(北見地方)である。面積はほぼ関東平野とかわらない。この時の関東平野の定数は解らないが、小選挙区になってこの地方はほぼ3つの選挙区になり、衆議院の議員定数は僅か3名になってしまった。同等の面積の関東平野では現在丁度100名である。環境格差、あるいは地方格差から言うと実に33倍である。
かなり前に、札幌の創成川だと思うが柳の木の伐採反対運動があった。反対の署名は極めて短期間に数万人集まったと聞く。同じ時期に、知床の自然木の伐採反対運動があったが、とてもじゃないが署名人数があつまらない。田舎では10名取るのも大変なのである。
300年を経たナラの大木に体を縛り付け抵抗したパフォーマンスは、大きく報道された。知床の木は誰かが訴えなければ知ることのない自然木である。方や札幌の木は植栽された柳で、多くの人たちが毎日見つめている木である。伐採の反対者の数は歴然と異なる。植栽された柳の木を残したい人の方が多くなるのは当然である。人知れず存在する知床のナラの木は誰も知ることがなく、人の評価が極めて薄い。人の数による格差、これが民主主義であるはずがない。
人間の数に応じて権利の大小、過多、濃淡を設定するのは人間の驕りである。一票の格差があって当然である。この世は人が住んでいるだけではないからである。