
上の写真は、アホウドリのヒナのお腹の中である。食事経験が浅く成長期で食欲の旺盛なヒナが、見えるものや浮遊するもの次々と食べたことが伺える。アホウドリは人類が住む陸地から遠く離れた大洋の中にいる鳥である。プラスチックの海洋汚染が深刻で広範囲及んでいることが推測される。
5ミリ以下のものを一般的にマイクロプラスチックと呼ぶ。私たち人類が利便性の元に、主に石油から大量に生産したものである。紫外線に分解され難く潰瘍に放出される量は、800万トンと推定されている。特にマイクロプラスチックは海洋に浮遊し、生態系に深刻な影響を与えている。とりわけ資源を海に求める海洋国日本は、世界に先駆けて取り組まなければならない、極めて大きな問題である。
ところが、カナダで開催されたG7で、日本とアメリカが海のプラスチックごみを減らすための数値目標を盛り込んだ文書に署名しなかった。世界の環境団体から、「恥ずべき行為」と厳しい非難が、日本とアメリカに浴びせられている。海洋ごみ問題に取り組む環境団体JEAN代表理事は「海から恩恵を享受している日本は、プラスチックごみ問題に率先して対応する必要がある。長年政府と連携して削減に取り組んできた立場として理解できない」と不満を示している。グリーンピースからも「日米が署名しなかったのは恥ずべきこと。必要なのは業界の自主規制ではなく、使い捨てプラスチックの禁止」との声明を公表した。
アメリカと北朝鮮を巡る動きばかりが騒ぎ立てられているが、世界共通の深刻なマイクロプラスチックの問題は、すでに取り組みには遅すぎる感すらある問題である。他の環境問題と異るのは、現状のプラスチック対策は極めて時間と費用が膨大に明かるが、効果は極めて疑問があることである。
根本対策はグリンピースの言うように、使い捨てプラスチックの禁止も検討しなければならないのかもしれない。
それにしても、安倍晋三の署名しなかった理由が、「企業の理解が得られないから」とは、政治主導を放棄する政治家にあるまじき発言である。
そりゃ、今までは企業のためなら何でもやるというのが、安倍晋三・自民党の立場ではあったろうが、環境問題まで顔色を窺おうというのであろうか。それとも、トランプとは一体であるとでもいうか。










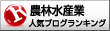

 世界的ベストセラー『銃・病原菌・鉄』で知られる、進化生物学者ジャレド・ダイアモンド博士がアメリカ・ロサンゼルスで、若者向けに行った特別授業が12回放送された。今回は”ヒトの秘密”と題されていたが、例によって人類学から文明論まで幅広い範囲に及ぶ、ダイヤモンド氏独特の分析は、頭の柔らかい若者たちにとって理解し易かったように見える。
世界的ベストセラー『銃・病原菌・鉄』で知られる、進化生物学者ジャレド・ダイアモンド博士がアメリカ・ロサンゼルスで、若者向けに行った特別授業が12回放送された。今回は”ヒトの秘密”と題されていたが、例によって人類学から文明論まで幅広い範囲に及ぶ、ダイヤモンド氏独特の分析は、頭の柔らかい若者たちにとって理解し易かったように見える。
 環境省北海道地方環境事務所は昨日(9日)、シマフクロウへの給餌について、環境省の認める保護増殖事業以外は「安易な餌づけ」だとし、やめるよう指導する方針を明らかにした。このことは釧路市で開かれた「シマフクロウ保護増殖検討会」で提示された。
環境省北海道地方環境事務所は昨日(9日)、シマフクロウへの給餌について、環境省の認める保護増殖事業以外は「安易な餌づけ」だとし、やめるよう指導する方針を明らかにした。このことは釧路市で開かれた「シマフクロウ保護増殖検討会」で提示された。
 沖縄の翁長雄志知事は13日、前県政が出した名護市辺野古の埋め立て承認を取り消した。翁長知事は「今後も辺野古に新基地は造らせないという公約実現に向け、全力で取り組む」と述べた。
沖縄の翁長雄志知事は13日、前県政が出した名護市辺野古の埋め立て承認を取り消した。翁長知事は「今後も辺野古に新基地は造らせないという公約実現に向け、全力で取り組む」と述べた。

 どうしても容認できない、公共事業の使い方がある。北海道の東の地方の中核都市、北見市の真ん中を国道が通っているのであるが、この町の西側に流れる常呂川には急激な崖があったりして、開発されずに残っていた。ここにバイパス道路を作るというのである。
どうしても容認できない、公共事業の使い方がある。北海道の東の地方の中核都市、北見市の真ん中を国道が通っているのであるが、この町の西側に流れる常呂川には急激な崖があったりして、開発されずに残っていた。ここにバイパス道路を作るというのである。








