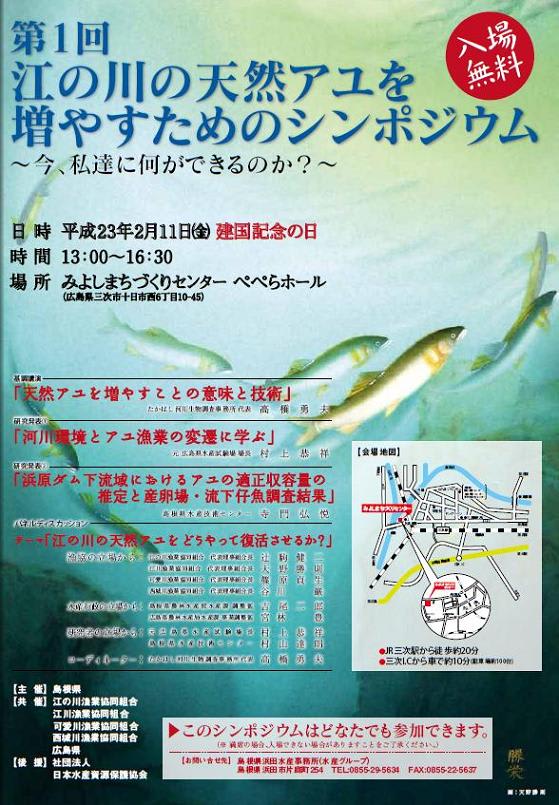《写真:メバル 水産技術センターHPより》




1月日のブログで
“旬魚シリーズ”「メバル」についての
「松江水産事務所○○氏の“つぶやき”」を、
ご紹介しましたが、
水産技術センターホームページ
「島根のさかな」に掲載されている、
メバルに関する話題もご紹介します。
■メバル(メバル、ウスメバル)
メバルという名前の由来は、
眼が体に比べて大きく、
飛び出しそうなほど丸くパッチリし、
張り出ていることからきています。
メバル類の仲間は種類が多く、
メバル、ウスメバル、
トゴットメバル、ハツメなど、
ざっと数えても30種類にのぼります。

《写真:ウスメバル 水産技術センターHPより》
生息水深は数mの藻場から
150mくらいまでの岩礁域に棲み、
海底より少し上方で群れを作っています。
島根県では生息水深の違いから
沿岸域に生息するメバルを「灘メバル」、
やや沖合域に生息するウスメバルや
トゴットメバルを「沖メバル」と呼んでいます。
従って、防波堤での魚釣りでは「沖メバル」に
お目にかかることはまずありません。
メバル類は起伏のある岩礁に棲むため、
一度に大量に獲ることは難しい魚です。
島根県ではメバル・カサゴ類は
釣・はえ縄による漁獲が最も多く、
全体の70%はこの漁法によるもので、
次いで刺し網が20%を占めています。
メバル類は、魚類では珍しく、
卵ではなくて仔魚を産みます。
産み出された仔魚は、
約1ヶ月間浮遊生活を送った後、
流れ藻に付きながら成長します。
5cmくらいになると、
流れ藻から離れて
海底の岩場に移り
棲みつくようになります。
メバルは天候に敏感な魚といわれ、
これを釣る場合は、
一に天候、ニに船頭、三に仕掛け
といわれ、
「めばる凪」と呼ばれるくらい
波が穏やかな日が最適とされています。
メバルはあまり神経質な魚ではないようで、
群れに当ると針の数だけ釣れるのが魅力で、
初心者にも良く釣れる魚でもあります。
メバル類はいつ食べても美味しく、
身は白く適度な弾力があってしまっており、
味は淡白です。
特に冬から春にかけては脂がのり、
口の中でとろけるような旨みがあります。
煮付け、刺身、塩焼き、唐揚げ、味噌汁
などに調理されますが、
身離れがよいために煮付けが一般的です。
以上、水産技術センターのホームページから、一部ご紹介しました。
詳しくはコチラにアクセスしてみてください
 http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html
(島根のさかな メバル)




1月日のブログで
“旬魚シリーズ”「メバル」についての
「松江水産事務所○○氏の“つぶやき”」を、
ご紹介しましたが、
水産技術センターホームページ
「島根のさかな」に掲載されている、
メバルに関する話題もご紹介します。
■メバル(メバル、ウスメバル)
メバルという名前の由来は、
眼が体に比べて大きく、
飛び出しそうなほど丸くパッチリし、
張り出ていることからきています。
メバル類の仲間は種類が多く、
メバル、ウスメバル、
トゴットメバル、ハツメなど、
ざっと数えても30種類にのぼります。

《写真:ウスメバル 水産技術センターHPより》
生息水深は数mの藻場から
150mくらいまでの岩礁域に棲み、
海底より少し上方で群れを作っています。
島根県では生息水深の違いから
沿岸域に生息するメバルを「灘メバル」、
やや沖合域に生息するウスメバルや
トゴットメバルを「沖メバル」と呼んでいます。
従って、防波堤での魚釣りでは「沖メバル」に
お目にかかることはまずありません。
メバル類は起伏のある岩礁に棲むため、
一度に大量に獲ることは難しい魚です。
島根県ではメバル・カサゴ類は
釣・はえ縄による漁獲が最も多く、
全体の70%はこの漁法によるもので、
次いで刺し網が20%を占めています。
メバル類は、魚類では珍しく、
卵ではなくて仔魚を産みます。
産み出された仔魚は、
約1ヶ月間浮遊生活を送った後、
流れ藻に付きながら成長します。
5cmくらいになると、
流れ藻から離れて
海底の岩場に移り
棲みつくようになります。
メバルは天候に敏感な魚といわれ、
これを釣る場合は、
一に天候、ニに船頭、三に仕掛け
といわれ、
「めばる凪」と呼ばれるくらい
波が穏やかな日が最適とされています。
メバルはあまり神経質な魚ではないようで、
群れに当ると針の数だけ釣れるのが魅力で、
初心者にも良く釣れる魚でもあります。
メバル類はいつ食べても美味しく、
身は白く適度な弾力があってしまっており、
味は淡白です。
特に冬から春にかけては脂がのり、
口の中でとろけるような旨みがあります。
煮付け、刺身、塩焼き、唐揚げ、味噌汁
などに調理されますが、
身離れがよいために煮付けが一般的です。
以上、水産技術センターのホームページから、一部ご紹介しました。
詳しくはコチラにアクセスしてみてください
 http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html
http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/umi_sakana/sakana/2/2-42.html(島根のさかな メバル)





















 浜田の海山の幸×広島の牡蠣
浜田の海山の幸×広島の牡蠣 ひろしま牡蠣小屋が浜田にやってくる
ひろしま牡蠣小屋が浜田にやってくる 11:00~ 先着200名様に牡蠣小屋で使える500円券プレゼント!
11:00~ 先着200名様に牡蠣小屋で使える500円券プレゼント!



 病気のない、
病気のない、 遺伝的な悪影響を及ぼす心配のない、
遺伝的な悪影響を及ぼす心配のない、 確実にその川で再生産するアユ
確実にその川で再生産するアユ