今朝はいつもより早く起きてました。
これから、今年度最後となる、
第4回「議員と市民の勉強会」のレジメのプリントアウトをします。
勉強会は参加者一人一人にあわせた実践的かつオーダーメイドの構成。
毎回、参加者は調査したり、考えたりした課題をたくさん提出して当日を迎えます。
一泊二日の勉強会で何をしているのか、出来たてのホヤホヤの内容をお知らせします。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで,
先週の日曜日、滋賀県の県都・大津市の市長選挙で、
36歳の越直美さんが当選されました。
越直美さんの公約は「子育てと教育の最優先」「介護と医療の充実」。
きっと滋賀県知事の嘉田由紀子さんと“共闘”して
政治を変えていかれるのでしょう。
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

これから、今年度最後となる、
第4回「議員と市民の勉強会」のレジメのプリントアウトをします。
勉強会は参加者一人一人にあわせた実践的かつオーダーメイドの構成。
毎回、参加者は調査したり、考えたりした課題をたくさん提出して当日を迎えます。
一泊二日の勉強会で何をしているのか、出来たてのホヤホヤの内容をお知らせします。
| 第4回「議員と市民の勉強会」 「予算議会に向けて~議会活動・議員活動のスキルアップのために」 2012年1月28日(土)13時から29日(日)12時まで 29日午後に【オプション講座】 会場:ウイルあいち 講師:寺町みどり&ともまさ 【セッションA】 《財政/予算編~基本は予算の構造の理解から始まる。情報公開で上級へ》 1.総論《自治体における「予算」とはなにか-予算の基本》 (1)政策的な観点から「予算は政策の事前評価」 (2)予算の法令での位置づけと「予算案」のできるまで 法律的な観点から 自治体予算は法令でどう位置づけられるか~地方自治法 自治体財務・予算のしくみと編成の時系列 2.3月の予算議会での審議の流れ (1)予算案上程→ 予算案説明→ 本会議質疑→ 委員会付託→ 委員会審査(委員会質疑 討論 採決)→ 委員長報告→ 質疑→ 討論→ 採決 (2)いつ、どこで、発言するかのタイミング 質疑・一般質問でなにを発言するのか 予算案審議のじっさい~ 議員の力をフルに発揮しよう 3.「予算書」を読む~決算を予算につなぐ 予算案を実地に即して検討する/「大枠でみる」「個別でみる」 4.深まった議論をしよう/ 今後は「予算編成過程」の情報公開 (1)基本的な資料の集め方 情報公開をつかいこなす 政策実現のために/議員として働くテクニック (2)「予算編成過程」の情報公開 (3)データを具体的に使う取り組みの事例 (4)テクニカルにやる議員に & とことんやる議員に 【セッションB】 一般質問編 《一般質問で望む答えを獲得する~現状と対策》 1.「一般質問の事後評価」~反省を次の議会に生かすために 「事後評価」はなぜ必要なのか/12月議会の一般質問をどう評価するか 2.予算議会に向けて「一般質問」を組み立てる 取り組みたいテーマ、事業に関する論点と手法 ☆「一般質問の組み立て方」 【セッションC】 《発言の手法とスキルアップのために~ 1年を振り返って》 1.「議案質疑」と「一般質問」の課題と解決方法 2.「議案質疑」と「一般質問」をつかいこなす 3.問題提起「なぜ質疑・質問がうまくできないのか」 ディスカッション 「どうすれば質疑・質問ができるようになるのか」 【第4回のまとめ】【議員と市民の勉強会を終えて】 ◇現在の課題/今後の展望 【オプション講座】 市民派議員として働くために「議会で抱えている問題」の解決方法をアドバイスします。 |
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
ところで,
先週の日曜日、滋賀県の県都・大津市の市長選挙で、
36歳の越直美さんが当選されました。
越直美さんの公約は「子育てと教育の最優先」「介護と医療の充実」。
きっと滋賀県知事の嘉田由紀子さんと“共闘”して
政治を変えていかれるのでしょう。
| 【社説】女性首長 優しい目をもつ政治へ 2012年1月25日 中日新聞 大津市長選は、民主、社民推薦の越直美氏が、自民、公明の推す現職を破って初当選した。三十六歳女性市長。人に優しい政治は始まるのだろうか。どんな仕事を見せてくれるのか、楽しみだ。 県と県都の長をいずれも女性が占めるのは、初めてだ。当選を決めた越氏は、選挙事務所に駆けつけた滋賀県の嘉田由紀子知事と握手を交わし、「娘の立場で母を支えたい」と、女性首長同士の連帯を強調した。 越氏を推薦した地域政党の「対話でつなごう滋賀の会」と民主は、嘉田知事の与党でもある。だが、知事は表向き「中立」を堅持した。現職を推す自民が昨年春の県議選で過半数を獲得し、副知事を一人に減らされるなど、難しい県政運営を迫られているからだ。しかし、嘉田知事の次男が応援のマイクを握るなど、“共闘”は明らかだった。一昨年の知事選で史上最多の約四十二万票を獲得した嘉田人気は健在で、無名の新人を背後から支えていた。 明確な争点があったわけではない。それでも、昨年十一月の大阪府知事・大阪市長ダブル選で、橋下徹氏の地域政党「大阪維新の会」が巻き起こした変化の旋風は、琵琶湖畔にも吹いてきた。 橋下氏と同じ弁護士の越氏には、格好の追い風だった。 この閉塞(へいそく)感を破ってほしい。何かを変えたい、変えてほしいと願う風である。長年続いた男性主導の土建中心政治から、女性による福祉型政治へ。老練から若さへ。勇ましさから気配りへ。変革を求める嵐は、しばらくは収まるまい。 京都、大阪通勤圏の大津では、市街地に相次いでマンションが建設され、子育て世代の流入が増えている。それに伴い、保育所の待機児童増加は深刻化、JR湖西線沿線に多い、団塊の世代の高齢化はこれから進む。 「子育てと教育の最優先」「介護と医療の充実」。越氏が掲げた働く女性目線の公約は、全国の自治体が財政難の中で解決すべき共通の課題である。女性首長はまだ、全体の2%にすぎないが、人に優しい政治を望み、身近な暮らしの問題に答えを出してほしいと切望する、有権者の期待は強い。 米国のオバマ大統領や、日本の民主党の例を引き合いに出すまでもなく、風はやがて吹きすぎる。国際派弁護士の越氏も行政手腕は未知数だ。身近な課題に、まず、どのような答えを出すか。ひと味違う“母娘タッグ”の次なる戦いぶりを、見せてもらおう。 |
最後まで読んでくださってありがとう


 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね













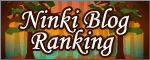












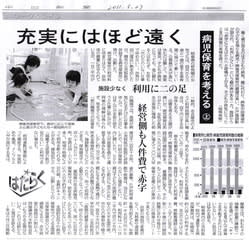
 働く親が困るのは子どもの病気。親に代わり、病気や回復途中の子どもを預かる病児・病後児保育所の要望は高い。ただ施設数が限られ、「利用しにくい」という親の声がある一方、施設からは「赤字になるばかり」と悲鳴が上がる。子どもが病気になったときの保育の実情を探った。 (稲熊美樹)
働く親が困るのは子どもの病気。親に代わり、病気や回復途中の子どもを預かる病児・病後児保育所の要望は高い。ただ施設数が限られ、「利用しにくい」という親の声がある一方、施設からは「赤字になるばかり」と悲鳴が上がる。子どもが病気になったときの保育の実情を探った。 (稲熊美樹)























