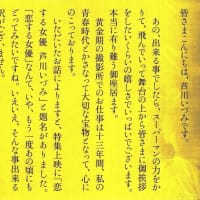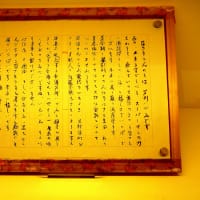ドイツの総選挙は9月26日に行われたが、ようやく連立協議が終わりそうである。社会民主党と緑の党、自由民主党で協議を続けていたが、何とか年内に社民党ショルツ政権が発足するようだ。次期政権が発足するまでは、今回の総選挙に立候補しなかったアンゲラ・メルケルが首相を続けている。日本では憲法で衆議院選挙終了後30日以内に国会を開かなければならないので、一ヶ月以内に必ず新内閣が発足する。選挙制度が違うため、ドイツでは勝者が決着しない事態を想定しているのである。
選挙制度のことは別に書きたいが、ドイツと日本では選挙の争点も大きく違った。ドイツでは地球温暖化など環境問題が大きな争点で、緑の党が前回よりほぼ倍増して118議席を獲得して第3党になった。一方、日本では地球環境問題などが中心的テーマとなったとは思えない。ドイツでは原発や歴史認識などはとっくに解決済みで、ナチスを擁護する発言などあり得ない。麻生氏が長く副首相を務めるなど不可能である。メルケル首相はキリスト教民主党に所属する保守政治家だが、原発廃止に舵を切り、移民受け入れにも積極的だった。日本がいつまでも解決できない諸問題をドイツでは解決して、次の世界的課題が争点になっている。
「保守」の基準がヨーロッパと日本では異なっている。戦争責任を直視せず、ナショナリズムをあおるような政治家はヨーロッパでは「極右」と呼ばれるだろう。脱原発を進めるメルケル首相は、日本だったら自民党には居られないだろう。メルケルは国家主義を批判し、科学者出身の政治家として冷静なコロナ対策を進めた。メルケル首相は日本だったら立憲民主党しか居場所がないのではないか。アンゲラ・メルケルがトップに付くような自民党だったら、もしかしたら僕も支持するかもしれない。枝野前代表が「立憲民主党は保守本流」と言ったのも、ヨーロッパ基準ではあながち間違いとは言えない。
この日独の違いは一体どこに理由があるのだろうか。歴史的、社会的な相違も大きいけれど、一番大きな違いは「冷戦後の国際環境」だと僕は考えている。「冷戦」(つまり戦後の米ソ対立)は、1946年のチャーチル英首相の有名な「鉄のカーテン」演説で可視化された。そこでは「バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで、ヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが降ろされた」と表現されていた。シュテッティンはポーランドの西北端の都市である。まだこの段階では「東ドイツ」(ドイツ民主共和国)は建国以前だったためこのような表現になった。(ドイツは米ソ英仏の4ヶ国の占領。)しかし、要するに東西ドイツが冷戦の最前線だったわけである。そして1990年のドイツ統一でヨーロッパの冷戦は完全に終結した。
それに対して、そもそも東アジアでは「冷戦」どころか、朝鮮半島とインドシナ半島では「熱戦」が起こってしまい、遙かに厳しい状況が続いた。ヴェトナムは1976年に統一されたが、朝鮮半島の分断はなお続いていて解決の見通しがない。また台湾や香港などの「未回収の中国」(「未回収のイタリア」から借りた表現)が存在している。そんな状況の中で、日本には「冷戦終結の恩恵」はほとんどなかったのである。それどころか、近隣諸国と領土問題を抱えて、ナショナリズムをあおるような勢力が政治的影響力を持っている。その上に、中国の台頭とともに米中の対立が激しくなり、「新冷戦」とまで言われる状況になっている。
ドイツが「冷戦の最前線」だったように、日本は「新冷戦の最前線」にある。「朝鮮有事」も「台湾有事」も日本にとって死活的な重大性を持っている。そんな中で、衆議院選挙が行われた時期に合わせるかのように、中国とロシアの艦隊が合同演習を行い、そのまま津軽海峡を併走して日本列島を一周する事態が起こった。演習は10月14日から17日に掛けて行われ、津軽海峡を通過したのは衆院選公示前日の18日だった。そして、翌19日の公示日には北朝鮮が弾道ミサイルを発射した。
 (津軽海峡で併走する中ロの艦隊)
(津軽海峡で併走する中ロの艦隊)
津軽海峡は国際海峡なので、どの国の艦艇も自由に通行することが出来る。だから国際法違反ではなく、日本政府も特に問題視はしていない。しかし、国際海峡の説明をきちんとしないで、ただニュースで映像だけを流すと、いかにも挑発的な行動に見える。実際、中ロでそろって列島を一周するというのは、日本というよりも東アジアの米軍に対する「挑発」的な作戦行動ではあるだろう。(ちなみに、かつてイランによるホルムズ海峡閉鎖が噂された時期に、僕は「国際海峡サミット」を日本主導で開くべきだと書いた。インドネシア、トルコ、イギリス、フランスなどと共同で国際海峡の自由を守る国際的枠組を作る重要性が必要だ。)
 (中ロの艦隊が列島一周)
(中ロの艦隊が列島一周)
まるで中国や北朝鮮は、日本の選挙に影響を与える(自民党を支援する)かのような時期に軍事行動を起こすのは何故だろう。もちろん裏で自民党政権と通じているというわけじゃないだろう。そもそも総選挙は11月だと言われていたのだし、急に中ロ大演習などできるものではない。それにこの間明らかになったのは、日本はしょせん米国の影であって、直接日本を相手にしていても何も解決しないという厳然たる事実だろう。では、何で中国やロシアが日本周辺で共同演習を行ったのだろうか。日本人が意識しないだけで、日本側が最初に「挑発」したという方が正しいのではないかと僕は思っている。
 (イギリス艦と自衛隊が共同訓練)
(イギリス艦と自衛隊が共同訓練)
2015年に成立した「安保法制」はその後「順調」に実施され、既成事実化しつつある。日本の自衛隊は以前から事実上米軍と共同していたが、その後オーストラリアの艦艇を自衛隊が警護するようになった。アメリカが主導する「自由で開かれたインド太平洋」、事実上の「反中国同盟」に自衛隊も組み込まれている。そして、今年の8月25日にはイギリスの空母「クイーン・エリザベス」が日本近海まで来て沖縄沖で日英の合同訓練が行われたのである。これは中国から見たら「香港を奪った英国」と「台湾を奪った日本」という中国近代史で一番大被害を与えられた「帝国主義国」の挑発に見えるのではないだろうか。
 (イギリス艦を「警護」する自衛隊)
(イギリス艦を「警護」する自衛隊)
ところで、こんな風に言う人がいる。「安全保障」の考え方が共通していないと、国民は安心して政権交代に踏み切れない。では、政権交代のためには、憲法上疑義がある「集団的自衛権」が既成事実化した事態を野党も受け入れるべきなのだろうか。自衛隊や日米安保も本来は疑問があったわけだが、今やそれは問題化されなくなってしまった。それにしても、「安保法制は認めない」というのが立憲民主党の初志だったはずだ。かつて民主党政権で閣僚を務めた細野豪志は、自民党に入党を認められたが、テレビで見た選挙演説では「安保では現実主義に立つが、国内問題では今後も弱いものの立場だ」と言っていた。
国内問題の理解も疑問だと思ったが、それは別にして「安保で現実主義」というのは、米軍と一体化して東アジアの最前線で中国と向かい合うということなのだろうか。「新冷戦」の最前線国家として、日本では「平和主義」が空洞化しつつある気がする。ナショナリズムをあおる勢力が影響力を強め、「リベラル」の存在空間が狭まっているのではないか。日本国憲法の原則である「平和主義」「基本的人権の尊重」の立場に立つことによって、中国も批判し、アメリカも批判し、安易に他国に追随することなく平和を守る道はあるのだろうか。単に立憲民主党の消長に止まらず、戦後日本の重大な岐路に立っていると思う。
選挙制度のことは別に書きたいが、ドイツと日本では選挙の争点も大きく違った。ドイツでは地球温暖化など環境問題が大きな争点で、緑の党が前回よりほぼ倍増して118議席を獲得して第3党になった。一方、日本では地球環境問題などが中心的テーマとなったとは思えない。ドイツでは原発や歴史認識などはとっくに解決済みで、ナチスを擁護する発言などあり得ない。麻生氏が長く副首相を務めるなど不可能である。メルケル首相はキリスト教民主党に所属する保守政治家だが、原発廃止に舵を切り、移民受け入れにも積極的だった。日本がいつまでも解決できない諸問題をドイツでは解決して、次の世界的課題が争点になっている。
「保守」の基準がヨーロッパと日本では異なっている。戦争責任を直視せず、ナショナリズムをあおるような政治家はヨーロッパでは「極右」と呼ばれるだろう。脱原発を進めるメルケル首相は、日本だったら自民党には居られないだろう。メルケルは国家主義を批判し、科学者出身の政治家として冷静なコロナ対策を進めた。メルケル首相は日本だったら立憲民主党しか居場所がないのではないか。アンゲラ・メルケルがトップに付くような自民党だったら、もしかしたら僕も支持するかもしれない。枝野前代表が「立憲民主党は保守本流」と言ったのも、ヨーロッパ基準ではあながち間違いとは言えない。
この日独の違いは一体どこに理由があるのだろうか。歴史的、社会的な相違も大きいけれど、一番大きな違いは「冷戦後の国際環境」だと僕は考えている。「冷戦」(つまり戦後の米ソ対立)は、1946年のチャーチル英首相の有名な「鉄のカーテン」演説で可視化された。そこでは「バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで、ヨーロッパ大陸を横切る鉄のカーテンが降ろされた」と表現されていた。シュテッティンはポーランドの西北端の都市である。まだこの段階では「東ドイツ」(ドイツ民主共和国)は建国以前だったためこのような表現になった。(ドイツは米ソ英仏の4ヶ国の占領。)しかし、要するに東西ドイツが冷戦の最前線だったわけである。そして1990年のドイツ統一でヨーロッパの冷戦は完全に終結した。
それに対して、そもそも東アジアでは「冷戦」どころか、朝鮮半島とインドシナ半島では「熱戦」が起こってしまい、遙かに厳しい状況が続いた。ヴェトナムは1976年に統一されたが、朝鮮半島の分断はなお続いていて解決の見通しがない。また台湾や香港などの「未回収の中国」(「未回収のイタリア」から借りた表現)が存在している。そんな状況の中で、日本には「冷戦終結の恩恵」はほとんどなかったのである。それどころか、近隣諸国と領土問題を抱えて、ナショナリズムをあおるような勢力が政治的影響力を持っている。その上に、中国の台頭とともに米中の対立が激しくなり、「新冷戦」とまで言われる状況になっている。
ドイツが「冷戦の最前線」だったように、日本は「新冷戦の最前線」にある。「朝鮮有事」も「台湾有事」も日本にとって死活的な重大性を持っている。そんな中で、衆議院選挙が行われた時期に合わせるかのように、中国とロシアの艦隊が合同演習を行い、そのまま津軽海峡を併走して日本列島を一周する事態が起こった。演習は10月14日から17日に掛けて行われ、津軽海峡を通過したのは衆院選公示前日の18日だった。そして、翌19日の公示日には北朝鮮が弾道ミサイルを発射した。
 (津軽海峡で併走する中ロの艦隊)
(津軽海峡で併走する中ロの艦隊)津軽海峡は国際海峡なので、どの国の艦艇も自由に通行することが出来る。だから国際法違反ではなく、日本政府も特に問題視はしていない。しかし、国際海峡の説明をきちんとしないで、ただニュースで映像だけを流すと、いかにも挑発的な行動に見える。実際、中ロでそろって列島を一周するというのは、日本というよりも東アジアの米軍に対する「挑発」的な作戦行動ではあるだろう。(ちなみに、かつてイランによるホルムズ海峡閉鎖が噂された時期に、僕は「国際海峡サミット」を日本主導で開くべきだと書いた。インドネシア、トルコ、イギリス、フランスなどと共同で国際海峡の自由を守る国際的枠組を作る重要性が必要だ。)
 (中ロの艦隊が列島一周)
(中ロの艦隊が列島一周)まるで中国や北朝鮮は、日本の選挙に影響を与える(自民党を支援する)かのような時期に軍事行動を起こすのは何故だろう。もちろん裏で自民党政権と通じているというわけじゃないだろう。そもそも総選挙は11月だと言われていたのだし、急に中ロ大演習などできるものではない。それにこの間明らかになったのは、日本はしょせん米国の影であって、直接日本を相手にしていても何も解決しないという厳然たる事実だろう。では、何で中国やロシアが日本周辺で共同演習を行ったのだろうか。日本人が意識しないだけで、日本側が最初に「挑発」したという方が正しいのではないかと僕は思っている。
 (イギリス艦と自衛隊が共同訓練)
(イギリス艦と自衛隊が共同訓練)2015年に成立した「安保法制」はその後「順調」に実施され、既成事実化しつつある。日本の自衛隊は以前から事実上米軍と共同していたが、その後オーストラリアの艦艇を自衛隊が警護するようになった。アメリカが主導する「自由で開かれたインド太平洋」、事実上の「反中国同盟」に自衛隊も組み込まれている。そして、今年の8月25日にはイギリスの空母「クイーン・エリザベス」が日本近海まで来て沖縄沖で日英の合同訓練が行われたのである。これは中国から見たら「香港を奪った英国」と「台湾を奪った日本」という中国近代史で一番大被害を与えられた「帝国主義国」の挑発に見えるのではないだろうか。
 (イギリス艦を「警護」する自衛隊)
(イギリス艦を「警護」する自衛隊)ところで、こんな風に言う人がいる。「安全保障」の考え方が共通していないと、国民は安心して政権交代に踏み切れない。では、政権交代のためには、憲法上疑義がある「集団的自衛権」が既成事実化した事態を野党も受け入れるべきなのだろうか。自衛隊や日米安保も本来は疑問があったわけだが、今やそれは問題化されなくなってしまった。それにしても、「安保法制は認めない」というのが立憲民主党の初志だったはずだ。かつて民主党政権で閣僚を務めた細野豪志は、自民党に入党を認められたが、テレビで見た選挙演説では「安保では現実主義に立つが、国内問題では今後も弱いものの立場だ」と言っていた。
国内問題の理解も疑問だと思ったが、それは別にして「安保で現実主義」というのは、米軍と一体化して東アジアの最前線で中国と向かい合うということなのだろうか。「新冷戦」の最前線国家として、日本では「平和主義」が空洞化しつつある気がする。ナショナリズムをあおる勢力が影響力を強め、「リベラル」の存在空間が狭まっているのではないか。日本国憲法の原則である「平和主義」「基本的人権の尊重」の立場に立つことによって、中国も批判し、アメリカも批判し、安易に他国に追随することなく平和を守る道はあるのだろうか。単に立憲民主党の消長に止まらず、戦後日本の重大な岐路に立っていると思う。