4期目の途中で辞任した石原慎太郎(1932~)は、1999年から2012年まで東京都知事を務めた。石原は1975年にも立候補し、美濃部亮吉に敗れていた。1968年に参議院全国区に立候補し300万票を獲得し当選、1972年に衆議院議員に鞍替え当選した。都知事選後に再度衆議院に戻り、合計8期。その間、環境庁長官、運輸大臣を務め、1989年の参院選に自民党が大敗した後の総裁選に立候補したこともある。1995年に勤続25年表彰の場で突然議員辞職を表明して、議員を引退した。
 (辞任表明する石原都知事)
(辞任表明する石原都知事)
1999年は青島幸男知事が再選を目指すなら有利と言われていたが、突然2期目に立候補しないと表明した。自民党は元国連事務次長の明石康を立てたが4位で落選。次点は亡くなったばかりの鳩山邦夫、3位が舛添要一だった。最後の最後に立候補を表明したのが石原慎太郎だったが、先に述べたように「事実上の政界引退」をしていたから、誰も25%を取れずに再選挙ではないかと言われていた。やってみたら石原が30%を獲得して当選となったが、それでもたった3割の得票だったのである。もし決戦投票制度があり、鳩山邦夫が当選していたら、日本はどうなっていただろうか。
都知事になるまでと知事選の経緯を簡単に書いておいた。案外こういうことは忘れてしまうものだから。作家として、あるいは国会議員や閣僚としての活動を書いていると、終わらなくなるので省略。このように石原知事は「知名度」と「経歴」はあるが、都議会に支持会派はなく、有権者の支持も万全ではなかったのである。その後、テレビ受けする「パフォーマンス」を繰り広げたり、トップダウンで新政策を打ち出していく。本人の資質もあるだろうが、「国」を仮想敵に見立てて都民世論に訴えるという戦略を取ったんだろうと思う。(2期目以降は、事実上自民が支持に回るようになる。しかし、最後まで正式な推薦はどの党からも受けなかった。)
 (石原都知事当選のとき)
(石原都知事当選のとき)
石原知事には「暴言」や「差別発言」が山のようにあった。また石原知事によって選ばれた教育委員の顔ぶれは、どう見ても「偏向」していた。「保守派」さえほとんどいなくて、各界でタカ派と呼ばれていたり、改憲派として知られる「極右」的な人ばかりが選任されていた。それらのことも書きだせばいくらでも書けるが、長くなるからこれも省略したい。ここでは「銀行税」と「新銀行東京」の問題を中心に書いておきたい。テレビの舛添問題報道を見ていたら、「石原は実績があった」と言う人が多くてビックリした。ディーゼル車規制問題はともかく、銀行税や新銀行を「実績」と思い込んでいる人がいるのだ。知らないということは恐ろしいと改めて思った次第。
「新銀行東京」から書くと、これは東京都が1千億円を出資して2005年に作った銀行である。でも、新設したと思っている人が多いと思うけど、「BNPパリパ信託銀行」を公有化して作られたものである。当時は中小企業への大銀行の「貸し渋り」が問題化していた。だから無担保で中小企業を支援できる銀行を作ろうと石原知事が言い出したのである。トップダウンの典型で、さすがに都庁官僚も頭を痛めたに違いない。これは発想がムチャである。「中小企業支援策の拡充」はいいけど、銀行は地方自治体がやることではないだろう。やったら不正融資や焦げ付きの温床となるだろうし、現にそうなった。
そういう銀行があるらしいとは知っていても、都民のほとんどは具体的には見たこともないだろう。都市銀行のように駅前に支店があるわけでもないし、ATMで振り込んだりすることもできない。全国銀行協会からも銀行扱いされてなくて、接続されていない。(現時点では、セブン銀行やゆうちょ銀行など一部ではATMで取引可能。)そして、都が出資しているにもかかわらず、都税を納める先にもなっていない。なんでも石原宏高の選挙区の中小企業への融資が多いという情報もあって、存在自体が「怪しい」感じである。名前もおかしい。「新銀行東京」とか「首都大学東京」とか、普通は銀行だぞ、大学だぞと名乗るところ、順序が逆で「東京」が強調されている。「オレサマ」意識を感じる命名だ。
新銀行東京は当初から赤字が続き、2008年には「400億円の追加出資」が必要になった。政府やマスコミの多くも(普段は石原支持の読売や産経も)銀行清算を求め、大もめにもめた挙句、自民、公明の賛成で都議会は通過した。2010年代に入って、単年度決算は黒字の年もあるようになったが、膨大な出資金はどうなっているのか。2015年になって、新銀行東京は「東京TYフィナンシャルグループ」との経営統合交渉を進めることになった。とみん銀行と八千代銀行が統合したグループである。2016年4月に、正式に新銀行東京は「株式交換」で東京TYフィナンシャルグループの100%子会社になった。東京都は経営から撤退し、都民の出資金も生きてくる可能性が出てきたのかもしれない。新銀行東京は石原の実績ではなく石原の失政であり、その行き先を決めたのは「舛添の実績」と言うべきだ。
「銀行税」とは、一定規模以上の大手銀行に対し3%の外形標準課税を課すというものである。当時は長期の不況が続き、地方財政は危機に陥っていた。職員給与の臨時削減措置があったのはこの頃だろうか。一方、「銀行はもうけすぎ」との声が高く、新財源を探していた都は銀行を狙い撃ちにしたわけである。これは「その後の経過を知らない人」から、今でも「石原知事の快挙」などと言われる。だけど、当初から僕は「なんで銀行だけなのか」「無理があるのでは」と感じていた。案の定、銀行側は「公平の原則」に反するとして、東京地裁に提訴したのである。
一審東京地裁は都側の敗訴だった。銀行税は地方税法に違反し、すでに徴収した725億円を返還せよという判決だった。都側は控訴したものの、東京高裁も都側の主張を退けた。もっとも「銀行に課税」という点は違法とはせず、税率が高すぎるのが不公平とした。都はさらに最高裁に上告したが、その後「和解」になったので、多くの都民の印象には残っていないのではないか。和解により、東京都は税率が高すぎるという点を認めて、3%から0.9%に引き下げた。その税率を当初から適用するということで、3173億円の税収のうち、2344億円を銀行側に返金した。そして、そのうち、123億円は加算金である。つまり、取りすぎた分に対する利息である。強引に進めたことによって、都民は支払う必要のない金を払わざるを得なくなったのである。どこが実績なのか。
ここで考えるべきことは、「弱い者への差別」だけではなく、「強いもの」に対しても「法の下の平等」は適用されるという当たり前のことである。「公平性」「中立性」の観点から、当初からおかしかったのである。「税金の取り方をどう決めるか」がもともと民主主義の始まりである。「取られる側」の納得なしに「人気取り」のようなことで始めてしまったのが間違いだった。これは「差別への目」を日ごろから磨いていれば、ちょっと無理かなと気づくことだと思う。その一番肝心な点が石原知事には欠けていた。その結果、都民は123億円を失った。失政による損失は、為政者がぜいたくしたなどという問題とはけた違いの損失をもたらす。もちろん公金によるぜいたくは抑制しないといけないけれど。
2012年4月に石原知事は、「尖閣諸島を東京都で買う」とアメリカで表明した。これなど新銀行東京以上に、地方自治体がやることではない。当時の民主党政権の外交、防衛政策を揺さぶろうという目的だったのだろう。さすがに都税を直接投入するとは言えず、「寄付金を募る」ことになった。14億円以上の寄付金が集まったが、あれはどうなったんだろうか。猪瀬副知事の発想らしいが、迷惑なものを残したものだ。後半からの石原都政は、国威発揚手段としての東京五輪、民主党政権揺さぶりの手段としての尖閣買い上げ計画など、もう都民ではなく「国」にしか関心がなかったのだろう。
最終的には、憲法改正、「国防軍」創設を目指し、だから意図して日中関係悪化を目指していたのだと思う。都議会で「私は日本国憲法は認めません」と言い放ったのが石原知事だった。改憲を目指すという政策を持ってもいいけど、「憲法を認めない」のなら、そもそも憲法で認められた地方自治の直接選挙に立候補すること自体がおかしい。そんな知事のもと、もうすでに巨額の損失を都民は受けているが、多分オリンピックを通してさらなる巨額の負担を強いられるだろう。
 (辞任表明する石原都知事)
(辞任表明する石原都知事)1999年は青島幸男知事が再選を目指すなら有利と言われていたが、突然2期目に立候補しないと表明した。自民党は元国連事務次長の明石康を立てたが4位で落選。次点は亡くなったばかりの鳩山邦夫、3位が舛添要一だった。最後の最後に立候補を表明したのが石原慎太郎だったが、先に述べたように「事実上の政界引退」をしていたから、誰も25%を取れずに再選挙ではないかと言われていた。やってみたら石原が30%を獲得して当選となったが、それでもたった3割の得票だったのである。もし決戦投票制度があり、鳩山邦夫が当選していたら、日本はどうなっていただろうか。
都知事になるまでと知事選の経緯を簡単に書いておいた。案外こういうことは忘れてしまうものだから。作家として、あるいは国会議員や閣僚としての活動を書いていると、終わらなくなるので省略。このように石原知事は「知名度」と「経歴」はあるが、都議会に支持会派はなく、有権者の支持も万全ではなかったのである。その後、テレビ受けする「パフォーマンス」を繰り広げたり、トップダウンで新政策を打ち出していく。本人の資質もあるだろうが、「国」を仮想敵に見立てて都民世論に訴えるという戦略を取ったんだろうと思う。(2期目以降は、事実上自民が支持に回るようになる。しかし、最後まで正式な推薦はどの党からも受けなかった。)
 (石原都知事当選のとき)
(石原都知事当選のとき)石原知事には「暴言」や「差別発言」が山のようにあった。また石原知事によって選ばれた教育委員の顔ぶれは、どう見ても「偏向」していた。「保守派」さえほとんどいなくて、各界でタカ派と呼ばれていたり、改憲派として知られる「極右」的な人ばかりが選任されていた。それらのことも書きだせばいくらでも書けるが、長くなるからこれも省略したい。ここでは「銀行税」と「新銀行東京」の問題を中心に書いておきたい。テレビの舛添問題報道を見ていたら、「石原は実績があった」と言う人が多くてビックリした。ディーゼル車規制問題はともかく、銀行税や新銀行を「実績」と思い込んでいる人がいるのだ。知らないということは恐ろしいと改めて思った次第。
「新銀行東京」から書くと、これは東京都が1千億円を出資して2005年に作った銀行である。でも、新設したと思っている人が多いと思うけど、「BNPパリパ信託銀行」を公有化して作られたものである。当時は中小企業への大銀行の「貸し渋り」が問題化していた。だから無担保で中小企業を支援できる銀行を作ろうと石原知事が言い出したのである。トップダウンの典型で、さすがに都庁官僚も頭を痛めたに違いない。これは発想がムチャである。「中小企業支援策の拡充」はいいけど、銀行は地方自治体がやることではないだろう。やったら不正融資や焦げ付きの温床となるだろうし、現にそうなった。
そういう銀行があるらしいとは知っていても、都民のほとんどは具体的には見たこともないだろう。都市銀行のように駅前に支店があるわけでもないし、ATMで振り込んだりすることもできない。全国銀行協会からも銀行扱いされてなくて、接続されていない。(現時点では、セブン銀行やゆうちょ銀行など一部ではATMで取引可能。)そして、都が出資しているにもかかわらず、都税を納める先にもなっていない。なんでも石原宏高の選挙区の中小企業への融資が多いという情報もあって、存在自体が「怪しい」感じである。名前もおかしい。「新銀行東京」とか「首都大学東京」とか、普通は銀行だぞ、大学だぞと名乗るところ、順序が逆で「東京」が強調されている。「オレサマ」意識を感じる命名だ。
新銀行東京は当初から赤字が続き、2008年には「400億円の追加出資」が必要になった。政府やマスコミの多くも(普段は石原支持の読売や産経も)銀行清算を求め、大もめにもめた挙句、自民、公明の賛成で都議会は通過した。2010年代に入って、単年度決算は黒字の年もあるようになったが、膨大な出資金はどうなっているのか。2015年になって、新銀行東京は「東京TYフィナンシャルグループ」との経営統合交渉を進めることになった。とみん銀行と八千代銀行が統合したグループである。2016年4月に、正式に新銀行東京は「株式交換」で東京TYフィナンシャルグループの100%子会社になった。東京都は経営から撤退し、都民の出資金も生きてくる可能性が出てきたのかもしれない。新銀行東京は石原の実績ではなく石原の失政であり、その行き先を決めたのは「舛添の実績」と言うべきだ。
「銀行税」とは、一定規模以上の大手銀行に対し3%の外形標準課税を課すというものである。当時は長期の不況が続き、地方財政は危機に陥っていた。職員給与の臨時削減措置があったのはこの頃だろうか。一方、「銀行はもうけすぎ」との声が高く、新財源を探していた都は銀行を狙い撃ちにしたわけである。これは「その後の経過を知らない人」から、今でも「石原知事の快挙」などと言われる。だけど、当初から僕は「なんで銀行だけなのか」「無理があるのでは」と感じていた。案の定、銀行側は「公平の原則」に反するとして、東京地裁に提訴したのである。
一審東京地裁は都側の敗訴だった。銀行税は地方税法に違反し、すでに徴収した725億円を返還せよという判決だった。都側は控訴したものの、東京高裁も都側の主張を退けた。もっとも「銀行に課税」という点は違法とはせず、税率が高すぎるのが不公平とした。都はさらに最高裁に上告したが、その後「和解」になったので、多くの都民の印象には残っていないのではないか。和解により、東京都は税率が高すぎるという点を認めて、3%から0.9%に引き下げた。その税率を当初から適用するということで、3173億円の税収のうち、2344億円を銀行側に返金した。そして、そのうち、123億円は加算金である。つまり、取りすぎた分に対する利息である。強引に進めたことによって、都民は支払う必要のない金を払わざるを得なくなったのである。どこが実績なのか。
ここで考えるべきことは、「弱い者への差別」だけではなく、「強いもの」に対しても「法の下の平等」は適用されるという当たり前のことである。「公平性」「中立性」の観点から、当初からおかしかったのである。「税金の取り方をどう決めるか」がもともと民主主義の始まりである。「取られる側」の納得なしに「人気取り」のようなことで始めてしまったのが間違いだった。これは「差別への目」を日ごろから磨いていれば、ちょっと無理かなと気づくことだと思う。その一番肝心な点が石原知事には欠けていた。その結果、都民は123億円を失った。失政による損失は、為政者がぜいたくしたなどという問題とはけた違いの損失をもたらす。もちろん公金によるぜいたくは抑制しないといけないけれど。
2012年4月に石原知事は、「尖閣諸島を東京都で買う」とアメリカで表明した。これなど新銀行東京以上に、地方自治体がやることではない。当時の民主党政権の外交、防衛政策を揺さぶろうという目的だったのだろう。さすがに都税を直接投入するとは言えず、「寄付金を募る」ことになった。14億円以上の寄付金が集まったが、あれはどうなったんだろうか。猪瀬副知事の発想らしいが、迷惑なものを残したものだ。後半からの石原都政は、国威発揚手段としての東京五輪、民主党政権揺さぶりの手段としての尖閣買い上げ計画など、もう都民ではなく「国」にしか関心がなかったのだろう。
最終的には、憲法改正、「国防軍」創設を目指し、だから意図して日中関係悪化を目指していたのだと思う。都議会で「私は日本国憲法は認めません」と言い放ったのが石原知事だった。改憲を目指すという政策を持ってもいいけど、「憲法を認めない」のなら、そもそも憲法で認められた地方自治の直接選挙に立候補すること自体がおかしい。そんな知事のもと、もうすでに巨額の損失を都民は受けているが、多分オリンピックを通してさらなる巨額の負担を強いられるだろう。










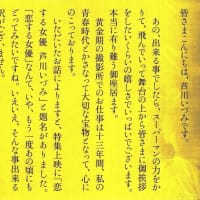
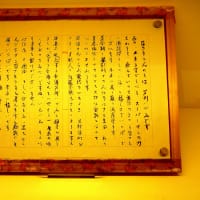








そして、彼がやったのは、樺太での木材の切り出しから運搬までの作業の親分でした。
つまり、裕次郎映画で見れば、安倍徹などが度々演じた悪役ボスだったのです。
石原慎太郎の言動がやくざまがいなのは、この父親の遺伝だと私は思っています。
反して、石原裕次郎は温厚で人間的な方で、慕う人も多かったそうです。
その結果裕次郎の石原プロは今も存続しています。
一方、石原慎太郎は、中川一郎から青嵐会をを受け継ぎますが、結局誰も付いて来なくなります。
その結果一人でできる都知事に出た、ということだと思います。それはある意味で彼に合っていたのですが。
早めに動いた石原元都知事はこうなることを見越していたのではないのでしょうか
偏ったブログですね