 | 科学者という仕事―独創性はどのように生まれるか (中公新書 (1843))酒井 邦嘉中央公論新社このアイテムの詳細を見る |
科学者という仕事
中公新書
いや、義妹が科学者で、しかも量子物理学者で、現在の最先端の科学なので、なのでもう本当にバリバリに科学者なのです。
こんな人なんですが。
 | ようこそ量子 量子コンピュータはなぜ注目されているのか (丸善ライブラリー)根本 香絵,池谷 瑠絵丸善このアイテムの詳細を見る |
そして共著は妻(義妹の姉)なんですが。
で、ちょっと彼女と話したときに、科学者という仕事ってすごいなと思ったことがあって、先にそのことを書きます。
以下は彼女の言葉ではなく僕の理解なのですが、科学者っていうのは、自分が生涯追うテーマを決めて、それをとにかく専一に追求する。そしてその研究が一番効率的にできる場所を世界中から探す。だから大学や研究所ってのは、あくまでその時最良と思われる場所であって、誰かに言われたことをやるのではなく、自分が決めたことをやる、そのために世界中で一番研究がしやすいところを選ぶ。(もちろんアプライし、認められることが必要だ)研究費も同じで、それには自分の研究テーマと成果のプレゼンをし、研究費や助成金を獲得する。それも誰かに言われたものをするのではなく、自分がやりたいことでやってくわけで。
つまり、これって、ビジネス本にある「ライフタイムミッション」というものではないだろうか。自分は人生で何をなしたいと思うか。それが科学者という仕事では、研究テーマそのものとなる。ライフタイムミッションってのはさ、会社に言われたことでも、会社の利益目標でもないし、頼まれた仕事をちゃんとやることですらない、自分が人生で何をなすのかという本質的な問いであって、これが明瞭な人生というのは、素晴らしいことだ。しかも科学や技術の進展ってのは、後述の本にもあるけど、基本的には人間の幸福に資するモノであって、自分の使命が、誰に命じられたモノでもなく自分で見つけたモノで、そこに全力で自らを投じることで自己実現ができ、しかも、それが人類の幸福に資する素晴らしいですよね。
で、長くなったのが、そんな印象を持っていたこともあって、この本を読んでみたわけでした。読んでみたら、とてもいい本でした。僕の前説とは直接関係なく、素直に理系の学生に対して研究者になるための心構えが書かれた本でしたが、アインシュタインやチョムスキー、キューリー夫人などのエピソードも挿入されており、そして何より酒井邦嘉という著者(東大教授)の、後進への熱い想いと愛情が感じられて素晴らしかった。ビバ理系!
一生を捧げても惜しくない研究テーマを見つけるまで、研究を始めるな。
というセリフも引用されていて、これはまさに「ライフタイムミッション」を指すよね。
これについては今なお悩みつつあるオレであるが故、科学者という仕事ってすごいな、と思ったわけです。ちなみに会社員諸氏、会社の事業計画が自分のライフタイムミッションではないので、そこのところ、よく気をつけた方がいいよ。
ところで、面白い話があった。いい研究者になれるかどうかがわかる問題だそうです。
問題1
何かおもしろい問題を考えよ
問題2
問題1で作った問題に答えよ
もひとつ、さらに参考になった話。サイエンスとは切り捨てることだそうで、「何をやらないか。フォーカスすることに尽きる。」のだとか。そして至言は「重大な発見をしたいなら、重大な問題に取り組まなければならない。」
一生を捧げても惜しくない研究テーマを見つけるまで、研究を始めるな、も至言。人生は短い。
そうですよね。さすがです。














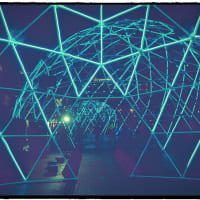




・宇宙とは何か
・物質とは何か
・生命とは何か
・知能とは何か
by ハーバート・サイモン
というのもあります。
とてもわかりやすいと思います。