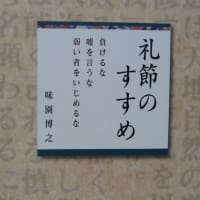第2465号 27.09.28(月)
.
天道は盈(み)つるを虧(か)いて謙に益す。『易経』
.
天の道は、満ちたものがあれば、必ずそれを欠き、不足にあって謙遜の態度を守っている者に対しては、それを補い益すものだ。
満ちれば欠け、欠くれば満ちる月の道理である。224
.
【コメント】森信三先生のご著書に、戦争で男の兵士が数多く戦死したら、その翌年から男子の出生率が増えるということを書いてあります。上の易経が訓戒する事と同じ道理なのでしょうか。
----------------------
『臥牛 菅実秀』(第4回)
.
序
.
憶昔恩栄在武州 春風雙馬四方遊
天時一変難同返 腸断雨声愁裡秋
.
この詩は、祖父忠篤が戊辰の役後、東京芝清光寺に於て謹慎を仰せ付けられたその当時の詩である。当時わずか十六才であった。賊軍の汚名を蒙り、しかも帰順降服という最も苦難の多かった時代に、祖父たちは、如何にその苦難に堪え、荘内の再建をめざして生きぬいたことであろうか、今日の我々の想像に絶するものがあったろう。祖父は私が生れる前に世を去ったが、私の幼心に残る赤沢経言、加藤景重など、御維新当時からの古老のおもかげが、今はなつかしく思い出される、それらの古老や父忠良がよく話してくれたのは、菅臥牛先生のことであった。
.
あの維新前後の苦難に立った荘内を一身に担って再建の方途を確立した臥牛菅実秀先生は、西郷南洲翁と共に、我々荘内人が永遠の師と仰慕する賢哲である。
臥牛先生と南洲翁との交わりは、正に「賢、賢を知る」の古言そのままのものであったかと信ずる。
臥牛先生に関しては、高弟赤沢経言の執筆による「臥牛先生行状」があり、又その教を門弟たちが書きとどめておいたものを、同高弟加藤景重が苦心編集した「臥牛先生遺教」があるが、何れも世に公にされているわけでは無く、その他諸般の記録、文献はあってもこれらを集成統一したものではなかった。(二回にわけてご紹介致します。酒井忠明)
.
(上に忠篤公が〈苦難に堪え〉と書いてありますが、そこの所を読み想像を絶する御苦労を知り得たものですから、昨年忠篤公の墓前に額づいたのでした。)
---------------
『南洲翁遺訓』を誘い文句にいろいろ事を進めている人々がいるらしいですが、荘内の先達の先生方の御苦労を、本当に分かろうとしているのでしょうか。我が日本空手道少林流円心会の師範・仲間たちは、臥牛先生、赤沢先生方の本当の心を知りたくて、真剣に学んでいるのです。『臥牛菅実秀』『名君忠徳公』『教えの國・荘内』『臥牛先生遺教』等々をです。
--------------
『論語』(第402)
.
子曰はく、吾の人に於ける、誰をか毀(そし)り誰をか誉めん。如し誉むる所の者あらば、其れ試みる所あるなり。斯の民や三代の直道にして行ふ所以なり。
.
孔子がいうには、「わしは人に対して、誰をそしり誰を褒めようぞ。無責任に誉めたりそしったりはしない。もしわしが褒めたならば、それは実際に其の行いをためした上のことじゃ。今日の人民は、ずいぶん悪い事もするが、元来昔の夏殷周三代の純朴の民と同じく真っ直ぐな一本道を行く徳性をもってゐるのであって、それが横道にずれこむのは、必ずしも彼等の罪ばかりではなく、教育や政治にも責任があるのだから、めったに誉めもそしりも出来ぬではないか。」
.
.
今日の事象と似ているようです。今日、学校では「正座」をさせることは体罰になるのだそうです。長年、禅の世界も研究してきましたが、正座は精神生活をおくる上からも大変善い事なのです。だから私は、道場では子供たちに正座・黙想を進めていす。40年前・平井先生は静坐道を学んだといって、終日座って居ても平気でした。お心の素晴らしい先生でした。
--------------
『農士道』(第281回)
.
「翁又曰、茶師利休が歌に『寒熱の地獄に通ふ茶柄杓も、心なければ苦しみもなし』と云へり。此歌未だ盡さず、如何となれば、其心無心を尊ぶといへども、人は無心なるのみにては、国家の用をなさず。夫れ心とは我心の事なり。只我を去りしのみにては未だ足らず、我を去て其上に一心を決定し毫末も心を動さざるに到らざれば尊ぶにたらず。故に我常に云ふ此歌未だ盡さずと。
今試みに詠み直さば『茶柄杓の様に心を定めなば、湯水の中も苦しみはなし』とせば可ならんか。夫れ人は一心に決定し動かざるを尊ぶなり。夫れ富貴安楽を好み貧賤勤労を厭ふは、凡情の常なり。婿嫁たる者、養家に居るは、夏火宅に居るが如く、冬寒野に出づるが如く、又実家に来る時は、夏氷室に入るが如く、冬火宅に寄るが如き思ひなるものなり。
-----------
.
天道は盈(み)つるを虧(か)いて謙に益す。『易経』
.
天の道は、満ちたものがあれば、必ずそれを欠き、不足にあって謙遜の態度を守っている者に対しては、それを補い益すものだ。
満ちれば欠け、欠くれば満ちる月の道理である。224
.
【コメント】森信三先生のご著書に、戦争で男の兵士が数多く戦死したら、その翌年から男子の出生率が増えるということを書いてあります。上の易経が訓戒する事と同じ道理なのでしょうか。
----------------------
『臥牛 菅実秀』(第4回)
.
序
.
憶昔恩栄在武州 春風雙馬四方遊
天時一変難同返 腸断雨声愁裡秋
.
この詩は、祖父忠篤が戊辰の役後、東京芝清光寺に於て謹慎を仰せ付けられたその当時の詩である。当時わずか十六才であった。賊軍の汚名を蒙り、しかも帰順降服という最も苦難の多かった時代に、祖父たちは、如何にその苦難に堪え、荘内の再建をめざして生きぬいたことであろうか、今日の我々の想像に絶するものがあったろう。祖父は私が生れる前に世を去ったが、私の幼心に残る赤沢経言、加藤景重など、御維新当時からの古老のおもかげが、今はなつかしく思い出される、それらの古老や父忠良がよく話してくれたのは、菅臥牛先生のことであった。
.
あの維新前後の苦難に立った荘内を一身に担って再建の方途を確立した臥牛菅実秀先生は、西郷南洲翁と共に、我々荘内人が永遠の師と仰慕する賢哲である。
臥牛先生と南洲翁との交わりは、正に「賢、賢を知る」の古言そのままのものであったかと信ずる。
臥牛先生に関しては、高弟赤沢経言の執筆による「臥牛先生行状」があり、又その教を門弟たちが書きとどめておいたものを、同高弟加藤景重が苦心編集した「臥牛先生遺教」があるが、何れも世に公にされているわけでは無く、その他諸般の記録、文献はあってもこれらを集成統一したものではなかった。(二回にわけてご紹介致します。酒井忠明)
.
(上に忠篤公が〈苦難に堪え〉と書いてありますが、そこの所を読み想像を絶する御苦労を知り得たものですから、昨年忠篤公の墓前に額づいたのでした。)
---------------
『南洲翁遺訓』を誘い文句にいろいろ事を進めている人々がいるらしいですが、荘内の先達の先生方の御苦労を、本当に分かろうとしているのでしょうか。我が日本空手道少林流円心会の師範・仲間たちは、臥牛先生、赤沢先生方の本当の心を知りたくて、真剣に学んでいるのです。『臥牛菅実秀』『名君忠徳公』『教えの國・荘内』『臥牛先生遺教』等々をです。
--------------
『論語』(第402)
.
子曰はく、吾の人に於ける、誰をか毀(そし)り誰をか誉めん。如し誉むる所の者あらば、其れ試みる所あるなり。斯の民や三代の直道にして行ふ所以なり。
.
孔子がいうには、「わしは人に対して、誰をそしり誰を褒めようぞ。無責任に誉めたりそしったりはしない。もしわしが褒めたならば、それは実際に其の行いをためした上のことじゃ。今日の人民は、ずいぶん悪い事もするが、元来昔の夏殷周三代の純朴の民と同じく真っ直ぐな一本道を行く徳性をもってゐるのであって、それが横道にずれこむのは、必ずしも彼等の罪ばかりではなく、教育や政治にも責任があるのだから、めったに誉めもそしりも出来ぬではないか。」
.
.
今日の事象と似ているようです。今日、学校では「正座」をさせることは体罰になるのだそうです。長年、禅の世界も研究してきましたが、正座は精神生活をおくる上からも大変善い事なのです。だから私は、道場では子供たちに正座・黙想を進めていす。40年前・平井先生は静坐道を学んだといって、終日座って居ても平気でした。お心の素晴らしい先生でした。
--------------
『農士道』(第281回)
.
「翁又曰、茶師利休が歌に『寒熱の地獄に通ふ茶柄杓も、心なければ苦しみもなし』と云へり。此歌未だ盡さず、如何となれば、其心無心を尊ぶといへども、人は無心なるのみにては、国家の用をなさず。夫れ心とは我心の事なり。只我を去りしのみにては未だ足らず、我を去て其上に一心を決定し毫末も心を動さざるに到らざれば尊ぶにたらず。故に我常に云ふ此歌未だ盡さずと。
今試みに詠み直さば『茶柄杓の様に心を定めなば、湯水の中も苦しみはなし』とせば可ならんか。夫れ人は一心に決定し動かざるを尊ぶなり。夫れ富貴安楽を好み貧賤勤労を厭ふは、凡情の常なり。婿嫁たる者、養家に居るは、夏火宅に居るが如く、冬寒野に出づるが如く、又実家に来る時は、夏氷室に入るが如く、冬火宅に寄るが如き思ひなるものなり。
-----------