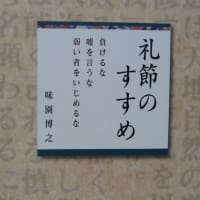第2732号 28.06.23(木)
.
身を脩め言を踐む、之を善行と謂う。行脩まり言道あるは、禮の質なり。禮は人に取らるるを聞けども、人を取るを聞かず。禮は来り學ぶを聞けども、往きて教ふるを聞かず。『礼記』
.
身の行いは(優れた先人)の教を参考にし、口に言ったことは実践しなければならない。これが善行の基本である。そして、行いが教えにかない、言々は道理に合っており、それを実践することができるなら、こうした状態こそ礼の裏付けとなるものである。(善行が実質であり、礼儀は形式である。)
礼というものは、世の人々によってまねられ、自然に周囲に感化するものであって、強いて他人に学ばせ、普及させようと計るべきものではない。礼は、人が伝え聞いて学びに来るものであって、こちらから押しかけて行って広めるべきものではない。(訳・筆者にて一部修正)
.
【コメント】昨日は抜歯後の消毒に行きました。車を運転している時は、天風師の本を録音したものを聞き、病院についた時は、坐って一分以内に本を開き読むことにしています。いつもそうです。読まない時は筆写をしています。
現在は『首丘の人 西郷隆盛』、『礼記』を読んでいます。何の取り柄もない私ですが、こういった歴史的財産を読めるということは有難いと思っています。
私の空手道教室でおけいこする子供たちには、『礼記』を普通の人が理解できるように修正解説して教えています。現在の礼記の処は優秀であったとされる元知事様が辞職したことと関係する処もありますので、特に念を入れて教えています。
.
一般の母親様方は知的偏重に与しすぎるきらいがあります。それは社会経験が乏しく、先を洞察することが出来ないからです。だから「徳」等関係ないから偏差値が上ればいいのだと思っているのでしょう。本当は徳の涵養こそが優先されるべきなのです。
.
つい先日、北海道の警察官二人が、飲酒運転をして逃げた後逮捕されました。その母親様方は今どういう心境でしょう。地獄の底に突き落とされた心境ではないでしょうか。
かく申す私は、77歳になり、人様が経験しない貧乏家庭で、父が残してくれた借金返済に身体ごとぶつかってきたから、いろいろ血肉に沁みついています。
.
今日のインターネットには、舛添氏の元愛人が強烈に罵っている記事が紹介されています。片山さつき氏と夫婦関係にありながら、子供を産ませ、捨てられたらしいとのことです。
そういうことは世の中に無いことではないので、自分一人が聖人ぶった言い方をし、他人を見下げてきたからこそ、反感が増幅しているのだと思います。
.
先日も書きましたが、それらを真摯に後拭いすれば、天も必要以上に諌めることはしないであろうと思います。それでも思いあがっていれば、御子孫にいろいろと禍があるような気が致します。天風著『成功の実現』48頁を御読みになるようお勧め致します。
-------------
『臥牛菅実秀』(第268回)
.
ある日、次第に開けていく丘陵を経塚森から望んだ忠発は、そこに立ち働く人たちの、戦場を思わせる激しい気魄に感嘆して、さっそく組長を集めて勞を謝し、自ら筆をとって『松ケ岡』と書いた標札を丘の上にたてた。それ以来『松ケ岡』が、この開墾場の総称となったのである。
一方、農村の人々も応援隊として開墾に協力し、あるいは餅をつき、わらじを作っておくり、また町家の人々からは、事業達成のための寄金があった。
経塚森の下に田川郡藤島村から本陣を移して幹部の集会所を兼ねた事務所にしたが、これも鶴岡の富商、風間吉郎右衛門、田林重兵衛、平田太次右衛門、工藤良右衛門、三井弥惣右衛門、広瀬伊八郎の六人が、その経費を負担して建てたものであった。
.
本陣----この建物は加藤清正の子忠弘が寛永九年(一六三二)に荘内に流されたときの居館として丸岡(櫛引村)に建 てたもので、のちに藤島(藤島町)に移し、参勤交代のときの休憩所とし本陣と称した。
.
平成28年、大河ドラマは真田一族のものですが、歴史を知る上では参考になりますが、国家的に見て国民が奮い立ってみるというものではないようです。今日も若い青年たちがテレビに出演し偉そうなことを言っていましたが、建設的ではないと拝見しました。そこに来て、開墾のこの模様をご紹介すれば、菅原先生が、物も言わずに、ただ働けという訓戒の有難さが理解できると信じます。
.
阿曾先生昨日は誠に有り難うございました。お礼の御手紙を認めたいと思っています。
高木先生、コメント有り難うございました。早速長々とメールをお送りしましたが、舞い戻ってきました。郵便でお送り致します。
--------------
『農士道』(第544回)
.
實に道の真諦は知行合一、学業一如にあらねばならぬ。「知」「学」は道の、内的隠幽的方面のものであり、「行」「業」はその外的顕現的方面のものである。此の意味に於て私共の主張は決して学問の否定ではなくて、「学」をして、「業」の隠幽的存在、内助的存在たらしむることである。「学」と「業」との間に真箇の位分を立つることである。鋤鎌取っての業術に眞に内在する農道的教学を建設することである。巖上の亭々たる喬松が、其の根の生命力によって、断えず無機物たる巖石までを溶解して養分を吸収同化しては、「松」としての生長を助長するがごとく、私共は常にあらゆる方面より農道を助長する様な学的養分を吸収同化せねばならぬ。
-----------------
.
身を脩め言を踐む、之を善行と謂う。行脩まり言道あるは、禮の質なり。禮は人に取らるるを聞けども、人を取るを聞かず。禮は来り學ぶを聞けども、往きて教ふるを聞かず。『礼記』
.
身の行いは(優れた先人)の教を参考にし、口に言ったことは実践しなければならない。これが善行の基本である。そして、行いが教えにかない、言々は道理に合っており、それを実践することができるなら、こうした状態こそ礼の裏付けとなるものである。(善行が実質であり、礼儀は形式である。)
礼というものは、世の人々によってまねられ、自然に周囲に感化するものであって、強いて他人に学ばせ、普及させようと計るべきものではない。礼は、人が伝え聞いて学びに来るものであって、こちらから押しかけて行って広めるべきものではない。(訳・筆者にて一部修正)
.
【コメント】昨日は抜歯後の消毒に行きました。車を運転している時は、天風師の本を録音したものを聞き、病院についた時は、坐って一分以内に本を開き読むことにしています。いつもそうです。読まない時は筆写をしています。
現在は『首丘の人 西郷隆盛』、『礼記』を読んでいます。何の取り柄もない私ですが、こういった歴史的財産を読めるということは有難いと思っています。
私の空手道教室でおけいこする子供たちには、『礼記』を普通の人が理解できるように修正解説して教えています。現在の礼記の処は優秀であったとされる元知事様が辞職したことと関係する処もありますので、特に念を入れて教えています。
.
一般の母親様方は知的偏重に与しすぎるきらいがあります。それは社会経験が乏しく、先を洞察することが出来ないからです。だから「徳」等関係ないから偏差値が上ればいいのだと思っているのでしょう。本当は徳の涵養こそが優先されるべきなのです。
.
つい先日、北海道の警察官二人が、飲酒運転をして逃げた後逮捕されました。その母親様方は今どういう心境でしょう。地獄の底に突き落とされた心境ではないでしょうか。
かく申す私は、77歳になり、人様が経験しない貧乏家庭で、父が残してくれた借金返済に身体ごとぶつかってきたから、いろいろ血肉に沁みついています。
.
今日のインターネットには、舛添氏の元愛人が強烈に罵っている記事が紹介されています。片山さつき氏と夫婦関係にありながら、子供を産ませ、捨てられたらしいとのことです。
そういうことは世の中に無いことではないので、自分一人が聖人ぶった言い方をし、他人を見下げてきたからこそ、反感が増幅しているのだと思います。
.
先日も書きましたが、それらを真摯に後拭いすれば、天も必要以上に諌めることはしないであろうと思います。それでも思いあがっていれば、御子孫にいろいろと禍があるような気が致します。天風著『成功の実現』48頁を御読みになるようお勧め致します。
-------------
『臥牛菅実秀』(第268回)
.
ある日、次第に開けていく丘陵を経塚森から望んだ忠発は、そこに立ち働く人たちの、戦場を思わせる激しい気魄に感嘆して、さっそく組長を集めて勞を謝し、自ら筆をとって『松ケ岡』と書いた標札を丘の上にたてた。それ以来『松ケ岡』が、この開墾場の総称となったのである。
一方、農村の人々も応援隊として開墾に協力し、あるいは餅をつき、わらじを作っておくり、また町家の人々からは、事業達成のための寄金があった。
経塚森の下に田川郡藤島村から本陣を移して幹部の集会所を兼ねた事務所にしたが、これも鶴岡の富商、風間吉郎右衛門、田林重兵衛、平田太次右衛門、工藤良右衛門、三井弥惣右衛門、広瀬伊八郎の六人が、その経費を負担して建てたものであった。
.
本陣----この建物は加藤清正の子忠弘が寛永九年(一六三二)に荘内に流されたときの居館として丸岡(櫛引村)に建 てたもので、のちに藤島(藤島町)に移し、参勤交代のときの休憩所とし本陣と称した。
.
平成28年、大河ドラマは真田一族のものですが、歴史を知る上では参考になりますが、国家的に見て国民が奮い立ってみるというものではないようです。今日も若い青年たちがテレビに出演し偉そうなことを言っていましたが、建設的ではないと拝見しました。そこに来て、開墾のこの模様をご紹介すれば、菅原先生が、物も言わずに、ただ働けという訓戒の有難さが理解できると信じます。
.
阿曾先生昨日は誠に有り難うございました。お礼の御手紙を認めたいと思っています。
高木先生、コメント有り難うございました。早速長々とメールをお送りしましたが、舞い戻ってきました。郵便でお送り致します。
--------------
『農士道』(第544回)
.
實に道の真諦は知行合一、学業一如にあらねばならぬ。「知」「学」は道の、内的隠幽的方面のものであり、「行」「業」はその外的顕現的方面のものである。此の意味に於て私共の主張は決して学問の否定ではなくて、「学」をして、「業」の隠幽的存在、内助的存在たらしむることである。「学」と「業」との間に真箇の位分を立つることである。鋤鎌取っての業術に眞に内在する農道的教学を建設することである。巖上の亭々たる喬松が、其の根の生命力によって、断えず無機物たる巖石までを溶解して養分を吸収同化しては、「松」としての生長を助長するがごとく、私共は常にあらゆる方面より農道を助長する様な学的養分を吸収同化せねばならぬ。
-----------------