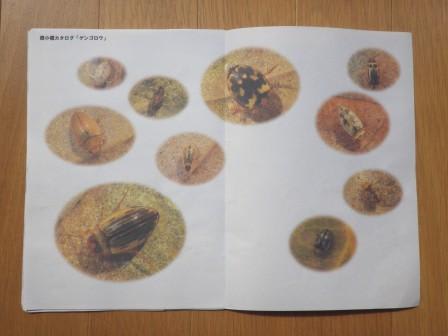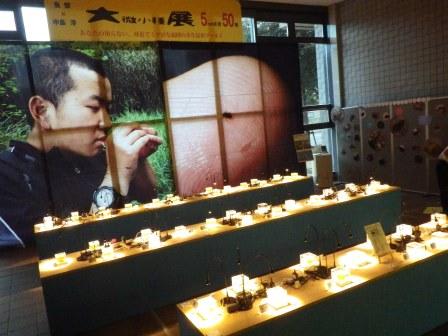先日、あるところでご高齢の男性に話しかけられた。
小学校5年生の頃に、終戦を迎えたそうだ。
福岡市の方にお住まいだったようで、
その頃はよく川に入っていたという。
それが「薬院新川」。
行ったことはないが、博多駅もほど近いその地名から察するに
今はコンクリートの川か、暗渠化しているのかと
思いながら耳を傾けていた。
すると、「ゲンゴロウ」がいたと言いながら
手で大きさを示す、そのサイズは紛れもなくタダゲン!
「タガメはいなかったですか?」
「ああ、アシガッパじゃろ!」

へえ、タガメ=アシガッパ、だって。
鎌で挟まれるようで、あまりいい気持ちがしなかったそう。
また、タダゲンは「食い付く」と言っていたそうだ(たしかに!)。
さらに、「ドジョウはおらんやったですか?」と聞くと
「おったよ、2種類おった。黒いのと、それとスナドジョウが。」

おお、シマドジョウ属もいたのね、そんな小さな川に。
ヤマトシマなのか、もしかして例の中型種なのか・・
砂地の川だったと言っていた。
他にも、焼夷弾の筒(!)の中に、ウナギやナマズが入っていた、
小さいウナギは「糸ウナギ」と呼んでいた、
戦後ある時からアメリカザリガニが急に増えだした、
しかしそれも住めない川にその後なってしまった・・・等々。
自分にとっては、ものすごく貴重な話を聞けた。
70年前の薬院新川からすると、今の薬院新川は想像できんやろうね。
今の薬院新川からすると、70年前の薬院新川は想像できん。
だって、タガメやタダゲン、たくさんのミズスマシ、
そしてシマドジョウがいる姿なんて、あり得ない。
今の姿は、宮崎アニメでいうと
「千と千尋の神隠し」のハク、ですかねぇ。
洒落たカッコして、洒落た食いもんくったりして
我がもの顔に人間が歩いていても、
そんな光景はホンのここ数十年のこと、なんですね。